GMS(次の項目に略語の説明があります!)という業態が衰退し、現在、唯一残ったとされるイオンも大きな赤字を抱え、いよいよGMSが終焉ということが囁かれています。
この記事では、
- GMSの衰退は消費者ニーズ・消費者行動の変化に、ビジネスモデルを変更し、進化させることが出来なかった当然の帰結だ
ということを、簡単にまとめました。
☆本記事は、GMS各社、並びにイオンを中傷・非難する意図はありません。
- GMSが衰退している要因
- イオンの業績悪化が示す業界の現状
- GMS衰退の真の原因とは?
この記事で語る「GMS衰退論」は、実は「テレビ業界衰退」と同根であるという、こちらの記事もどうぞ。
GMSの台頭から衰退までの概論
かつて日本の小売業界を牽引していたのはGMS(総合スーパー)という業態です。
GMSの台頭
GMSは「General Merchandise Store(ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア)」の略で、日本語では「総合スーパー」と呼ばれる業態を指します。この業態は、食料品、衣料品、日用品、家電、家具など、生活に必要な幅広い商品を一つの店舗で取り揃え、セルフサービス方式で販売するのが特徴です。
GMSは、もともと1920年代のアメリカで誕生し、日本では戦後の高度経済成長期に普及しました。当時の会社名で記すと、ダイエー、イトーヨーカドー、西友、ジャスコといった大手チェーンがその代表例です。
GMSの特徴として、以下の点が挙げられます:
- 幅広い品揃え:衣食住に関連する商品を一度に購入できる利便性を提供。
- 大規模な売り場:郊外や広い敷地を活用した店舗展開が多い。
- セルフサービス方式:顧客が自由に商品を選び、購入する形式。
1971年にダイエーがそれまでの小売業日本一であった百貨店を抜き、小売業日本一になりました。
1970年代・1980年代に掛けて、「ワンストップショッピング」(一箇所で何でも揃って便利!)といったGMSのビジネスモデルは消費者の心をつかみ、ダイエー・イトーヨーカドー・西友・ジャスコといった大手GMSが跋扈する時代となりました。
GMSの衰退
その後、消費者行動が変化してきました。消費者は、より専門性の高い、深掘りした品揃えを欲するようになってきたのです。
しかし、近年では専門店やネット通販の台頭により、GMSの市場シェアは縮小傾向にあります。特定のカテゴリーに特化した業態(例:ユニクロやニトリ)や、利便性の高いECサイト(例:Amazon、楽天市場)に顧客を奪われてしまうことに歯止めが出来なかったのです。
GMSは、かつて「ワンストップショッピング」の利便性で消費者に支持されましたが、現代の多様化する消費者ニーズに対応するためには、さらなる変革が求められています。
残念ながら、立て付けが巨大になりすぎてしまったGMSは、そういう消費者ニーズ・消費者行動の変化に全く対応できませんでした。
ダイエー、西友、イトーヨーカドーという順番にGMSのビジネスモデルが瓦解していきます。そして、最後に残ったGMSの雄・イオン(元ジャスコ)にも衰退が顕著になったのです。
イオンが2024年2月10日に発表した2024年3〜11月期の連結決算では、最終損益が156億円の赤字(前年同期は183億円の黒字)となり、大きな変調をきたしていることが明らかになりました。
かつての成長モデルが機能しなくなった背景には何があるのでしょうか?
GMSの衰退が進んできた背景
GMS(総合スーパー)は、日用品から衣料品、生鮮食品までをワンストップで購入できる便利な業態として長年、消費者に支持されてきました。しかし、近年の市場環境の変化により、かつての成功モデルが崩れつつあります。
専門店・ECの台頭
消費者は、より専門性の高い店舗や、利便性の高いECサイトを利用する傾向が強まっています。
特に、アマゾンや楽天市場などのECサイトの成長により、GMSの存在意義が薄れています。
品揃えの多さだけで勝負する時代は終わり、価格競争に巻き込まれたGMSは利益を確保しにくくなっています。
ライフスタイルの変化
核家族化や単身世帯の増加により、大量購入よりも少量・高品質志向へと消費者ニーズが変化しました。
GMSが提供する大量仕入れ・低価格販売のモデルは、こうしたライフスタイルの変化に適応しきれていません。
価格競争とコスト増
ディスカウントストアやドラッグストアの価格競争が激化し、GMSの強みである価格優位性も揺らいでいます。
一方で、最低賃金の上昇や物流コストの増加が利益を圧迫し、経営を苦しめています。
イオンの業績悪化が示すGMS業界の未来
GMSの最大手であるイオンは、GMS業界のトレンドを反映する存在です。そのイオンが2024年3〜11月期の決算で156億円の赤字を計上したことは、業界全体の厳しさを象徴しています。
特に、イオンは食品スーパーを強化し、PB(プライベートブランド)戦略やデジタル活用を進めてきました。
しかし、それでもなお業績の悪化を止められなかったのは、GMS業態自体の限界を示唆しています。
GMS衰退の真の原因とは?
GMS衰退の真の原因は、結局のところ 「消費者行動・消費者ニーズの変化にビジネスモデルの変更・進化が対応できなかった」 ことに尽きます。
- ニーズの多様化に対応できなかった → 専門性の高い店舗やECに顧客を奪われた
- 従来の大量販売モデルが時代に合わなくなった → 小回りの利く業態(コンビニ・ドラッグストア)にシェアを奪われた
- 価格競争とコスト増に対応できなかった → 利益を確保できず、持続的成長が困難に
これらの要因が重なり、GMSの衰退はもはや不可避の流れとなっているのです。
まとめ:GMSの未来はあるのか?
GMS業態は、日本の小売業を支えてきた重要な存在でした。しかし、時代の変化に適応できなかったことで、徐々にその役割を終えつつあります。
イオンの業績悪化が示すように、今後もGMS業界は厳しい状況が続くでしょう。生き残るためには、既存の枠組みにとらわれず、新たなビジネスモデルを模索することが不可欠です。
GMSの衰退は単なる偶然ではなく、消費者ニーズと市場の変化に適応できなかった結果であることを、今こそ改めて認識するべきではないでしょうか。
このように、事業のコアとなっているビジネスモデルを消費者ニーズ・消費者行動の変化に対応すべく、変化・進化させてこれない業界は終焉を迎えるいうことです。これはGMS以外の業界、例えば、テレビ局などについても同様のことが言えるのかもしれません。

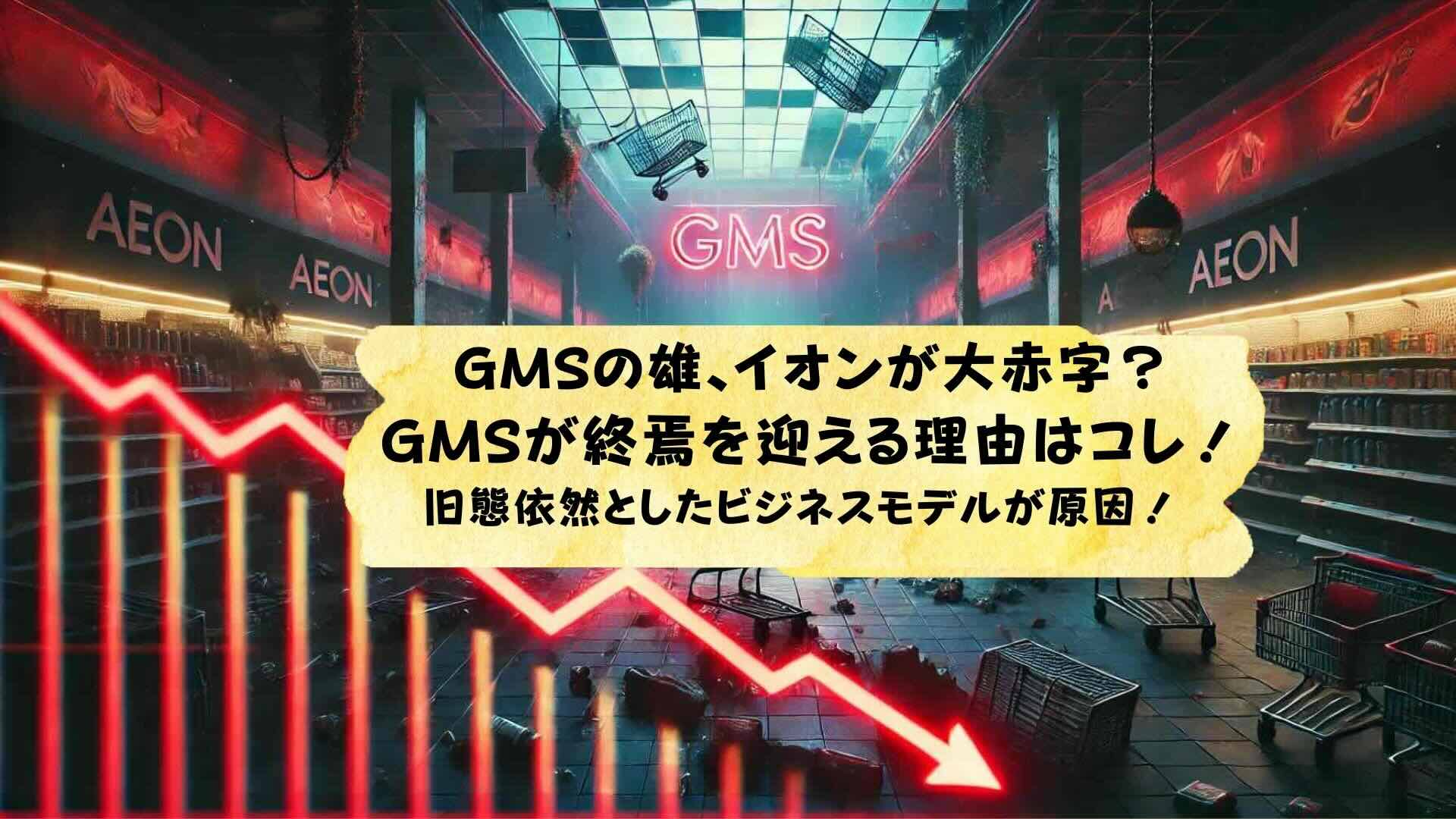
コメント