高速道路のサービスエリア、劇場の休憩時間、花火大会の会場……。
「女性用トイレ」の前に伸びる、絶望的な長蛇の列。
列に並びながら、横目でスイスイと用を済ませて出てくる男性たちを見て、こう思ったことはありませんか?
「なんで女ばっかりこんなに並ばなきゃいけないの?」
「化粧直しが長いから? 服の脱ぎ着に時間がかかるから? 仕方ないことなの?」
いいえ、それはあなたの思い過ごしでも、女性の動作が遅いせいだけでもありませんでした。
実は、日本の公衆トイレには、長年放置されてきた「構造的な欠陥(設計ミス)」があったのです。
その事実にたった一人で立ち向かい、メジャーを持って全国1000カ所以上のトイレを測り続け、ついに国(国土交通省)まで動かした一人の女性がいます。
この記事では、私たちが長年「当たり前」だと思って我慢させられてきた「トイレ行列」の真犯人と、これから変わりゆく日本のトイレ事情について解説します。
この記事で分かること
- 「女性トイレだけ行列」を引き起こしていた、建築設計上の「不都合な真実」
- たった一人で国を動かした行政書士・百瀬まなみさんの執念の調査結果
- 世界も注目する「2way」や「オールジェンダー」など、行列を消す最新トイレ
「我慢すべき」ではなかった! 一人の女性が暴いた行列の正体
「女性のトイレ行列は、社会問題として認識されていない」
そう声を上げたのは、長野県松本市出身の行政書士、百瀬まなみさん(61)です。

Yahoo!ニュースなどでも大きく取り上げられ話題となっていますが、彼女の行動力は並大抵のものではありませんでした。
彼女は「なぜ並ぶのか?」という疑問を解明するために、なんと全国4000カ所以上のトイレを視察し、そのうち1000カ所以上で便器の数を独自に数えて回ったのです。
「面積は平等」の罠
百瀬さんの調査で浮き彫りになったのは、設計段階における「見せかけの平等」でした。
多くの施設では、トイレを作る際、男女のトイレスペース(床面積)を「ほぼ同じ広さ」で確保します。
一見、公平に見えますよね?
しかし、ここに大きな落とし穴があります。
- 男性用:
- 小便器は省スペースで設置できるため、同じ面積でも「数」を多く置ける。
- 女性用:
- 全て個室(ブース)である必要があり、1つあたりの占有面積が大きくなる。
その結果、「面積は同じでも、一度に使える『便器の数』は圧倒的に女性の方が少ない」という逆転現象が起きていたのです。
さらに、女性は生理現象や服装の構造上、どうしても男性より滞在時間が長くなります(男性の2倍〜3倍かかると言われています)。
「時間がかかるのに、数は少ない」。これでは行列ができて当たり前なのです。
国もついに動いた!「1:1」から「機能重視」への転換
百瀬さんのこの執念のデータ提示と提言は、ついに国を動かしました。
国土交通省は11月6日、有識者らによる協議会を発足させ、女性用トイレの環境改善に向けた対策に本腰を入れることを発表しました 2。
これまでの「なんとなく男女半々のスペース」という思考停止した設計から、「利用実態に合わせた器具数の確保」へと、ルールが変わろうとしているのです。
これからのトイレはどうなる?
すでに先進的な商業施設やスタジアムでは、新しい試みが始まっています。
- 女性用エリアの拡張最初から女性用トイレの面積を男性用の1.5倍〜2倍確保し、個室数を大幅に増やす設計。
- 「2way」トイレの導入混雑状況に合わせて、仕切りを動かして「男性用エリア」の一部を「女性用」に変えたり、男女共用エリアを可変させたりする仕組み。
- オールジェンダートイレそもそも男女を分けず、すべて個室にして空いているところに順次入っていくスタイル(欧米で増えている形式)。
「トイレに行列がない」。そんな当たり前の日常が、ようやく日本にも訪れようとしています。
行列は待てても「災害」は待てない! 今見直すべきトイレの備え
普段のショッピングモールの行列なら、イライラしながらも待てば済みます。
しかし、私たちが直面する「トイレ問題」の中で、絶対に待ってくれない状況があります。
それは、「災害時」と「渋滞中の車内」です。
今回のニュースを見て「トイレの数って大事なんだな」と痛感した今こそ、ご自宅や車の「携帯トイレ」の備蓄を見直してみてください。
能登半島地震などの災害現場でも、一番深刻だったのは「食料」でも「寒さ」でもなく、「劣悪なトイレ環境」でした。
水が流れないトイレ、汚物で溢れかえる便器……。そんな地獄を避けるために、これだけは持っておいてください。
驚異の防臭袋「BOS(ボス)」付き非常用トイレ
災害用トイレで一番重要なのは「臭い」対策です。この「BOS」という袋は、医療向けに開発されたもので、うんちの臭いすら完全に封じ込めます。
マンションなどで排水管が壊れ、トイレが流せない期間が1週間続いた時、この袋があるかないかで生活の質(メンタル)が決まります。
>>[PR] 【うんちが臭わない袋】 BOS非常用トイレ (Bセット) 50回分 災害/携帯/簡易トイレ/防災グッズ/15年保存 ◆防臭 防菌◆ 臭わない袋BOS付き
渋滞の救世主「車載用 携帯ミニトイレ」
行楽シーズンの高速道路、事故渋滞、大雪での立ち往生。
車の中で尿意を催した時の絶望感は、言葉にできません。特に女性やお子様がいる家庭では必須アイテムです。
吸水ポリマーで素早く固め、臭いを漏らさないタイプを、ダッシュボードに常備しておきましょう。
[★ここにAmazonリンク:携帯トイレ 車 登山 男女兼用]
海外の公衆トイレに関する面白ネタ11選
日本のトイレは「行列」が問題ですが、清潔さや機能性においては世界トップクラスです。
では、海外のトイレ事情はどうなっているのでしょうか?
ここでは、海外旅行に行った時に役立つ(かもしれない)、世界の公衆トイレに関するトリビアや面白ネタを11個集めました。
- 【アメリカ】
- ドアの隙間が広すぎて目が合うアメリカの公衆トイレの個室は、足元が大きく開いているだけでなく、ドアの隙間(縦のライン)も驚くほど広いです。外から中の人が見えるレベルで、防犯目的と言われていますが、日本人には落ち着かないことこの上ありません。
- 【ヨーロッパ全般】
- 「小銭がないと漏らす」有料文化駅や街中のトイレの多くは有料です。入り口にゲートがあり、50セント〜1ユーロ程度のコインを入れないと中に入れません。キャッシュレス化でカード対応の場所も増えましたが、小銭がない時の絶望感は異常です。
- 【中国】
- 伝説の「ニーハオトイレ」は絶滅危惧種仕切りがなく、隣の人と顔を見合わせながら用を足す、いわゆる「ニーハオトイレ」。北京オリンピックなどを機に激減し、都市部では日本並みに綺麗なトイレが増えましたが、地方に行くとまだ現役の場所も……。
- 【イタリア・フランス】
- なぜか「便座」がない女子トイレに入ると、洋式便器なのに「便座」がなく、陶器のリムが剥き出しになっていることがよくあります。「空気椅子」状態で用を足す強靭な足腰が求められます(衛生面や破損防止で外されている説が有力)。
- 【イギリス等】
- 青いライトで血管が見えない一部の公衆トイレでは、照明が怪しげな「青色」になっていることがあります。これはムーディーな演出ではなく、麻薬常用者が静脈を見つけにくくして、トイレ内での注射を防ぐための防犯対策です。
- 【台湾・韓国他】
- 紙は流さずゴミ箱へ(変化中)配管が細かったり水圧が弱かったりするため、拭いた紙は便器に流さず、横にある巨大なゴミ箱に捨てる国がアジアには多いです。最近は「流せる」ようにインフラ整備が進んでいますが、まだ習慣として残っている場所も。
- 【インド・中東】
- 「左手」は不浄の手紙を使わず、備え付けの小さいシャワーや水桶と「左手」を使って洗う文化圏があります。そのため、食事や握手は必ず「右手」で行うのがマナー。郷に入っては郷に従えですが、旅行者は紙を持参しましょう。
- 【オランダ】
- 男性用トイレが開放的すぎるアムステルダムの街中には、螺旋状の覆いがあるだけの、ほぼ野外に近い男性用小便器(通称:エスカルゴ)が設置されています。外から足や背中が見える開放感に、日本人男性は度肝を抜かれます。
- 【ドイツ】
- トイレおばさんへのチップデパートなどのトイレの入り口に、掃除係のおばさんが座っていて、小皿にお金を置くシステムがあります。彼女たちの厳しい視線(と素晴らしい掃除技術)の前では、小銭を払わずには通れません。
- 【スウェーデン】
- 男女共用がスタンダードジェンダー平等先進国の北欧では、個室トイレがズラッと並び、男女の区別がない「オールジェンダー」タイプが一般的です。日本のように「男子はこちら」「女子はこちら」と分かれていないので、最初は戸惑うかもしれません。
- 【世界共通】
- 「赤」は空き?使用中?日本の鍵は「青=空き」「赤=使用中」が常識ですが、海外では鍵の色表示がないことも多く、ドアノブをガチャガチャ回して確認するのがデフォルトの国も。また、ごく稀に色が逆(赤が空き)の場合もあり、油断なりません。
まとめ – 声が届けば社会は変わる!
たった一人の行政書士の「なぜ?」という疑問と、地道な調査が、国を動かして「トイレの常識」を変えようとしています。
- 行列の原因:
- 女性の動作が遅いからではなく、建築上の「数」の不平等が原因だった。
- 解決の兆し:
- 国交省が動き出し、今後は「利用実態に合わせた設計」が標準になる可能性大。
次に長い行列に並ぶときは、「私のせいじゃない、設計のせいなんだ」と思って、少しだけ気持ちを楽に持ってください。そして数年後、日本のどこに行ってもスッとトイレに入れる未来が来ることを期待しましょう。
(そして、災害時のトイレ対策だけは、国の対応を待たずに自分で準備しておきましょうね!)
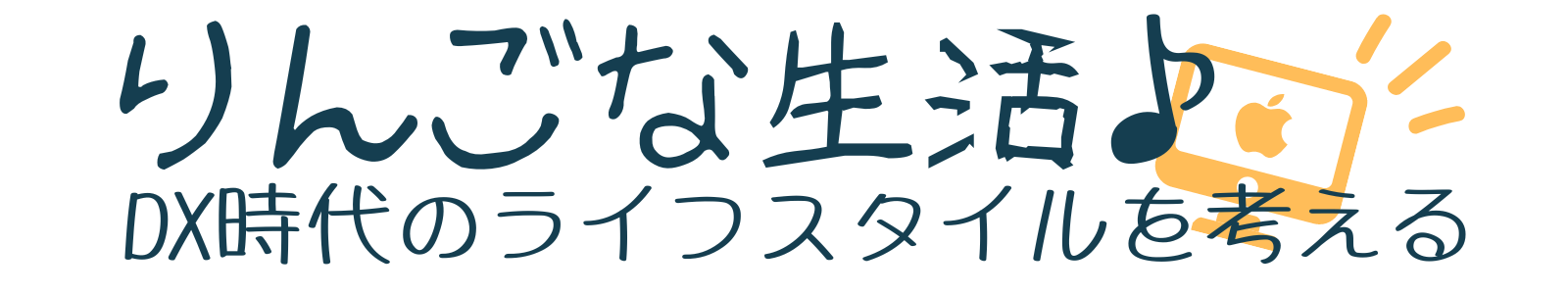
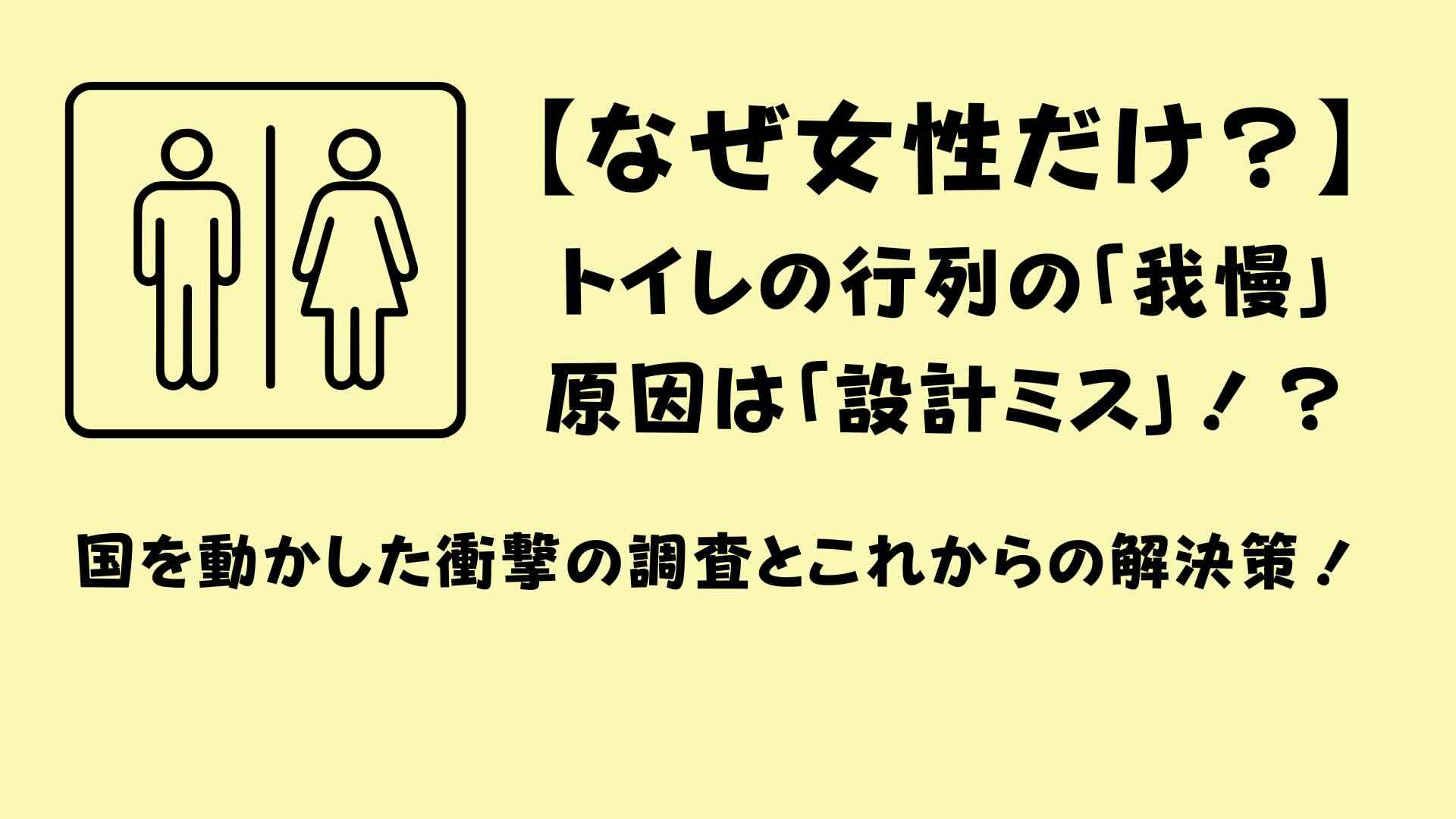
コメント