2025年春場所(3月場所)も、中日(8日目)を終えました。
今場所、優勝が期待された横綱・豊昇龍、大関・琴櫻、大関・大の里ですが、序盤戦5日間で、早々に黒星を喫しています。
そして、中日が終わった時点で、新横綱・豊昇龍は3敗、カド番で迎えた大関・琴櫻も3敗、3度目の優勝を狙う大関・大の里は1敗となっています。
そんなこんなで、「荒れる春場所」ということが序盤戦から囁かれていました。
そこで…
- 「荒れる春場所」ってそもそも何?
- なぜ、そういうことが言われるようになったの?
- 実際に他の場所と比べて春場所は荒れるのか?
ということを調べました。
そして、「実際に3月場所は荒れるのか?」ということも、具体的に調べました。
- 大相撲「荒れる春場所」って何?なぜ、そう言われるようになったのか。
- 過去46年間の実績を調べて、実際に春場所(3場所)は荒れてきたのか。
大相撲「荒れる春場所」って、なぜそう言われるようになったのか?
「荒れる春場所」が大衆に認識されるようになったきっかけ、理由、なぜそう言われるようになったのかを調べました。
「3代目・朝潮」説
ブラウザの検索窓に「荒れる春場所」と入れて検索した結果、Wikipediaの大相撲関係の情報が出てきました。
「荒れる春場所」と呼ばれ、番付上位が負けるいわゆる波乱の結果が多いとされる。 もともと大阪には大坂相撲の歴史があって相撲人気の根強い土地であり、毎年大いに盛り上がる場所である。 3代目朝潮がこの場所で強く1956年から3連覇するなど通算5回の優勝のうち4回を大阪で達成、「大阪太郎」と呼ばれた。
引用元:Wikipedia / 本場所
ちょうど、太文字になっていましたが、「番付上位が負けるいわゆる波乱の結果が多いのが春場所だ」・・・ということのようです。
そもそも、「荒れる春場所」と言われるようになったのが、1956年の3代目朝潮の活躍だった・・・というのがWikipediaの情報です。
ちなみに、この「3代目朝潮の1956年から3連覇」とは次のことを指します。
- 1956年(昭和31年)春場所 関脇・12勝3敗で初優勝
- 1957年(昭和32年)春場所 関脇・13勝2敗で2度目の優勝
- 1958年(昭和33年)春場所 大関・13勝2敗で3度目の優勝
3度目の優勝時、朝潮は大関です。大関が優勝するのは、通常の感覚では「荒れる」という言葉を使うのは適切ではないかもしれません。
ところで、朝潮が3年連続で春場所を優勝していたころ、横綱は4人いました。
より具体的には、昭和30年1月から昭和33年1月の間の4横綱は・・・・
- 第41代・千代の山
- 第42代・鏡 里
- 第43代・吉葉山
- 第44代・栃 錦
この4横綱がいても、春場所は3連続で朝潮に優勝されてしまったというワケです。
それでは、この4横綱が、歴代のなかで弱かったのかというと、そういうことはありません。
当時は、年4場所・5場所と今とは違う場所数でしたが、4横綱が活躍していた昭和30年1月から昭和33年1月までの全14場所中、横綱が優勝したのは9場所、横綱の優勝率は、64.3%。
筆者 TOPIOは、この記事を書くにあたり、直近261場所の分析をしました。
この261場所中、横綱優勝は159場所で、率にして59.3%。
要するに「荒れる春場所」が認識されたち言われる「朝潮が活躍していた当時」、横綱が優勝する率は、直近269場所と大して変わらないし、平均よりは若干強かったとも言えるのです。
そんな強い4横綱がいたのに「3年連続で春場所は朝潮にもっていかれた!」=「荒れる春場所」ということになったのでしょう。
当時、朝潮は「関脇、その後、大関」ですから、「番付上位が負けるいわゆる波乱の結果が多い」は適切ではないと考えています。
横綱が勝てなかったという点では「番付上位(=横綱)が負ける」はありましたが、「3回の優勝は、関脇(3度目は大関)だった朝潮」ですから、「波乱」というほどではない、というのが筆者 TOPIOの考えです。
「昭和28年春場所、4横綱総崩れ」説
一方、違う解説をする方もいます。
よく荒れる春場所と表現がされますがその起源としては昭和28年の春場所(第一回目の大阪での春場所)とされているようです。昭和28年の春場所は4横綱のうち羽黒山が初日から休場。鏡里と東富士が4日目を終えて2勝2敗、千代の山が1勝3敗で千代の山は翌日も敗れて1勝4敗となった所で休場し、2場所連続途中休場と言う成績不振からもう一度大関の地位からやり直させてほしいと横綱返上を申し出でる事態となった事が起源とされています。
※後に先にも横綱返上を申し出た力士は千代の山のみです理由は定かで無いですが、春場所は上位陣が揃って序盤に敗れるイメージが強く初優勝力士が多い印象があります。(最近に限って言うと3年連続で関脇が優勝し初優勝が3人中2人)
引用元:魁ノ進 / 荒れる春場所と呼ばれる考えられる理由と起源
いろいろな時代、「4横綱」体制がありましたが、「4横綱全員が序盤で総崩れ」ということがありました。それが昭和28年春場所です。
当時の4横綱、昭和28年春場所は、こんな感じでした。
- 第36代・羽黒山 全休
- 初日から休場
- 第41代・千代の山 1勝5敗9休
- 2日目から4連敗で6日目から休場
- 第42代・鏡里 10勝5敗
- 2日目・4日目と黒星、さらに終盤に3つ星を落とす
- 第40代・東富士 12勝3敗(準優勝)
- 2日目・4日目と黒星、以後、白星。13日目負けるも、結果、12勝3敗で準優勝
ちなみに、この場所の優勝は、14勝1敗で大関・栃錦が優勝しました。
この昭和28年春場所は、休場者も含め、4横綱は序盤振るわず。
しかし、結果、優勝は大関・栃錦、横綱・東富士は準優勝となりました。
昭和28年春場所は、4横綱が序盤不振だったものの、優勝は大関・栃錦(のちに横綱)、横綱・東富士は準優勝ですから、これをもって「荒れる春場所」とするのは無理があるのではないでしょうか。
結局、荒れる春場所は・・・
結局…
- いろいろ調べた結果は、「荒れる春場所」の元となった出来事は良く分からない
これが結論です。
次に、「荒れる春場所」を次の通り定義することにします。それは…
- 春場所は、上位陣が勝てずに、上位陣以外の力士が優勝する頻度が、他の月に比べて多い
- 上位陣の定義
- 定義1:横綱・大関
- 定義2:横綱・大関・関脇
- 定義3:横綱・大関・関脇・小結
- 上位陣の定義
次の項目では、この定義にあった「荒れる春場所」が正しいのかどうかを調べました。
「荒れる春場所」は正しいのか?
調査対象。
1980年1月場所から2025年1月場所までの271場所(うち、2場所は開催無し)のうち、269場所について詳細に調べました。
定義3〜場所毎に「前頭が優勝した場所数」を調べる
定義3、すなわち、前頭以外(横綱+三役)を上位陣と定義し、上位陣以外、すなわち前頭が優勝した場所数を調べました。
対象は、過去269場所です。
- 1月場所優勝回数 4回
- 3月場所優勝回数 3回
- 5月場所優勝回数 3回
- 7月場所優勝回数 4回
- 9月場所優勝回数 4回
- 11月場所優勝回数 2回
結果、春場所(3月場所)は、他の場所より前頭が多く優勝すると言えません。つまり…
- 定義3の場合、「荒れる春場所」は成立しません
定義2〜場所毎に「前頭か小結が優勝した場所数」を調べる
定義2、すなわち、前頭と小結以外を上位陣と定義し、上位陣以外、すなわち前頭あるいは小結が優勝した場所数を調べました。
対象は、同じく過去269場所です。
- 1月場所優勝回数 4回
- 3月場所優勝回数 4回
- 5月場所優勝回数 6回
- 7月場所優勝回数 4回
- 9月場所優勝回数 5回
- 11月場所優勝回数 5回
結果、春場所(3月場所)は、他の場所より前頭が多く優勝すると言えません。つまり…
- 定義2の場合、「荒れる春場所」は成立しません
定義1〜場所毎に、「前頭か小結か関脇が優勝した場所数」を調べる
定義1、すなわち、前頭と小結と関脇以外を上位陣と定義し、上位陣以外、すなわち前頭、小結、あるいは関脇が優勝した場所数を調べました。
対象は、同じく過去269場所です。
- 1月場所優勝回数 9回
- 3月場所優勝回数 8回
- 5月場所優勝回数 8回
- 7月場所優勝回数 7回
- 9月場所優勝回数 9回
- 11月場所優勝回数 3回
結果、春場所(3月場所)は、他の場所より前頭が多く優勝すると言えません。つまり…
- 定義1の場合、「荒れる春場所」は成立しません
結局・・・
以上より…
- 上位陣が勝てない、優勝できないことを持って荒れる春場所とするのには無理がある、真実では無い
ということが分かりました。
おまけ〜過去46回の春場所の優勝者を列挙しました
せっかく調べたので書きます(笑)。
過去44回の春場所(八百長事件で中止の場所を除く)の優勝者一覧です。
なお、関脇・小結・前頭が優勝力士だった場所には綠マーカーを引いています。
- 2024年 前頭・尊富士 13勝2敗
- 2023年 関脇・霧 島 12勝3敗
- 2022年 関脇・若隆景 12勝3敗
- 2021年 関脇・照ノ富士 12勝3敗
- 2020年 横綱・白 鵬 13勝2敗
- 2019年 横綱・白 鵬 15勝
- 2018年 横綱・鶴 竜 13勝2敗
- 2017年 横綱・稀勢の里 13勝2敗
- 2016年 横綱・白 鵬 14勝1敗
- 2015年 横綱・白 鵬 14勝1敗
- 2014年 大関・鶴 竜 14勝1敗
- 2013年 横綱・白 鵬 15勝
- 2012年 横綱・白 鵬 13勝2敗
- 2011年 ★八百長問題により場所中止
- 2010年 横綱・白 鵬 15勝
- 2009年 横綱・白 鵬 15勝
- 2008年 横綱・朝青龍 13勝2敗
- 2007年 大関・白 鵬 13勝2敗
- 2006年 横綱・朝青龍 13勝2敗
- 2005年 横綱・朝青龍 14勝1敗
- 2004年 横綱・朝青龍 15勝
- 2003年 大関・千代大海 12勝3敗
- 2002年 横綱・武蔵丸 13勝2敗
- 2001年 大関・魁 皇 13勝2敗
- 2000年 前頭・貴闘力 13勝2敗
- 1999年 大関・武蔵丸 13勝2敗
- 1998年 大関・若乃花 14勝1敗
- 1997年 横綱・貴乃花 12勝3敗
- 1996年 横綱・貴乃花 14勝1敗
- 1995年 横綱・曙 14勝1敗
- 1994年 横綱・曙 14勝1敗
- 1993年 小結・若花田 14勝1敗
- のちの横綱・若乃花
- 1992年 大関・小 錦 13勝2敗
- 1991年 横綱・北勝海 13勝2敗
- 1990年 横綱・北勝海 13勝2敗
- 1989年 横綱・千代の富士 14勝1敗
- 1988年 横綱・大乃国 13勝2敗
- 1987年 大関・北勝海 12勝3敗
- 1986年 関脇・保 志 13勝2敗
- 1985年 大関・朝 潮 13勝2敗
- 4代目朝潮
- 1984年 大関・若嶋津 14勝1敗
- 1983年 横綱・千代の富士 15勝
- 1982年 横綱・千代の富士 13勝2敗
- 1981年 横綱・北の湖 13勝2敗
- 1980年 横綱・北の湖 13勝2敗
まとめ
今年の春場所(3月場所)、早々に横綱・大関の勝ちっぱなしが無くなり、「荒れる春場所」ということを見聞きするようになりました。
筆者 TOPIOも、過去記事で春場所について「荒れる春場所」と何回か書いた覚えがあります。
そこで、ふと考えました。
- 「荒れる春場所」って、そもそもいつから、どういう理由で言われるようになったのか?
- 春場所は、他の場所と比べて、本当に荒れる(上位陣が勝てない!)のか?
これらを調べることにしました。
結果は、読んでいただいた通り…
- 「荒れる春場所」と言われる確固たる事由が見当たらない
- 春場所が他の場所に比べて、荒れる(=上位陣が勝てない!)ということは無い
ということが分かりました。
さて、今年の春場所、中日が終わって、横綱・大関陣の成績は次の通り。
- 新横綱・豊昇龍 5勝3敗
- 大 関・大の里 7勝1敗
- 大 関・琴 櫻 5勝3敗
より具体的には、次の力士のなかから優勝が出るでしょう。
具体的な、春場所の優勝予想は、この記事のあとに、しっかり書きます!
なお、「現段階での実質的な優勝争い候補」は★印をつけた8人です。
理由は別記事にて。
【7勝1敗】
- ★大 関・大の里
- ★前頭4・高 安
- 前頭14・美ノ海
【6勝2敗】
- ★前頭6・尊富士
- ★前頭7・玉 鷲
- 前頭11・明 生
【5勝3敗】
- ★横 綱・豊昇龍
- ★大 関・琴 櫻
- ★関 脇・大栄翔
- ★前頭1・若元春
- 前頭9・伯桜鵬
- 前頭11・翠富士
- 前頭12・阿武剋
- 前頭13・獅 司
- 前頭15・安青錦
- 前頭16・朝紅龍

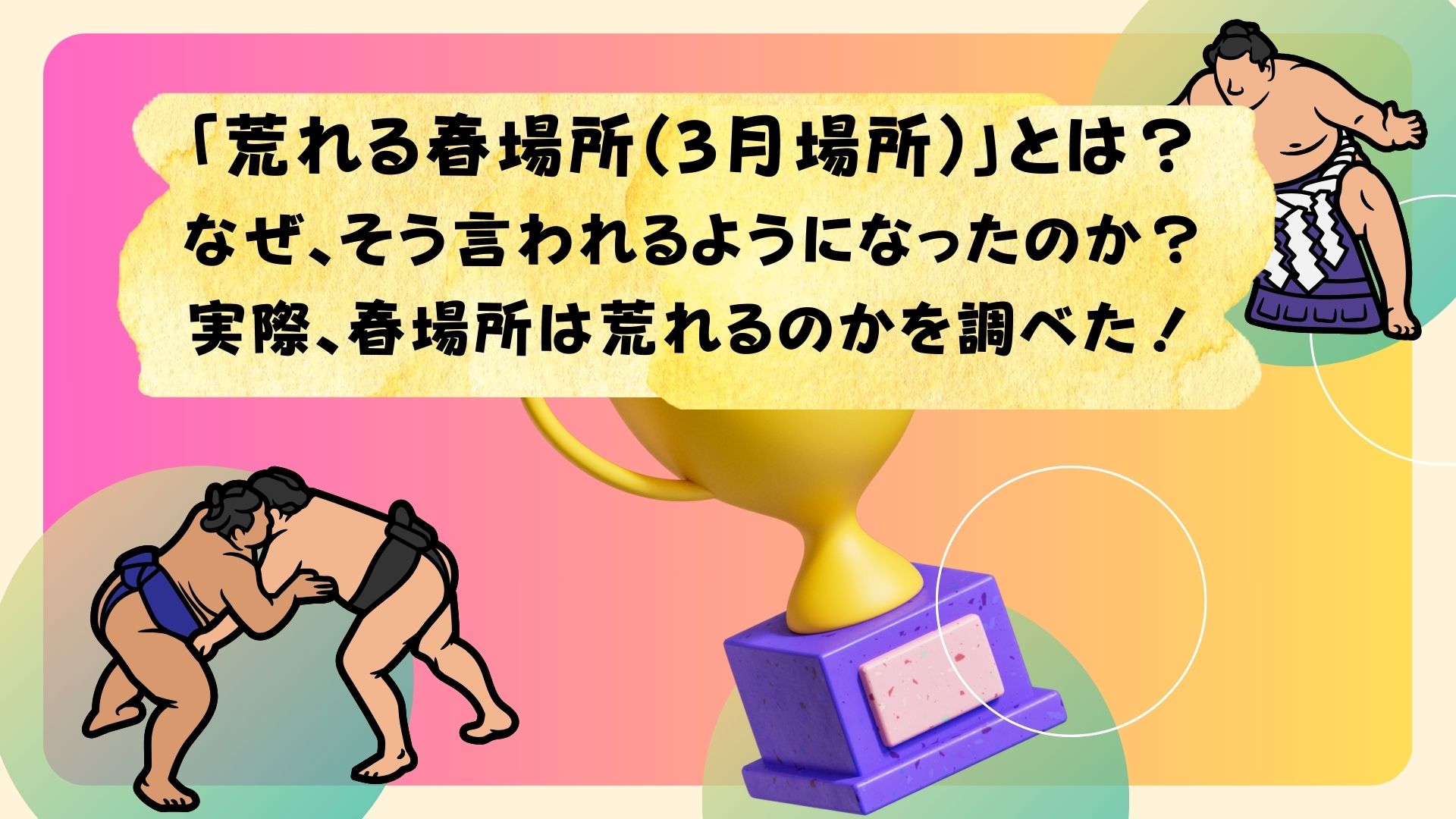
コメント