


大の里にとって、5月場所は
「横綱昇進挑戦場所」なんだって。
ほんとに横綱になれるのかな?



3月場所は優勝したけど、
微妙な取り口が多いよね。
強さは本物なのに、見えない「壁」がありそうですね。
このままじゃ夢の横綱昇進も遠のくかもしれません。
そこで、今回は大の里が横綱昇進を実現するために乗り越えなければならない3つの壁についてまとめました!
- 横綱昇進の条件とは
- 大の里の前に立ちはだかる壁
- ブレイクスルーの鍵とは
なお、5月11日から始まる大相撲5月場所については、次の記事もどうぞ。
大の里のことをいろいろ書きました。
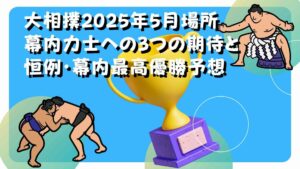
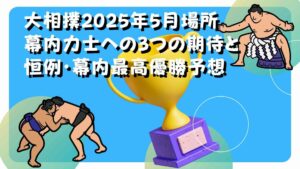
大の里が横綱を目指す理由と今の実力
大の里は、なぜこれほど早く横綱を目指せる位置にいるのでしょうか。
その理由は、彼の並外れた実力と土俵外での姿勢にあります。
彼の現在地を把握することで、どんな壁に直面し、どう乗り越えようとしているのかが見えてくるのではないでしょうか。
以下では、大の里がなぜ横綱を目指すのか、そしてどんな力を持ちながらも、どんな課題を抱えているのかを詳しく見ていきましょう。
大の里は、なぜ横綱を目指すのか
大の里は、石川県河北郡津幡町で誕生。
誕生時、4,036gのジャンボなベビーだったとか。
父親の身長は184cm、母親は165cmということもあって、両親の遺伝子を受け継いだのか大きく育ちました。
幼少からスポーツも大好きで、小学校にあがる頃、父親に「野球がやりたい」と言ったそうです。
相撲経験者の父親は、身体がまだ未熟な息子を見て「足腰を鍛えるために相撲を習わせる」ことにしました。
そうやって、大の里は小学一年生から相撲を始めました。
大の里が小学一年生で入った地元・津幡町少年相撲教室では、父が自らまわしを着けて指導。
他人の子の手前でしょうか、父は息子には特に厳しく接したようです。
それでも、大の里は相撲を続けます。
相撲の強い中学ということで、県外である新潟県の中学校を、大の里自らが選択。
このあたりから、「相撲で強くなる」という意識が大の里のなかに確実にあったわけです。
その後は、新潟県の高校に進学し、日本体育大学に進学します。
大学での戦績は次の通り。
- 1年時
- 国体、相撲競技成年の部、個人戦優勝
- 全国学生相撲選手権大会、学生横綱
- 3年時
- 全日本相撲選手権、アマチュア横綱
- 4年時
- ワールドゲームズ無差別級、金メダル
- ワールドゲームズ重量級、銀メダル
- 国体、相撲競技成年の部、個人戦優勝(連覇)
- 流行病で中2年は相撲競技開催無し
- 全日本相撲選手権、アマチュア横綱(連覇)
4年時には、「大相撲の幕下10枚目格付出」の資格を取得し、卒業を控えた3月には、二所ノ関部屋入門が決まりました。
_/_/_/
ここまで、大の里の相撲の履歴をまとめました。
きっかけは相撲経験者の父親の影響でしたが、それは決していやいやではなく、好きで続けたことは明らか。
県外の中学進学も自らの選択。
そして、大学での抜群の戦績。
恵まれた体躯だけで成し遂げる戦績ではありません。
そこには、人知れぬ努力の積み重ねがあったことと推測。
それも「好き」だからこそ。
つまり、「好き」が大の里の土台にあったのです。
相撲大好きな大の里は、「子どもたちの憧れになるような力士に」と思い、語るようになります。
その先には、大相撲の頂点、横綱があることは間違いありません。
相撲大好きな大の里にとって、大相撲の頂点を目指すのは、ごく自然な流れだったのです。
大の里のいまの強さの根拠
大の里のように学生横綱のタイトルを獲得して大相撲界に入門した力士はたくさんいます。
Wikipediaの「学生横綱」情報によると、これまでに37人の学生横綱が大相撲界に入っています。
そのなかで、三役以上(小結・関脇・大関・横綱)になったのは14人。
また、横綱まで登り詰めたのは第54代横綱・輪島だけです。
ちなみに、大関までになったのは現大関・大の里を含め、7人。
- 横綱・輪 島(日大)
- 大関・朝 潮(近代)
- 大関・琴光喜(日大)
- 大関・正 代(東農大)
- 大関・御嶽海(東洋大)
- 大関・大の里(日体大)
(※表示は入門順)
さらに、現在、幕内・十両で活躍している力士は、7人。
- 西前頭10・正 代(東農大)
- 東十両1・御嶽海(東洋大)
- 東十両12・水戸龍(日大)
- 出身国:モンゴル
- 東 大 関・大の里(日体大)
- 東前頭6・欧勝馬(日体大)
- 出身国:モンゴル
- 東前頭8・阿武剋(日体大)
- 出身国:モンゴル
- 西十両1・草 野(日大)
(※表示は入門順)
さて、そんな学生横綱たちのなかでも、大の里は、圧倒的な「立ち合い」が武器だ。
初土俵からわずか1年4カ月。
幕内昇進後に3回の幕内最高優勝を飾り、この5月場所では新横綱昇進挑戦が目前にある。
ここまでの華々しい活躍は、強靭なフィジカルに支えられた立ち合いと、土俵際での粘りにある。
具体的には、初動のスピードが速く、相手に先手を許さない。
さらに押しの強さは幕内上位力士にも引けを取らない。朝乃山や霧馬山といった実力者相手にも、互角以上の相撲を取っている。
大の里が、これからの大相撲界を牽引する逸材であることは間違いない。
大の里のいまの危うさ
もう、大相撲ファンは感じて居るであろう、大の里には「安定感」に欠ける一面がある。
突進力は申し分ないが、一方で相手にいなされたときの対応がまだ粗い。
もっというと、立ち会いの力強さも冷静に観察すると「いまいち」かもしれない…。
特にベテラン力士との取り組みでは、引き技を誘われて落ちる場面も多々ある。
また、体調面の不安も小さくない。
急成長に伴い、腰や膝への負担も増しているかもしれない。
現代相撲のスピードと重圧に耐えきれるのか。
その見極めは、昇進審議委員会の目にも留まるポイントとなるだろう。



大の里の凄さも課題も、両方見えてきたね
大の里が横綱昇進で直面する3つの壁
順調に見える大の里のキャリアにも、大きな壁が立ちはだかっている。
ここで取り上げる3つの壁は、いずれも過去に他の力士を苦しめてきたものばかり。
いかにしてこれを乗り越えるかが、横綱昇進への分かれ道になる。
次からは、これら3つの壁について、それぞれ深掘りしていく。
壁1、豊昇龍の横綱昇進と不振
勢いだけでは、横綱にはなれない。
豊昇龍もかつて「次期横綱」と呼ばれた若手の星だった。
だが、昇進が現実味を帯びたとたんに成績が乱れ始め、期待がプレッシャーに変わってしまった。
新横綱で迎えた3月場所は、途中休場というていたらく!
5月場所前も腹痛で一時稽古が出来なかったとか…。
これは大の里にとって、他人事ではない。
連続優勝や準優勝が求められる中で、一度の不調が昇進を白紙にしかねない。
それほど、横綱昇進の道は厳しく繊細なのだ。
しかも、肝心なことは、横綱昇進してから継続的に強さを維持することなのだ。
豊昇龍の昇進事例が、大の里昇進に際して、マイナスに影響する可能性は大いにあるのかもしれない。
反論を恐れずに書くと、底上げ状態で推敲すると日本相撲協会としても痛い目に遭う・・・ということだ。
壁2、二所ノ関部屋の不祥事と大の里の関わり
力士個人の実力だけでは、土俵に立てない。
大の里が所属する二所ノ関部屋では、過去に若い力士への指導をめぐる問題が報じられたことがある。
本人が直接関与したわけではないが、こうした「部屋の空気」や外部の目は、昇進に大きく関わる。
なぜなら、横綱は「品格・力量・実績」がセットで問われる存在だからだ。
つまり、土俵外での環境や部屋の透明性も、評価の一部となる。
本人の努力ではどうにもならない部分。
それが壁になるとき、どう乗り越えるかが問われる。
壁3、琴風がいう「毒まんじゅう」の懸念
強くなったときこそ、誘惑が近づく。
NHKの大相撲解説者で元関脇・琴風が語る「毒まんじゅう」とは、出世街道に乗った若手力士が外部の甘い誘惑に足を取られることを指す。
より具体的に言うと、不用意な引き技だ。
3月場所の大の里の取組を振り返ると、かなりの回数、引き技を使っている。
それは勝ちに結びつくものもあれば、負けの敗因になったものもある。
大の里が横綱になって、活躍し続けることを実現するためには、この毒饅頭は大の里のためにはならない。



横綱って、勝ち方も求められるよね
大の里がブレイクスルーするための3つの鍵
壁はあるが、超えられないものではない。
大の里が横綱になるために必要なのは、「地道な努力」と「冷静な判断」、そして「明確な目標設定」である。
ここでは、それぞれの壁にどう立ち向かうべきか、具体的な方向性を示す。
次に、それぞれのブレイクスルーの鍵を、順を追って確認していこう。
壁1の対処、5月場所の優勝ラインは14勝以上
結果が、すべてを動かす。
横綱昇進に必要な条件は、明文化されていないが「2場所連続優勝」または「優勝+準優勝」が基本線とされる。
特に、大の里のような新鋭には、文句なしの成績が求められる傾向がある。
だからこそ、5月場所での目標は明確だ。14勝以上の成績を残し、優勝争いの中心にいること。
それが昇進審議委員会への最強のアピールになる。
「内容も求められる」と言われるが、まずは“勝つこと”。
その土台の上に技術や品格が乗ってくる。
_/_/_/
事前の情報では、5月場所、大の里が優勝しなくても12勝の準優勝ならば横綱昇進もあり・・・などという甘い関係者の話も聞こえてくる。
筆者 TOPIOを含めて、多くの大相撲ファンたちが、大の里の5月場所後の新横綱昇進を望んでいるが、それは単に、新横綱が誕生すればいいということでは無い。
強い横綱、強くありつづける横綱を望んでいる。
確かに、豊昇龍の横綱昇進前3場所の勝ち星合計は33勝という低レベルだった。
そして、新横綱場所でのていたらく。
私たち大相撲ファンは、弱い横綱の実現を望んではいない!
だからこその、14勝以上での横綱昇進を期待しています。
壁2の対処、二所ノ関部屋の運営態勢のクリア化
土俵外の印象が、土俵内の評価を左右する。
過去の事例を見ても、部屋全体の印象が昇進に影響することは否定できない。
だからこそ、二所ノ関部屋は再発防止策や部屋内の運営方針を明確に外部へ伝えていく必要がある。
大の里本人も、リーダー的な立場として「自分が変える」という姿勢を示せば、部屋全体の印象改善につながる。
力士としての強さだけでなく、人格も磨かれる。
品格とは、自分の言葉で未来を語れる力士に宿る。
壁3の対処、「引き技」の封印
攻める姿勢が、横綱にふさわしい。
大の里は時折、立ち合いで形勢不利になると「引き技」に逃げる傾向がある。
これは勝敗を分ける選択肢としては正しいが、横綱を目指す者としては“美しくない”とされることがある。
特に昇進が議論される時期は、内容も問われる。
たとえ1敗しても、前に出る姿勢を貫く方が評価につながる。
実際、かつての稀勢の里も「勝ち星より内容」で昇進を勝ち取ったと言われている。
相撲は勝負であり、美学でもある。それを証明する覚悟が求められる。



勝ち方まで考えてこそ、本物の横綱候補だね!
まとめ 大の里の横綱挑戦とブレイクスルー
今回は、大の里が横綱昇進を実現するために乗り越えなければならない3つの壁についてまとめました!
- 大の里が横綱を目指す理由
- 横綱昇進を阻む3つの壁
- 壁をブレイクスルーする3つの方向性
大の里が横綱を目指す中で直面する課題や、乗り越えてきた困難をまとめました。特に5月場所での14勝以上や、部屋運営の透明化など、具体的な打開策にも触れています。



大の里がどんな壁を越えてきたのかがよくわかったね
彼の挑戦から学べることがきっとあります。今後の取り組みにも注目してください。


コメント