来年の番組編成にともない、かつては人気のあった番組のいくつかが来年3月に終了することが発表されています。
この記事では、それぞれの終了の背景などを分析して、それらの共通項を探ります。
そして、その共通項から導き出される「人気番組終了の裏にある本当の恐慌」を勝手に考えてみて、それをコンパクトにまとめました。
来年3月終了の番組とその共通の背景について
本記事公開日現在、来年3月で終了が発表されている番組は次の4つ。他にもあるかもしれませんが、有名どころをピックアップしました。
終了予定の番組
- 「行列のできる相談所」(日本テレビ系列)
- 長年にわたり視聴者に親しまれてきたこの番組は、視聴率の安定や話題性を維持してきましたが、来年3月で幕を閉じる予定です。
- 「ワイドナショー」(フジテレビ系列)
- 松本人志が出演するこの番組も終了が予定されています。松本氏の性加害疑惑や訴訟問題が影響している可能性が指摘されています。
- 「だれかtoナカイ」(フジテレビ系列)
- 旧名「まつもtoナカイ」
- 中居正広が司会を務めるこの番組も終了予定です。視聴率や制作方針の見直しが背景にあるとされています。
- 「世界一受けたい授業」(日本テレビ系列)
- 教育バラエティ番組です。堺正章さんが校長役、くりぃむしちゅーの上田晋也さんが教頭役、有田哲平さんが学級委員長役を務め、多くの視聴者に親しまれてきました。
番組終了背景の共通項
- 視聴率や制作費の問題
- テレビ業界全体で視聴率の低下が続いており、制作費の削減が求められる中、長寿番組の終了が相次いでいます。特に、若年層のテレビ離れや配信サービスの台頭が影響しているとされています。
- 出演者のスキャンダル
- 松本人志の性加害疑惑やフワちゃんの不適切発言問題など、出演者のスキャンダルが番組のイメージに影響を与えた可能性があります。特に松本氏に関しては、訴訟取り下げ後も批判が続いており、テレビ業界内での世代交代を求める声も上がっています。
- 時代の変化とコンプライアンスの強化
- 過去には許容されていた表現や演出が、現在のコンプライアンス基準にそぐわないとされるケースが増えています。松本人志の「いじり」やフワちゃんの自由奔放なキャラクターも、時代の変化に対応しきれなかった部分があると指摘されています。
番組個別の詳細
行列のできる相談所
1. 視聴率の低下
「行列のできる相談所」は、かつては20%を超える高視聴率を誇っていましたが、近年では視聴率が低下し、平均6%台にまで落ち込んでいます。視聴者のライフスタイルやメディア視聴習慣の変化が影響しています。
2. 出演者のスキャンダルと影響
レギュラーだったフワちゃんのスキャンダル問題も番組終了の遠因になったのかもしれません。
3. 時代の変化と競争の激化
動画配信サービスの普及により、地上波バラエティ番組の競争が激化しています。特に若年層をターゲットにしたコンテンツが増え、視聴者層の多様化が進んでいます。
4. 番組内容の変遷
番組は法律相談からバラエティ色の強い内容へとシフトしましたが、視聴者の期待に応えきれず、マンネリ化が指摘されています。
5. 番組の役割の終焉
長年にわたり視聴者に親しまれてきたものの、番組としての役割を果たしたと判断され、終了が決定しました。
ワイドナショー
1. 視聴率の低下
「ワイドナショー」は、かつての高視聴率から大きく低下し、最近では3.3%にまで落ち込んでいます。裏番組との競争も激化しており、視聴率の回復が難しい状況です。
2. 出演者のスキャンダルと影響
松本人志の降板やスキャンダルが番組のイメージに影響を与え、視聴者離れを加速させました。
3. 番組の役割の終焉
11年間続いた番組は、一定の役割を果たしたとされ、終了が決定しました。
だれかtoナカイ
1. 視聴率の低下
視聴率の低下が続き、他の人気番組との競争に苦戦しています。
2. 出演者のスケジュールと問題
松本人志の活動休止や中居正広とのコンビが番組の魅力の一部でしたが、スケジュールの問題や出演者の変更が影響しました。
3. 番組の役割の終焉
番組はその役割を果たしたとされ、改編期に合わせて終了が決定しました。
世界一受けたい授業
1. 視聴率の低下
番組開始当初は安定して10%台後半の視聴率を記録していましたが、近年では7~8%程度に落ち込んでいます。ただし、これは現在のテレビ業界全体の視聴率低下を考慮すると「決して悪い数字ではない」とも言われています。
2. 時代の変化と競争の激化
同じ時間帯には、テレビ朝日の「池上彰のニュースそうだったのか!!」など、同ジャンルの教育・情報番組が放送されており、視聴者層が分散していることも影響しています。また、配信サービスの台頭により、テレビ離れが進んでいることも無視できません。
3. 出演者の高齢化とスケジュール問題
堺正章さんは現在77歳と高齢であり、体力的な問題が指摘されています。また、くりぃむしちゅーの多忙なスケジュールも影響している可能性があります。
4. 番組の役割の終焉
番組関係者は「レギュラー番組としての役目を果たした」と述べており、一定の役割を終えたと判断されたようです。終了後も特番として放送される予定があるため、完全に消えるわけではありません。
テレビ視聴の減少
ここ10年スパンくらいでテレビ視聴が減少してきたという統計などをピックアップしてみました。
1. 総視聴率(PUT/HUT)の減少
- **PUT(総個人視聴率)やHUT(総世帯視聴率)**は、テレビを視聴している人の割合を示す指標です。この数値は過去10年間で大幅に減少しています。
- 例えば、ゴールデンタイム(19~22時)のHUTは、この四半世紀で約20%減少しました。
- 特に2020年以降、視聴率の下落ペースが加速しており、2023年にはPUTが過去最低水準に達しています。
2. 若年層のテレビ離れ
- NHKの調査によると、10代や20代の若年層ではテレビ視聴時間が顕著に減少しています。
- 10代の平均視聴時間は2020年に1時間を下回り、16~19歳では「ほぼテレビを見ない」と答えた割合が約半数に達しました。
- 20代でもテレビ保有率が低下しており、単身世帯では約7割がテレビを所有していないというデータもあります。
3. 全体的な視聴時間の減少
- 総務省のデータによると、2000年から2020年にかけて、テレビの平均視聴時間は全世代で減少傾向にあります。
- 特に50代以下の層で顕著で、10年間で視聴時間が大幅に短縮されています。
- 2020年の調査では、国民全体で1日にテレビを見る人の割合が79%に減少しました(2010年比で減少)。
テレビ視聴者減少の背景
テレビ視聴者減少の背景です。
1. インターネットと動画配信サービスの台頭
- NetflixやYouTube、Amazon Prime Videoなどの動画配信サービスが普及し、テレビ視聴の代替手段として利用されています。
- 2023年には、ストリーミングサービスの視聴時間が全体の38.7%を占め、従来のテレビ(地上波・ケーブル)の視聴割合を初めて上回りました。
- 特に若年層では、SNSや動画配信サービスが主要な情報源となっており、テレビのニュースや番組を見る必要性が低下しています。
2. ライフスタイルの変化
- 朝や夜のテレビ視聴時間が減少し、その代わりに睡眠や身の回りの用事、インターネット利用に時間を費やす傾向が見られます。
- また、テレビを「ながら視聴」するケースが増え、SNSやスマートフォンと併用する形での利用が主流になっています。
3. 全体的な視聴時間の減少
- 若年層を中心に、テレビを所有しない世帯が増加しています。
- 例えば、29歳以下の世帯主がいる家庭では、約20%がテレビを所有していないというデータがあります。
- チューナーレステレビ(インターネット接続専用テレビ)の普及も進んでおり、従来のテレビ放送を視聴しない層が増えています。
明らかな事実から導かれること?
以上より、テレビ視聴が今以上に盛んになることは「無い」と断言していいでしょう。
つまり、テレビを見なく人は、今以上に多くなるということです。これから導かれることは明らか。
地方局からまずテレビ局時代が傾き始めます。統廃合が起こるでしょう。
そして、テレビに関わる人たち、「テレビ局で働く社員たち」「テレビ制作外注を受ける人たち」「テレビに出演する人たち」「テレビ局にコマーシャルを流す人たち」「ドラマをつくる人たち」の働き方が急激に変化するということです。
ものすごく個人的なことですが、筆者 taoの家族は3人。テレビは4台。1台はリビング。このリビングのテレビは朝、時計代わりにつけているだけで、番組は家人の誰も見ません。
そして、残り3台のテレビは、私を含め家人それぞれの部屋にあり、すべてAmazonのFireTVを接続して、それぞれにVOD(ビデオ・オン・デマンド)やYouTube動画を見ています。家族揃ってテレビを見るシーンなどはここ数年なくなりました。
実は、VODやYouTubeもテレビ画面で見るよりも、スマホやタブレットで見ることが多いですね。自宅はWi-Fiが通っているので、どこでも見られる。
このような状況、周りの知り合いに聴くと、だいたい同じような感じですね。
みんなが見なくなるのですから、テレビ局で働く人たちや、番組制作をする人たち、テレビに出る人たちは仕事なくなりますね。また、テレビをみんなが見なくなるので、テレビ番組にCMを投入する企業もなくなりますね。
そうそう、我が家では、どうしてもテレビ番組見たいなというときは、個々人がリアルタイム視聴するのではなく、たいがい「TVer」で見ますね。それもスマホやタブレットで。
_/_/_/
つまり、テレビをみんなが見なくなるという傾向は、不可逆的であり、割けられない。要するに、大量の失業者、転職者を生むということです。
同じような流れで、新聞関係も同じ…ではないでしょうか。
まとめ
かつては人気のあった番組のいくつかが、来年の番組改編にともない3月で終わる。
それをきっかけに、テレビのことを勝手な切り口で考えてみました。
結論的には、ここ数年でテレビ関係で大量の失業者・転職者を生むのではということです。
ラストにまた個人的なことですが、筆者 taoがテレビをじっくりみたのは、記事を書く必要があったので「THE W 2024」のファイナルを最初から最後まで見た数時間だけです。
これも、記事を書く必要がなく、それでも興味があった場合は、後日ゆっくりスマホでTVerすればよかったのです。
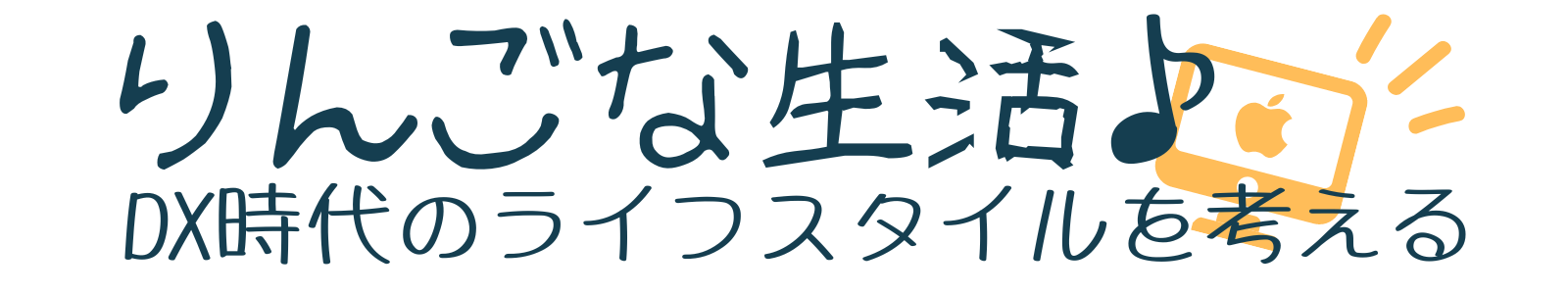
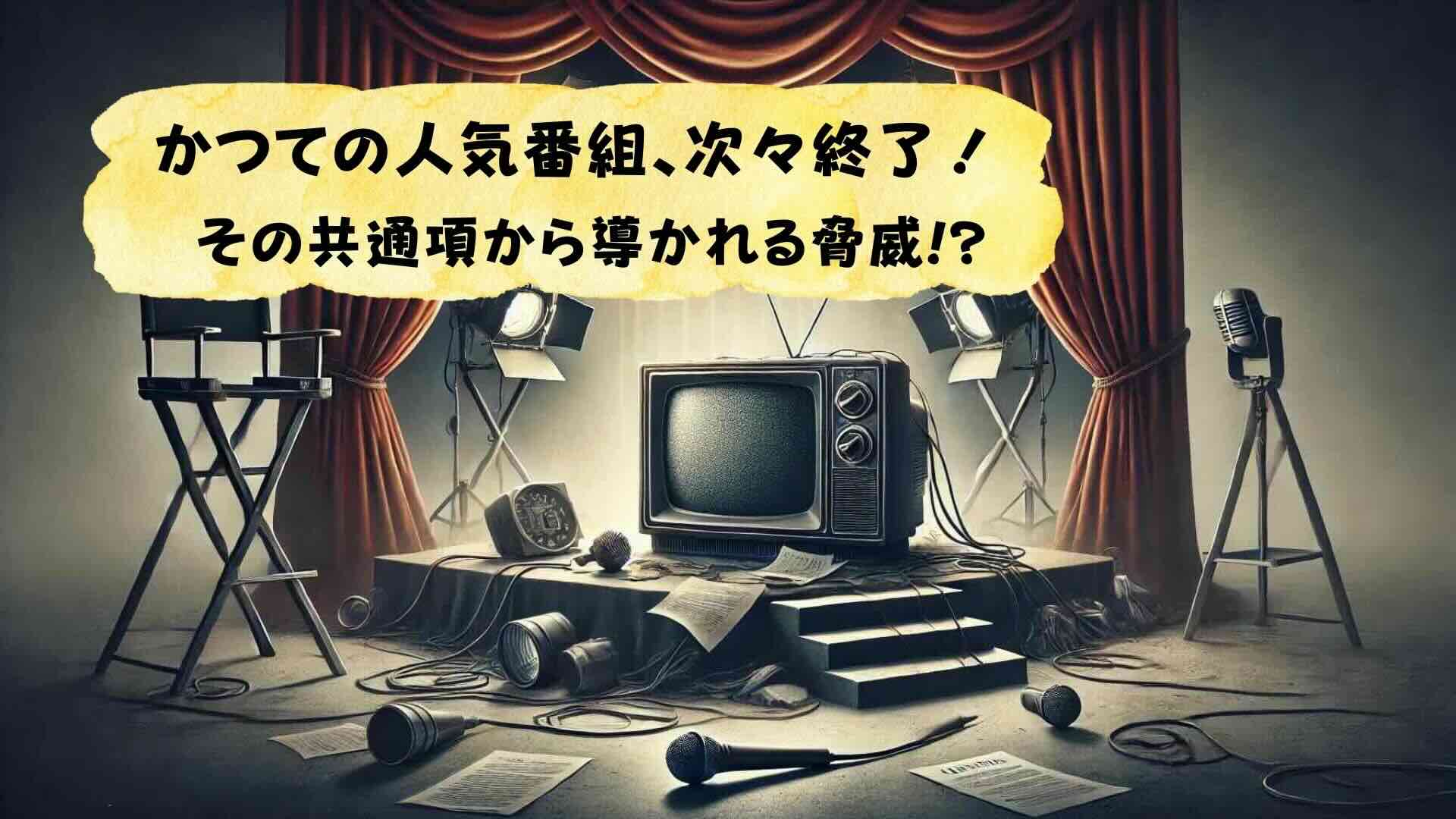
コメント