NHK連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロイン・松野トキを演じる髙石あかりさんと、そのモデルとなった小泉八雲の妻・小泉セツさん。
一見すると異なる時代に生きた二人の女性を深く結びつけるのが、セツさんの回想録『思ひ出の記』と、作品の根底に流れる「化ける」というテーマです。
この記事では、この「化ける」というキーワードが、セツさんの波乱に満ちた生涯、ドラマ『ばけばけ』の奥深さ、そして髙石あかりさんの女優としての魅力にどのように共通するのかを、『思ひ出の記』を手がかりに紐解いていきます。
小泉セツ『思ひ出の記』が伝える真実の物語
『思ひ出の記』は、明治期の日本を生きた文豪・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の妻である小泉セツさん自身が、夫との生活や彼女自身の波乱に満ちた生涯を綴った回想録です。
この書物は、八雲の著作に大きな影響を与えたセツさんの視点から、当時の日本の文化や生活、そして異文化間での夫婦の絆が描かれた貴重な一次情報源となっています。
激動の時代を「化け」て生き抜いた小泉セツの半生
朝ドラ『ばけばけ』の主人公・松野トキは、この実在の人物、小泉セツさん(1868-1932)をモデルに描かれています。セツさんは松江藩の士族の家に次女として生まれましたが、明治維新による家禄の喪失により困窮しました。
11歳からは家計を助けるために機織り職人として働き、18歳で婿養子を迎えるも、夫が出奔し22歳で離婚を経験します。その後、松江に赴任してきた外国人英語教師ラフカディオ・ハーン(後の小泉八雲)の住み込み女中となり、やがて彼と結婚し、三男一女をもうけました。
セツさんの人生は、士族の娘から職人、離婚経験者、外国人の家の女中、そして文豪の妻兼創作パートナーへと、激動の時代の中で何度も自身を「化け」(変身させ)なければならなかった、まさに「変化」の連続でした.
小泉八雲とセツを繋いだ「ヘルンさん言葉」の絆
セツさんの夫となった小泉八雲は、アイルランド系ギリシャ生まれの新聞記者、紀行文作家、日本研究家です。
八雲は日本に来て英語教師として教鞭を執り、日本語を学びましたが、二人の間には、八雲が話す片言の日本語である「ヘルンさん言葉」があり、セツさんはこれを正確に理解し、夫婦間の意思疎通を可能にしました。
八雲は西洋人でありながら、日本の古い映画や文化を愛し、武士道にも魅了されるなど、日本文化を深く愛した人物でした.
『怪談』誕生の裏側:「語り部」としての小泉セツの貢献
小泉セツは、八雲の日本語理解を助けただけでなく、彼の著述活動を支える上で極めて重要な存在でした。
幼い頃から昔話や民話、伝説を聞いて育った物語好きなセツさんは、八雲の創作活動において単なる妻ではなく、「語り部」であり「リテラリーアシスタント」として不可欠なパートナーでした。
八雲はセツさんに、書物から得た物語であっても、本を見ずにセツさん自身の言葉で語る「語り部」であることを要求し、セツさんはそれに応じました。
これにより、彼女の語り口が八雲の作品に独自の温かみと信頼性を与え、特に『怪談』の誕生に大きく貢献したのです.
髙石あかりに宿る「化ける」才能:セツとの深い共鳴
『ばけばけ』というタイトルが示す「化ける」というテーマは、物語の核心にあります。モデルとなった小泉セツさんが、時代の波の中で自身を何度も「化け」させながら生き抜いたように、ヒロインの松野トキもまた、多様な変化を経験するでしょう.
そして、この物語を体現する髙石あかりさん自身も、役柄によって全く違う顔を見せる「カメレオン女優」として評価されています。
彼女は役に憑依し、完全にその人物になりきる没入型の演技スタイルで知られており、制作統括からも「ばけていく魅力」があると評されています。
髙石さんの持つ「自然体」で「誠実」な演技スタイルは、『思ひ出の記』から浮かび上がる、強く、しなやかで、創造性豊かなセツさんの人物像を表現するのに適していると言えます。
セツさんの多岐にわたる人生と、ドラマのテーマ、そして髙石さんの女優としての特質が、「化ける」という一つの言葉で完璧に共鳴しているのです.
まとめ
小泉セツが激動の明治時代を「化ける」ことで生き抜き、文豪・小泉八雲の創作を支えた物語。
そして、その人生を演じる髙石あかりさんの「カメレオン女優」としての才能は、見事に重なり合っています。
彼女の「自然体」で「誠実」な演技が、セツさんの人間的な魅力と強さを引き出し、視聴者に深い感動を与えることでしょう。
『思ひ出の記』に記されたセツさんの言葉と人生は、髙石あかりさんの演技を通して、現代に生きる私たちに新たな息吹とともに届けられます。

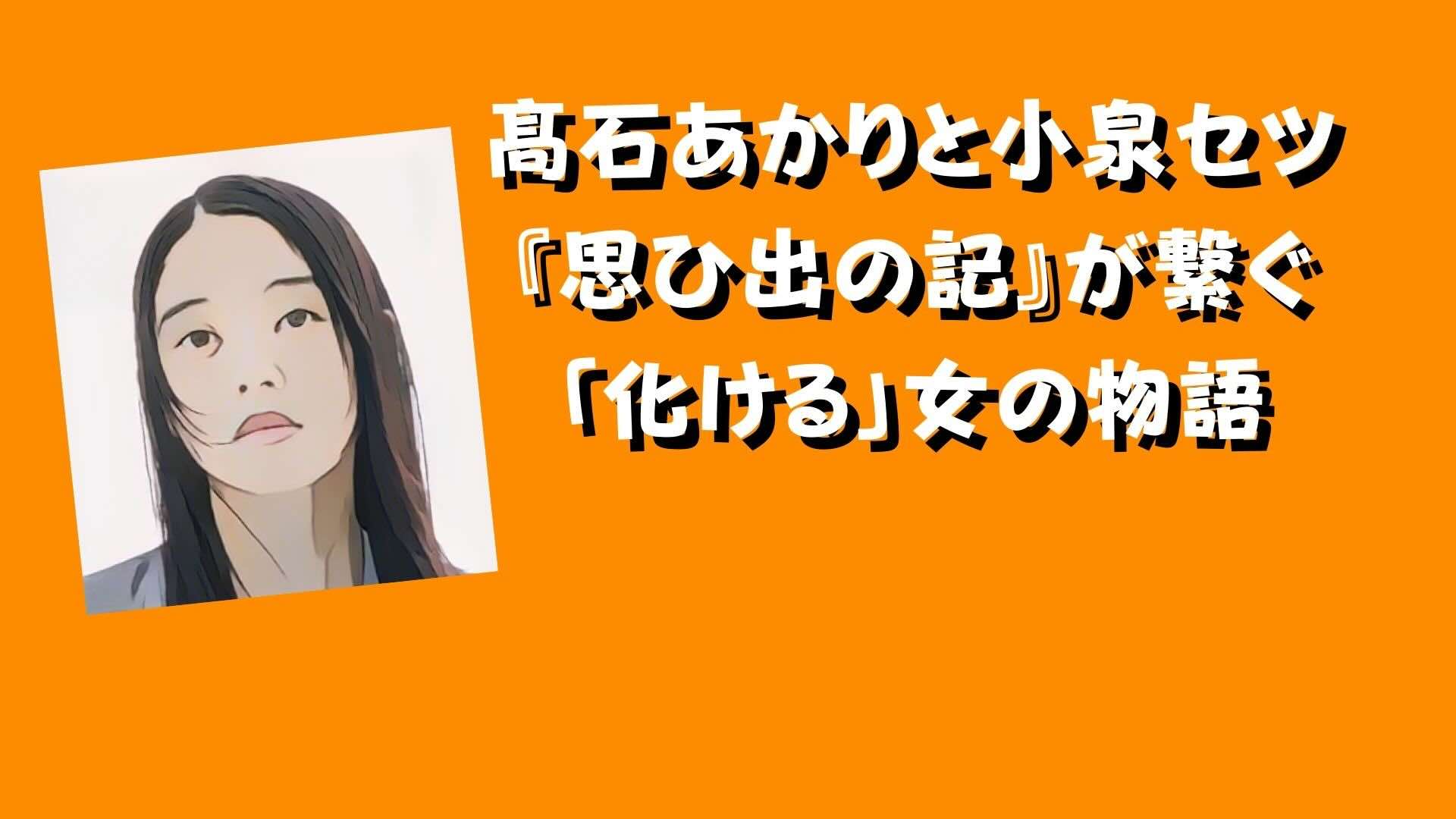

コメント