2025年、読売新聞、朝日新聞、日経新聞といった日本の大手新聞社が、アメリカの生成AI大手「Perplexity(パープレキシティ)」に対し、相次いで著作権侵害を理由に提訴に踏み切りました。
「なぜChatGPTやGeminiではなく、Perplexityが集中的に狙われているの?」 「Perplexityって、他のAIと何が違うの?」
多くの人が抱くこの疑問。実は、その理由はPerplexity特有の「仕組み」に隠されています。この記事では、Perplexityが提訴された背景を、その仕組みや他のAIとの違いから分かりやすく解き明かしていきます。
- なぜ新聞社がPerplexityだけを提訴したのか、その核心的な理由
- PerplexityとChatGPTなど他のAIとの仕組みの決定的な違い
- 今回の提訴がAIとメディアの未来に与える大きな影響
大手新聞社によるPerplexity提訴の概要
2025年8月、日本の大手新聞3社が相次いでPerplexityを東京地方裁判所に提訴しました。各社の提訴内容は以下の通りです。
読売新聞(2025年8月7日提訴)
- 請求内容:
- 記事利用の差し止めと、約21億7000万円の損害賠償。
- 主張:
- 約12万件の記事や画像が無断で取得・利用され、著作権(複製権、公衆送信権)を侵害されたとしています。
朝日新聞・日本経済新聞(2025年8月26日に共同提訴)
- 請求内容:
- 記事利用の差し止めと、各社22億円(合計44億円)の損害賠償。
- 主張:
- 読売新聞と同様に、記事コンテンツの無断利用による著作権侵害を主張。報道機関のビジネスモデルを揺るがす「ただ乗り」行為であると厳しく批判しています。
このように、日本のジャーナリズムを代表する企業が足並みを揃えて法的措置に踏み切ったことで、生成AIと著作権の問題は新たな局面を迎えています。
Perplexityとは?「会話型検索エンジン」の仕組み
Perplexityは、一見するとChatGPTのような対話型AIに見えます。しかし、その本質は「会話型検索エンジン」です。
- ChatGPT/Gemini:
- 膨大な学習済みデータをもとに、AIが文章を「生成」して回答する。
- Perplexity:
- ユーザーの質問に対し、リアルタイムでWebをクロール(巡回)し、複数の情報源から内容を要約・再構成して回答する。
Perplexityの最大の特徴は、回答と同時に情報源のリンク(引用元)を示す点です。これにより、ユーザーは情報の正確性を確認しやすく、「AIの嘘(ハルシネーション)」が起きにくいと評価されてきました。
しかし、この「Webから情報を集めて要約する」という仕組みこそが、今回の提訴の引き金となったのです。
なぜ提訴された?問題視される3つのポイント
大手新聞社側が問題視しているのは、主に以下の3点です。
ポイント①:記事の「丸写し」に近い要約
Perplexityが生成する回答が、元記事の内容をほぼそのまま抜き出したような、創造性のない「丸写し」に近い要約になっているケースが指摘されています。
これは、著作権法で保護される表現を無断で複製していると見なされる可能性があります。
ポイント②:不十分な引用元表示
回答に引用元リンクが表示されるものの、それが記事のどの部分に基づいているのかが不明確です。
結果として、ユーザーはPerplexityの回答だけで満足してしまい、新聞社のサイトを訪れなくなります。
これは、メディアが広告収入などを得る機会を奪う「ただ乗り(フリーライド)」行為だと批判されています。
ポイント③:有料記事への無断アクセス疑惑
最も深刻なのが、本来は有料の会員登録をしなければ読めないはずの記事を、Perplexityが要約して提示している事例が報告されていることです。
これが事実であれば、新聞社のビジネスモデルの根幹を揺るがす重大な著作権侵害となります。
ChatGPTやGeminiはなぜ提訴されていないのか?
では、アメリカ生成AI大手のOpenAI(ChatGPT)やGoogle(Gemini)は、なぜ、同様の提訴を免れているのでしょうか。
それは、両者の仕組みとビジネス方針の違いにあります。
仕組みの違い
OpenAI(ChatGPT)やGoogle(Gemini)などは、あくまで「学習データ」をもとに回答を生成します。
特定のサイトからリアルタイムで情報を丸ごと取得し、要約するわけではありません。(※Webブラウジング機能もありますが、その動作はPerplexityとは異なります)
メディアとの連携
OpenAI(ChatGPT)やGoogle(Gemini)は、メディア企業とのパートナーシップを積極的に進めています。
コンテンツ利用料を支払う契約を結ぶことで、著作権問題をクリアしようと動いているのです。
Perplexityの場合
一方、Perplexityはメディアとの対話よりも技術的な優位性を優先しているように見え、結果として法的な対立構造を生んでしまいました。
著作権法から見る論点とメディアの危機感
日本の著作権法では、AI開発のための情報収集や学習(インプット)は、著作権者の利益を不当に害しない限り、原則として許可されています。
しかし、今回の問題はAIが回答を生成・利用する(アウトプット)段階の話です。AIの回答が元記事の表現に酷似しており、かつメディアの収益機会を奪うのであれば、それは著作権侵害にあたる可能性が高い、というのが新聞社側の主張です。
新聞社にとって、時間とコストをかけて制作した記事は大切な資産です。その資産が無断で利用され、収益化の機会まで奪われることになれば、報道機関としての存続が危ぶまれます。今回の提訴には、質の高いジャーナリズムを守るための防衛策という側面が強くあります。
この訴訟はどこへ向かう?AIと共存する未来への試金石
今回の訴訟は、単なる一企業の著作権侵害問題を越えて、「生成AIとコンテンツホルダーがどう共存していくべきか」という大きなテーマを社会に突きつけています。
考えられる今後の展開は、
- ケース1 / 和 解:
- Perplexity側がメディアに対価を支払う形で和解する。
- ケース2 / 判 決:
- 司法の場で著作権侵害の有無が判断され、今後のAI開発のルール形成に大きな影響を与える。
- ケース3 / 法整備:
- 現行法では対応しきれないと判断され、新たな法整備やガイドライン策定の動きが加速する。
いずれにせよ、この訴訟の結果は、Perplexityだけでなく、すべての生成AIとメディアの関係性を方向づける重要な一歩となるでしょう。
Perplexity提訴についてのFAQ
Perplexity提訴についてのFAQ(よくあるQ&A)をまとめました。
Q1. Perplexity側の主張はどうなっていますか?
A1. Perplexityは自社の仕組みを「インターネットをよりアクセスしやすくするためのもの」と位置づけています。著作権侵害の意図はなく、情報源へのトラフィックを促進していると主張していますが、メディア側との見解には大きな隔たりがあります。
Q2. 私たちがPerplexityを使うこと自体に法的なリスクはありますか?
A2. 現時点では、個人がPerplexityを日常的に利用することで直ちに法的責任を問われる可能性は極めて低いです。問題となっているのは、サービスを提供するPerplexity側の事業モデルです。ただし、生成された内容を著作権表示なくコピーして公開するなど、二次利用する際には注意が必要です。
Q3. 海外でも同様の訴訟は起きていますか?
A3. はい。アメリカではニューヨーク・タイムズがOpenAIとマイクロソフトを提訴しています。また、画像生成AIをめぐっても、アーティストやゲッティイメージズなどが開発企業を訴えるケースが相次いでおり、世界的な潮流となっています。
Q4. 検索エンジンによる記事の表示と何が違うのですか?
A4. 検索エンジンは記事のタイトルと短い抜粋(スニペット)を表示し、ユーザーをサイトへ誘導することを主目的としています。一方、Perplexityは記事全体を包括的に要約して回答内で完結させてしまうため、サイトへの誘導が起きにくい点が根本的に異なります。
Q5. なぜ今、一斉に提訴が始まったのですか?
A5. 生成AIの技術が急速に進化し、社会への影響が無視できないレベルになったことが大きいです。特に、有料記事が無断で要約されるなど、具体的な被害が明らかになってきたことで、メディア側も看過できないと判断し、法的措置に踏み切ったと考えられます。
Q6. この問題、最終的にどうなると思いますか?
A6. 多くの専門家は、最終的にはAI企業がメディアに対価を支払うライセンス契約を結ぶ方向に進むと予測しています。司法判断で明確なルールが示される可能性もありますが、ビジネス的な解決(和解や提携)が現実的な落とし所になるとの見方が有力です。
Q7. 提訴によってPerplexityのサービスは停止しますか?
A7. 訴訟の結果次第ですが、直ちにサービスが停止する可能性は低いです。ただし、判決によっては、日本国内でのサービス内容の変更(特定のメディアサイトのクロール停止など)を余儀なくされる可能性はあります。
まとめ
今回は、大手新聞社によるアメリカ生成AI大手・Perplexity提訴のニュースを深掘りしました。
- 提訴の理由:
- PerplexityがリアルタイムでWeb情報を収集・要約し、その過程で著作権を侵害している疑いが強いから。
- 他のAIとの違い:
- 学習済みデータから生成するChatGPTなどに対し、Perplexityは「会話型検索エンジン」としてWebサイトから直接情報を取得する仕組み。
- 問題の核心:
- 記事の丸写し、不十分な引用、有料記事へのアクセス疑惑が、メディアのビジネスモデルを脅かしている。
この一件は、進化し続けるAI技術と、既存の権利やビジネスがどう向き合っていくべきかを示す象徴的な出来事です。
私たちの情報収集のあり方にも関わるこの問題の行方を、今後も注視していく必要があるでしょう。

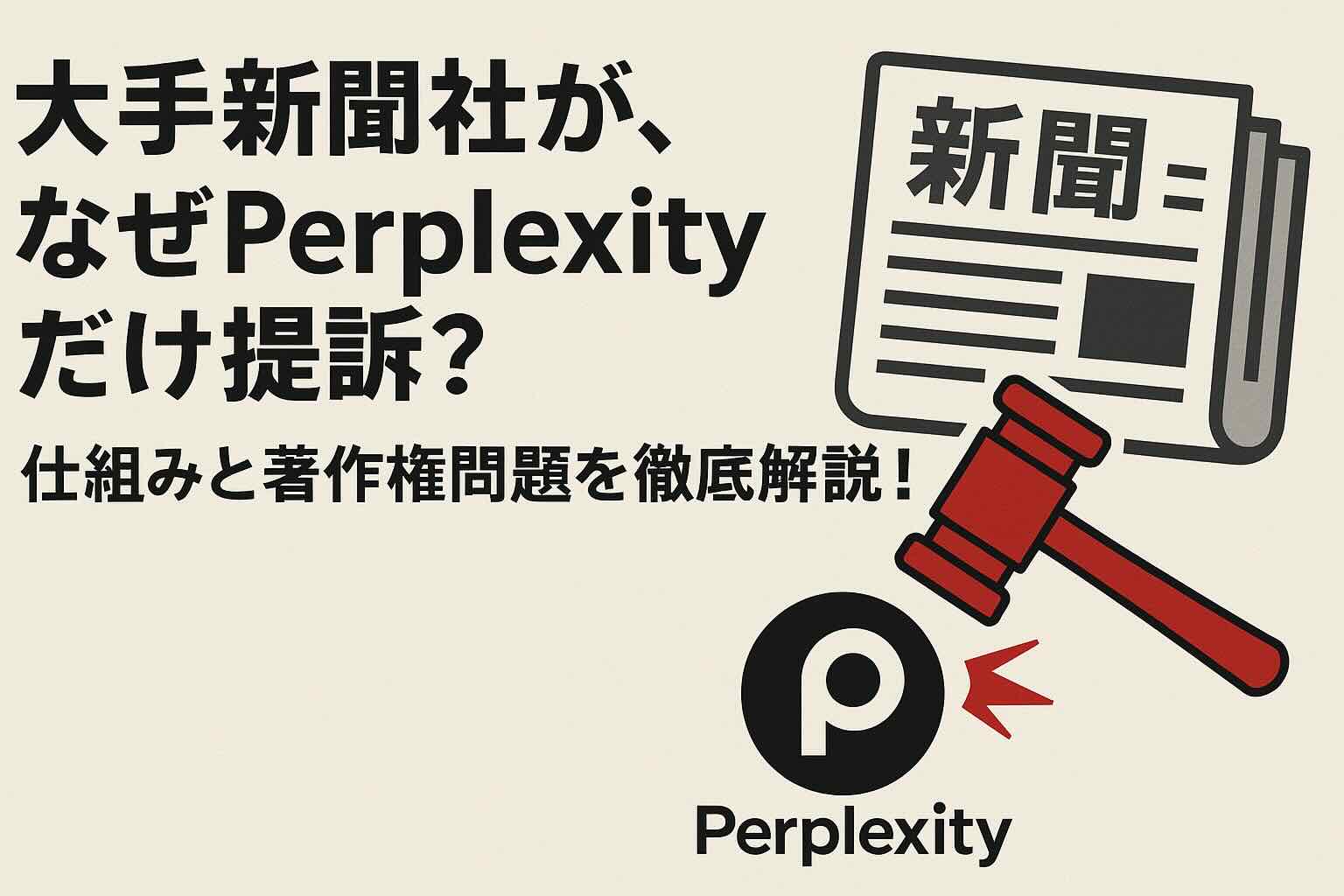
コメント