1969年に国民的大ヒット曲となった『黒ネコのタンゴ』。この曲で日本中の心を捉えた皆川おさむさんが、2025年7月23日に62歳で永眠されていたことが分かりました。
糖尿病を起因とする慢性腎不全という病気と長年闘いながらも、生涯を子どもたちの音楽教育に捧げた皆川おさむさん。
彼の鮮烈なデビューから、表舞台を退いた後の人生、病との壮絶な闘い、そして晩年に子どもたちに残した温かい遺志まで、その波乱に満ちた人生の光と影を深く掘り下げていきます。
国民的大ヒット『黒ネコのタンゴ』誕生の裏側
皆川おさむさんの名を一躍有名にした『黒ネコのタンゴ』は、元々イタリアの童謡が原曲です。
1969年3月に開催されたイタリアの童謡コンテスト「第11回ゼッキーノ・ドーロ」で3位に入賞した『Volevo un gatto nero』(黒ネコがほしかったのに)がその原曲で、当時4歳の少女ヴィンチェンツァ・パストレッリさんが歌い、900万枚ものセールスを記録するヒットとなりました。
このイタリアでのヒット情報をつかんだ日本の音楽関係者は、日本語版の制作を企画。その際、皆川おさむさんに白羽の矢が立ちます。
皆川おさむさんは、伯母である皆川和子さんが主宰する「ひばり児童合唱団」に3歳から所属しており、その合唱団に日本語版リリースのオファーが来たことがきっかけでした。特別なオーディションもなく、皆川おさむさんが歌い手としてあっさり決定したといいます。
日本語の歌詞は、見尾田みずほさんが原詞の翻訳ではなく独自に作詞し、小森昭宏さんが編曲を担当しました。
皆川おさむさんの舌足らずながらも一度聞いたら忘れられない愛らしい歌声と、原曲のタンゴのリズム、どこか哀愁を帯びた短調のメロディー、そしてネコを恋人に見立てた洒落た歌詞が絶妙に融合。この「大人びた楽曲」と「子どもらしい歌声」というギャップが聴く者に強烈なインパクトを与え、空前の大ヒットへとつながりました。
このヒット規模は当時としては驚異的で、1969年10月5日にシングルレコードが発売されると、オリコンチャートでなんと14週連続1位を記録。累計売上枚数は公式発表で223万枚以上、一説には260万枚に達したともいわれています。
皆川おさむさんが初めて1位を獲得した時の年齢は6歳10ヶ月で、これはオリコン史上、現在に至るまで破られていない最年少1位獲得記録です。
当時、童謡のレコードは物品税(※1940年[昭和15年]から1989年[平成元年]3月31日まで贅沢品を対象とした物品税法が施行されていました)が非課税扱いでしたが、あまりのヒットに東京国税局が「これは本当に童謡なのか?」と調査に乗り出し、試聴会の結果「童謡である」と認定されたという逸話も残っています。
『黒ネコのタンゴ』大ヒット以降の芸能活動と転身
『黒ネコのタンゴ』の爆発的ヒットにより、皆川おさむさんは歌番組のみならず、テレビドラマや映画『恋の大冒険』などにも出演し、一躍日本で最も有名なお子さんとなりました。
彼の成功は、当時の日本の音楽業界に「子供歌手ブーム」という新たなトレンドを生み出し、各レコード会社は競って子供歌手をデビューさせました。
森あきよさんの『ドラネコのゴーゴー』や、斉藤浩子さんの『おへそ』、さらにアメリカから来たジミー・オズモンドさんの日本語曲『ちっちゃな恋人』なども大ヒットしました。
しかし、このブームは幼い子どもたちを過度な商業主義に巻き込むという負の側面も持ち合わせていました。皆川おさむさん自身も、後に「当時は忙しすぎて記憶がほとんどない」と語っているほどです。
思春期を迎え、子ども特有の高音が出なくなる「声変わり」が訪れると、皆川おさむさんは潔く歌手活動の一線から退くことを決意されました。
彼はその栄光に安住することを選ばず、次に選んだ道は音楽の学術的な探求でした。洗足学園音楽大学(当時は短期大学)に進学し、歌ではなく「打楽器」を専攻されました。
この選択からは、彼が単なる人気者ではなく、一つのイメージに縛られまいとする強い意志と多才さがうかがえます。
大学卒業後も、彼は音楽の世界から一旦離れ、インダストリアルデザイナー(工業デザイナー)として一般企業に就職した時期もありました。スターダムから退き、学問に専念し、一般社会で職を経験するといった彼の多様な経験は、その後の人間性を豊かにし、指導者としての深みへと繋がっていったことでしょう。
難病「慢性腎不全」との壮絶な闘い
皆川おさむさんの命を奪った直接の病名は「慢性腎不全」でした。62歳という若さでの逝去は、多くの人々に衝撃を与えました。
彼の闘病の原点は、長年にわたる持病であった糖尿病です。50歳を過ぎてから体調不良に悩まされ、自身も「糖尿病で腎臓を悪化させて、人工透析を受けていた」と明かしていました。糖尿病は、高血糖状態が続くことで腎臓の微細な血管が傷つき、血液をろ過する機能が失われる「糖尿病性腎症」を引き起こします。
絶望的な状況の中、皆川おさむさんに希望の光が差したのは、約10年以上前(2012年頃)のことです。実の姉である坂井礼子さんが腎臓のドナーとなることを決意し、「命の絆」とも呼ぶべき生体腎移植が行われました。手術は成功し、皆川おさむさんは一時的に透析治療から解放され、体調も劇的に回復したといいます。
しかし、移植はゴールではなく、拒絶反応を抑えるための免疫抑制剤の服用は生涯続き、常に感染症のリスクと隣り合わせの生活となりました。
晩年、彼は再び病との激しい闘いに直面します。2024年11月には、持病の糖尿病が再燃し、高血糖のために入院。入院中には、追い打ちをかけるように過去に手術した大腿骨の古傷が感染症を引き起こし、複数回の手術に耐えなければなりませんでした。
さらに2025年2月には、軽い脳梗塞も見つかりました。これらの度重なる身体的ダメージにより、姉から受け継いだ大切な腎臓の機能も再び低下し、人工透析に戻らざるを得ない状況となりました。
リハビリ専門病院への転院も計画されていましたが、その願いも虚しく、逝去前日の7月22日には実姉の礼子さんと変わらずメールを交わしていたものの、その夜に容体が急変し、翌23日未明に息を引き取られたとのことです。長きにわたる病との壮絶な闘いの末、静かに人生の幕を閉じられました。
晩年の活動と子どもたちへの遺志
皆川おさむさんの人生の羅針盤であり、実質的な育ての親でもあった伯母の皆川和子さんが2004年に脳梗塞で倒れ、ひばり児童合唱団の運営が困難に陥った際、彼の人生に大きな転機が訪れました。
皆川おさむさんは、長年に渡って和子さんを支えてきた姉の礼子さんと共に、伯母が命をかけて築き上げた合唱団を守ることを決意されます。
そして2014年、皆川和子さんの逝去後、皆川おさむさんは正式に「ひばり児童合唱団」の代表に就任しました。彼が代表として掲げたモットーは「誰もが楽しく歌える合唱団」でした。
自らが幼少期に受けた厳しい指導とは異なり、現代の子どもたちに寄り添い、まずは音楽の楽しさを伝えることに心を砕かれました。表舞台での露出はほとんどありませんでしたが、彼は日本の未来の音楽文化を育むという、地道で、しかし極めて重要な仕事に情熱を注ぎ続けました。
歌手活動としては、1999年には大ヒット曲『だんご3兄弟』のカバーをシングルCDとしてリリースし、2008年にはアニメ『ケロロ軍曹』のエンディングテーマ『ケロ猫のタンゴ』をひばり児童合唱団の子どもたちと共演する形で歌唱されています。最期のテレビ出演は、2020年1月のBSフジ『クイズ!脳ベルSHOW』でした。
昨年2024年に開催された合唱団創立80周年の記念コンサートでは、既に体調が優れない中、客席の隅で子どもたちの歌声にじっと耳を傾けていた皆川おさむさんの姿があったといいます。
生涯独身を貫かれた皆川おさむさんでしたが、彼にとっての「家族」とは、命を繋いでくれた姉の礼子さんとの絆や、育ての親である伯母の皆川和子さんの存在、そしてひばり児童合唱団で共に歌い、成長を見守ってきた子どもたちそのものであったのかもしれません。
彼の人生は、音楽に始まり、音楽に終わる、美しい円環を描いていたのです。
子どもの歌と皆川おさむさんに関する、よくあるQ&A
子どもの歌と皆川おさむさんに関する、よくあるQ&Aをあつめました。本文との重複部分もあります。
Q1: 皆川おさむさんはどのような人物でしたか?
A1: 皆川おさむさんは、1963年1月22日に東京都で生まれ、3歳で伯母の皆川和子が創設した「ひばり児童合唱団」に入団しました。6歳の時、1969年に「黒ネコのタンゴ」でレコードデビューし、260万枚を売り上げる大ヒットを記録。オリコン史上最年少でのシングル1位獲得者となりました。子役としても映画やテレビドラマに出演しましたが、声変わりを機に芸能活動の一線から退きました。その後、洗足学園音楽大学で打楽器を専攻し、卒業後はインダストリアルデザイナーとして活動。2004年には伯母の皆川和子が脳梗塞で倒れたことをきっかけに、ひばり児童合唱団の運営に関わるようになり、2014年の伯母の死去後は合唱団の代表に就任しました。「誰もが楽しく歌える合唱団」をモットーに、子供たちの音楽教育に献身しました。2025年7月23日、慢性腎不全のため62歳で亡くなりました。生涯独身でしたが、姉の礼子さんとの絆は深く、彼女は皆川さんの腎臓ドナーでもありました。
Q2: 「黒ネコのタンゴ」はどのような経緯でヒットしましたか?
A2:「黒ネコのタンゴ」の原曲は、1969年3月にイタリアの童謡コンテスト「ゼッキーノ・ドーロ」で3位に入賞した「Volevo un gatto nero」(黒ネコがほしかったのに)です。この曲の情報を得た日本の音楽関係者が日本語版の制作を企画し、皆川おさむさんが歌うことになりました。日本語詞は原詞の翻訳ではなく、見尾田みずほ氏によって独自に作詞され、小森昭宏氏が編曲を担当しました。皆川さんの舌足らずで愛らしい歌声と、従来の童謡にはない短調のタンゴリズム、そして大人も楽しめる洒落た歌詞が融合し、空前の大ヒットとなりました。1969年10月5日の発売後、オリコンシングルチャートで14週連続1位を記録し、累計223万枚以上の売上を達成。皆川さんは6歳10ヶ月でオリコン史上最年少1位の記録を樹立しました。この大ヒットは「子供歌手ブーム」を巻き起こし、多くの子供歌手がデビューするきっかけとなりました。
Q3: 「ひばり児童合唱団」はどのような合唱団ですか?
A3: 「ひばり児童合唱団」は、1943年に皆川和子さんによって東京都杉並区荻窪で設立された日本の児童合唱団です。当初は皆川和子さんが近所の子供たちに歌唱指導を始めたことから始まり、戦後の1946年に「ひばり児童合唱団」と改名されました。その後、皆川和子さんの転居に伴い、本部が神奈川県横浜市鶴見を経て、現在の東京都目黒区洗足に移転しました。年1回の定期演奏会のほか、アーティストのコンサートへの出演、オペラ、テレビ出演、CM、CDレコーディングなど多岐にわたる活動を行っています。3歳から高校3年生までの子供たちが在籍し、由紀さおり・安田祥子姉妹、松島トモ子、吉永小百合(個人レッスン)[以上、敬称略]など、数多くの著名な歌手や芸能人を輩出しています。皆川和子さんの甥である皆川おさむさんが、2014年の和子さんの死去後、合唱団の代表を務めました。
Q4: 慢性腎不全とはどのような病気ですか?
A4: 慢性腎不全は、腎臓の機能が数ヶ月から数十年かけて徐々に低下していく病気です。腎臓は体内の老廃物を排泄し、水分や電解質のバランスを調整し、血圧の調整や血液を作る指令を出すなど、生命維持に不可欠な役割を担っています。腎機能が半分近くまで低下しても自覚症状が現れにくいことが特徴で、「静かなる殺人者(サイレントキラー)」とも呼ばれます。
主な原因疾患としては、皆川おさむさんのケースのように長期間の高血糖が腎臓の血管を破壊する「糖尿病性腎症」が最も多く(40%以上)、次いで腎臓のフィルターに炎症が起こる「慢性糸球体腎炎」(約25%)、高血圧が原因で腎臓の血管が硬くなる「腎硬化症」(約15%)が挙げられます。症状は腎機能の低下度合いに応じてステージ1から5に分類され、ステージが進むにつれて倦怠感、食欲不振、むくみなどの尿毒症症状が現れ、最終的には透析や腎移植が必要となります。一度失われた腎機能は元に戻せないため、食事療法、薬物療法、そして末期には血液透析、腹膜透析、腎移植といった治療法が選択されます。予防には、糖尿病や高血圧の管理、バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙、定期的な健康診断が重要です。
Q5: 皆川おさむさんはなぜ生涯独身だったのですか?
A5: 皆川おさむさんは生涯独身で、配偶者や子供はいませんでした。結婚しなかった具体的な理由は公にされていませんが、彼の特異な人生背景からいくつかの可能性が推察されます。まず、6歳で国民的スターとなり、華やかな芸能界で幼少期を過ごした経験が、人間関係の築き方やプライベートな関係の構築に影響を与えた可能性があります。また、青年期に大きな挫折を経験した後、より内省的な人生を歩むことを選んだのかもしれません。
最も大きな要因として考えられるのは、彼が晩年心血を注いだ「ひばり児童合唱団」の子供たちへの愛情です。彼は「合唱団の子供たちが、自分の子供のようなもの」と語っており、結婚や家庭とは異なる形で次世代に愛情を注ぐ人生を選んだと考えられます。また、伯母である皆川和子さんも生涯独身を貫き、合唱団の活動に人生を捧げたことから、その影響も考えられます。彼は、血縁関係だけでなく、音楽で結ばれた合唱団という共同体の中で、自らの人生の意義を見出していたと言えるでしょう。
Q6: 昔の子どもの歌と最近の子どもの歌にはどのような変化が見られますか?
A6: 戦後の子どもの歌には明確な変化が見られます。大正時代から昭和20年代にかけては、芸術性を重視し、良い歌を子供に与えようとする傾向が強く、本格的な作曲家が携わっていました(例:「ぞうさん」「めだかの学校」)。これらの歌は日本語の抑揚に即した自然な言葉遣い、ゆったりとしたテンポ、狭い音域、四分音符や八分音符を主体とした落ち着いたメロディーが特徴で、オノマトペ(※自然界の音・声、物事の状態や動きなどを音[おん]で象徴的に表した語)も多用されていました。季節の歌など、昔から歌い継がれている曲にはこれらの特徴が多く見られます。
しかし、それ以降は子供が楽しめることを第一条件に歌が作られるようになり、一流の作曲家が子どもの歌の分野から撤退し、代わりに子どもの歌専門の作曲家やポピュラー音楽の作曲家が登場しました。最近の子どもの歌は、動作や踊りがつけやすいリズミカルなものが多く、歌自体も長尺化し、途中で転調を繰り返す曲も見られます。歌詞は言葉遊びの要素が強く、掛け声が入ることもあります。テンポは速く、歌詞の言葉数も多いため早口で歌う傾向があり、メッセージ性や物語性が強いと感じられます。メディア(特にテレビ)を通じて普及する曲が多く、「ノリが良いけれど、ブームが過ぎれば使い捨てられていく」という消費される傾向も見られます。
Q7: 子どもの歌において、長期にわたって歌い継がれる曲と一時的な流行で終わる曲の違いは何ですか?
A7: 長期にわたって歌い継がれる子どもの歌にはいくつかの共通する特徴があります。まず、季節行事に関する歌が多く、日本語の抑揚に合わせた自然な話し言葉で書かれている点です。全体的にゆったりとしたテンポで、子供が落ち着いて歌えるメロディーが多く、オノマトペ(擬音語・擬態語)が頻繁に使用されています。また、調性もハ長調やヘ長調が多く、子供の声域を考慮した狭い音域で作曲されています。これらの歌は、耳馴染みが良く、子供が安心して歌えるため、世代を超えて親しまれています。
一方、一時的な流行で終わる子どもの歌は、テレビや映画などのメディアと連動してヒットすることが多く、キャラクターのかわいらしさや「ノリの良さ」が重視されます。アップテンポで、歌詞に言葉遊びが多く、ブームが過ぎると忘れ去られやすい傾向にあります。例えば、「ぼくコッシー」や「おしりかじり虫」などがこの傾向に当たります。宮崎駿監督の映画の歌「さんぽ」のように、メディア発でありながら定番化する例もありますが、多くは上映終了後1年ほどで歌われなくなる曲も存在します。親や周囲の大人から直接歌い継がれる「家庭環境」も、歌が定着するかどうかに大きく影響することが、調査結果から示唆されています。
まとめ
『黒ネコのタンゴ』で一世を風靡した皆川おさむさんの生涯は、まさに波乱万丈という言葉に尽きます。
6歳で国民的スターダムに駆け上がり、声変わりと共に表舞台を退かれ、青年期には挫折も経験されました。しかし、彼はそこから立ち上がり、長年にわたる慢性腎不全との壮絶な闘いを続けながらも、最終的には自らを育ててくれた音楽の世界、特に子どもたちのための音楽教育へと回帰されました。
晩年は「ひばり児童合唱団」の代表として、未来を担う子どもたちに歌うことの喜びと素晴らしさを伝えることに、その人生の全てを捧げられました。
皆川おさむさんの人生は、私たちに成功とは何か、幸福とは何か、そして挫折からいかにして立ち上がるべきかを、静かに、しかし力強く問いかけています。
心よりご冥福をお祈りいたします。
更新メモ:20250727 30 08

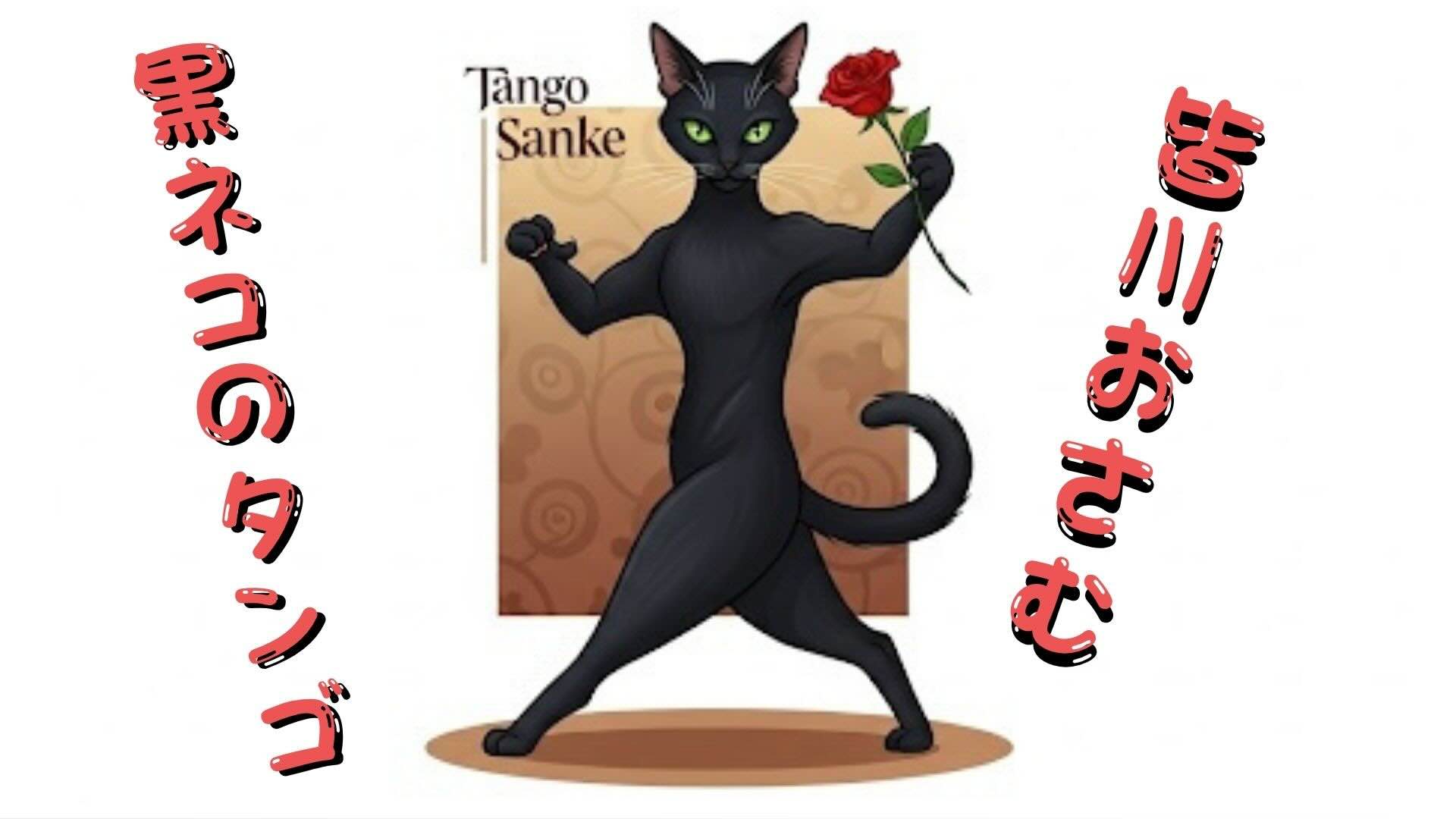
コメント