秋風が吹き抜け、角界の注目が令和七年大相撲九州場所へと移る中、角界の未来を背負う第75代横綱・大の里が、その真価を問われる場所を迎えます。
先場所(2025年9月場所 – 秋場所)において、大の里は横綱昇進後初となる、通算5度目の幕内最高優勝を果たしました。
特に、ライバル横綱・豊昇龍との息詰まる16年ぶりとなる横綱同士の優勝決定戦を制した姿は、「怪物の証明」 にふさわしい劇的な幕切れでした。
しかし、最高位に立つ者には、歓喜の余韻に浸る暇はありません。次に彼に課せられるのは、横綱としての連続優勝という、さらなる重い責務です。強さを見せつけた先場所の土俵裏には、克服すべき数多くの課題も垣間見えました。
この九州場所で、大の里の連続優勝を阻む「壁」とは何でしょうか?本記事では、先場所の激闘と、最新の角界情勢を徹底分析し、大の里関が直面する七つの具体的な障壁と、それを乗り越えるための鍵を詳細に解説します。
- 大の里が九州場所で連続優勝できない具体的な可能性を理解できます。
- 九州場所という特異な舞台で、大の里関の成功を妨げる七つの障壁を知り、より深い知識を持って相撲を追いかけられます。
- 大の里が横綱としてさらなる成長を遂げるために何を改善すべきか、今後の展望を把握できます。
大の里、九州場所で連続優勝なるか?注目の焦点を整理
先場所の本割と優勝決定戦から見える「強みと弱み」
横綱・大の里は、2025年秋場所において13勝2敗で五度目の幕内優勝を果たしました。
この優勝の最大の功績は、千秋楽の決定戦で見せた「素早い切り替え」と「心理的回復力」です。
本割では、豊昇龍に「一気に押し出され」て「惨敗」とも呼べる内容で敗北し、優勝が一度手からこぼれ落ちました。
しかし、わずか数分のうちに、師匠である二所ノ関親方(元横綱・稀勢の里)からの「淡々といきなさい」という助言 を胸に、冷静さを取り戻し、決定戦では豊昇龍の投げをしのいで寄り倒し、勝利を掴みました。
この土壇場での精神力は、横綱としての最大の「強み」と言えます。
一方で、技術的な「弱み」も指摘されています。
大の里は、新横綱として経験した先場所の「苦しい経験」(名古屋場所での11勝4敗) を乗り越えるため稽古に励んだと語り、実際に左手の使い方を「武器化」し、より高度な相撲への変貌を遂げつつあると評価されています。
しかし、以前から指摘されてきた「引き癖」 は依然として残っており、特に右を差せなかった時に引きを選択するのが早すぎるという課題が垣間見えています。
この不安定な相撲の組み立て方は、長期政権を目指す上で解決すべき大きな弱点です。
九州場所の特徴と大の里にとっての意味
九州場所(11月場所)は、一年の大相撲を締めくくる最終の場所であり、福岡国際センターで開催されます。
場所の終盤ということもあり、力士たちは一年間の疲労が蓄積した状態で臨みます。
大の里にとって、この九州場所は「横綱としての連続優勝への挑戦」の舞台となります。
大の里の大関昇進は、昨年の九州場所後(2024年11月場所)であり、その新大関としての成績は9勝6敗でした。
これは彼の大関在位中の成績としては最も低い星であり、当時の元2代栃東の玉ノ井親方からは「大関らしくない内容」「体に張りがない」と不安視されていました。
つまり、九州場所は、過去に彼が「壁」にぶつかった経験を持つ因縁の地であるとも言えます。
今回の九州場所では、先場所の劇的な優勝の勢いを維持しつつ、年末の疲労や過去の低迷を乗り越え、真の「強者」として連続優勝を果たせるかどうかが問われます。
大の里の優勝を阻む7つの壁とは?
壁①:横綱・豊昇龍〜「因縁」と土壇場の攻防
先場所・秋場所で、大の里関の前に最後まで立ちはだかったのは、第74代横綱・豊昇龍でした。
星の差1つで先行していた大の里でしたが、千秋楽の本割の取組で、大の里は豊昇龍に敗れ、両者は13勝2敗で並び、平成21年(2009年)秋場所の朝青龍と白鵬以来となる16年ぶりの横綱同士の優勝決定戦を戦いました。
大の里は本割(本章に掲げたYouTube動画を参照ください)では、豊昇龍に「一気に押し出され」るという屈辱的な「惨敗」を喫しており、この敗戦は大の里の脳裏に深く刻まれているはずです。
大の里は、豊昇龍とこれまでに10戦して、3勝7敗という戦績です。しかも、3勝のうちの1つは不戦勝。完全に分が悪い状況です。
豊昇龍は、立ち合いの駆け引きや強引な投げ技、そして型にこだわらない万能型の相撲が特徴です。直近のロンドン公演でも大の里関との横綱決戦を制しており、その実力は拮抗以上のものがあります。
大の里にとって、豊昇龍は単なるライバルではなく、技術的にも心理的にも最も乗り越えがたい因縁の相手です。
豊昇龍は先場所の決定戦で敗れたものの、その直前の本割では大の里関を圧倒しており、技術的には「勝っていた」という自負があるでしょう。
大の里が、豊昇龍の予測不能な相撲や投げ技への圧力に屈することなく、「淡々と」 自分の相撲を取り切れるかどうかが、九州場所の最大の焦点となります。
特に、豊昇龍は、大関昇進後、立ち合いの駆け引きや強引な投げ技が影を潜めつつあるという高評価も受けており、横綱としての安定感を増してきているため、さらに手強い存在となっています。
豊昇龍の「土俵上での勝負強さ」 は、九州場所での再度の激突を予感させます。
壁②:新関脇・安青錦〜その急成長と「打倒横綱」の勢い
今場所の九州場所で、大の里にとって最も注意すべき新たな脅威は、史上最速となる所要13場所で関脇に昇進した新関脇・安青錦です。
ウクライナ出身で、初土俵からわずか12場所で三役に到達した安青錦は、破竹の勢いを維持しています。
特に注目すべきは、彼が新入幕から4場所連続で二桁勝利(11勝4敗)と三賞を獲得しているという驚異的な安定感です。
安青錦は、下げた頭を付けての下からの攻めを得意とする右四つ・寄り相撲を基本とし、師匠の安治川親方(元安美錦)譲りの技巧相撲の技術指導を受けています。
その強さは数字にも表れており、豊昇龍には現在2勝0敗と「キラー」としての相性を持ちながら、大の里関には0勝2敗とまだ勝利がありません。
専門家からは、安青錦が豊昇龍を倒し続けることで、結果的に大の里関の一強時代を助長する可能性も指摘されていますが、これは裏を返せば、安青錦自身が「横綱・大の里を倒してこそ大関昇進」という明確な目標を持つことを意味します。
安青錦の「勝つ姿を見せたい」という強い意気込み と、その驚異的なスピード出世の勢いは、大の里が初土俵から所要9場所で大関昇進という最速記録を保持していたこと と比べても遜色なく、新世代の波が横綱に直接襲いかかる形となります。
壁③:大関・琴櫻〜怪我からの復帰と「横綱級」の意地
東大関・琴櫻は、先場所の秋場所14日目に右膝内側側副靱帯損傷により休場を余儀なくされましたが、復帰戦に懸ける思いは強いはずです。
琴櫻は2024年に年間最多勝(66勝)に輝き、大の里が横綱に昇進する直前の場所でも、横綱審議委員会から「横綱に近い風格と落ち着き」と高く評価されていました。
しかし、大関昇進後は8勝7敗が続くなど、安定感を欠く土俵が目立ち、元大関・琴風から「脇役の琴櫻…先代が天国で泣いているぞ」と厳しい指摘を受けるなど、その真価が問われています。
琴櫻にとって、九州場所は、怪我からの完全復活を印象付け、大の里への対抗意識を燃やす絶好の機会となります。
彼が本来持つ、廻しの切り方や下からの攻めの技術、そして2歳からの相撲歴で培った相撲勘 が完全に機能すれば、大の里関の圧力相撲に真っ向から対抗できる数少ない力士の一人です。
先場所、不戦勝という形で勝利を掴みかけた大の里ですが、万全の琴櫻との対戦は、再び激しい火花を散らすこととなるでしょう。
壁④:自身が抱える「引き癖」という技術的課題
大の里の優勝を阻む最大の技術的な壁は、「得意の右を差せなかった時に、引きを選択するのが早すぎる」という、大関昇進前から繰り返し指摘されてきた「引き癖」です。
大の里は、立ち合いの圧力で前に出る相撲(突き・押し、右四つ・寄り)を得意としていますが、その長所が裏目に出て、不利な体勢になると、安易に引き技に頼ってしまう傾向があります。
専門家は、彼の引き方が「自分の方にまっすぐ引くので、呼び込みやすい」と悪さを指摘しており、前に出るべきか、引くべきかの判断の精度が低いことが、彼の相撲が安定しない原因の一つとされています。
師匠である二所ノ関親方(元稀勢の里)も、大関昇進前後に「引かないこと」を課題として挙げており、この癖は、相手に勝機を与える要因となりえます。
特に、技巧派力士や、豊昇龍のように流れを変えるのが得意な相手にとっては、この「引き癖」こそが最大のカウンターチャンスとなるでしょう。
横綱として長期政権を築くためには、不利な体勢からでも引かずに攻める技術、つまり「左と右のバランスをもう少ししっかりやって、右より左の左を武器にして持ってきた」 という、自己分析通りの進化を土俵で証明する必要があります。
壁⑤:上位陣の徹底マークと「研究対策」
横綱・大の里は、初土俵から所要13場所での横綱昇進という、昭和以降最速の記録を打ち立てた「怪物」です。
しかし、スピード出世であるがゆえに、彼の相撲はまだ完成形ではなく、課題や弱点が明確であると、親方衆からも指摘されてきました。
大関昇進後には、同門の親方衆から「稽古が圧倒的に足りない。このままでは必ず怪我をする」と忠告されるなど、稽古量への懸念が繰り返し示されています。
また、武蔵川親方(元武蔵丸)からは、相手に合わせた「遅い相撲」を取る傾向や、「腰高」の癖、押し相撲に弱い点などが指摘されており、上位陣はこれらの弱点を徹底的に研究し、九州場所で対策を練ってくることは確実です。
大の里は、先場所のインタビューで「苦しい経験は二度としたくないと稽古に励んだ」と語っていますが、横綱としての地位は、これまで以上に「追われる立場」 として、常に全力で、かつ完璧な相撲が求められます。
上位陣からの執拗なマークと研究は、彼の持つ爆発的な圧力を封じ込め、連勝をストップさせる要因となり得ます。
壁⑥:九州場所特有の「魔物」とコンディション調整
九州場所は、一年間の激闘の総決算の場です。
9月場所が終わり、巡業(特にロンドン公演など海外巡業)を経て、休む間もなく迎える11月場所は、肉体的・精神的な疲労がピークに達しているでしょう。
豊昇龍も、綱取り場所後の3月場所で途中休場したり、翌5月場所でも怪我で途中休場するなど、横綱に昇進してからのコンディション維持の難しさに直面しています。
大の里もまた、新大関として迎えた2024年の九州場所では9勝6敗と、大関在位中に唯一二桁勝利を逃す結果に終わっており、九州場所との相性に不安を残しています。
横綱として迎える今場所、先場所で見せたような「淡々」とした冷静な集中力 を15日間維持できるかがカギとなります。
特に、横綱という最高位の重圧 に加え、巡業や地方場所特有の調整の難しさが重なることで、場所の序盤からリズムを崩す「魔物」が潜んでいます。
疲労回復と怪我の予防が、優勝戦線に残るための絶対条件です。
壁⑦:ベテラン・髙安の「無冠の執念」と相性
髙安といえば、横綱・大の里土俵入りの太刀持ちをしています。
しかし、2025年九州場所の初日、髙安は太刀持ちを務めることができません。
初日、大の里の取組相手が髙安だからです。
髙安は、元大関であり、35歳というベテランの域に達しながらも、いまだ幕内最高優勝を経験していません。
初優勝への想いは強いものがあります。
それと同時に、今も大関復帰に向けて精進しているといいます。
そんな髙安は、大の里にとって侮れない存在です。
初土俵から所要4場所で入幕した大の里ですが、その後の髙安との対戦は2連敗を喫していました。
初めて勝ったのは三戦目。
それは優勝決定戦での髙安との対戦でした。
大の里自身も、この決定戦では、過去の敗戦を意識しつつ「最後は気持ち」で臨んだことを明かしています。
それ以降の対髙安戦は白星を重ねている大の里ですが、髙安の土俵際の粘りや、左四つからの型に持ち込むうまさは、若き横綱の圧力を封じ込める力を持っています。
髙安は、自らの悲願を叶えるために、九州の土俵で「最後の最後まで必死」の相撲を見せるでしょう。
そのベテランの執念が、若き横綱の連続優勝を打ち砕く可能性は、常に潜んでいます。
九州場所の展望と読者が注目すべき取組
カギを握る“初日〜中日”の流れ
大の里が連続優勝を達成するためには、序盤戦でリズムを掴むことが極めて重要です。
横綱の地位について「あまり考え過ぎずに、いつもどおり、いままでどおり、自分がやることが全てかなと思った」と語った大の里関にとって、場所前の準備と初日の入りが、結果を左右します。
特に、先場所では4日目に初黒星を喫し、中盤まで豊昇龍を「追う展開」となりました。
九州場所では、序盤の平幕や新鋭との対戦で星を落とさず、中日(8日目)までに万全の態勢(8連勝または7勝1敗)を確立することが、後半の上位戦に臨む上での心理的安定に直結します。
初日から中日までの流れが、大の里が横綱の重圧を払拭し、「淡々」とした自分の相撲を取り切るための生命線となるでしょう。
7つの壁をどう乗り越えるか?陣営の戦略予想
大の里がこの七つの壁を乗り越えるための戦略は、師匠である二所ノ関親方の教えを体現した「基礎基本の徹底」と「冷静な技術修正」に尽きます。
- 「淡々」とした心構えの徹底:
- 豊昇龍や髙安との因縁の対戦においても、感情的にならず、師匠から受け継いだ「淡々と」という相撲哲学を実践し続けること。
- 引き癖の克服:
- 右を差せない場合でも、安易に引かず、左のおっつけやハズ押しで攻めながら、次の右差しを伺うという、専門家が指摘する技術改善 を稽古で身につけ、土俵で披露すること。
- 万全のコンディション:
- 九州場所前に懸念される疲労や過去の不調を払拭するため、巡業の疲れを考慮した緻密な体調管理と、足りないと指摘されるスタミナの強化。
特に、秋場所の優勝後に「左手がすごく使えていた」「もっと磨きをかけてやっていきたい」と語ったように、左手を「武器」として昇華させることが、型にはまらない相手や突き押し力士への対抗策となるでしょう。
大の里の優勝を左右する“ライバル力士”一覧
九州場所で大の里関の優勝を左右する、特に注目すべきライバル力士は以下の4名です。
| 番付 | 力士名 | 注目ポイント |
|---|---|---|
| 西横綱 | 豊昇龍 智勝 | 先場所の決定戦での雪辱に燃える最大のライバル。本割で大の里を圧倒した力は健在。 |
| 東大関 | 琴櫻 将傑 | 怪我からの復帰戦。横綱昇進を期待されながら大関で足踏みが続く中、意地と風格を見せられるか。 |
| 東関脇 | 安青錦 新大 | 史上最速で関脇に昇進した新鋭。打倒横綱に燃える「大関コンテンダー」の勢い。 |
| 西小結 | 髙安 晃 | 大の里が本割で未だに勝てないベテラン。無冠の悲願を懸けて、再び優勝争いをかき乱す可能性。 |
横綱・大の里に関するFAQ
- Q1. 大の里関が横綱に昇進するまでのスピード記録は何ですか?
- A1. 初土俵から所要13場所での横綱昇進は、昭和以降最速記録です。新入幕からでは9場所で、これも史上最速記録となります。
- Q2. 大のの四股名の由来は何ですか?
- A2. 大正時代の大関・大ノ里萬助が由来となっており、師匠の二所ノ関親方が出世した際に案に上がった四股名です。
- Q3. 横綱として行っている土俵入りの型は何型ですか?
- A3. 師匠の二所ノ関親方(元稀勢の里)と同じく「雲竜型」を選択しています。
- Q4. 大の里関の出身地はどこですか?
- A4. 石川県津幡町出身です。地元では「津幡町広報特使」も務めています。
- Q5. 2025年秋場所で獲得した懸賞金の総額と本数はどれくらいでしたか?
- A5. 獲得懸賞本数は519本で、獲得金額としては歴代最多を更新しました(3114万円)。
- Q6. 「淡々といきなさい」という言葉は誰の教えですか?
- A6. 千秋楽の決定戦に向かう際に、師匠である二所ノ関親方(元横綱・稀勢の里)からアドバイスされた言葉です。これは師匠の現役時代の相撲哲学そのものでもあります。
- Q7. 大の里が横綱に昇進する前の地位での優勝回数は何回ですか?
- A7. 横綱昇進までに幕内最高優勝を4回果たしており、そのうち小結、関脇、大関の地位で優勝した史上唯一の力士です。
- Q8. 大の里は相撲以外でどのような趣味を持っていますか?
- A8. 公式サイトのプロフィールには書かれていませんが、元横綱白鵬関の話を聞いてから、巡業の空き時間にトレーニングを兼ねてキャッチボールに興じている姿が目撃されています。
- Q9. 大の里関が初土俵を踏んだのはいつですか?
- A9. 2023年5月場所で幕下付け出しとして初土俵を踏みました。
- Q10. 大の里が新横綱の場所(2025年7月場所)で喫した不名誉な記録は何ですか?
- A10. 13日目に西前頭15枚目琴勝峰に敗れた際、新横綱で昭和以降ワーストとなる4個目の金星を配給し、大正以降で横綱が最も番付下位の力士に敗れるという不名誉な記録を作りました。
- Q11. 大の里の父が彼に送ったモットーは何ですか?
- A11. 角界入りした際に父から「唯一無二」の力士を目指すようにと伝えられており、大の里の大関昇進時にもこの言葉が化粧まわしに込められました。
まとめ
- 大の里は横綱昇進後初の連続優勝に挑む。
- 最大のライバルは豊昇龍だが、最速昇進の安青錦や復調を目指す琴櫻も無視できない脅威である。
- 技術的な「引き癖」の克服と、師匠の教えである「淡々と」した心構えこそが、連続優勝の鍵となる。
大相撲九州場所は、横綱・大の里が、横綱としての地位を確固たるものにする上で、極めて重要な試金石となるでしょう。
先場所の劇的な優勝は彼の精神的な強さを証明しましたが、九州の土俵には、ライバル、新鋭の勢い、そして自身が抱える技術的な課題という七つの強大な壁が待ち受けています。
大の里が、師の教えである「淡々と」 の精神を貫き、引かない相撲と左手の進化 を見せることができれば、連続優勝という高みを掴むことができるはずです。
我々ファンは、横綱として新たなステージに立った大の里が、この七つの壁をいかに乗り越え、いかに成長していくのか、興奮をもって15日間を見守っていくことでしょう。

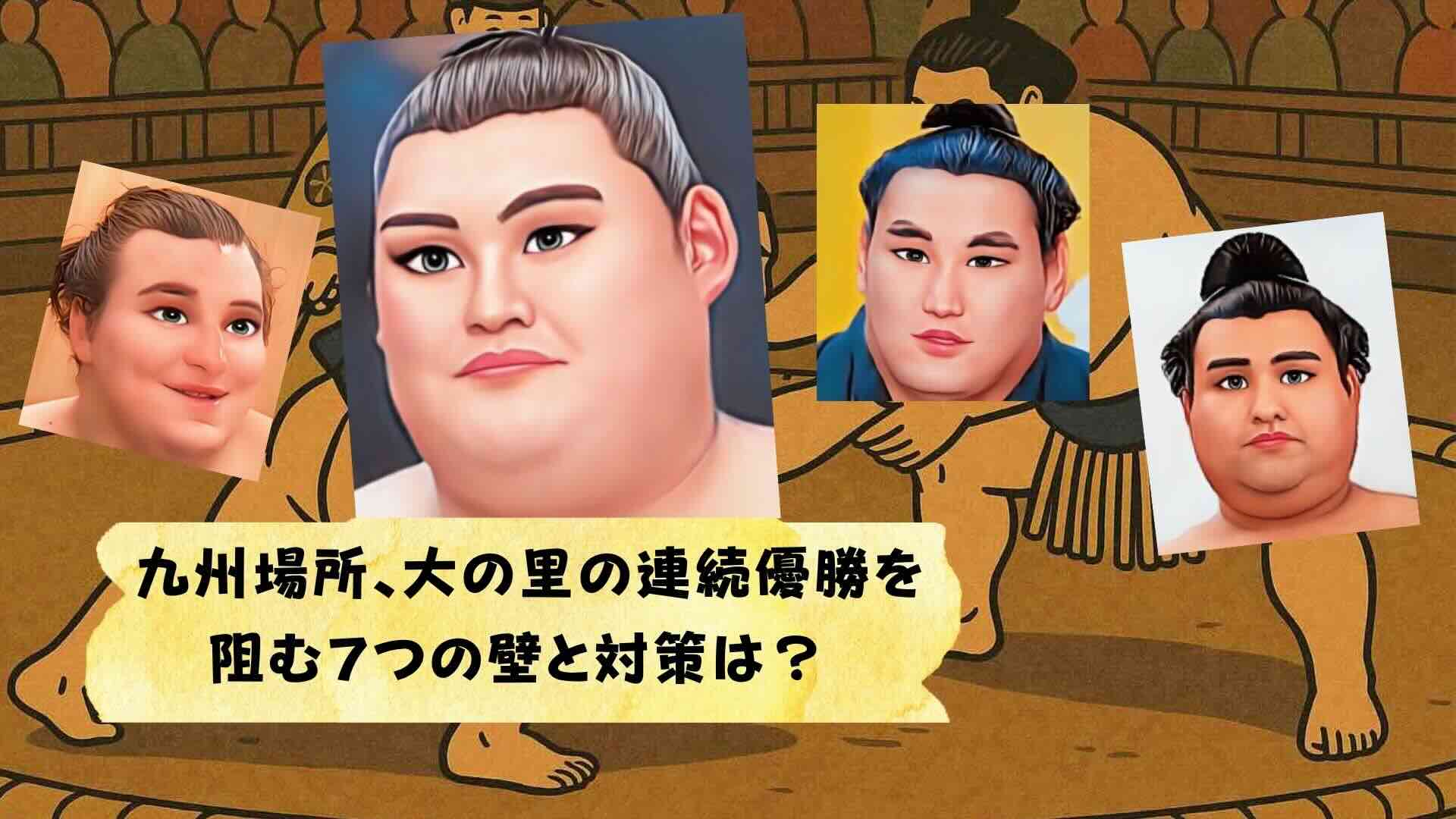
コメント