


マイナ保険証って、結局どうやって使えばいいの?
そんな疑問をお持ちなら、この記事で一発解決。



マイナ保険証の使い方や登録手順、メリットや注意点まで、わかりやすくまとめました。
マイナンバーカードと健康保険証を連携させた“マイナ保険証”は、病院での受付がスムーズになったり、医療費の軽減につながったりと便利な点が多い反面、「事前準備」や「機器の使い方」で戸惑う人も少なくありません。
本記事では、マイナ保険証を使うための登録方法から病院での使い方、注意点までをやさしく解説。
初めてでも安心して使えるよう、最新の利用状況やよくある質問にも触れています。
- マイナ保険証の制度概要と仕組み
- 病院での使い方と準備ステップ
- 登録・設定方法と確認のコツ
- 使うメリットと注意すべきポイント
- よくある質問と不安への対処法
マイナ保険証とは?制度の概要と導入の背景
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる新しい仕組みです。これにより、医療機関での受付や情報共有がよりスムーズになります。
従来の紙の保険証と異なり、カード1枚で本人確認から医療情報の提供までをカバーできるのが特徴です。
制度の狙いは、より効率的な医療提供と本人確認の簡素化です。ただし、導入初期には課題も多く、利用率の伸び悩みが現実としてあります。
では、具体的にどのような点が従来と異なり、どのような仕組みで動いているのか、さらに導入後の利用状況を順に見ていきましょう。
従来の保険証との違いとは?
シンプルな違い、それは「紙」か「ICチップ付きカード」か。
マイナ保険証は、ICチップに医療情報の連携設定がされており、医療機関の受付で専用機器にかざすことで本人確認と保険資格の確認が同時に行えます。紙の保険証のように提示だけで済むものではありませんが、裏を返せば一度の手続きで多くの確認が済む点が利点です。
たとえば、職場で保険証が切り替わった際も、最新情報がオンラインで確認できるため、無効な保険証で診療を受けてしまう心配がありません。
マイナンバーカードとの連携による仕組み
ポイントは「カード単体では使えない」という点です。
マイナ保険証を使うには、まずマイナンバーカードに健康保険証としての利用登録を行う必要があります。これはオンライン(スマホ・PC)や窓口で可能で、設定が済んで初めて医療機関での使用ができる状態になります。
また、カードと本人の情報が紐づけられているため、なりすまし防止や誤診防止にもつながるのが特長です。受付機のカメラによる顔認証または暗証番号入力で本人確認が行われます。
利用率の伸びは鈍い?制度導入後の利用状況を確認
制度のスタート時と比較して、普及率は徐々に伸びているものの、決して急激ではありません。
具体的な利用率の推移は以下の通りです。
- 2024年12月:25.42%
- 2025年1月:25.42%
- 2025年2月:26.62%
- 2025年3月:27.26%
- 2025年4月:未発表
背景には、機器の不備や登録手続きの難しさ、病院側の対応遅れといった課題があります。多くの方が「便利そうだけど、どうやるの?」と感じている状態なのです。
そもそも、マイナカードの普及率自体に問題もありそうです。
マイナンバーカードの普及率は、発行開始から10年目となる現在、人口に対する保有枚数率が80.5%(2025年4月時点)に達しているものの、政府の目標である「ほぼすべての国民に交付する」には程遠い状況です。過去にはマイナポイントによる普及促進策も実施されましたが、その伸びは鈍化傾向にあります。



マイナ保険証は登録してこそ使える仕組みです
病院でのマイナ保険証の使い方:受付から診療までの流れ
病院でマイナ保険証を使うときは、事前の準備と当日の手順を押さえるだけで、スムーズに受付が完了します。
「何を持って行けばいいの?」「受付機の前で止まらないか不安…」そんな声に応えるために、準備から診療までの一連の流れを整理しました。
「準備したのに受付で使えなかった」そんな事態を避けるためにも、具体的な流れと注意点を次から見ていきましょう。
事前に必要なもの・準備すること
まず大前提。登録しないと使えません。
マイナ保険証として使うためには、マイナンバーカードに健康保険証利用の登録が必要です。登録はスマホ・パソコン・窓口のいずれでも可能。さらに、マイナポータルアプリがインストールされたスマホがあれば、保険証利用の設定も確認しやすくなります。
- マイナンバーカード
- 4桁の暗証番号
- マイナポータル(任意)
- 顔認証(または暗証番号入力)に対応する環境
これらを準備した上で、医療機関へ向かいましょう。
受付時の提示方法と機器の使い方
受付機に向かった瞬間、不安で足が止まることも。
多くの医療機関では、顔認証付きカードリーダーが設置されています。マイナンバーカードをかざすだけで、顔写真による本人確認と健康保険資格の確認が同時に行われます。もし顔認証が苦手な方は、暗証番号での確認も選べます。
使い方は以下の通り。
- カードリーダーにカードを置く
- 画面の指示に従って顔認証(または暗証番号入力)
- 保険資格の確認完了メッセージを確認
この手順が完了すれば、従来の保険証のように窓口に提示する必要はありません。
よくある戸惑いポイントとその対処法
「機械が反応しない」「本人確認に失敗した」そんなトラブル、あります。
よくあるのは、以下のようなケースです。
- カードが反応しない → カードの向きを確認
- 顔認証に失敗 → マスク・帽子を外す
- 「登録なし」と表示される → 登録状況を再確認
受付機のそばに職員がいれば、遠慮なく声をかけましょう。特に初めての方には親切に案内してくれるケースが多いです。



準備と使い方が分かれば、受付も怖くないね!
マイナ保険証の登録・設定方法をやさしく解説
マイナンバーカードを健康保険証として使うには、事前に登録が必要です。
「面倒そう」「どこから手をつければいいか分からない」と感じる方も多いですが、実際の作業は意外とシンプル。方法さえ分かれば、5分で完了するケースもあります。
それぞれの登録方法を、分かりやすく解説していきます。
スマホ・PCでの登録ステップ
自宅にいながら、登録完了までできる方法です。
スマホまたはパソコンを使えば、マイナポータルから簡単に健康保険証利用の登録が行えます。操作手順もシンプルで、途中で迷うポイントも少なめです。
- マイナポータルにアクセス
- 「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」を選択
- カードを読み取る(スマホならかざすだけ)
- 画面の指示に従って登録を完了
スマホがマイナンバーカードの読み取りに対応していない場合は、パソコン+ICカードリーダーの利用が必要になります。
つまり、「パソコンでもできる」と言われているものの、それにはICカードリーダーが必須となるので、現実的ではないですね。
コンビニや市区町村窓口でも登録可能
「スマホは苦手」「ICカードリーダーなんて持ってない」そんな人も安心です。
多くの自治体では、市区町村の窓口や一部のコンビニに設置された端末でマイナ保険証の登録が可能です。職員が操作方法を案内してくれるため、初めての方にも安心のサポート体制が整っています。
- 本人確認書類(マイナンバーカード)を持参
- 登録端末または窓口で「保険証利用登録」
- その場で完了。確認票を受け取る
コンビニのマルチコピー機からも一部申込が可能ですが、対応状況は自治体によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
登録完了の確認方法とエラー時の対処法
登録して「終わったつもり」がトラブルの元になります。
マイナ保険証の利用登録が正しく完了しているかは、マイナポータルや病院受付機で確認が可能です。確認を怠ると、せっかく登録したのに「未登録」と表示されてしまうことも。
- マイナポータルで「健康保険証の利用状況」をチェック
- 病院受付で「登録済み」と表示されるか確認
- エラー表示が出たら、自治体または健康保険組合へ連絡
まれに、連携先の保険組合の登録遅れなどで、利用できないケースもあります。1週間経っても「連携未完了」の場合は問い合わせをおすすめします。



登録後は、ちゃんと使えるか確認しよう!
使うメリットは?マイナ保険証の活用ポイント
「マイナ保険証って何が便利なの?」そんな疑問に答える3つの利点があります。
健康保険証としての利用だけでなく、医療費の負担軽減や安全な診療の実現にもつながるため、使わないのはもったいない制度です。
この3つの活用ポイントを知ることで、日常の医療体験がもっとラクになります。
医療費が安くなる?高額療養費制度との関係
実は、医療費が窓口で軽減されることも。
マイナ保険証を利用することで、高額療養費制度に基づいた「限度額適用認定証」の提示が不要になる場合があります。これにより、病院での支払いが最初から一定額に抑えられ、後から返金を待つ必要がなくなるケースがあります。
たとえば、突然の入院や高額な治療を受ける際、登録さえしていれば、自己負担額が事前に抑えられます。これだけでも安心感が全然違いますよね。
薬剤・健診情報の共有でより安全な診療に
医師があなたの健康履歴をすぐに確認できるようになります。
マイナ保険証を使うことで、過去の薬剤情報や健診結果などが共有され、診療の質が向上します。重複投薬の防止や持病に配慮した治療の提案も可能になるため、安心して医療を受けられます。
特に高齢の家族や、複数の病院を利用している方にとっては、情報の一元化が大きなメリットになります。
医療機関の受付がスムーズに
受付での待ち時間、少しでも短くしたいですよね。
マイナ保険証を使えば、受付での本人確認や保険資格の確認が瞬時に完了します。紙の保険証の提示や説明が不要になり、医療機関の業務効率もアップ。結果として、患者側もスムーズに受付から診療へ進めるようになります。
「病院って待つだけで疲れる…」そんな悩みを軽減する一手になるでしょう。
_/_/_/
今後、スマホでマイナ保険証が使えるようになります。
本記事公開日(2025年5月18日)現在、導入に関しては、iPhoneは5月21日からスタート、Androidは7月からのスタートとなります。
また、各医療機関での運用は、9月頃になる見込みです。
また、すべての医療機関で対応するわけではないので、スマホでのマイナ保険証利用に関しては、事前に確認することをおすすめします。



マイナ保険証、使えば便利で安心なんだね
使う前に確認したい注意点と落とし穴
便利なマイナ保険証ですが、すべてがスムーズにいくわけではありません。
「登録したのに使えない」「行った病院で非対応だった」など、実際の運用では思わぬ落とし穴があるのも事実です。使う前に知っておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
利用前に確認すべき重要なポイントをひとつずつ解説します。
すべての病院・薬局で使えるわけではない
「行ったら対応してなかった…」そんなケースもあります。
全国すべての医療機関でマイナ保険証が使えるわけではありません。対応機器が未設置だったり、システムの関係で未導入の施設も存在します。
事前にその病院や薬局が対応しているか確認しておくと安心です。病院の公式サイトや電話問い合わせで簡単に確認できます。
なお、マイナ保険証に対応している医療機関・薬局は、厚生労働省のウェブサイトで確認することもできますが、PDF対応なので実用できではありません。
ただし、厚生労働省のウェブサイトには、「マイナンバーカードの健康保険証利用対応施設を検索できるサイトはこちら」というのがあります。
一応、ここでそれらをリストしておきますね。
- Caloo 病院口コミ検索サイト (カル-株式会社)
- e-NAVITA (表示灯株式会社)
- お医者さんガイド (株式会社医事公論社)
- 病院なび (株式会社eヘルスケア)
- 病院検索ホスピタ (株式会社イーエックス・パートナーズ)
- 症状検索エンジン ユビー (Ubie株式会社)
- SCUEL 医療総合情報サイト (ミーカンパニー株式会社)
- EPARKくすりの窓口 (株式会社くすりの窓口)
- いしゃまち医療機関検索 (株式会社メディウィル) ※ワクチン助成または健診を受けられる医療機関の検索サイト
登録しても「連携未完了」で使えないケースも
「登録したのに“未登録”ってどういうこと?」
マイナポータルで登録が完了していても、実際の医療機関で「連携未完了」と表示されることがあります。これは、健康保険組合や共済などの側で連携処理がまだ行われていないケースです。
登録から反映までに数日〜1週間程度かかることもあります。急ぎで使いたい場合は、念のため紙の保険証も携帯しておくと安心です。
通信障害や機器トラブル時の対応策
「カードリーダーが動かない」「読み取りできない」そんなとき、慌てないで。
受付機のトラブルや回線障害により、一時的にマイナ保険証が使えないこともあります。その場合、従来の健康保険証を提示すれば問題なく診療は受けられます。
- 紙の保険証は念のため持参
- 受付職員に状況を伝える
- 診療は通常通り受けられる
不測の事態に備えて、当面はマイナ保険証と紙の保険証を併用するのがベストな対応です。
紙の保険証ですが、通信障害や機器トラブルが発生した場合、従来の健康保険証を提示することで、問題なく診療を受けることができます。念のため、紙の保険証を携帯しておくことをおすすめします。



使えない場面もあるから、保険証はまだ必要(^_^;)
よくある質問とその答え|不安をなくして安心受診へ
マイナ保険証について、よくある疑問をまとめました。
実際に利用を考えると、「紙の保険証はもう不要?」「子どもはどうするの?」など、さまざまな不安や疑問が浮かびます。ここでは、特に多い質問に分かりやすく答えていきます。
不安をひとつずつクリアして、安心して使える状態を目指しましょう。
健康保険証はもういらない?併用は可能?
現時点では残念ながら(?)、「併用」が基本かも・・・です。
マイナ保険証の利用が可能でも、紙の健康保険証は引き続き使用できます。むしろ、通信障害や未対応施設がある現段階では、紙の保険証を携帯しておく方が安心です。
将来的には紙の保険証が廃止される方向ではありますが、当面は「両方使える状態」がもっとも安全で現実的な選択です。
マイナンバーカードがない家族はどうする?
子どもや高齢の家族など、マイナンバーカードを持っていない場合もありますよね。
その場合は、これまで通り紙の健康保険証を使用することになります。本人名義のマイナンバーカードがなければ、マイナ保険証としては使えません。
ただし、マイナンバーカードの申請は年齢に関係なく可能です。家族の代理申請や窓口申請もできるため、必要に応じて手続きを進めると良いでしょう。
紛失した場合はどうすればいい?
マイナンバーカードをなくしたら、まずは停止手続きを。
マイナ保険証として登録されているマイナンバーカードを紛失した場合、悪用を防ぐためにも速やかに「マイナンバーカードコールセンター」へ連絡し、カード機能の一時停止を行ってください。
- 24時間対応:0120-95-0178(無料)
- カード停止後、再発行申請を行う
- 再発行後、再度保険証利用登録が必要
マイナンバーカードを紛失した場合、速やかに「マイナンバーカードコールセンター」へ連絡し、カード機能の一時停止を行ってください。再発行後、再度保険証利用登録が必要です。カード番号や登録状況をメモする際は、セキュリティに十分注意してください。



疑問を解消すれば、安心して使えるね!
まとめ|マイナ保険証の“迷い”を解消しよう
今回は「マイナ保険証って、実際どう使うの?」という疑問に答え、制度の仕組みから病院での利用手順、さらにはメリット・注意点までをやさしく解説しました。
- マイナ保険証の制度概要と仕組みがわかる
- 受付での具体的な提示方法・操作手順を解説
- 登録・設定方法や注意点もひと目で整理
特に、機器の使い方や事前準備のポイント、よくある戸惑いへの対処法など、「現場で困らないための知識」を丁寧にまとめています。



制度の全体像が見えることで、不安を取り除き、自信を持って使えるようになりますよ。
「制度の全体像を理解することで、不安を取り除き、自信を持って利用できるようになります。この記事を参考に、マイナ保険証の利用を検討してみてください。

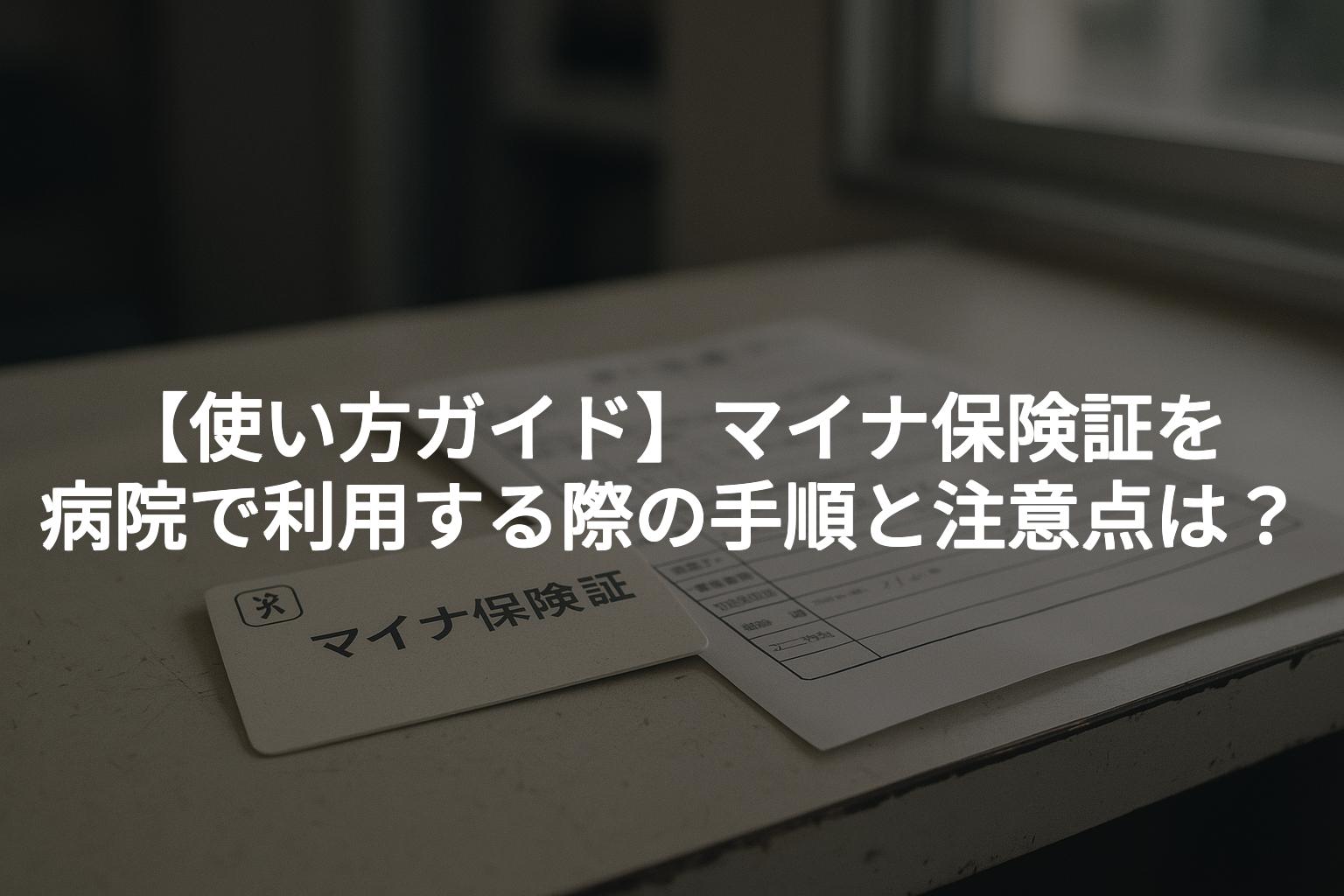
コメント