不動産投資商品「みんなで大家さん」は、個人投資家から総額で2,000億円超の巨額な資金を集めたと報道されています。
しかし、配当の支払い遅延や停止、さらに解約手続きの滞りが相次ぎ、大きな社会問題となっているようです。
年7%近くという高利回りを謳っていて、 テレビCMなどもあったことで、老後の生活資金などに不安を抱える多くの個人投資家が、「不動産投資だから安心」というイメージのもと出資しました。
ところが、主力プロジェクト「ゲートウェイ成田」の開発は遅延し、運用実態の不透明さから、新規の出資金を既存の出資者への配当に回すというポンジ・スキーム(Ponzi scheme)ではないかという疑惑(★コラム1参照)も指摘されています。
投資家の方々は、この巨大ファンドの「現在の運用状況」と「今後どうなるのか」、そしてなぜこれほど大きな問題にもかかわらず「なぜ事業継続している?」という法的論点について、強い不安を抱いています。
- 「みんなで大家さん」の現在の運用状況と具体的なトラブルの進捗。
- 「なぜ今も事業継続?」という疑問に対する法的・構造的な考察。
- 「返金されない」状況をふまえ、投資家として今どう行動すべきかという判断軸。
「みんなで大家さん」とは?
まずは、報道情報を一つ紹介。カンテレnewsのYouTube動画です。
★参照情報1
それでは、「みんなで大家さん」の仕組みとこれまでの流れについて。
高利回りで注目された不動産ファンドの仕組み
「みんなで大家さん」は、都市開発システム株式会社(運営元は都市綜研インベストファンド株式会社)が運営する不動産小口化商品、または不動産特定共同事業(「不特法」)を用いた投資スキームです。投資家は事業者と匿名組合契約を結び、土地・建物の開発・運営で得られた収益を出資者に分配するとされています。
投資単位は原則として1口100万円からで、想定利回りは年6.0%〜7.0%という高水準です。特に「成田シリーズ」などの複数案件が、立地の良さ(例:成田空港隣接)や高利回りを謳って出資を集めていたと報道されています。
なぜ人気を集めたのか?投資家心理と広告戦略
「みんなで大家さん」が大規模に資金を集められた背景には、以下の3つの要因が考えられます。
- 不動産への安心感:
- 不動産投資は「土地・建物があるから安心」という一般的なイメージが働き、個人投資家が高利回りに飛びつきやすくなりました。テレビCMや新聞広告なども投資家への安心感を醸成したようです。
- 小口化と集金力:
- 小口(100万円から)で参加できる形態であったため、多数の個人から出資を募ることができ、短期間で資金規模が拡大しました。
- 配当実績による信頼感:
- 初期段階では実際に配当が支払われていたため、「本当に収益が出ている」という信頼感が醸成されました。
分配金遅延・返金トラブルはいつから始まったか
深刻なトラブルは、「シリーズ成田(GATEWAY NARITA)」プロジェクトの運用実態に疑問が持たれる中で表面化しました。この大規模開発プロジェクトは6年前に開始されたにもかかわらず、2025年1月時点での進捗率はわずか2.3%とであり、建設現場は、ほぼ更地のままだと報じられています。
この開発遅延によって収益構造が稼働していない可能性があるとの指摘もあり、2025年7月末には、出資者への分配金の支払いが突然停止しました。
さらに、「成田27商品」など多数の案件で配当が未払いとなり、解約申請後も1年以上書類が届かないなど、解約手続きが遅延・停止していると報道されています。
コラム1:ポンジ・スキームとは?
ポンジ・スキーム(Ponzi scheme) は、投資詐欺の一種です。この名称は詐欺師チャールズ・ポンジの名に由来しています。
その典型的な仕組みは、実際には事業による利益や収益がほとんどないにもかかわらず、非現実的なほど高い配当(高利回り)を約束して投資家を募る点にあります。そして、新しく集めた投資家からの出資金を、あたかも運用益であるかのように装って、既存の出資者への配当金として支払います。
これは新しい資金の流入を絶えず必要とする破綻が前提の「自転車操業」であり、資金繰りが続かなくなると配当が停止し、スキーム全体が破綻します。その結果、後から参加した出資者ほど元本を失うなど、大きな損害を被ります。投資詐欺の多くがこの手法で行われるとされています。
現在どうなっている?
最新の運用状況をチェック…
公式ホームページはどうなっている?
「みんなで大家さん」のホームページは、本記事公開日現在も普通に閲覧できます。
ホームページを閲覧する限りにおいては、普通に事業継続している様子です。
報道では、「運営会社である都市綜研インベストファンドと販売会社は、行政処分や分配遅延が発生した後、ウェブサイトを通じてお詫びと今後の対応に関するお知らせを公表しています。」などとありますが、そのような「お詫びと今後の対応に関するお知らせ」は見当たりません。
一方、2025年10月14日に行政指導が公告などで公表されたことに遺憾の意をホームページ上で表明しています。
出資金はどうなった?実際の返金状況まとめ
出資総額2,000億円超の行方については、元関係者から「もうほぼないです。いろんなものに全部使っています」という衝撃的な内情が報道されています。
- 資金ショートの懸念:
- 会計分析では、都市綜研インベストファンドの固定資産(主に土地)が自己資本(純資産)の23倍(固定比率2344%)にも達しており、財務体質が極めて脆弱で、資金ショート寸前である兆候が示されています。
- 解約の状況:
- 行政処分直後の24時間で、28億円以上の解約申し入れが発生しました。運営側は譲渡契約を再開したものの、全ての譲渡に応じるには6ヶ月から12ヶ月かかるとの見通しを発表しています。
- 集団訴訟:
- 2025年7月以降の分配金停止を受け、投資家による集団訴訟が始動しています。すでに合計1億円の返還を求める提訴が行われており、今後、1000人を超える出資者が100億円規模の損害賠償を求めて提訴する方針だと報じられています。
投資家の声とSNS・掲示板の動向
分配金の停止や解約に応じられない状況に対し、出資者からは「単なる事業の失敗では許されない」と憤りの声が上がっています。
SNSや掲示板では、その高利回りや運用実態の不透明さから「ヤバすぎる」といった声が多数上がっています。老後の生活資金を投資した71歳の出資者は、2,000億円もの大金が行方不明になっている状況に対し、「半分でも100万円でもいいから、本当に返してほしい」と切実な思いを語っています。
なぜ事業継続できるの?
法的仕組みとグレーゾーン …
詐欺にはあたらない?金融商品取引法との関係
「みんなで大家さん」は、グループ内の開発業者に土地を貸し出し、その地代を分配金の原資とするという構造を採っていますが、元関係者からは、実際には「何一つ収益が上がっていなくても、グループ内で収益を立ててぐるっと回した」に過ぎず、新しい出資金を配当に回していた可能性が濃厚であるとの指摘が出ています。
会計分析でも、新規資金に依存する「自転車操業」の兆候が指摘されています(参照情報2)。
しかし、専門家からは、その構造が「ポンジ・スキームの典型と非常に近い」のは間違いないものの、現時点(ソース内記述時点)で「法的に“ポンジ・スキームだ”と明確に認定されたわけではない」という中間的な状況にあるとの見解も示されています。
法的な詐欺罪として立件されるには、当初から騙す意図(故意)の立証が必要となります。
★参照情報2
行政処分の有無とその影響
「みんなで大家さん」は、過去に複数回、行政処分を受けています。
- 2013年:
- 都市綜研インベストファンド株式会社は、新規出資金を過去の投資家への分配金に充てるなど、自転車操業の状態に陥っていたとして、金融庁から分別管理義務違反や虚偽表示を理由に業務停止命令を受けています。
- 2024年6月:
- 直近では、東京都・大阪府より、運営元(都市綜研インベストファンド)と販売会社(みんなで大家さん販売)に対し、不動産特定共同事業法(不特法)違反に基づく業務停止命令等が出されました。
- 処分理由には、建設計画の大幅な変更や収益性への影響を投資家に十分説明しなかったこと、開発許可の対象外の土地を書類に記載したことなどが含まれます。
- 直近では、東京都・大阪府より、運営元(都市綜研インベストファンド)と販売会社(みんなで大家さん販売)に対し、不動産特定共同事業法(不特法)違反に基づく業務停止命令等が出されました。
この行政処分をきっかけに、投資家の不安が増大し、大規模な解約申し入れと集団訴訟への動きに繋がりました。
消費者庁・金融庁・国交省のスタンスと動き
「みんなで大家さん」は不特法に基づく事業であり、主たる監督は国土交通省(または地方行政庁)が行います。行政は、2024年6月の処分において、投資家に対する情報開示や説明の義務違反を厳しく指摘しました。
今回の問題は、不特法に基づく案件であっても、投資家保護の仕組みが不十分になる可能性があることを浮き彫りにしています。今後、行政と司法の両面で対応が注目されており、高利回りを謳うスキームに対する監督・運用実態開示の強化が議論されています。
今後どうなる?
シナリオ別に見通しを整理…
分配金再開の可能性は?
分配金の原資は、本来、不動産の賃料収入など事業の利益であるべきです。しかし、「ゲートウェイ成田」プロジェクトの進捗は遅れており、収益を生む建物が完成していません。
会計分析によれば、都市綜研は当面、約140億円のキャッシュを保有しているため、すぐに資金の問題でトラブルが起こる可能性は低いという見立てもありますが、これは「打出の小槌」のようなグループ内での資金循環(★コラム2参照)に依存しているためと報道されています。
もしこの循環が止まるか、新規の出資金流入が滞れば、健全な事業収益がないままでは、分配金の継続的な支払いが困難になる可能性が高いと予想されます。
清算・倒産リスクは?
都市綜研インベストファンドの財務体質は、固定比率が2344%と極端に高く、「見せかけの資産計上」の疑いなど、極めて脆弱な会計構造に原因があり、資金ショート寸前である兆候が指摘されています。新規出資が途絶え、自転車操業が破綻すれば、運営会社の倒産リスクは高まります(参照情報3)。
ファンド運営事業者が倒産した場合、投資は元本保証がないため、返金は保証されません。成田案件のような開発途中の土地を売却して現金化(早期清算)しようとしても、収益力が確立されていないため、投資資金のごく一部しか回収できない可能性が高いとみられています。
★参照情報3
投資家として今できる判断は?
投資家は、元本保証のない投資において、以下の点を教訓として冷静に判断することが重要です。
- 利回りの根拠の検証:
- 高利回り(例:年6〜7%以上)に対しては、「なぜその利回りなのか?」を必ず確認し、健全な事業収益から生み出されているかを疑うこと。
- 事業実態の透明性確認:
- 開発進捗状況や、情報開示の一貫性、事業者の過去の行政処分歴や財務健全性(決算書)を徹底的にチェックすること。
- 分散投資の徹底:
- 一つの投資商品や事業者に資金を集中させるリスクを避け、適切な分散投資を心がけること。
コラム2:グループ内の資金循環とは?
グループ内の資金循環とは、複数の関連会社を持つ企業グループ内で、資金や資産を移動させることで、外部からは健全な収益が上がっているように見せかける仕組みを指します。
以下、一般的な事例です。
- 資金の流入と移動:
- 運営元A社が投資家から出資金を集めます。
- グループ内取引:
- A社が集めた資金を、開発プロジェクト担う同じグループ内の開発業者 B社等に送ります。
- 収益の擬装:
- このB社等は、A社が保有する土地を借り上げ、その地代(賃料)をA社に支払います。
- 分配の原資化:
- A社は、このグループ内からの地代収入を「事業収益」として計上し、それを投資家への分配金の原資として支払います。
返金されないときの対応法と相談窓口
弁護士・専門家に相談する前に確認すべきこと
返金や解約が滞っている場合、まず以下の情報や記録を整理することが、その後の法的対応の可否を分ける鍵となります。
- 契約内容の精査:
- 重要事項説明書、契約約款、リスク説明書などを再確認し、分配金の仕組み、中途解約の条件、投資対象の現況を理解する。
- 勧誘時の記録:
- 勧誘時に「元本保証のような印象を与える表現」や「高利回りを強調する文言」が用いられていなかったか、リスク説明が十分になされたかを記録する。
- 資金の使途の確認:
- 集めた資金が開発費用に使われたのか、他の案件への流用や分配金の補填に回されていた可能性がないか、運営会社側に説明を求める。
実際に返金請求した人の事例
すでに分配の不履行や契約内容の乖離などを争点として、運営会社(都市綜研インベストファンド)に対し、投資家が契約解除と出資金の返還を求める集団訴訟を大阪地裁や東京地裁に提起しています。
被害者の中には、退職金を取り崩した人も含まれており、早ければ2025年10月下旬にも、100億円規模の損害賠償を求める提訴が予定されていると報道されています。
被害者救済を目的として「みんなで大家さん被害対策弁護団」が結成されており、相談を受け付けています。
詐欺だった場合に備える心構えと記録の残し方
今回の問題は、不動産投資業界における投資家保護のあり方を問う重要な事例となっています。投資家は、現時点で「法的に詐欺と断定されていない」としても、自転車操業の気配がある場合(配当遅延・停止、解約困難など)はリスクが非常に高いと判断し、慎重の上にも慎重な運用姿勢を持つことが求められます。
もし事業者による説明義務違反があった場合、金融商品販売法に基づき、元本欠損額を損害額と推定して損害賠償責任を問える可能性があります。
そのため、勧誘や説明に関する資料や記録を可能な限り保存しておくことが重要です。
「みんなで大家さん」に関するFAQ
- Q1. 「みんなで大家さん」の運営会社はどこですか?
- A1. 運営(営業者)は都市綜研インベストファンド株式会社、販売代理人はみんなで大家さん販売株式会社が担っており、持株会社は共生バンクです。
- Q2. 出資者の総人数と総額はどれくらいですか?
- A2. 2024年時点の投資家数は約3万8000人に達しており、総額は2,000億円超を集めたとされています。
- Q3. なぜ「シリーズ成田」の開発は遅れているのですか?
- A3. 当初の開業予定は2021年でしたが、2025年1月時点で進捗率はわずか2.3%と報道されています。元関係者の一部からは、計画の遅延や建設費・人件費の高騰が要因として挙げられています。
- Q4. 過去の行政処分ではどのような問題が指摘されましたか?
- A4. 2013年には新規出資金の分配への充当(自転車操業)や分別管理義務違反、2024年6月には建設計画の変更に関する投資家への説明義務違反や事実と異なる記載など、不特法違反が指摘されています。
- Q5. 匿名組合契約とは何ですか?
- A5. 投資家は事業者と匿名組合契約を結び、事業収益に対する分配金請求権を持ちます。投資家は、対象不動産の所有権や直接的な賃借人への請求権を持ちません。
- Q6. 不動産小口化商品は元本保証されていますか?
- A6. いいえ。不動産特定共同事業法に基づく商品であり、元本保証は法律により禁止されています。運用状況次第では元本割れのリスクがあります。
- Q7. 集団訴訟はどこで提起されましたか?
- A7. 2025年9月以降、東京地方裁判所などで出資金返還を求める集団訴訟が始動しています。
- Q8. もし倒産した場合、投資した資金はどうなりますか?
- A8. 投資資金の返金は保証されません。成田案件のように開発途中で収益を上げていない場合、不動産を売却しても投資資金のごく一部しか回収できない、資産保全の見通しは厳しい状況です。
- Q9. 行政処分後に解約は可能になりましたか?
- A9. 行政処分後に解約希望が殺到しましたが、2024年7月29日に譲渡契約が再開されました。ただし、希望者全てに対応するには6ヶ月〜12ヶ月かかるという見通しが公表されています。
- Q10. 財務体質が危険だと言われる具体的な理由は?
- A10. 財務諸表(バランスシート)の分析において、固定資産が自己資本の23倍(固定比率2344%)と極端に高く、流動比率も低いなど、資金繰りの脆さと「見せかけの資産計上」の疑いが指摘されています(参照情報1、2を参照ください)。
- Q11. 「みんなで大家さん」のスキームは、健全な不動産クラウドファンディング(不特法)とどう違いますか?
- A11. 健全な不特法活用事例では、地域課題解決や施設利用特典など金銭以外のリターンも提供し、事業実態の透明性が確保されています。一方「みんなで大家さん」は、高利回り追求のため、グループ内取引によって収益を偽装し、新規資金に依存する自転車操業的な構造が問題視されています。
まとめ
- 総額2,000億円超を集めたが、2025年7月末から配当停止・解約遅延が深刻化している。
- 主力開発プロジェクトの進捗は極めて限定的で、資金繰りが新規出資に依存していた疑いが強い。
- 過去に分別管理違反や虚偽表示などで複数回、不特法違反の行政処分を受けている。
- 投資家は集団訴訟を開始しており、100億円規模の損害賠償請求が予定されている。
- 高利回りの案件に投資する際は、その根拠や事業者の透明性を慎重に見極める必要がある。
「みんなで大家さん」問題は、約3万8000人の個人投資家から集めた総額2,000億円超の巨大ファンドが、主力案件「ゲートウェイ成田」の開発遅延と、それに伴う分配金・解約の停止・遅延によって深刻化している事態だと報道されています。
元関係者や一部の会計分析の結果からは、新規出資金で既存の配当を賄うというポンジ・スキーム的な自転車操業の可能性も指摘されています。
過去に複数回、不特法違反で行政処分(業務停止命令)を受けている点も、事業運営の信頼性の欠如を示しています。
現在、投資家による集団訴訟が本格化しており、今後の司法判断と行政の規制強化の動向に注目が集まっています。
投資家としては、高利回りだけに惑わされず、運用実態、情報開示の透明性、および事業者の財務健全性を徹底的にチェックすることが、将来的な被害を避けるための重要な教訓となります。

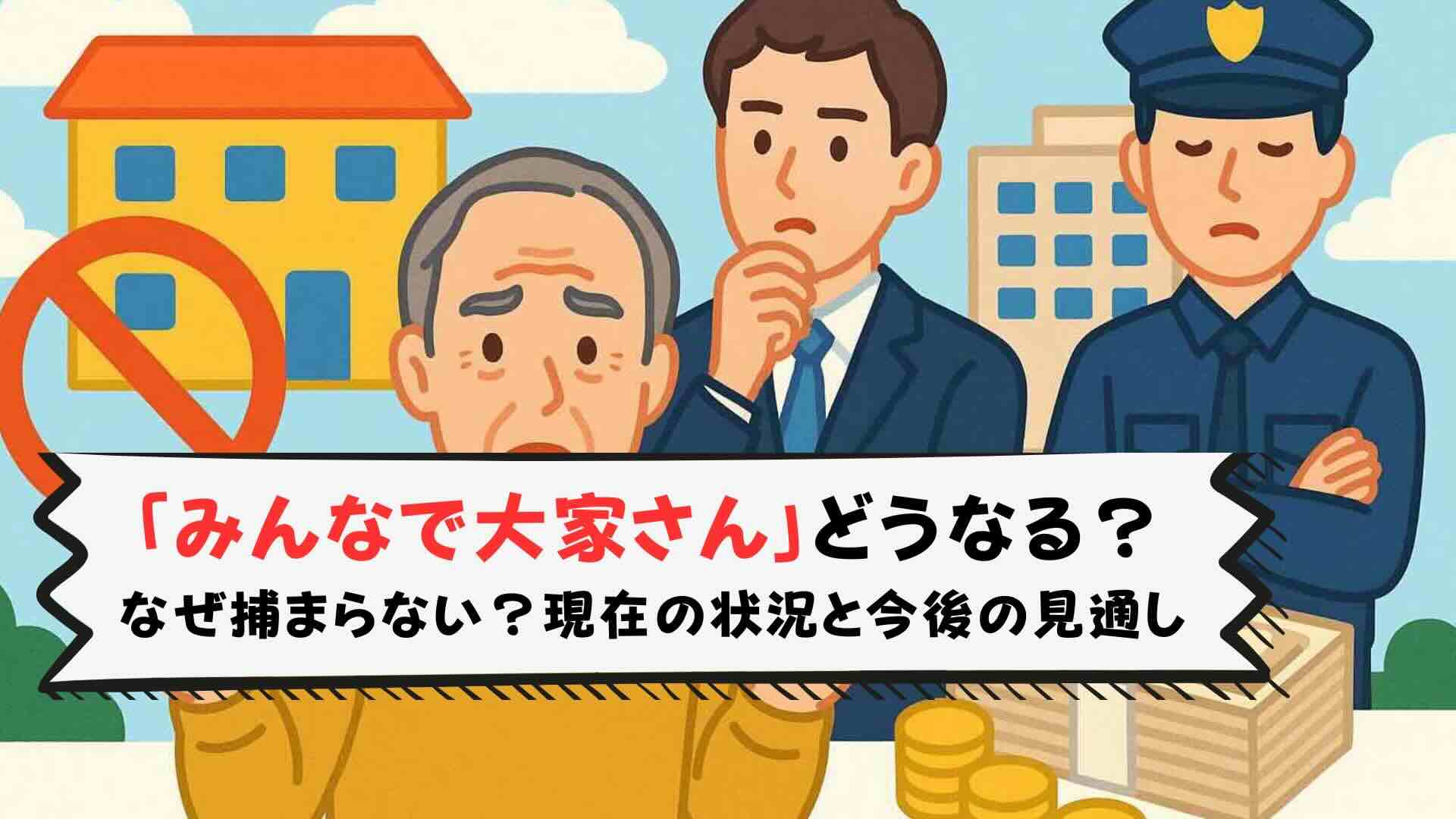
コメント