コンビニエンスストアの定番商品であるおにぎり は、私たちの食生活に欠かせない「即食」の要ですが、その短い賞味期限ゆえに、店舗での廃棄ロスという社会課題とも表裏一体の関係にありました。また、近年深刻化する「物流の2024年問題」により、従来の頻繁な配送体制の維持も難しくなっています。
こうした中、ローソンは「冷凍おにぎり」という新たな選択肢を導入し、11/4から販売開始。この複合的な課題に挑んでいます。冷凍技術を活用して商品の寿命を「約1年」まで延ばすことで、食品ロス削減と物流効率化を同時に実現し、さらに製造コスト削減により価格を常温品より1〜2割安く設定可能となりました。
この記事では、普段利用するコンビニに登場した「冷凍おにぎり」の誕生秘話から、それがどのように社会課題の解決に繋がるのか、そして私たち消費者がこの新しい選択肢を選ぶ意味について、詳しく解説します。
- 冷凍おにぎり導入の目的・背景
- 食品ロス削減への具体的な効果
- 店舗展開や今後の動向
冷凍おにぎりとは?ローソンの新商品、その狙いとは
ローソン冷凍おにぎりの背景と狙いについて。
なぜ今「冷凍おにぎり」?背景にある2つの課題
ローソンが「冷凍おにぎり」の導入を拡大する背景には、主に「食品ロス問題」と「物流問題(2024年問題)」という二つの喫緊の課題があります。
- 食品ロス問題への対応:
- 従来のコンビニの常温おにぎりの賞味期限は通常約1日と非常に短く、需要予測の難しさも相まって、売れ残りが廃棄されることが課題でした。ローソンは「食品ロスゼロのコンビニ構想」を掲げており、冷凍おにぎりの賞味期限を約1年に延長することで、店舗側での廃棄数を極限まで減らすことを目指しています。冷凍技術は「時間を止める」新しい発想と評されています。
- 物流の2024年問題への対策:
- 2024年4月以降、ドライバーの時間外労働の上限規制(年間960時間以下)が適用され、物流業界全体で人手不足と輸送能力の不足が懸念されています。常温・チルドのおにぎりは鮮度維持のため、1日2回配送、あるいはそれ以上の頻度で配送されていましたが、冷凍おにぎりであれば配送を1日1回に抑えることが可能です。これにより配送効率を改善し、物流負荷の軽減に貢献します。
常温販売と何が違う?品質・保存・流通の工夫
冷凍おにぎりは、通常の常温おにぎりとは異なる流通・製造プロセスを採用しています。
- 製造・コスト構造:
- 冷凍おにぎりは、一括製造し、作り置きができるため、原材料の調達や製造に必要な人員の計画が立てやすくなります。その結果、製造コストを削減でき、常温おにぎり(例:ごま鮭おにぎり税込167円)と比べて、10~20%ほど安い価格(例:冷凍ごま鮭おにぎり税込140円)で提供が可能となっています。
- 品質・食感:
- ローソンは、冷凍食品の「即食需要」への浸透を促すため、あえて常温おにぎりからレシピを大きく変更せず、そのまま冷凍させたものを販売する実験を実施しました。また、ラインナップには餅米を使った「おこわ」も含まれますが、これは解凍時に普通の米よりも味覚が落ちにくいという特性を活かしています。
- 包装の工夫:
- 冷凍おにぎりは、購入者が電子レンジで温めてすぐに食べることを前提としているため、海苔は解凍時に湿る問題を避けるために「パリパリ」ではない直まきを採用しています。また、加熱後に熱くなったパッケージの端を「つかんで持てる」よう、あえて大きな袋に入れるパッケージの工夫もされています。
食品ロス削減への効果とは
次に、食品ロスについて。
廃棄ロスはどこまで減る?試験導入時のデータから分析
冷凍おにぎりは、主に賞味期限の長期化を通じて、コンビニ業界の大きな課題である当日廃棄を根本的に変える可能性を持っています。
通常のチルド食品は賞味期限が短いため、需要予測が外れると、新鮮さや品質を保てないという理由から、売れ残り商品や材料が廃棄されやすい状況にあります。これに対し、冷凍おにぎりは賞味期限が約1年と長いため、店舗や家庭での長期ストックが可能となり、期限切れによる廃棄リスクを大幅に低減させます。
また、コンビニ業界ではAIを活用した需要予測の改善に取り組む動きがあるものの、即食性の高いおにぎりを冷凍化し、在庫期間を延長することで、予測ミスによる廃棄を防ぐという、技術的な対策(中食食品の冷凍食品化)としても位置づけられています。
冷凍おにぎりがコンビニの“当日廃棄”問題をどう変えるか
従来の常温おにぎりは、製造ベンダーが予測に基づいて製造・配送するモデルのため、注文量と実際の需要のズレが生じやすく、特にご飯は一度製造すると次回納品分に回せないため、食品ロスが発生しやすい商材です。
冷凍おにぎりは、この構造的な問題を以下の点で変えます:
- 計画生産と一括製造:
- 需要予測に基づいて安定的に大量生産が可能になり、日々の需要変動に左右される「鮮度対応生産」の負担が軽減されます。
- 物流効率化:
- 配送頻度が減ることで、配送コストの削減とCO2排出量削減に貢献します。
- 在庫リスクの軽減:
- 店舗側は、当日中に売り切る必要がなくなり、在庫を長期的に保持できるため、廃棄ロスを減らし、欠品による販売機会の損失(機会ロス)も同時に削減できる見込みです。
これは、食品ロスが年間464万トン(令和5年度推計値)に上る日本において、コンビニエンスストアという流通の要が持続可能なサプライチェーンを構築する上で、重要な一歩となります。
全国展開の状況と今後の見通し
ローソンでの対象店舗、そして、商品の今後の展開について。
対象店舗・商品は?今買えるローソン一覧
ローソンは、2023年から段階的に冷凍おにぎりの導入を進めてきました。
- 初期実験:
- 2023年8月から11月までの3か月間、福島県と東京都の合計21店舗で実験販売を実施しました。福島県を選んだのは、おにぎりを電子レンジで温めて食べる習慣がある地域(福島県は96%の店舗で温めるか聞かれる)であり、即食への行動変容が受け入れられるかを検証する狙いがありました。
- 販売拡大状況:
- 2025年2月からは東京都の約400店舗で本格販売を開始し、5月13日からは茨城県、栃木県、山梨県、千葉県、東京都、神奈川県の約1,700店舗に拡大しました。
- 全国展開:
- 2025年11月4日からは、東北地区、山口県、広島県・島根県の一部、沖縄県の店舗へ展開し、販売店舗数はおよそ12,000店となり、全店舗の約85%で取り扱われる見込みです。
現在の冷凍おにぎりラインナップ(4品)
🍙 焼きさけおにぎり


🍙 鶏五目おにぎり
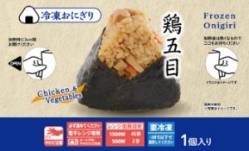
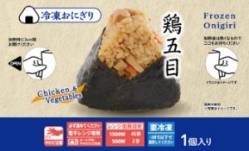
🍙 胡摩さけおにぎり


🍙 わかめごはんおにぎり


| 商品名 | 価格(税込) | 特徴 |
|---|---|---|
| 焼さけおにぎり | 279円 | 脂のりのよいアトランティックサーモンのハラミを醤油麹に漬けて焼いて中具に入れた、厳選国産米のおにぎり。 |
| 鶏五目おにぎり | 157円 | 鶏肉・ごぼう・人参・椎茸・筍などを入れて、砂糖と醤油などの調味料で炊いたおにぎり。 |
| 胡麻さけおにぎり | 140円 | 粗めにほぐした鮭と金胡麻を、昆布・かつお節の旨味がきいた出汁で炊いたご飯に混ぜ込んだもの。 |
| わかめごはんおにぎり | 140円 | わかめと金胡麻を、昆布・かつお節の旨味がきいた出汁で炊いたご飯に混ぜ込んだもの。 |
今後の展開予定と「他の商品」への応用の可能性
ローソンは、2026年度中に国内のおよそ14,000店舗(冷凍ケースがない店舗等を除く)への冷凍おにぎりの導入を目標としています。
また、ローソンはこれまでにも、コロナ禍の需要変化に対応するため、冷凍食品の製造を拡大し、冷凍弁当や冷凍寿司、冷凍調理パンなど様々なジャンルの冷凍販売の実験を行ってきました。
特に冷凍おにぎりの成功を足掛かりに、今後は冷凍調理パンの全国展開も続く予定です。お客様のニーズに合ったおいしさの提供と食品ロスの削減を目的に、今後も様々なカテゴリーで冷凍食品の販売を行っていく方針です。
冷凍おにぎりは生活者に何をもたらすのか?
冷凍おにぎりが私たち消費者にもたらすものは?
消費者として選ぶ意味とは?
冷凍おにぎりは、価格や利便性の面で消費者にとって大きなメリットをもたらします。
- 価格メリット:
- 常温おにぎりよりも1〜2割安く購入できるため、物価高騰が続く中で、家計の節約に繋がります。例えば、「胡麻さけおにぎり」は常温の「焼さけおにぎり」や「三陸産わかめごはんおにぎり」(いずれも税込167円)と比べて140円(税込)となっており、低価格でおにぎりを提供し続けるというコンビニの競争力維持にも繋がっています。
- 利便性(ストック・即食):
- 自宅での長期保存(ストック需要)が可能であり、また、コンビニに常設されている電子レンジを使用すれば、温かいおにぎりをその場ですぐに食べられる(即食需要)という利便性があります。
- 美味しさ:
- 「冷凍食品を即食する」という行動変容には「違和感」の壁があるとされていましたが、冷凍技術の進化により、従来の常温品と比べて遜色ない、あるいは人によっては「むしろ好みかも」と感じられる品質が実現されています。
サステナブルな買い物行動としての価値
冷凍おにぎりを選ぶことは、個人の消費活動を通じて、社会全体の持続可能性に貢献することに繋がります。
冷凍おにぎりの購入は、ローソンが推進する食品ロス削減(廃棄ロスを減らす)、および物流効率化(CO2排出削減) の取り組みを直接的に支援する行動となります。消費者の「お得に買い物をしたい」というニーズ が、結果的に「食品ロス削減に貢献したい」というエシカルな動機と結びつく、「一石二鳥」の買い物行動と言えるでしょう。
冷凍食品技術の応用による「中食食品の冷凍食品化」は、小売業における食品ロス削減の鍵を握る技術の一つであり、消費者がこれを選択することで、持続可能な社会の実現に一役買うことができます。
ローソンの冷凍おにぎりに関するFAQ
- Q1. 価格は常温おにぎりより安いですか?
- A1. 冷凍おにぎりは、一括製造による製造コスト削減が可能なため、常温おにぎりと比べて10~20%ほど安い価格で提供されています。
- Q2. 賞味期限はどのくらいですか?
- A2. 冷凍おにぎりの賞味期限は約1年と長く設定されています。これは、常温おにぎり(通常約1日)と比較して、店舗側の廃棄ロスを大幅に削減する要因となります。
- Q3. 配送頻度はどう変わりますか?
- A3. 常温おにぎりが1日2回配送なのに対し、冷凍おにぎりは1日1回の配送で済むため、物流効率改善とCO2排出量削減に寄与します。
- Q4. 冷凍おにぎりは常温のものと味が違いますか?
- A4. 初期の実験では、常温と全く同じレシピをそのまま冷凍させていました。また、餅米(おこわ)は解凍時に味覚が落ちにくいという特性が利用されています。温めて「おいしい」と感じてもらうことが重要視されています。
- Q5. 冷凍おにぎりの販売拡大の最終目標はいつですか?
- A5. ローソンは、2026年度中に国内の約14,000店舗(冷凍ケースが無い店舗等を除く)への導入を目指しています。
- Q6. 冷凍なのに「即食」のニーズに応えられるのはなぜですか?
- A6. 冷凍おにぎりは、店内に設置されている電子レンジで温めることで、すぐに温かい状態で食べられるため、「即食」の需要にも対応しています。これは、冷凍食品を「ストック」としてだけでなく「即食」として利用する消費行動の変容を促す狙いもあります。
- Q7. なぜ海苔がパリパリではないのですか?
- A7. 冷凍・解凍の過程で海苔が湿ってしまう問題を解決することが難しいため、パリパリの海苔(手巻きおにぎりに多い)ではなく、最初から巻かれている直まき(ウェット海苔)が採用されています。
- Q8. 冷凍おにぎりは他にどのような社会課題解決に貢献しますか?
- A8. 冷凍による流通の効率化は、日本の喫緊の課題である「物流の2024年問題」への対策となります。また、配送頻度が減ることにより、CO2排出量の削減にも貢献します。
- Q9. なぜ福島県で実験が行われたのですか?
- A9. コンビニでおにぎりを購入する際に「温めるか」を聞かれる習慣は地域差があり、福島県は特にその割合が高い(96%)ため、温めて食べる習慣がある地域で冷凍おにぎりが受け入れられるかを検証する目的がありました。
- Q10. 冷凍おにぎり以外にも冷凍食品化が進んでいますか?
- A10. ローソンは以前から、冷凍弁当、冷凍寿司、冷凍調理パンなどの冷凍販売の実験を行っており、今後も食品ロス削減と顧客ニーズに応えるために、様々なカテゴリーで冷凍食品の販売を拡大していく計画です。
- Q11. 加熱後のパッケージに工夫はありますか?
- A11. パッケージは加熱を前提としたものに変更されており、レンジアップ後に熱くなってもパッケージの端を「つかんで持てる」ように、あえて大きな袋が使われています。
まとめ
- 冷凍おにぎりは、賞味期限を約1年に延ばし、食品ロス削減に貢献。
- 物流効率化(配送頻度削減)により、物流の2024年問題やCO2排出削減に対応。
- 価格は常温おにぎりより1〜2割安く、消費者にもメリットがある。
- 2025年11月4日から販売店舗が約12,000店に拡大し、全国展開が進む。
- 冷凍おにぎりの購入は、お得なだけでなくサステナブルな消費行動である。
ローソンが拡大する冷凍おにぎりの販売は、単なる新商品ではなく、コンビニ業界が抱える構造的な課題を解決するための戦略的な一手です。
冷凍おにぎりは、賞味期限を約1年と大幅に延長することで、店舗での廃棄ロスを削減する効果があります。また、配送頻度を1日1回に集約し、物流の効率化とCO2排出量の削減にも貢献します。さらに、製造効率化により、消費者に常温品より1〜2割安い価格というメリットをもたらしています。
この取り組みは、従来のコンビニのビジネスモデルであった、利便性と食品廃棄が表裏一体という状況からの脱却を目指すものです。私たちが冷凍おにぎりを選ぶという行動は、お得感を得られるだけでなく、食品ロス削減と物流効率化というサステナブルな社会の実現に貢献する買い物行動となります。ローソンは、2026年度中には国内約14,000店舗での導入を目標としており、この冷凍技術の応用は、今後冷凍調理パンなど他のカテゴリーにも拡大していく見通しです。
冷凍おにぎりは、美味しさと利便性を両立させながら、環境負荷の少ない豊かな未来を築く一助となる、新しい消費の形を提案していると言えるでしょう。

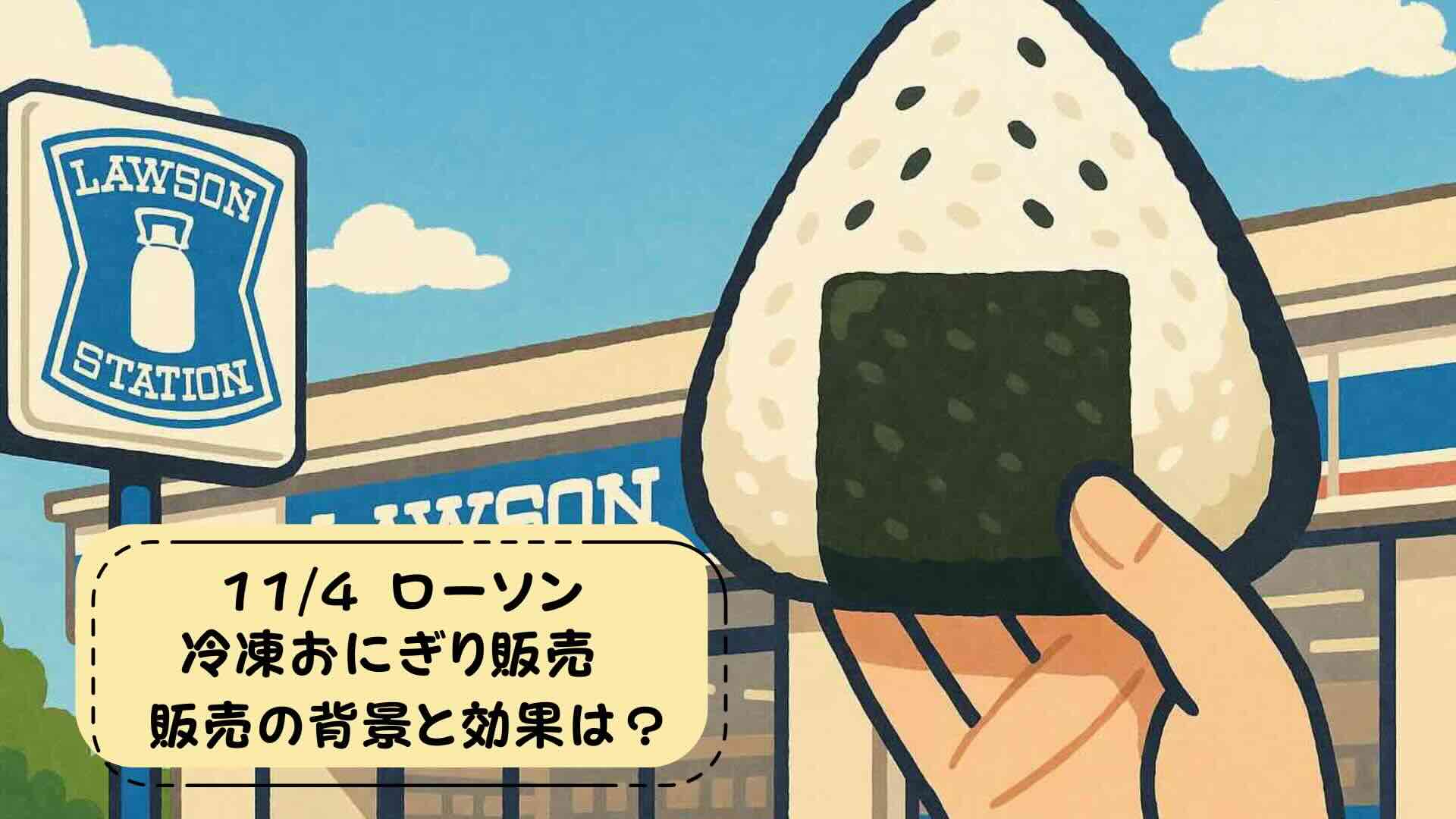
コメント