作家、編集者、そしてテレビタレントとして、日本の文化を長きにわたり牽引し続けた嵐山光三郎さんが、2025年11月14日に83歳で逝去されました。
その訃報は、長年にわたり彼の活動に親しんできた多くの読者や視聴者に、深い驚きと哀悼の念をもって迎えられています。
嵐山さんは、文芸、旅、食といったテーマを独自のユーモアと軽妙な筆致で描き、特にその斬新な文体、「昭和軽薄体」は、当時の日本語の文章表現に革新をもたらしました。
また、『笑っていいとも!増刊号』の初代編集長としてのコミカルで知的な姿は、お茶の間にも「場が和むタイプ」として親しまれました。
嵐山さんの読者層は、昭和の雑誌文化の熱狂を肌で知り、読書や旅、食に関心が高い50代から70代以上の方々が中心です。
彼が残した、文人たちの「悪食」や「暴食」を暴いた評伝、そして晩年の「老い」を肯定的に捉えたエッセイは、人生の折り返しを過ぎた私たちにとって、今こそ読み返す価値のある普遍的な洞察に満ちています。
彼の豊かな知識とユーモアで文化を身近に伝え続けた功績は、今後も作品や記録を通じて語り継がれていくことでしょう。
この記事では、多才な才能を発揮した嵐山光三郎さんの83年の生涯を敬意をもって振り返ります。
編集者、作家としての異色の経歴と、『文人悪食』『悪党芭蕉』といった代表作の功績を再評価するとともに、読者が気にかける死因や、彼の創作活動を支えた家族への想いについても詳しく解説します。
- 嵐山光三郎さんの死因や葬儀に関する正確な情報
- 平凡社「太陽」編集長から作家へ転身した異色の経歴や、「昭和軽薄体」の衝撃
- 『文人悪食』や『悪党芭蕉』など、今こそ読み返したい代表作と受賞歴
- 「超獣」と呼んだ妻や家族に見守られた晩年の様子と、家族構成
嵐山光三郎さん83歳で死去、その死因と最後の日々
訃報:11月14日に肺炎のため死去
作家、エッセイストとして長く第一線で活躍を続けた嵐山光三郎さんが、2025年11月14日に83歳で逝去されました。 訃報は、ご逝去から約2週間が経過した同年11月28日に公表されました。
報道によると、嵐山さんの死因は肺炎であったとされています。
このニュースはX(旧Twitter)などでも大きく話題となり、「哀悼!w(゜o゜)w」や、「長く文化に触れてきた人がまた一人いなくなったか…」といった追悼の声が寄せられました。
嵐山さんは、本名を祐乗坊 英昭(ゆうじょうぼう ひであき)といい、そのユニークなペンネーム「嵐山光三郎」は京都の嵐山に由来しています。
静岡県浜松市に生まれ、1950年からは東京都国立市で育ち、晩年までその地を拠点としていました。
葬儀・告別式は近親者のみで執り行われた
公表された情報によると、嵐山光三郎さんの葬儀および告別式は、ご遺族の意向により、近親者のみで静かに執り行われました。
突然の訃報であったため、多くの読者や文化人が驚きと寂しさを感じています。
生前の多岐にわたる功績は幅広く、エッセーや編集、テレビ出演を通して日本の文化を豊かにしてくれたと評価されています。
彼の機知に富んだエッセイや『笑っていいとも!増刊号』での出演による遺産は、今後も不朽の作品を通じて生き続けるでしょう。
晩年の様子と「生涯現役」だった執筆活動
嵐山さんは、83歳という高齢になっても、その好奇心と創作意欲が衰えることはありませんでした。
彼は、老いというテーマに正面から向き合い、それを否定するどころか、積極的に楽しむ独自の哲学を持っていました。
その哲学が凝縮されているのが、2025年に刊行された83歳の新刊『爺の流儀』です。
彼はこの本の中で、老いを受け入れ、愉しむ自身の姿を綴り、65歳のときに決めたという「老いの流儀十カ条」に注目が集まりました。
この老いの哲学の根源には、還暦を迎える頃に先輩作家たちから教えられた「65歳からビンボーになる」という現実がありました。
65歳になると、精力が衰え、体力が続かず、性欲、金欲、表現欲が弱くなるのだ、と教えられ、実際に仕事量が減り、収入が50歳の頃の半分になったといいます。
しかし、退職金が出ず年金も少ない自由業者の身として、嵐山さんは「生活するためにいつまでも働かなければいけない」という現実を受け入れました。
その中で彼が発見したのが、「楽しみは人生の下り坂にあり!」という「下り坂の極意」です。
55歳で友人の坂崎重盛(エッセイスト)とママチャリで『奥の細道』を走破した自転車旅行の際に、ぜいぜい息を切らして登りきった後の下り坂の爽快感を体感し、この思想に辿り着きました。
彼は、上昇志向のものが多い世間の「ジジイ指南書」に対し、「年をとったら、ヨロヨロと下り坂を楽しめばいい」とし、「落ちめの快感は、成り上りの快感に勝る」と喝破しました。
また、彼は自身の健康不安さえも創作の力に変えました。
腱鞘炎や肩こり、眼科系の疾患などを経験しながらも、それを「病気自慢」としてエッセイで面白おかしくレポートする転換力を持っていました。
雑誌『週刊朝日』で連載されていたエッセー「コンセント抜いたか」は、1100回を超える長期連載となり、2020年1月からは土曜日の日本経済新聞夕刊でも「あすへの話題」を連載するなど、最晩年まで精力的に筆を執り続けた「生涯現役」の作家でした。
追悼・今読み返したい嵐山光三郎さんの5冊の著書
嵐山光三郎さんの著作活動は、編集者としての知見、旅人としての足跡、そして文人としての深い教養に裏打ちされていました。
彼の名を不朽のものとした代表作の数々は、今改めて読むことで、彼の多面的な功績と人間的魅力に触れることができます。
受賞歴
嵐山光三郎さんが生前に受賞した主要な文学賞は以下の通りです。
- 1988年: 『素人庖丁記』にて第4回講談社エッセイ賞を受賞。
- 2000年: 『芭蕉の誘惑』(後に『芭蕉紀行』と改題)にて第9回JTB紀行文学大賞を受賞。
- 2006年: 『悪党芭蕉』にて第34回泉鏡花文学賞を受賞。
- 2007年: 『悪党芭蕉』にて第58回読売文学賞(評論・伝記賞)を受賞。
紹介1:『素人庖丁記』(1987)
『素人庖丁記』は、嵐山さんが長年『週刊現代』に連載していた「素人庖丁記」をまとめたもので、彼の料理への愛とユーモアが溢れるエッセイです。
この作品は、1988年に講談社エッセイ賞を受賞し、彼の作家としての地位を確立しました。
プロの技術ではなく、素人ならではの視点で料理を語り、日常の食卓に潜む喜びや失敗、そして「ごはんの力」といったテーマを軽やかに描いています。
料理を趣味としていた嵐山さんにとって、この作品は自身のライフスタイルを反映した原点とも言える一冊です。
紹介2:『文人悪食』(1997)
嵐山文学の代名詞とも言えるのが、この『文人悪食』です。
このエッセイは、夏目漱石、森鴎外、島崎藤村、芥川龍之介、太宰治など、総勢37人の近代日本の文士たちに焦点を当て、彼らの食の好みや「悪食」(あくじき)の傾向から、その裏側にある人間性や文学の本質に迫っています。
例えば、夏目漱石が夫人に隠れてピーナッツの砂糖まぶしを食べ続けた逸話や、島崎藤村がまずい料理を「しんしんと冷える悲しさ」をもって表現する天才だったという分析は、読者に大きなインパクトを与えました。
嵐山さんは、「粗食淫乱は、青年の特質である。貧乏青年は、藤村に限らず、みな粗食淫乱である」と喝破するなど、文士たちの私生活と文学の関連性を軽妙かつ大胆に結びつけています。
この作品は、文化を身近に伝え続けた嵐山さんの功績を象徴する一冊であり、2000年に新潮文庫からも刊行されました。
紹介3:『芭蕉の誘惑』(2000)
『芭蕉の誘惑 全紀行を追いかける』は、嵐山さんの長年のテーマであった「旅」と「文人」を組み合わせた本格的な紀行文です。
中学三年で芭蕉の言霊に触れたという嵐山さんが、松尾芭蕉の全紀行を自ら辿り、旅の道中で得た感覚や思索を綴った作品です。
この旅の記録は、2000年にJTB紀行文学大賞を受賞しました。
この作品で嵐山さんは、神格化された俳聖としての芭蕉ではなく、一人の人間としての芭蕉の姿を追求し、後の大作『悪党芭蕉』へと続く足跡を記しています。
紹介4:『悪党芭蕉』(2006)
嵐山光三郎さんの作家キャリアにおける最高峰の一つが、この『悪党芭蕉』です。
彼はこの作品で、芭蕉を「俳聖」としてではなく、弟子たちを巧みに束ね、句論を確立するために奔走した、ある種の「悪党」としての側面から捉え直しました。
この人間味あふれる、挑戦的な評伝は高く評価され、2006年に泉鏡花文学賞、そして翌年の2007年には読売文学賞評論・伝記賞という、権威ある二つの賞を立て続けに受賞しました。
『悪党芭蕉』は、嵐山さんが得意とする文学的批評眼と、取材に基づく詳細な知識、そしてユーモアが一体となった、評論・伝記文学における金字塔的な作品です。
紹介5:『漂流怪人・きだみのる』(2016)
『漂流怪人・きだみのる』は、晩年の嵐山さんが、異端の民俗学者・人類学者であったきだみのるの生涯を描いた評伝です。
きだみのるの波乱に満ちた人生や、常識の枠に収まらない「怪人」としての側面を、嵐山さんならではの視点で詳細に描写しています。
この作品は、嵐山さんが生涯を通じて追求した「不良中年」や「異端」といったテーマを、一人の人物を通じて深く掘り下げたものであり、評伝作家としての彼の探求心と筆力が示された一冊です。
喪主や遺族は?嵐山光三郎さんの家族構成
作家のプライベート、特に彼の「老い」の哲学を支えた家族の存在は、読者にとって大きな関心事でした。
嵐山さんは、その著作やエッセイの中で、家族をユーモアを交えながら愛情深く描き、その強い絆をうかがわせています。
妻や家族に見守られた静かな別れ
嵐山光三郎さんの葬儀および告別式は、ご遺族の希望により近親者のみで執り行われました。
喪主をはじめとする遺族の氏名は公表されていませんが、ご家族に見守られながら静かに最期の時を迎えたと推察されます。
嵐山さんは、8歳の頃から愛着を持って住み続けた東京都国立市を創作と生活の拠点としており、その穏やかな地域生活の中で、家族の献身的な支えがあったことは想像に難くありません。
プライベートで見せた素顔と家族への想い
嵐山さんの著作にたびたび登場する奥様は、彼の人生において最も重要な存在でした。彼は2008年の著書『妻との修復』の中で、奥様を畏敬とユーモアを込めて「超獣」と表現しました。
この「超獣」という言葉は、嵐山さんが家庭内では奥様に頭が上がらない、いわゆる「恐妻家」であることを示していますが、これはネガティブな意味ではありませんでした。
奥様が家庭の経済面、健康面をしっかりと管理し、現実という地面に足をつけた「司令塔」として機能してくれたからこそ、嵐山さんは安心して不規則な作家生活や自由な旅に没頭することができたのです。
彼は、この「頭が上がらない状態」こそが、家庭の平和と円満の秘訣であると達観していました。
また、嵐山さんの人生観に大きな影響を与えたのが、103歳まで生きた母親、ヨシ子さん(祐乗坊ヨシ子さん)です。
嵐山さんは『おはよう!ヨシ子さん』や『ゆうゆうヨシ子さん-ローボ百歳の日々』の中で、夫に先立たれた後も塞ぎ込むことなく、俳句(84歳で句集『山茶花』を発表)を生きがいとして精力的に活動を続けた母のバイタリティを描いています。
嵐山さんが「枯れてたまるか!」と意気軒昂に執筆を続けられた尽きせぬエネルギーは、この母・ヨシ子さんの生命力から受け継いだものであると言えるでしょう。
なお、インターネット上で「息子」という検索キーワードが目立ちますが、これは主に、嵐山さんが親交の深かった檀一雄さんの長男である檀太郎さんとの交流に由来する可能性が高いです。
嵐山さんは檀一雄を心の師と仰ぎ、その息子である檀太郎さんとは兄弟のように親しい関係を築いていたため、読者や視聴者の中で誤解が生まれたと推測されます。
さらに、嵐山さんの父親は祐乗坊 宣明といい、朝日新聞社社員を経て多摩美術大学教授を務めたグラフィックデザイナー、教育者でした。
父親は2000年4月3日に肺炎で死去しており、嵐山さんはその介護と看取りの経験を『よろしく』などの著書で赤裸々に綴り、自身の死生観や老いに対する考え方を形成する重要な要素としました。
弟の祐乗坊 進は、造園コンサルタントで多摩美術大学講師を務めています。
編集者から作家へ、異色の経歴を振り返る
嵐山光三郎さんのキャリアは、伝統的な文人とは一線を画します。
彼の創造性の源は、雑誌編集者として培った知識、人脈、そして時代の空気を掴む鋭い感性にありました。
平凡社「太陽」編集長時代の伝説的仕事
嵐山光三郎さんは、國學院大學文学部国文科(中世文学専攻)を1965年に卒業後、同年、平凡社に入社しました。
当時の平凡社は「国民百科事典」の売上が絶好調な時期であり、嵐山さんはそこで雑誌『別冊太陽』と、特に『太陽』の編集に16年間携わりました。
後に編集長も務め、「年賀状の図案特集」をヒットさせるなど、辣腕を振るいました。
編集者として、彼は檀一雄、澁澤龍彦といった文豪たちと親交を結び、深沢七郎を「師匠」と呼び、また、唐十郎、篠山紀信、糸井重里、南伸坊など、ジャンルを超えた多くの才能と交流を持ちました。
特にイラストレーターの安西水丸さんとは平凡社で出会い、1976年には共作絵本『ピッキーとポッキー』を刊行。
これは40年間で70万部近くを売り上げるロングセラーとなりました。
安西さんのペンネームの「安西」は、嵐山さんが「あ」がつく名前が良いと提案したことがきっかけで、祖母の苗字から取られたものです。
作家転身と「昭和軽薄体」が与えた衝撃
1981年、平凡社の経営危機を背景に、嵐山さんは馬場一郎編集局長や部下らを率いて独立し、青人社を設立しました。
翌年には雑誌『DoLiVe 月刊ドリブ』を創刊し、作家としての活動を本格化させました。
この独立後の活動で、彼は椎名誠さんらとともに、1980年代の文章表現に大きな変革をもたらす文体、「昭和軽薄体」を確立しました。
この文体の特徴は、従来の堅苦しい文語調に対し、カタカナやアルファベットを多用し、日常の話し言葉の持つリズムとユーモアを文章に取り込んだ点にあります。
代表的な例として、「…なのでR」(である)や「ヒジョーに」(非常に)、「かなC」(悲しい)といった表現が挙げられます。
嵐山さんは、この一見ふざけているようにも見える文体について、「日常の話し言葉を文章化するのは大変技術がいること」であるとし、「言葉を変革する思いがあった」と述べています。
これは、硬直化した日本の文章表現を解きほぐそうという、高い教養とユーモアセンスに裏打ちされた知的な挑戦であり、雑誌『宝島』などで人気を博し、一世を風靡しました。
テレビ番組や「笑っていいとも!増刊号」での活躍
嵐山光三郎さんは、作家や編集者としての側面だけでなく、テレビタレントとしても広く親しまれました。
タモリさんが司会を務める『今夜は最高!』への出演がきっかけとなり、1982年からはフジテレビの長寿番組『笑っていいとも!増刊号』に、番組の「初代編集長」というユニークな肩書きでレギュラー出演しました。
本物の雑誌編集長としての経験を背景に、嵐山さんは番組を仕切る役割を担い、その知性とユーモア、機知に富んだ受け答えで、多くの視聴者に親しまれました。
SNSでも、「増刊号」での魅力的な出演は「多くの人々に喜びと洞察をもたらしました」と追悼されています。
この他にも、テレビ東京の『クイズ地球まるかじり』(1983年 – 1985年)に解答者として、また『コンピュートないと』(1984年)や『嵐の冗談本舗』(1988年)で司会を務めるなど、多忙なテレビタレントとしての顔も持っていました。
NHKの『食は文学にあり』の再放送が懐かしがられることもありました。
さらに、アートネイチャー(1984年)や、イラストレーターの南伸坊、湯村輝彦らと共演した東京ガス(1984年 – 1986年)など、多くのCMにも出演し、その存在感は文化界のみならず、お茶の間にも深く浸透していました。
嵐山光三郎さんに関するFAQ
嵐山光三郎さんの生涯、功績、そしてプライベートに関する、よくあるQ&Aをまとめました。
- Q1. 嵐山光三郎さんの本名は何ですか?
- A1. 本名は祐乗坊 英昭(ゆうじょうぼう ひであき)です。この珍しい苗字は静岡県に多いとされています。ペンネーム「嵐山」は京都の嵐山に由来し、本名を見た読者からは「嵐山という派手な発明よりさらに珍しいご本名で驚いた」といった声も上がっています。
- Q2. 嵐山さんの生年月日と没年月日、享年を教えてください。
- A2. 生年月日は1942年(昭和17年)1月10日で、没年月日は2025年11月14日です。83歳で亡くなられました。
- Q3. 嵐山さんの死因は何ですか?
- A3. 死因は肺炎と公表されています。
- Q4. 嵐山さんはどのような経歴で作家になったのですか?
- A4. 1965年に國學院大學文学部国文科を卒業後、平凡社に入社し、雑誌『太陽』の編集長を16年間務めました。1981年に独立して青人社を設立し、作家活動を本格化させ、文芸、旅、食のテーマで独自のエッセイ、評伝を発表しました。
- Q5. 嵐山さんが提唱した「昭和軽薄体」とはどのような文体ですか?
- A5. 1980年代に椎名誠さんらとともに生み出した、日常の話し言葉を文章化する文体です。「…なのでR」、「非常に」を「ヒジョーに」のように、カタカナやアルファベットを多用するのが特徴で、硬直化した文章表現に風穴を開ける、知的な挑戦でした。
- Q6. 『笑っていいとも!増刊号』での役割は何でしたか?
- A6. 「初代編集長」として、1982年からレギュラー出演しました。本物の編集長経験を活かし、番組を仕切る役割を担い、その知性とユーモアで長年親しまれました。
- Q7. 嵐山さんとイラストレーターの安西水丸さんの関係は深かったのですか?
- A7. 非常に深い親交がありました。平凡社時代に知り合い、1976年には共作絵本『ピッキーとポッキー』を刊行しロングセラーとなりました。安西さんのペンネーム「安西」は嵐山さんの提案によるものです。安西さんが亡くなった際、嵐山さんは朝日新聞に追悼文を寄稿しています。
- Q8. 嵐山さんの父親や弟はどのような人ですか?
- A8. 父親は祐乗坊 宣明で、朝日新聞社社員から多摩美術大学教授に転じたグラフィックデザイナー、教育者でした。弟の祐乗坊 進は造園コンサルタントで、多摩美術大学講師を務めています。
- Q9. 嵐山さんの妻を指す「超獣」という言葉の由来は何ですか?
- A9. 2008年の著書『妻との修復』で、奥様への畏敬の念とユーモアを込めて表現した言葉です。妻が家庭の経済や健康を管理し、夫が作家活動に専念できるよう支える「司令塔」としての揺るぎない存在感を「超獣」と称しました。
- Q10. 晩年の嵐山さんの「老い」に関する哲学は何ですか?
- A10. 著書『爺の流儀』などで提唱された「楽しみは人生の下り坂にあり!」です。年をとった後は、上昇志向ではなく、「ヨロヨロと下り坂を楽しめばいい」とし、「落ちめの快感は、成り上りの快感に勝る」と述べています。
- Q11. 嵐山さんは熱烈な野球ファンだったと聞きますが、どの球団を応援していましたか?
- A11. 20年来の熱烈な阪神タイガースファンでした。デイリースポーツでのエッセイでは、阪神の低迷期(暗黒時代)にファンを励まし、その姿勢は多くの共感を呼びました。
- Q12. 嵐山さんの作品で、文豪の食をテーマにしたものは『文人悪食』以外にありますか?
- A12. あります。『文人悪食』(1997年)の続編として、『文人暴食』(2002年)や、文人たちの妻に焦点を当てた『文人悪妻』、文士が通った店を紹介した『文士の料理店(レストラン)』(2013年)などがあります。
- Q13. 嵐山さんが提唱する老後の過ごし方で、具体的に避けるべきとされた発想は何ですか?
- A13. 彼は「まだまだこれから」「第二の人生」「若いモンには負けない」という上昇志向の発想そのものが老化現象であると指摘し、これらを避けるべきとしていました。代わりに、世間体や見栄を捨て、あらゆることを面白がる「愉快な老後」を提唱していました。
- Q14. 嵐山さんは作家として活躍する傍ら、地元でどのような活動をしていましたか?
- A14. 8歳から在住していた東京都国立市を愛し続け、2010年3月には国立市の教育委員に任命されています。また、地元で句会を主催したり、講演会を開いたりするなど、地域住民との交流を大切にしていました。
- Q15. 嵐山さんが最晩年に力を入れたテーマは何でしたか?
- A15. 松尾芭蕉の再評価と、老いや死生観に関するエッセイです。芭蕉に関する評伝『悪党芭蕉』では、泉鏡花文学賞と読売文学賞を受賞し、老いに関しては「楽しみは下り坂にあり」という哲学を提唱しました。
まとめ
編集者、作家、タレントとして、日本の文化・メディア界に長きにわたり貢献した嵐山光三郎さんが、2025年11月14日に肺炎のため83歳で逝去されました。
その多岐にわたる功績は、私たちに多くの教訓と楽しみを残してくれました。
嵐山さんのキャリアは、平凡社『太陽』編集長としての華々しい実績から、椎名誠さんらと確立した「昭和軽薄体」という革新的な日本語表現、そしてフジテレビ『笑っていいとも!増刊号』の初代編集長としての活躍と、常に時代の最前線にありました。
特に「昭和軽薄体」は、「…なのでR」に象徴されるように、硬直化した文章を解きほぐす役割を果たしました。
作家としては、食を切り口に文豪の人間像に迫った『文人悪食』、芭蕉を人間的な「悪党」として描いた『悪党芭蕉』(読売文学賞、泉鏡花文学賞受賞)といった評伝で知られ、知性とユーモアを融合させた独自の文学ジャンルを築きました。
彼の人生観は、奥様を「超獣」と呼び、その強固な生活力に支えられて自由な創作を続けたという、達観した夫婦関係に象徴されます。
また、103歳まで生きた母、ヨシ子さんのバイタリティは、彼の「枯れてたまるか!」という作家魂の源流となりました。晩年提唱した「楽しみは下り坂にあり!」という哲学は、老いを恐れるのではなく、いかに愉快に人生を終えるかという、現代人への重要なメッセージとなりました。
長年愛した国立市を拠点に、家族と地域社会とのつながりを大切にし続けた嵐山さんの生涯は、多くの人々の記憶に刻まれ続けるでしょう。心よりご冥福をお祈りいたします。
- 作家の嵐山光三郎さんは2025年11月14日、肺炎のため83歳で死去されました。
- 葬儀・告別式は近親者のみで執り行われ、訃報は11月28日に公表されました。
- キャリアは平凡社『太陽』編集長から始まり、1981年に独立して作家活動に入りました。
- 椎名誠らとともに、「…なのでR」で知られる「昭和軽薄体」を生み出し、日本語表現に革命を起こしました。
- テレビでは『笑っていいとも!増刊号』の初代編集長として活躍し、お茶の間に親しまれました。
- 代表作に『素人庖丁記』(講談社エッセイ賞)、『文人悪食』、『悪党芭蕉』(泉鏡花文学賞、読売文学賞)などがあります。
- 妻を「超獣」と呼んだことや、103歳まで生きた母ヨシ子さんの存在が、彼の人生観に大きな影響を与えました。
- 晩年は「楽しみは下り坂にあり!」という哲学を提唱し、老いを愉しむ姿勢を貫きました。

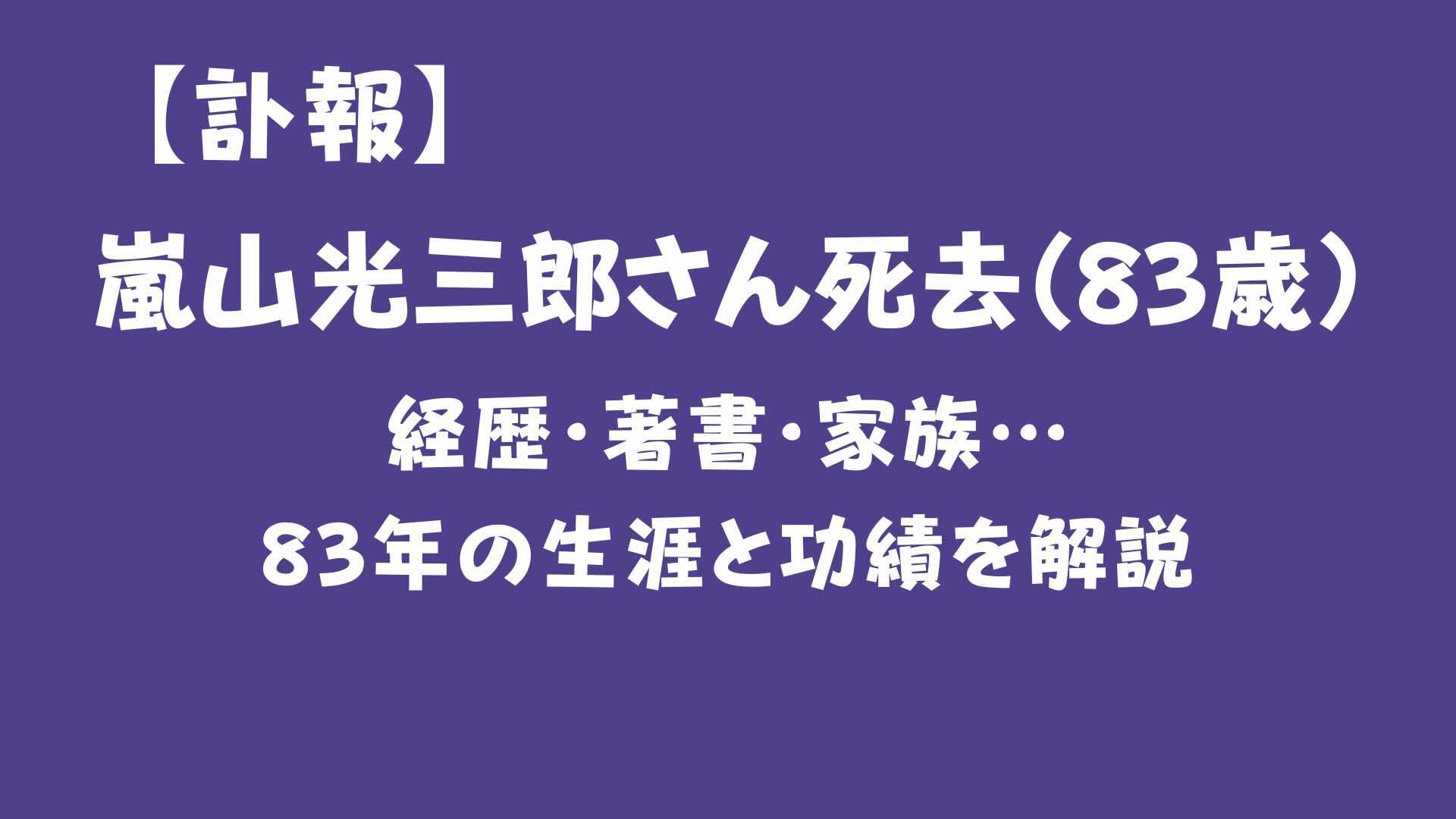





コメント