2025年9月20日、兵庫県姫路市で国勢調査員を務めていた80歳の男性が、調査活動中に倒れ、亡くなるという痛ましい出来事がありました。心臓に持病があったと報じられていますが、この一件は、日本の最も重要な統計調査である国勢調査が抱える構造的な問題を、私たちに突きつけています。
5年に一度、日本に住むすべての人と世帯を対象に行われる国勢調査。そのデータは、選挙区の画定や地方交付税の配分、防災計画の策定など、私たちの暮らしの根幹を支える政策に欠かせないものです。
この巨大な調査を最前線で支えているのが、全国で約60万人も任命される「国勢調査員」です。彼らは、担当地域を一軒一軒訪問し、調査票を配布・回収するという極めて重要な役割を担っています。しかし、その過酷な実態は、あまり知られていません。
今回の悲劇を単なる「不幸な事故」で終わらせてはなりません。調査員が直面する厳しい現実と制度疲労に目を向け、国勢調査のあり方そのものを、根本から見直すべき時が来ています。
疲弊する現場:国勢調査が抱える深刻な問題点!
今回の事件で亡くなった調査員が80歳だったという事実は、決して特別なケースではありません。国勢調査の現場では、調査員の高齢化が深刻な問題となっています。
調査員の高齢化と過酷な労働
地域の事情に詳しいという理由から、定年退職した方などが調査員を引き受けるケースが多く、必然的に調査員の平均年齢は高くなっています。体力的な負担は想像を絶します。炎天下や雨の中、重い調査用品を抱えて階段を何度も上り下りし、担当する数十〜百数十世帯を訪問するのです。
さらに、近年は精神的な負担も増大しています。プライバシー意識の高まりから、調査への協力を拒まれたり、「なぜそんなことまで答えないといけないのか」と詰問されたりすることも日常茶飯事です。中には、不審者扱いをされたり、罵声を浴びせられたりするケースも少なくありません。
オートロックマンションの増加で住民との接触自体が困難になり、共働きや単身世帯の増加で日中に訪問しても留守であることも多く、調査員の心身の疲労はピークに達しています。
深刻な「なり手不足」
こうした過酷な労働環境に加え、報酬の低さも「なり手不足」に拍車をかけています。調査員の身分は非常勤の国家公務員ですが、その報酬は調査区の世帯数などに応じて数万円程度。時給に換算すれば、最低賃金を下回ることも珍しくありません。
「地域の役に立ちたい」という善意や責任感に支えられてきた調査員制度ですが、もはやそれだけでは限界です。リスクと負担に見合わない報酬。その結果、自治会などが調査員の推薦に苦慮し、自治体の職員が通常業務と並行して調査員を兼務せざるを得ないケースも増えています。まさに、制度そのものが疲弊しきっているのです。
未来への提言:国勢調査はこう変わるべきでは?
このままでは、国勢調査の精度を維持することすら困難になります。私たちは、調査員の善意に頼り切った時代遅れの仕組みから脱却し、テクノロジーと制度設計によって、安全で効率的な調査を実現しなければなりません。
オンライン回答の「原則化」とインセンティブ導入
鍵となるのは、オンライン回答の更なる推進です。2020年の調査ではオンライン回答率が37.9%にとどまりましたが、これを原則とし、紙の調査票は希望者のみに配布する方式へ転換すべきです。これにより、調査員の訪問業務が大幅に削減され、負担とリスクを劇的に軽減できます。
さらに、オンライン回答者にはマイナポイントを付与するなど、国民が積極的にデジタルでの回答を選択するようなインセンティブも有効でしょう。
調査員制度の抜本的改革
調査員の役割も見直す必要があります。オンライン回答が主流になれば、調査員の仕事は、オンラインでの回答が困難な高齢者世帯などへのサポートが中心となります。専門的なスキルを持つ人材を「統計調査支援員」として専門職化し、待遇を大幅に改善することで、質の高い担い手を確保すべきです。また、訪問が必要な場合でも、必ず2人1組で行動するなど、安全確保のルールを徹底する必要があります。
マイナンバー制度との連携強化
将来的には、マイナンバー制度と連携し、住民基本台帳などの行政記録情報を活用する「レジスターベース」の調査への移行も視野に入れるべきです。これにより、国民の回答負担をなくし、調査員の訪問を必要としない、全く新しい形の国勢調査が実現できる可能性があります。プライバシー保護とのバランスを慎重に議論しつつ、次世代の統計調査の姿を模索していく必要があります。
_/_/_/
今回の悲劇は、私たち一人ひとりが国勢調査のあり方を真剣に考えるべきだという警鐘です。調査員の安全を守り、未来の日本のために正確なデータを残していく。その両立のために、今こそ、大きな一歩を踏み出す時です。
ここだけの話…
筆者 taoは、とある田舎町のさらに小さな行政区(自治会)の役員をしています。
今回の国勢調査については、町から指定人数の調査員を選出する旨の要請があり、自治区内で選出して、指定人数分申請しました。彼らの平均年齢は72歳。「60歳以下の現役世代では、なり手がいない」というのが現状です。
当自治会内では大きなマンションがなく、大変な階段の上り下りはないものの、それでも、昼間留守宅はとても多いです。つまり、一回の訪問で完徹する仕事ではありません。また、一回訪問して調査票を渡してそれでおしまいではなく、ネット回答の場合以外については回収の仕事もあります。
調査に際しては、町から幾ばくかの報酬がでるものの、それに費やす時間で割り返すと、とんでもない時給となります(あえて具体的な数字は書きませんが)。
さて、9月20日の昼頃、私は自宅2階の仕事部屋でいろいろやっていました。すると、階下からドンドンと音がします。その日、家人は留守で私一人で調査員の訪問に気がつきませんでした。2階から覗くと、調査員をお願いしたAさん(79歳)でした。慌てて、玄関まで行きます。
対面して、いろいろチェックしてくれたAさん。そして、調査票を受領しました。調査開始の初日から熱心に働くAさん、ありがとうございます。
Aさんには「私はこれからすぐにネットで回答します!」とお話して、Aさんがお帰りになってから、すぐにネット回答しました。
Aさんのお話では、20日は土曜日だからか、留守宅も多いとのお話でした。Aさんは何回か調査員をやっている方で、そういう面倒なこともすっかり受容して、懸命に仕事をしてくれる方。19日くらいからすっかり気候が変わり、涼しくなったので、それだけでも良かったと考えています。
数日前のような酷暑のなか80歳近くの方が、歩き回って調査書を配るのは、とんでもない激務だからです。
80歳の調査員が亡くなったというニュースを見聞きして、制度の問題点だなと感じて記事を書いた次第です。
国勢調査制度に関するFAQ
本文と重複しない形で、国勢調査制度に関する「よくあるQ&A」をまとめました。
- Q1. 国勢調査はなぜ5年ごとに行われるの?
- A1. 社会は常に変化しているため、定期的に日本の人口や世帯の実態を正確に把握する必要があるからです。5年ごとという周期は、国際的な慣行や、変化のスピードを捉える上で適切とされています。なお、国勢調査は1920年(大正9年)が最初の実施で、100年以上の歴史があります。ちなみに、調査対象は日本国内に居住するすべての人と世帯が対象です。
- Q2. 国勢調査に回答しないと、罰則はありますか?
- A2. はい、あります。統計法では、国勢調査のような基幹統計調査への報告は国民の義務と定められており、報告を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合は「50万円以下の罰金」が科される可能性があります。
- Q3. 調査員はどんな身分の人ですか?
- A3. 総務大臣によって任命される、調査期間中だけ特別に任命される「非常勤の国家公務員」です。調査員には、調査で知り得た秘密を守る義務(守秘義務)が課せられています。
- Q4. 調査で答えた個人情報は、本当に守られるのですか?
- A4. はい、統計法によって厳しく保護されています。調査員をはじめとする調査関係者には厳しい守秘義務が課されており、調査票の記入内容を他に漏らすことは固く禁じられています。違反した場合は、懲役または罰金が科されます。また、集められた調査票は厳重に管理され、統計作成の目的以外に利用されることは一切ありません。
- Q5. インターネットで回答するメリットは何ですか?
- A5. 24時間いつでも、ご自身の都合の良い時間にパソコンやスマートフォンから回答できる点です。また、調査員と顔を合わせる必要がないため、プライバシーの面でも安心感があります。入力漏れや誤りを自動でチェックする機能もあり、正確な回答がしやすいのもメリットです。なお、インターネット回答に際しては、調査票に記載されたログインIDとアクセスキーが必要です。
- Q6. 調査員には、どのような手当が支給されるのですか?
- A6. 報酬として、担当する調査区の世帯数などに応じて手当が支払われます。金額は自治体や担当エリアによって異なります。
- Q7. 「かたり調査」って何ですか? 見分ける方法は?
- A7. 国勢調査を装って、不正に個人情報を聞き出そうとする詐欺行為です。正規の調査員は、必ず顔写真付きの「国勢調査員証」と「腕章」を身につけています。訪問を受けた際は、まず身分証明書の提示を求めてください。また、調査員が電話やメールで銀行の暗証番号やクレジットカード番号を聞き出すことは絶対にありません。
- Q8. 調査票の配布や回収に来る時間帯は決まっていますか?
- A8. 特に厳密な決まりはありません。調査員は、日中不在の世帯も考慮し、朝や夜間、土日などに訪問することがあります。もし都合が悪い場合は、調査員が残した不在連絡票などを見て、訪問日時を調整することが可能です。
- Q9. オートロックのマンションには、どうやって入ってくるのですか?
- A9. 事前に管理人や管理組合に国勢調査の実施を説明し、許可を得て立ち入るのが基本です。場合によっては、エントランスで各戸のインターホンを鳴らして、調査の趣旨を説明して解錠してもらうこともあります。
- Q10. 日本に住んでいる外国人も調査の対象になりますか?
- A10. はい、国籍に関わらず、ふだん日本国内に住んでいる人はすべて調査の対象となります。これには、3か月以上日本に滞在している留学生や技能実習生なども含まれます。調査票は多言語に対応しています。
- Q11. 集められたデータは、具体的に何に使われているのですか?
- A11. 衆議院の選挙区の区割りや、国から地方自治体へ配分される地方交付税の算定基準、地域の防災計画(避難所の設置場所や備蓄品の量の決定など)、企業の出店計画や製品開発など、非常に幅広い分野で、私たちの生活を支えるための基礎資料として活用されています。
- Q12. 回答結果はどのくらいで公表される?
- 集計には時間がかかり、速報値は数か月後、詳細結果は1~2年後に公表されます。
まとめ
80歳の調査員が調査活動中に亡くなった痛ましい出来事は、単なる一個人の悲劇ではなく、調査員の善意と自己犠牲という、もはや限界に達している土台の上に成り立ってきた国勢調査制度そのものの歪みを象徴しています。
調査員の高齢化、過酷な労働、そして深刻ななり手不足という現実を直視し、私たちはオンライン回答の原則化やマイナンバー制度との連携といったテクノロジーの活用を急がなければなりません。
この悲劇を教訓に、調査員の安全を守りつつ、正確な統計を未来へつなぐための、持続可能で新しい調査の形を社会全体で構築していくことが今、強く求められています。

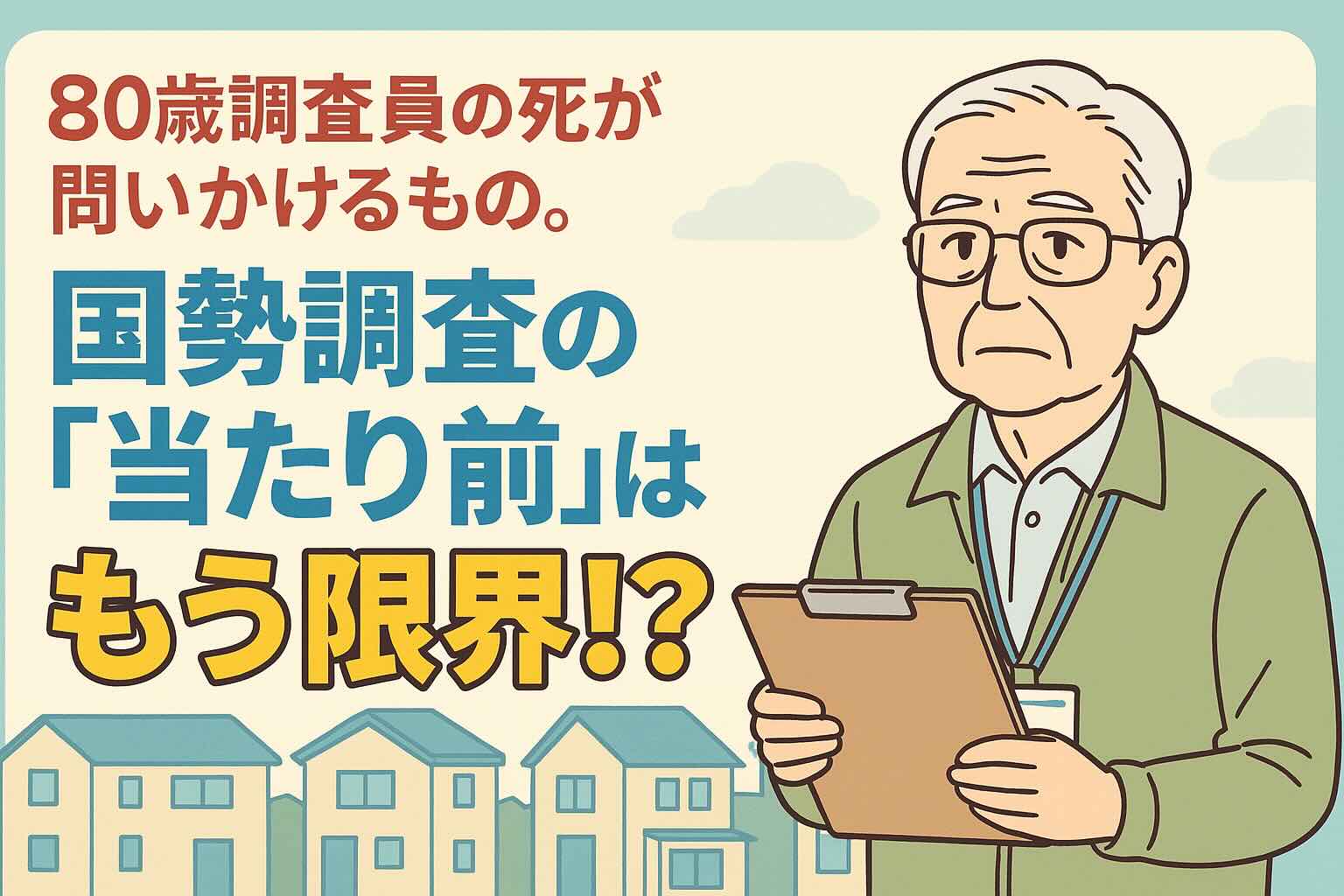
コメント