2025年10月31日、ガソリン価格の高騰に苦しむドライバーにとって待望の朗報が飛び込んできました。自民党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、公明党、共産の与野党6党の実務者間で、ガソリン税の旧暫定税率(1リットルあたり25.1円)を年内最終日となる12月31日に廃止することで合意が成立したのです。これは高市政権が打ち出す物価高対策の第1弾と位置づけられています。
しかし、この決定は単純な「値下げ」では終わらず、国と地方で年間約1.5兆円にも及ぶ巨額の税収減の穴埋めをどうするかという、代替財源問題に結論を先送りしたままの「政治的な大取引」の結果です。この合意の背景には、財政規律を重視する勢力や、財源不足を懸念する地方自治体からの強い抵抗がありました。
本記事では、この暫定税率廃止に至るまでの政治の舞台裏、制度の維持を主張した「抵抗勢力」の論拠、そして廃止後に私たちの生活や今後の税制全体にどのような影響が及ぶのかを詳細に解説します。
- ガソリン暫定税率12月廃止合意までの主要なプロセスとキープレイヤー(抵抗勢力含む)を整理。
- だれが抵抗したのか(例:自民党税制調査会、地方自治体など)を把握。
- 今回の合意がどういう影響をもたらすか、何が次のアクションかを理解。
動画&音声解説!
本記事の動画解説をつくりました。Notebook LMで作成。6分半ほどの動画です。ぜひ、ご覧ください!
また、より詳しい解説として、音声解説も作りました。なお、読み間違いがちょいちょいありますが、ご容赦ください。約23分弱と長い解説ですが、男女掛け合いの解説でわかりやすい説明となっています!
そもそもガソリン暫定税率とは?
現在、ガソリン価格のおよそ4割が税金で構成されています。その中で今回廃止が決定した旧暫定税率とは、ガソリン税(揮発油税と地方揮発油税)に1リットルあたり25.1円上乗せされている部分を指します。本来の税率(本則税率)は28.7円/Lに過ぎず、この上乗せ分が長らく維持されてきました。
この暫定税率は、1974年に田中角栄内閣の下で、道路整備の財源確保を目的とした「臨時措置」(当初2年間)として導入されました。しかし、その後50年以上にわたり延長され続け、「実質的な恒久増税」となっていました。
また、この税制の大きな問題点として「二重課税(タックス・オン・タックス)」が指摘されています。これは、ガソリン税などの税金を含んだ価格の総額に対して、さらに10%の消費税が課税される構造です。
なお、ガソリン暫定税率廃止については、次の記事もお薦めです。


ガソリン暫定税率12月廃止合意までの経緯を時系列で追う
発端はいつ?なぜ“暫定”税率がここまで残ったのか
前章で説明したことを、少し違った切り口から再度。
暫定税率は1974年に、道路整備財源の確保と第一次オイルショック後の燃料消費抑制という二重の目的で誕生しました。この税収は「道路特定財源制度」の強力な後ろ盾を得て、長らく道路族議員の政治的影響力の源泉となり、地方自治体のインフラ財源としても極めて重要視されてきました。
2009年には道路特定財源制度が廃止され、税収は一般財源化されましたが、国・地方の財政当局は年間約1.5兆円という巨額の税収減を避けるため、ガソリン暫定税率自体はそのまま維持されました。
世論の反発を恐れて本則税率への組み込みを怠り、「暫定」という建前を保ったまま実質的な恒久財源として取り扱い続けたことが、そもそもの問題の根源であると指摘されています。
2024年夏〜秋:棚上げされ続けた議論と焦点のすり替え
ガソリン価格高騰の局面では、長らく「トリガー条項」の凍結解除が野党から要求されてきました。
トリガー条項とは、ガソリン価格が160円/Lを3ヶ月連続で超えた場合に暫定税率分(25.1円)の課税を自動停止する仕組みですが、2011年の東日本大震災以降、復興財源確保と市場混乱防止のため凍結されたままです。
政府はトリガー条項の代わりに、2022年以降、燃料油価格激変緩和措置(補助金)を優先して実施してきました。
こうした中、議論はトリガー条項の凍結解除から、税金そのものである旧暫定税率の恒久的な廃止へと焦点が移り、野党(立憲民主党、国民民主党など)が強く廃止を主張する形となりました。
12月合意直前、政治の動きが一気に加速した理由
議論が加速した背景には、政治状況の変化があります。
- 高市総裁の受け入れ姿勢:
- 10月9日、自民党の高市早苗総裁(当時)が、首相に就任した際には野党提出の暫定税率廃止法案を「通さないといけない」と受け入れる考えを表明しました。
- 政局の混乱と大義:
- 10月10日には公明党が連立離脱を表明する政権の枠組みを揺るがす事態が発生しましたが、ガソリン価格の高騰対策は与野党共通の課題であり、政治状況がどう転んでも暫定税率の廃止は実現する可能性が極めて高い状況でした。
- 物価高対策の優先:
- 今回の合意は、政局の動向に関わらず、国民生活の負担軽減を優先する姿勢が示された結果であり、高市政権の物価高対策の第1弾として位置づけられました。
抵抗勢力、宮沢洋一と自民党税調らは、何を守ろうとしたのか
財政規律か既得権か:税調側の公式・非公式な論拠
ガソリン暫定税率の廃止に最も慎重な姿勢を示したのは、安定的な恒久財源の確保を旨とする自民党税制調査会や財務省といった勢力でした。
彼らの公式な論拠は「代替財源が確保されていない状態での減税(財源論なき減税)」には反対するというものであり、これは国家の財政運営の根幹に関わる問題でした。
非公式には、暫定税率が「意図せざるカーボンプライシング(炭素への価格付け)」として機能してきた側面があり、これを廃止することでガソリン消費を刺激し、日本のカーボンニュートラル目標達成を困難にしかねないという環境政策上の懸念も存在しました。
宮沢洋一氏の発言と影響力の源泉
財務省出身の宮沢洋一氏が税調会長を長く務めていた自民党税制調査会(自民党税調)は、税制の根幹に関わる議論を主導する立場であり、ガソリン暫定税率廃止については、代替財源優先との立場でした。
高市総裁実現で、税調会長は宮沢洋一税調会長に代わり、小野寺五典氏が就くことになり、与野党間の国対マターで取り組むことになっていました。
しかし、前税調会長らの動きによって、小野寺五典税調会長は、これを国対マターから税調マターへと変更してしまいました。
抵抗勢力側の影響力は、巨額の税収減(年1.5兆円)という現実的な財政の穴をどう埋めるかという課題に裏打ちされていました。
税制“官僚政治”のリアルと党内の沈黙
税制議論の難しさは、地方自治体の財政構造への影響にもありました。暫定税率による税収は、軽油引取税や地方揮発油譲与税を通じて、地方の道路整備や老朽化対策、防災・減災事業の貴重な財源(地方分だけで約5,000億円と試算)となっています。
全国市長会や全国知事会といった地方団体は、「唐突な廃止は財源不足を招き、地方行政が機能不全に陥る」として、代替の恒久財源措置を強く求めました。この地方財政への影響を無視できないことが、与党が廃止の決定を遅らせた大きな理由の一つでもあります。
もう一つの抵抗勢力、連立時代の公明党の主張は?
公明党は、ガソリン価格高騰対策の必要性を認めつつも、暫定税率の廃止を巡る議論においては、一貫して「代替財源の確保」が前提条件であるという慎重な立場を取りました。野党が主張する即時廃止の法案に対しては、財源不足を理由に自民党と共に反対姿勢を示していました。
公明党の姿勢は、単純な「抵抗」ではなく、「財源確保と国民生活への影響を考慮した上で、慎重かつ責任ある対応を求める勢力」として振る舞っていたと言えます。
高市政権と対抗勢力の攻防
宮沢税調会長ギリするも…
高市早苗総裁(当時)が野党提出法案の受け入れに前向きな姿勢を示したことは、財政規律を重んじる自民党税調内の慎重論に対する政治的な決断を促すものでした。
高市総裁は、物価高に苦しむ国民の負担軽減を最優先課題とし、政権発足直後の目玉政策として暫定税率廃止を推し進めました。
そして、税調会長を変更したのですが…。あとは前述した通りです。
公明党の連立離脱
高市総裁の廃止受け入れ表明直後に公明党が連立離脱を表明するという事態が発生しました。
しかし、ガソリン価格高騰対策は与野党共通の課題であったため、この政局の混乱の中でも、暫定税率廃止の流れが揺らぐことはありませんでした。
高市首相の苦悩:党内調整と選挙へのらせん的配慮
高市政権にとって、暫定税率の廃止は物価高対策として世論の支持を得るための重要な政策でしたが、同時に、財源問題や地方自治体の懸念といった党内・連立内の調整は避けて通れない苦悩でした。
最終的な与野党合意は、政局の動向に関わらず、国民生活の負担軽減を最優先するという姿勢を示す結果となりました。
総理官邸 vs 税調:政策決定の“戦場”とは
当初、暫定税率廃止は物価高騰に即応するため「国対マター」(国会対策上の緊急課題)として取り組まれていましたが、代替財源の検討が不可欠となったことで、議論の主戦場は「税調マター」(税制調査会の議論)へと移りました。
★国対マターから税調マターへ
最終的に与野党6党の実務者間で合意に至った合意文書には、野党側の主張する年内廃止が盛り込まれた一方で、自民党税調側が求める代替財源に関する具体的な検討項目(法人税の租税特別措置や超富裕層への課税強化など)も含まれ、両者の主張が妥協点を見出した形となりました。
廃止合意が成立する直前で何が起きていたか
“期限”と自民側の妥協案
最終的な合意の大きなポイントは、廃止の実施時期を優先し、安定財源の確保の結論を先送りした点です。
与野党6党は、廃止による年1.5兆円の税収減の穴埋めについて、当面は安易に国債発行に頼らず、税外収入など一時財源でまかなう方針で一致しました。
そして、代替となる安定財源の具体的な方策については、今後1年程度をめどに結論を得るとし、結論を年末の税制改正論議に先送りすることで妥協しました。
与党幹部の密室会談と決定の瞬間
2025年10月31日、自民党の小野寺五典税調会長ら実務者が国会内で協議を行い、合意文書をまとめました。
小野寺氏は協議後、「6党それぞれ違う考えがあるなかで一致できたことはとても大きな意義がある」と述べ、この歴史的な合意を明らかにしました。
ガソリン価格はどうなる?
ガソリン価格の急変動による現場(ガソリンスタンドなど)の混乱や、利用者の買い控えを防ぐため、廃止前に補助金を段階的に積み増すことが合意されました。
具体的には、現在1リットルあたり10円出ている補助金を、11月13日から2週間ごとに5円ずつ段階的に増額し、12月11日には暫定税率分と同じ25.1円相当まで引き上げます。
これにより、税制上の廃止日(12月31日)を迎える前に、価格は実質的に廃止された水準になる予定です。
今後の焦点:税収・ガソリン価格・自治体財源への影響
廃止による価格変動の予測と生活コストへの波及
ガソリン旧暫定税率(25.1円/L)の廃止と、それに伴う補助金の終了(10円/L)が同時に行われた場合、差し引きで約15円/Lの値下げとなる見通しです。
この減税により、自動車を所有する家庭の燃料費の年間支出は全国平均で約1.3万円(みずほリサーチ&テクノロジーズ試算では10,253円)削減されると試算されています。特に、四国、東北、沖縄、北陸といった自動車依存度の高い地域では、より大きな負担軽減効果が見込まれます。
また、軽貨物ドライバーなどの運送事業者にとっても、ガソリン代削減(軽貨物で年間約10万円の削減試算)は収入に直結します。物流コストの抑制は、店舗に並ぶ商品への価格転嫁を抑制し、物価上昇の抑制につながると期待されています。
地方自治体へのしわ寄せと代替財源の行方
廃止による国・地方合わせた年間1.5兆円の税収減のうち、軽油引取税や地方揮発油譲与税といった地方財源分は約5,000億円を占め、地方自治体は「財源論なき減税」に強く反対しています。地方では、道路や橋梁などの老朽化対策への財政需要が今後一層高まるため、安定的な財源確保が不可欠です。
軽油引取税の暫定税率(17.1円)は2026年4月1日に廃止されることが合意されましたが、これに伴う地方財政への影響や、運輸事業振興助成交付金の適切な対応が今後の議論の焦点となります。
代替財源の検討項目としては、法人税に関わる租税特別措置(租特)の見直しや、年間所得1億円を超える富裕層への課税強化(1億円の壁の是正)などが挙げられています。
年明け以降の税制改正全体に与える影響
今回の暫定税率廃止は、自動車に関する税制全体の大きな見直しの序章に過ぎない可能性があります。
- 車体課税の見直し:
- 2026年度からの自動車の車体課税の抜本的な変革がすでに自民党税制調査会の2024年税制改正大綱に盛り込まれています。具体的な動きとして、自動車税の課税指標を現在の排気量ベースから「重量」ベースに導入する検討が進んでいます。
- 走行距離課税の議論:
- 代替財源を確保するための手段として、自動車メーカーなどで組織する日本自動車工業会(自工会)が「絶対反対」の強い姿勢を示す「走行距離課税」が急浮上しています。
- 脱炭素政策への影響:
- ガソリン価格が下がることは、日本の「隠れカーボンプライシング」を解体する行為であり、EV(電気自動車)へのシフトを遅らせるなど、カーボンニュートラル達成に逆行するリスクが指摘されています。
軽油の暫定税率は?
軽油の暫定税率は廃止される見通しです。
主なポイントは以下の通りです。
- 廃止時期:
- 与野党6党の合意により、軽油引取税の暫定税率(1リットルあたり17.1円)は2026年4月1日に廃止される予定です。
- 現在の状況:
- 現在は、恒久的な措置として旧暫定税率分の税率水準が維持されていますが、これは法的には「当分の間」の措置とされています。
- 移行措置:
- 廃止までの移行措置として、現在実施されている補助金(燃料油価格激変緩和対策事業)が段階的に引き上げられ、2025年11月27日には暫定税率と同じ水準(17.1円)になる予定です。
- トリガー条項:
- 原油価格が異常に高騰した場合に、本則税率を上回る部分の課税を停止する「トリガー条項」がありますが、東日本大震災の復興財源確保のため、現在その適用は停止されています。
したがって、今後の法改正により、暫定税率は完全に廃止される方向で議論が進んでいます。
ガソリン暫定税率廃止に関するFAQ
- Q1: 暫定税率が「隠れカーボンプライシング」と呼ばれていたのはなぜですか?
- A1: 1974年の石油危機時に導入された際、道路財源の確保だけでなく、ガソリン消費抑制という目的も含まれていたためです。その高い税率が、意図せず運輸部門における最も強力な価格シグナル(炭素への価格付け)として機能してきました。
- Q2: 「二重課税」とは具体的にどういう問題ですか?
- A2: ガソリンの本体価格にガソリン税(暫定税率を含む)や石油石炭税を加えた合計額に対して、さらに10%の消費税が課税される構造を指します。国民は「税金に税金を払っている」と感じるため、税制への信頼を損なう要因となっています。
- Q3: 廃止によってガソリン価格は正確にいくら下がりますか?
- A3: 暫定税率分25.1円/Lが廃止されますが、現在支給されている10円/Lの補助金も同時に廃止されるため、差し引きで約15.1円/Lの値下げが見込まれます。
- Q4: 軽油の暫定税率廃止が遅れるのはなぜですか?
- A4: 軽油引取税は地方税(17.1円/L)であり、廃止すると地方自治体の財政(約5,000億円/年)に大きな影響が出ます。この地方財政への配慮が背景にあると見られています。
- Q5: 軽油の補助金はどうなりますか?
- A5: 軽油の暫定税率(17.1円)は2026年4月まで残りますが、その間も補助金は段階的に増額され、11月27日には17.1円分と同額になります。ガソリン以外の補助金は継続される可能性が高いと予想されています。
- Q6: 軽油の暫定税率を残したままガソリンの暫定税率を廃止すると、価格はどうなりますか?
- A6: ガソリン価格と軽油価格が逆転する可能性が高いです。現在20円/L程度ある価格差が5円/L程度に縮小するか、軽油の方が高くなるケースも考えられ、物流コスト増大につながるとして問題視されています。
- Q7: 廃止決定までに「政局の混乱」があったというのは本当ですか?
- A7: はい。10月9日に高市総裁が廃止受け入れを表明した直後の10月10日に、公明党が連立離脱を表明する事態が発生しました。しかし、ガソリン高騰対策は与野党共通の課題であったため、政局の動向に関わらず廃止は実現する可能性が高かったとされています。
- Q8: 代替財源として「走行距離課税」が検討されているのはなぜですか?
- A8: 電気自動車(EV)やハイブリッド車の普及が進むとガソリン消費が減少し、将来的にガソリン税収が減少するため、それを補う目的(税の公平性担保)で、走行距離に応じた課税が検討されています。
- Q9: 走行距離課税の導入にはどんな課題がありますか?
- A9: クルマが不可欠な地方在住者や運送事業者の負担増、輸送コスト増加による物価上昇、公正な走行距離の記録方法(不正対策)、EV普及促進というゼロエミッション政策との矛盾が課題として挙げられています。
- Q10: 暫定税率廃止が脱炭素化に逆行すると指摘されているのはなぜですか?
- A10: 価格が下がるとガソリン消費が促進され、CO2排出量が増加する可能性があるためです。国立環境研究所の試算では、運輸部門のCO2排出量が2030年時点で最大7.3%増加する可能性があると指摘されています。
- Q11: ガソリンスタンドの「事務負担」が増加するとはどういうことですか?
- A11: 廃止前に高い税率で仕入れた在庫について、税務署に還付申請を行う手続きが必要となります。これにより、在庫管理や還付申請の事務負担が増え、還付までに時間がかかることによるキャッシュフローの問題が懸念されています。
まとめ
- ガソリン旧暫定税率(25.1円)は2025年12月31日に廃止、軽油は2026年4月1日廃止で合意.
- 段階的な補助金増額により、12月11日には廃止と同水準の価格を実現.
- 代替財源(年1.5兆円)の結論は年末の税制改正議論に先送り.
- 地方自治体は財源確保を強く要求しており、今後の車体課税見直しが焦点となる.
- 減税は短期的には家計を助けるが、脱炭素政策への逆行リスクが指摘されている.
与野党6党は、長年の懸案だったガソリン旧暫定税率(25.1円/L)を2025年12月31日に廃止することで合意しました。
これにより、価格は補助金廃止と相殺されても約15円/Lの値下げが見込まれ、家計や運輸業界の負担軽減が期待されます。
軽油引取税の暫定税率廃止は2026年4月1日となる一方、ガソリン価格は段階的な補助金増額により、12月11日には実質的に廃止された水準に達します。
しかし、代替財源の確保(年1.5兆円の税収減)は結論を先送りし、当面は税外収入などで対応する方針です。
今後の焦点は、地方自治体の財源不足への対応、そして法人税の租税特別措置や車体課税の見直しなど、年末にかけて行われる代替財源と自動車税制全体の議論に移っています。
特に、減税後の自動車税制のあり方(走行距離課税の是非を含む)が、長期的な日本の国益と脱炭素化の達成を左右します。
短期的な利益で終わらせず、今後の税制の動向を注視することが、私たちユーザーに求められます。

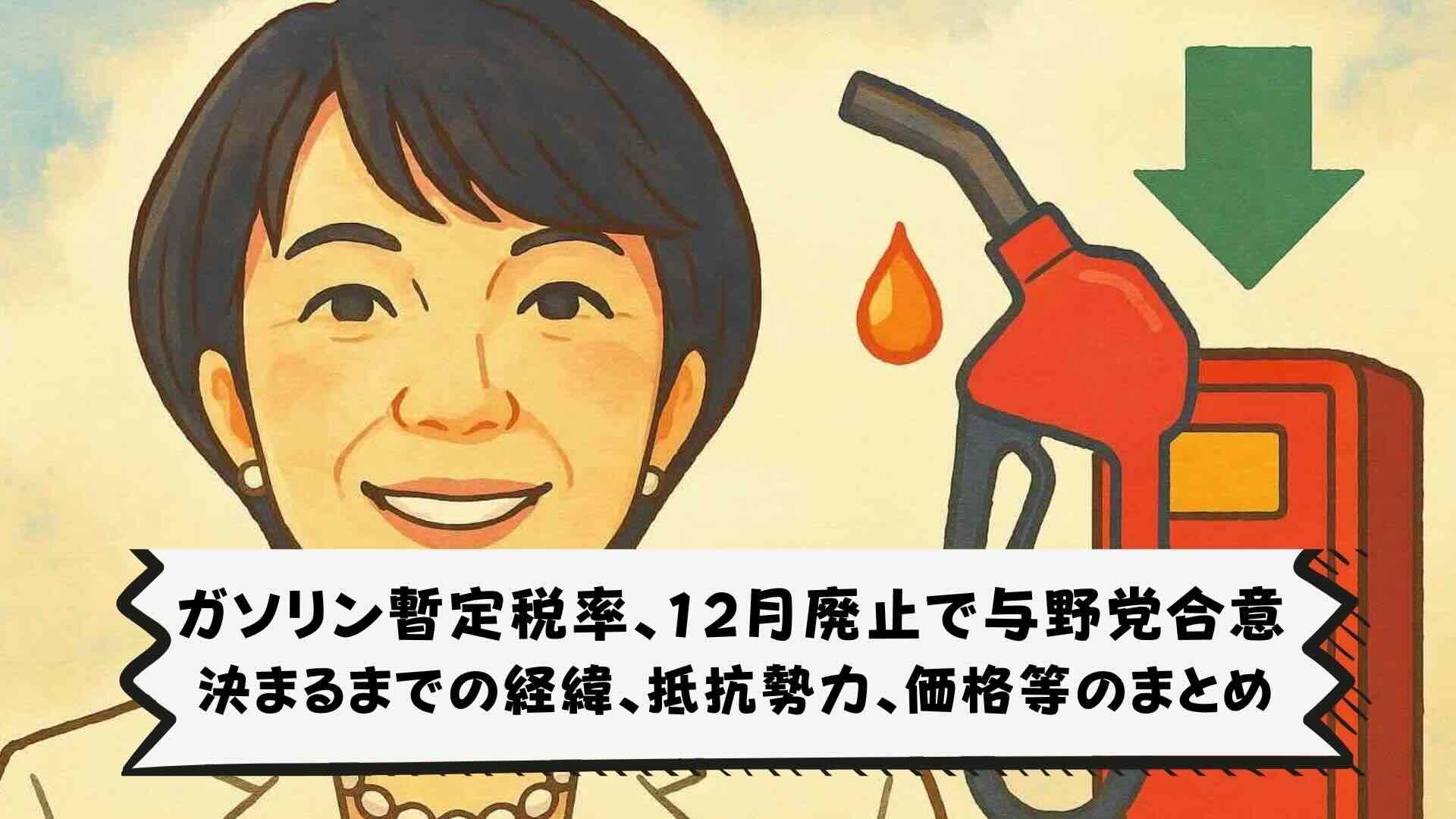
コメント