ヒアリは南米原産の毒アリであり、極めて攻撃性が強く、人体や生態系に深刻な被害を及ぼす「特定外来生物」です。2023年4月からは、まん延した場合に著しく重大な影響を与えるおそれがあるとして、「要緊急対処特定外来生物」に指定され、対策が強化されています。
近年、国際物流の拠点で大規模な集団が相次いで確認されており、その脅威は私たちの生活圏に差し迫っています。特に、東京港青海ふ頭では過去最多となる1万匹超の確認事例も報告されています。
この記事では、ヒアリの国内侵入状況、もたらされる具体的なリスク、そして国や自治体、そして私たち市民が今取るべき具体的な対策について、徹底的に解説します。
- 東京港で発生した大規模なヒアリ発見事例の詳細と侵入ルート
- ヒアリが人、社会インフラ、生態系に及ぼす深刻な影響
- 国・自治体の最新の対策と、市民が備えるべき3つの具体的行動
本記事の動画解説&音声解説!
実験的な取組として、本記事の動画解説と音声解説をNotebook LMで作りました。ただし、まだ誤読があります。たとえば、音声解説では「南相馬市」を「なんそうまし」なんて読んだりしています<(_ _)>
内容の間違いは、ほぼ無い・・・と言えますが、誤読については、今後調整していきますので、ご容赦ください。
【動画解説】
【音声解説】
都内でヒアリが1万匹発見!どこで?なぜ?何が問題?
どこで見つかった?都内の発見現場と状況の詳細
ヒアリの国内での確認事例は、2017年6月の初確認以来、2025年3月現在までに18都道府県で135事例に上っています。多くは港湾地域のコンテナヤードの地面、コンテナの内部や外面、積まれた荷物から見つかっています。
東京都内でも多くの確認事例が報告されており、特に東京港青海ふ頭では過去最多となる1万匹超の確認事例が報告されています。大規模な集団としては、2019年10月に東京港青海ふ頭のコンテナヤード内で、多数の女王アリを含む野外巣が発見されています。
また、2024年度の事例を見ても、東京都品川区の東京港大井ふ頭で約120匹、約70匹、約50匹の確認事例や、東京都江東区の東京港青海ふ頭で約100匹、約80匹の確認事例があり、港湾での監視の重要性が示されています。
中国からのコンテナが発端?ヒアリ侵入のルートとは
日本で発見されたヒアリは、主に船や飛行機に積まれた輸入貨物やコンテナに付着して入り込んでいます。
ヒアリが確認されたコンテナの多くは中国(特に南部)を出港したものとされています。運搬ルートが判明している海上コンテナからの発見事例のうち、出航地または経由地に中国が含まれていた事例が多いとされていますが、明確なデータの出典がなく、断定はできません。
ただし、ヒアリが原産地である南米からアメリカ合衆国等を経て、2000年代には中国でも定着し、その分布が急速に拡大しているという背景はあります。中国国内でのヒアリの分布エリアは、2020年時点で2012年時の3倍近くまで拡大しており、海外に輸出される貨物に紛れ込む機会が増えたと考えられています。
過去の発見事例と比較して何が異常なのか
日本国内では、ヒアリの定着(継続的に生存可能な子孫を作ることに成功する過程)には至っていないとみられています。しかし、発達した集団の確認が複数年続いていることが、対策の強化が必要な『定着のリスクが高まっている段階』であると有識者から警鐘されています。
過去の大規模な発見事例としては、以下のようなものが報告されています。
- 2019年10月:
- 東京港青海ふ頭のコンテナヤード内で多数の女王アリを発見。
- 2020年9月:
- 名古屋港飛島ふ頭の民間事業者敷地内で多数の女王アリを発見。
- 2021年9月:
- 大阪港咲洲で複数の女王アリと働きアリ1,000体以上を発見。
- 2022年10月:
- 広島県福山港で陸揚げされたコンテナ内で、複数の女王アリと働きアリ70,000体以上の大規模集団を確認。
これらの事例は、日本へのヒアリの侵入が単なる一時的なものではなく、集団での営巣や繁殖の試みが頻繁に起こっていることを示しており、定着を阻止するための初期防除の重要性が極めて高い状況にあります。
ヒアリ問題とは何か:人・社会・生態系への影響
健康被害:刺されるとどうなる?アレルギー症状と死亡例
ヒアリは極めて攻撃性が強いアリです。刺された場合、毒により熱感を伴う非常に激しい痛みを感じ、その後、水疱状に腫れ、膿が出るという症状が出ます。
特に問題となるのは、毒に含まれる成分に対するアレルギー反応です。体質によっては、局所的または全身に**かゆみを伴う発疹(じんましん)**が出現することがあります。
重度の症状(息苦しさ、声がれ、激しい動悸、めまいなど)が現れた場合は、アナフィラキシーショックの可能性が強く、進行すると意識を失い、処置が遅れると生命の危険を伴います。ヒアリの毒にはハチ毒との共通成分が含まれており、ハチ毒アレルギーを持つ方は特に注意が必要です。
海外(欧米)ではアナフィラキシー症例が報告されており、アメリカでは毎年数百万人がヒアリに刺されると推定されており、そのうち一部がアナフィラキシーを起こし、死亡の危険性があるとされています。過去のアンケート調査(1989年)では、アメリカ国内でアナフィラキシーによる合計30人の死亡例が報告されています。
社会インフラと物流へのリスク:都市機能が止まる危険性
ヒアリは集団で活動し、社会インフラにも深刻な被害をもたらす可能性があります。
- インフラ設備の破壊:
- 働きアリは体内に磁気に誘引される物質を持っているため、信号などの電気設備やインフラ設備に侵入し、漏電による火災や故障を引き起こし、破壊することがあります。
- 構造物の被害:
- ヒアリが都市の構造物や道の下に巣を作ると、それによって倒壊したり、道に穴が開く危険性があります。
- 物流・農業への影響:
- 農業機械や設備を破壊したり、多種多様な作物を食い荒らしたりする被害も報告されています。
海外の定着地では、ヒアリの被害や対策にかかる費用は膨大です。例えば米国では、対策費や被害額が年間数千億円に上ると推定されています。また、米国定着地では、ヒアリにより花見や花火大会を安心して行えなくなる、サンダルが履けないなど、国民の生活に多大な影響が出ています。
生態系への打撃:在来種の駆逐と生物多様性の喪失
ヒアリは「特定外来生物」であり、在来のアリ類を駆逐するなど、生態系への影響が懸念されています。
ヒアリは肉食性が基本ですが雑食性で、花蜜、樹液、種子から、昆虫、小型脊椎動物のトカゲなどを餌とします。その攻撃力と集団性により、在来のアリ類や節足動物だけでなく、爬虫類や小型ほ乳類をも集団で攻撃し捕食します(家畜への被害も報告されています)。
実際に、アメリカ合衆国テキサス州では、ヒアリの侵入によって餌となる昆虫が減少し、ソウゲンライチョウの亜種(アトウォーター・プレーリー・チキン)が野生絶滅に至ったと推定されています。ニュージーランドなど、ごく一部の国しか侵入後の根絶に成功しておらず、初期防除が極めて重要です。
ヒアリ対策はどう進んでいる?国・自治体の対応
国の水際対策と現場の課題:検疫とモニタリングの現状
ヒアリの国内定着を阻止するため、国(環境省)を始めとする関係機関は、早期発見と根絶を最重要視しています。
- 法規制の強化:
- ヒアリ類は2023年4月に「要緊急対処特定外来生物」に指定され、ヒアリ類が付着・混入するおそれのある物品の輸入等に関わる事業者は、発見・通報体制の整備が義務付けられました。
- 定期的な監視:
- 環境省は国土交通省の協力を得て、中国、台湾などヒアリ定着国からの定期コンテナ航路を有する港湾で、定期的(年に2回)な生息状況の確認調査を実施しています。
- 日常的な監視の課題:
- ヒアリは輸入に使用されたコンテナや貨物に混入・付着している可能性があるため、物流に関わる各者が日々の業務の中で、コンテナの開口部や床板の隙間など、重点的にチェックする日常的な監視が重要とされています。
また、発見時の確実な駆除と侵入防止のため、新たな技術の開発も進められています。
- 新技術の導入:
- 人間には見えない地中(20cm程度)に潜む少数のヒアリも見つけることができるヒアリ探知犬の導入が検討されています。
- 化学的・物理的対策:
- わさびの辛み成分(アリルイソチオシアネート)を用いた忌避効果・殺虫効果のある資材開発、およびコンテナヤードの舗装の割れ目をシリコン樹脂で簡易に補修する技術の開発も進められています。
自治体の防除体制:予算・人員・連携の実態
国内での定着阻止には、地方公共団体や港湾管理者が、地域や現場の実態に合わせて迅速かつ細やかに対応することが不可欠であり、早期防除において大きな役割を担っています。
- 連絡体制の整備:
- ヒアリと疑わしいアリが見つかった場合、数の大小に関わらず、専門家による同定を待たずに、環境省や地方公共団体等に連絡し、各主体が協力して対応に当たることが必要です。効率的かつ効果的な対策のためには、地方環境事務所や関連事業者との間で、予め役割分担や連携内容を整理した連絡体制を整備することが重要です。
- 地域独自の取り組み:
- 自治体独自の対策マニュアル作成も進められています。例えば、神戸市では独自のヒアリ対策マニュアルが作成されました。また、京都府では侵入定着を防ぐための「特定外来生物バスターズ」を結成し、侵入モニタリングと初期段階での徹底防除を実施しています。
- 根絶を目指す方法:
- 根絶を目指す防除では、「一斉防除」が推奨されています。これは、生息範囲を定めて集中的に駆除を行い、一気に個体群密度を下げた後、定期的なモニタリングで再発見された箇所を再度防除するという流れを繰り返すものです。駆除には、巣の奥に潜む女王アリや幼虫まで連鎖的に効果が期待できる遅効性のベイト剤が中心的に使用されます。
市民が今できること:3つの具体的行動と予防策
市民や事業者の通報は、ヒアリ侵入の早期発見と定着阻止に直結しています。ヒアリと疑わしいアリを見つけた場合や、刺された場合の対処法を理解し、冷静に対応することが重要です。
- 刺されないための予防と危険回避
- ヒアリと疑われる個体や巣(土で作られるドーム状のアリ塚)を見つけた場合、刺激(個体を踏みつける、巣を壊す等)を絶対にしないでください。
- ヒアリは強い毒性を持つため、たとえ死骸であっても素手で触らないでください。
- 多数のアリがいる場合や巣があるときは、踏んだり、水浴びをかけたりといった刺激は、ヒアリを拡散させる原因となるため絶対に避けてください。
- 発見・通報
- ヒアリの疑いがあるアリを見つけた場合は、数の大小に関わらず、環境省の**ヒアリ相談ダイヤル(0570-046-110、9時~17時、土日祝対応※年末年始除く)**に速やかに連絡してください。
- ヒアリは、肉眼でおおよそ「赤っぽくツヤツヤしている」「働きアリの大きさが2.5mm~6.0mmと連続的な変異がある」「行列を作り餌に集まる」といった特徴で区別できます。
- 刺された場合の緊急対処
- 刺された直後は、20~30分程度は安静にし、刺された部位を冷やしながら(冷たいタオルや保冷剤など)体調の変化がないか注意深く様子を見てください。
- 容体が急変(息苦しさ、声がれ、激しい動悸、めまいなど)した場合は、重度の症状(アナフィラキシーショック)の可能性があるため、すぐに救急車を要請してください。
- 救急隊員や医療機関には、「アリに刺されたこと」「アナフィラキシーの可能性があること」を伝えてください。刺したアリの死骸を持参すると診断の助けになります。
ヒアリに関するFAQ
本文に重複しない内容で、ヒアリに関する、よくあるQ&Aをリストしました。
- Q1:ヒアリの毒成分は何が特徴ですか?
- A1:ヒアリの毒成分の主成分は水不溶性のピペリジンアルカロイド(ソレノプシン)であり、細胞毒性、溶血性、壊死性、殺虫、抗菌作用などの特性を持っています。また、アナフィラキシーショックに関与している可能性のある複数のタンパク質も検出されていますが、具体的な数値については、現時点で確定的なデータはありません。
- Q2:ヒアリは日本で定着する可能性のある気候帯にいるのですか?
- A2:ヒアリは熱帯、温帯、乾燥帯、つまり最寒月平均気温が-3℃以上の場所に生息しています。日本の多くの地域はヒアリの生息可能地であると推定されています。
- Q3:日本国内の在来アリでヒアリと間違えられやすい種類はありますか?
- A3:一般人がヒアリと間違えるケースが多い在来種には、キイロシリアゲアリ、オオシワアリ、アミメアリなどがあります。特にキイロシリアゲアリは外見が似ており、繁殖期に灯火に多数飛来することでヒアリと誤認される例が最も多いとされています。
- Q4:ヒアリの巣(アリ塚)は日本で発見されていますか?
- A4:ヒアリはアリ塚を作ることが知られていますが、日本国内でこれまでに確認された巣は塚を作らずに発達している事例が多いとされています。環境省の対策においても、『アリ塚の存在』は定着の判断材料としない方針が取られています。日本では港湾エリアの地面で地中に集団で生息しているものが見つかっています。
- Q5:ワサビ成分がヒアリ対策に有効というのは本当ですか?
- A5:はい。ワサビの辛み成分であるアリルイソチオシアネート(AITC)は、ヒアリに対する忌避効果と殺虫効果を持つことが国内の研究で明らかになっています。この成分をマイクロカプセル化してシートなどに加工する技術が確立され、コンテナ輸送時の侵入防止策として期待されています。
- Q6:ヒアリの駆除において、連鎖殺虫効果のあるベイト剤の仕組みは何ですか?
- A6:ヒアリの働きアリは、餌としてベイト剤(遅効性殺虫成分を含む餌剤)を巣に持ち帰り、幼虫や他の成虫に分け与えます。これにより、巣の奥にいる女王アリや幼虫まで薬剤が浸透し、巣全体を効率的に駆除する効果が期待できます。
- Q7:くん蒸剤やくん煙剤はどのような状況で使用されますか?
- A7:くん蒸やくん煙は、ヒアリが荷物の隙間やコンテナ内に多数潜んでいる可能性が高い場合に検討されます。専門業者によるくん蒸は強力ですが、市販のくん煙剤もコンテナのような閉鎖空間内で高い防除効果が期待され、密閉性を高めた上で使用されます。
- Q8:在来のアリはヒアリの天敵になり得ますか?
- A8:日本の在来アリは、多数のヒアリのコロニーには太刀打ちできませんが、繁殖に不可欠な女王アリが単独でいる場合には、集団で攻撃し倒す可能性があるため、「敵」にはなると独自に主張する研究者もいます。
- Q9:ヒアリの防除作業で、駆除した後の廃棄物はどのように処理すべきですか?
- A9:ヒアリが確認された場所で、補修や雑草処理の際に出た廃土を含む廃棄物等は、ヒアリが付着して移動することがないよう、ワンプッシュ式エアゾール剤やくん蒸等による処理後に廃棄することが重要です。
- Q10:ヒアリはいつから日本に侵入し始めたのですか?
- A10:ヒアリが日本国内で初めて確認されたのは2017年6月です。これは中国の広東省広州市から神戸港へ運ばれた海上コンテナの中から発見された事例でした。
- Q11:ヒアリ対策の強化が急務とされる中で、「要緊急対処特定外来生物」に指定されたことの主なメリットは何ですか?
- A11:ヒアリ類が「要緊急対処特定外来生物」に指定されたことで、国は通関後の物品や土地、施設に対して検査、消毒、廃棄を命じる権限を持つことが可能になり、ヒアリか否かの同定作業中であっても物品等の移動を停止させることが可能になりました。
まとめ
南米原産のヒアリ(Solenopsis invicta)は、その極めて強い攻撃性と、刺された場合にアナフィラキシーショックを引き起こし生命の危険を伴う毒性から、人体にとって危険な**「要緊急対処特定外来生物」に指定されています。2017年6月に国内で初確認されて以来、2025年3月現在までに18都道府県で135事例**が報告されており、特に東京港青海ふ頭などの主要港湾が、主に中国(南部)からの輸入コンテナや貨物を介した侵入の主な拠点となっています。
国内では現在のところ定着には至っていないとされていますが、有識者からは**「定着しそうなギリギリの段階」にあると警鐘が鳴らされています。ヒアリが国内に定着した場合、健康被害だけでなく、電気設備などの社会インフラの破壊や、在来のアリ類や爬虫類、小型ほ乳類を捕食することによる生態系への深刻な打撃**が懸念されます。
この脅威を食い止めるためには、早期発見と確実な根絶が最も重要です。国や自治体は、2023年4月に「要緊急対処特定外来生物」に指定されたことを受け、通関後の検査や物品の移動制限といった強力な対処権限を活用し、水際対策を強化しています。また、地中の少数のヒアリも特定できるヒアリ探知犬の導入や、ワサビ成分を用いた忌避・殺虫技術など、新たな防除技術の開発も進められています。
私たち市民や事業者は、この定着阻止の最前線を担っています。「赤っぽくツヤツヤしている」「大きさが2.5mm〜6.0mmと様々」環境省のヒアリ相談ダイヤル(0570-046-110)へ通報することが、定着を防ぐための決定的な行動となります。万が一刺された場合は、20〜30分安静にし、呼吸困難や激しい動悸などの重篤な症状(アナフィラキシーショック)が出たら、直ちに救急車を要請し、「アリに刺されたこと」を伝える必要があります。関係するすべての主体が連携し、この侵略的外来種から日本の社会と自然を守るための取り組みを継続することが求められています。

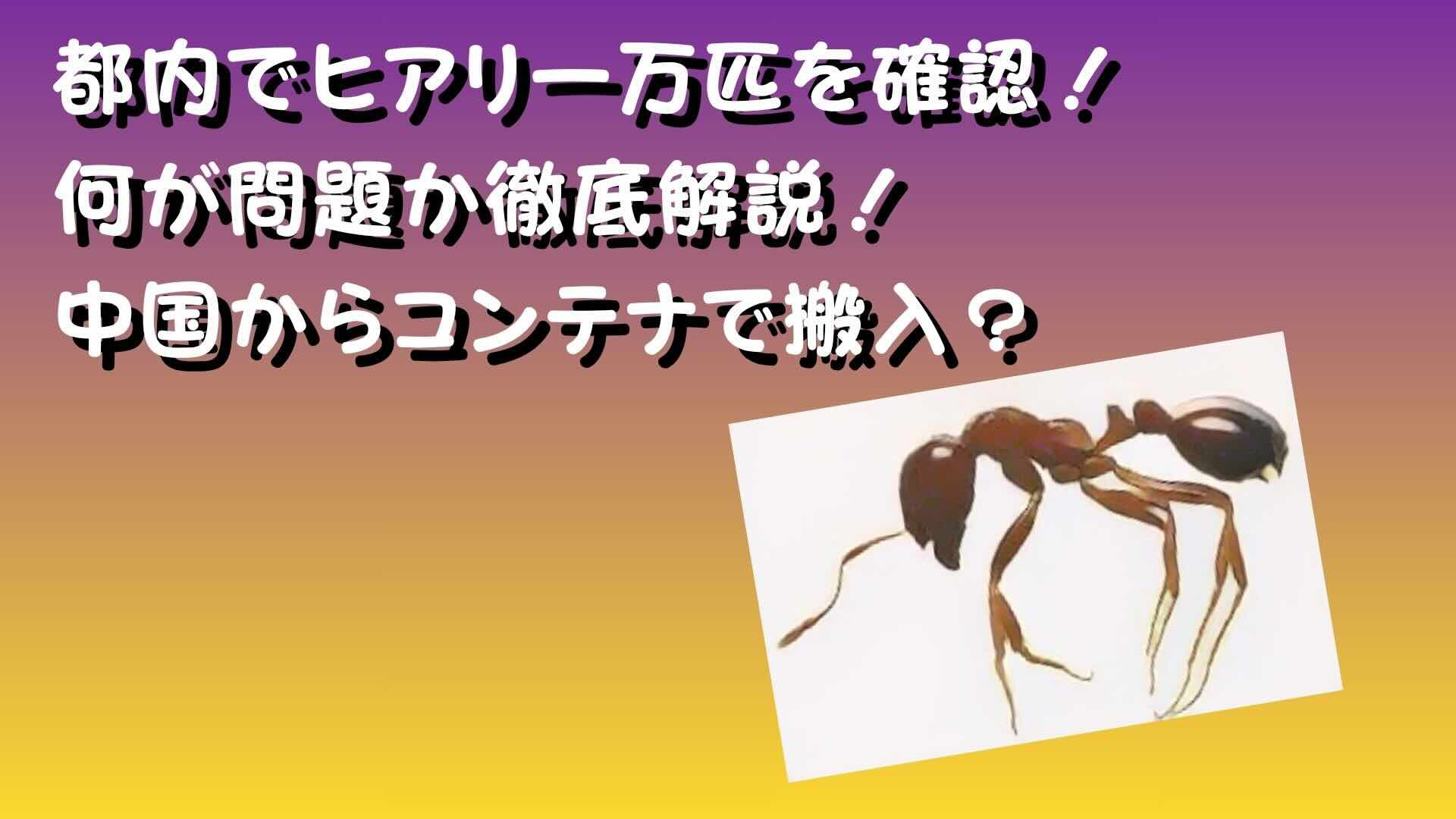
コメント