糖尿病について「一生治らない病気」「食事制限が厳しい」といったイメージを持っていませんか?この記事では、糖尿病患者やそのご家族が抱きがちな典型的な疑問からちょっとずれた10の疑問について、14年来の糖尿病患者が専門書&ネットを調べまくって回答をまとめました。またまとめた内容については、3つのAIにかけてファクトチェックをしました。
問題点がありましたら、ご指摘をいただければ、調査の上、修正させていただきます。
なお、糖尿病と関連性の高い歯周病予防として、電動歯ブラシが有効です。本ブログの姉妹サイトの記事のこちらもどうぞ。






そもそも糖尿病とは?
「糖尿病」とは
糖尿病とは、血液中のブドウ糖濃度(血糖値)を下げるホルモンであるインスリンの作用不足や分泌不足により、慢性的に血糖値が高くなる病気です(1)。血糖値の高い状態が持続すると、神経障害、網膜症、腎症などの三大合併症や動脈硬化症を引き起こし、患者のQOL(生活の質)を著しく低下させる可能性があります。適切な治療により血糖コントロールを良好に保てば、健康な人と変わらない生活を送ることができる疾患です。
日本における糖尿病の現状
現在、日本では成人の約6人に1人が糖尿病またはその予備群とされており、厚生労働省の調査によると糖尿病が強く疑われる人は約1,000万人、可能性を否定できない人(予備群)を含めると2,000万人近いと推計されています(2)。また、実際に医療機関で糖尿病治療を受けている患者数は約552万人となっています(3)。生活習慣の変化や高齢化に伴い、患者数は年々増加傾向にあります。
合併症の怖さ
糖尿病の真の恐ろしさは合併症にあります。進行すると失明、人工透析、手足の切断に至るケースもあり、新規透析導入患者の約36%は糖尿病性腎症が原因とされています。また、糖尿病性網膜症により毎年約3,000人が新たに視覚障害者として認定されていると報告されています(4)。
糖尿病に関する10の質問と回答
Q1: 糖尿病って治らないの?
A: 糖尿病は現在の医学では根治的な治療法は確立されていませんが、適切な治療と生活習慣の改善により、血糖コントロールを良好に保つことで合併症の発症を防ぐことが可能です。「治る」という表現は一般的には用いられず、「寛解(かんかい)」や「コントロール良好」と表現されます。しかし、適切な治療により血糖コントロールを良好に保つことで、健常者と変わらない生活を送ることが可能です。重要なのは「治す」のではなく「上手に付き合う」という考え方です。現在は治療選択肢も増えており、薬物療法、食事療法、運動療法を組み合わせることで、合併症の発症・進展を防ぎ、充実した人生を送れます。
Q2: 糖尿病になったら、眼科や歯科の受診も必要なの?
A: はい、定期的な眼科・歯科受診は必須です。糖尿病性網膜症は自覚症状なく進行し、放置すると失明に至る可能性があります。また、糖尿病患者は歯周病のリスクが高く、歯周病の悪化が血糖コントロールにも悪影響を与える悪循環を生みます。眼科は年1~2回、歯科は3~4ヶ月に1回の定期検診が推奨されています。糖尿病専門医だけでなく、眼科医・歯科医との連携による包括的な治療が、合併症予防の鍵となります。
Q3: 糖尿病になったら、手術ができないの?
A: 糖尿病でも手術は可能ですが、血糖コントロールの状態により注意が必要です。血糖値が高い状態では創傷治癒の遅延、感染リスクの増加、麻酔による合併症のリスクが高まります。そのため、緊急手術以外では術前に血糖コントロールを改善してから手術を行うのが一般的です。HbA1cが8.0%未満であることが手術の安全性の目安とされており、空腹時血糖値130mg/dL未満、食後2時間血糖値180mg/dL未満が望ましいとされています。
Q4: 糖尿病と歯周病って、深い関係性があるの?
A: 糖尿病と歯周病は**「双方向の関係」**にあります。糖尿病により免疫力が低下し歯周病が悪化しやすくなる一方、歯周病の炎症物質がインスリンの働きを阻害し血糖コントロールを悪化させます。歯周病治療により血糖値が改善することも多く報告されており、糖尿病専門医の間では「第6の合併症」と呼ばれることもあります。口腔ケアは血糖管理の重要な要素として位置づけられています。
Q5: 糖尿病だと肺炎が重篤化しやすいって本当なの?
A: 事実です。糖尿病患者は免疫機能の低下により、感染症全般にかかりやすく重篤化しやすい傾向があります。特に肺炎については、血糖コントロール不良の患者では死亡率が健常者の2~3倍高くなるとの報告があります。高血糖状態では白血球の機能が低下し、病原菌に対する抵抗力が弱まります。そのため、インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンの接種が推奨されており、日頃の血糖管理と感染予防策が重要です。
Q6: 歯周病を抑えるために電動歯ブラシって有効なの?
A: 電動歯ブラシは、正しく使えば手磨きよりもプラーク除去効果が高いとされており、歯肉炎の改善効果も報告されています。ただし、個人差があり、正しい使い方や定期的な歯科受診が重要です。特に糖尿病患者にとって、効率的な口腔ケアは血糖管理の観点からも重要です。ただし、電動歯ブラシを使用しても正しいブラッシング方法や定期的な歯科検診は必要です。歯科衛生士による指導を受け、個人に適した口腔ケア方法を確立することが大切です。
Q7: 糖尿病を放置すると、失明、人工透析、手足の切断に至るかもって本当なの?
A: 残念ながら事実です。糖尿病の三大合併症(網膜症、腎症、神経障害)と大血管障害により、これらの深刻な状況に至る可能性があります。新規透析導入の約36%が糖尿病性腎症、年間約3,000人が糖尿病性網膜症による視覚障害、下肢切断の約半数が糖尿病関連とされています。しかし、適切な血糖管理により、これらの合併症は予防可能です。HbA1c 7%未満を維持することで、合併症リスクを減らせることが多くの研究で示されています。
Q8: 糖尿病患者の場合、低血糖が危険というのは本当なの?
A: 低血糖は糖尿病治療における最も危険な急性合併症の一つです。血糖値が70mg/dL以下になると、冷汗、動悸、意識障害などの症状が現れ、重症の場合は昏睡状態となり生命に関わります。特に高齢者では、低血糖により心血管イベントや認知機能低下のリスクが高まります。インスリン注射やSU薬使用中の患者は特に注意が必要で、常にブドウ糖を携帯し、症状を感じたら直ちに対処することが重要です。
Q9: 糖尿病とアルツハイマーって関係性があるって聞いたけど本当なの?
A: 関係性は確実に存在します。糖尿病患者はアルツハイマー型認知症を含む認知症全体の発症リスクが1.5~2倍高いことが複数の研究で示されています。高血糖状態が脳血管障害を引き起こし、また、インスリン抵抗性が脳内のアミロイドβ蛋白の蓄積を促進することが原因と考えられています。そのため、認知症予防の観点からも血糖管理は極めて重要であり、「糖尿病は脳の病気でもある」と認識されつつあります。
Q10: 糖尿病という病名を変えようという動きがあるの?
A: 実際にそのような議論が存在します。現在の「糖尿病」という病名が患者に与える心理的負担や偏見を考慮し、日本糖尿病協会などでは病名変更の検討が行われています。候補として「糖代謝異常症」「代謝症候群」などが挙がっていますが、医療現場での混乱や国際的な統一性の観点から、慎重な議論が続いています。病名変更により、患者の心理的負担軽減や早期受診促進が期待される一方で、長年使用されてきた病名を変更することの影響も考慮する必要があります。
まずはできることから!
内科(できれば糖尿病専門医)の定期的受診
糖尿病は長期にわたる管理が必要な疾患です。月1回の定期受診を基本とし、血糖値、HbA1c、血圧、体重などの継続的なモニタリングが重要です(5)。可能であれば糖尿病専門医による診療を受けることで、最新の治療法や合併症の早期発見が期待できます。専門医が近くにいない場合は、内科医と専門医の連携による治療も効果的です。
眼科・歯科の定期的受診
眼科は年1~2回、歯科は3~4ヶ月に1回の定期検診を実践しましょう(6)。糖尿病性網膜症は自覚症状なく進行するため、症状がなくても定期的な眼底検査が必要です。歯科では歯周病の早期発見・治療により、血糖コントロールの改善効果も期待できます。各科の医師に糖尿病であることを必ず伝え、連携した治療を受けることが大切です。
電動歯ブラシで歯周病対策
効率的な口腔ケアのために電動歯ブラシの導入を検討しましょう(7)。手磨きよりもプラーク除去効果が高く、歯周病予防に効果的です。ただし、使用方法が重要なので、歯科衛生士による指導を受けることをお勧めします。歯間ブラシやデンタルフロスとの併用により、より効果的な口腔ケアが実現できます。
腹いっぱい食べる・間食をするからの卒業
「腹八分目」を心がけ、規則的な食生活を実践しましょう(8)。1日3回の規則正しい食事で、血糖値の急激な変動を防げます。間食をする場合は、時間と量を決めて、血糖値への影響を最小限に抑える工夫が必要です。食事記録をつけることで、自分の食習慣を客観視し、改善点を見つけることができます。
禁煙&ほどほどの飲酒(蒸留酒限定)
禁煙は糖尿病患者にとって最優先事項です(9)。喫煙は血管障害を促進し、合併症リスクを大幅に高めます。飲酒については、適量であれば必ずしも禁止ではありませんが、糖質の多いビールや日本酒は控えめにし、蒸留酒(焼酎、ウイスキーなど)は糖質が少ないため選択肢となります。ただし、飲酒量は控えめにし、医師と相談のうえで判断しましょう。飲酒時は低血糖に注意し、必ず何か食べながら飲むことが重要です。
まとめ
糖尿病に関する疑問の多くは、正しい知識を持つことで解決できます。14年間の糖尿病患者としての体験と、専門書籍・信頼できるWebサイトからの情報収集を通じて、以下の重要なポイントが明らかになりました。
重要なポイント:
- 糖尿病は完治しないが、適切な管理により健常者と変わらない生活が可能
- 眼科・歯科の定期受診は合併症予防に不可欠
- 歯周病と糖尿病は相互に影響し合う双方向の関係
- 低血糖は最も危険な急性合併症の一つ
- 認知症リスクの観点からも血糖管理は重要
- 病名変更の議論も進んでいる
早期発見・早期治療、そして継続的な自己管理により、糖尿病による深刻な合併症は予防できます。一人で抱え込まず、医療チーム(内科医、眼科医、歯科医、栄養士、薬剤師)と連携しながら、前向きに糖尿病と向き合っていきましょう。
正しい知識と適切な治療により、糖尿病があっても充実した人生を送ることは十分可能です。まずはできることから始めて、一歩ずつ改善していくことが、良好な血糖コントロールへの近道となります。

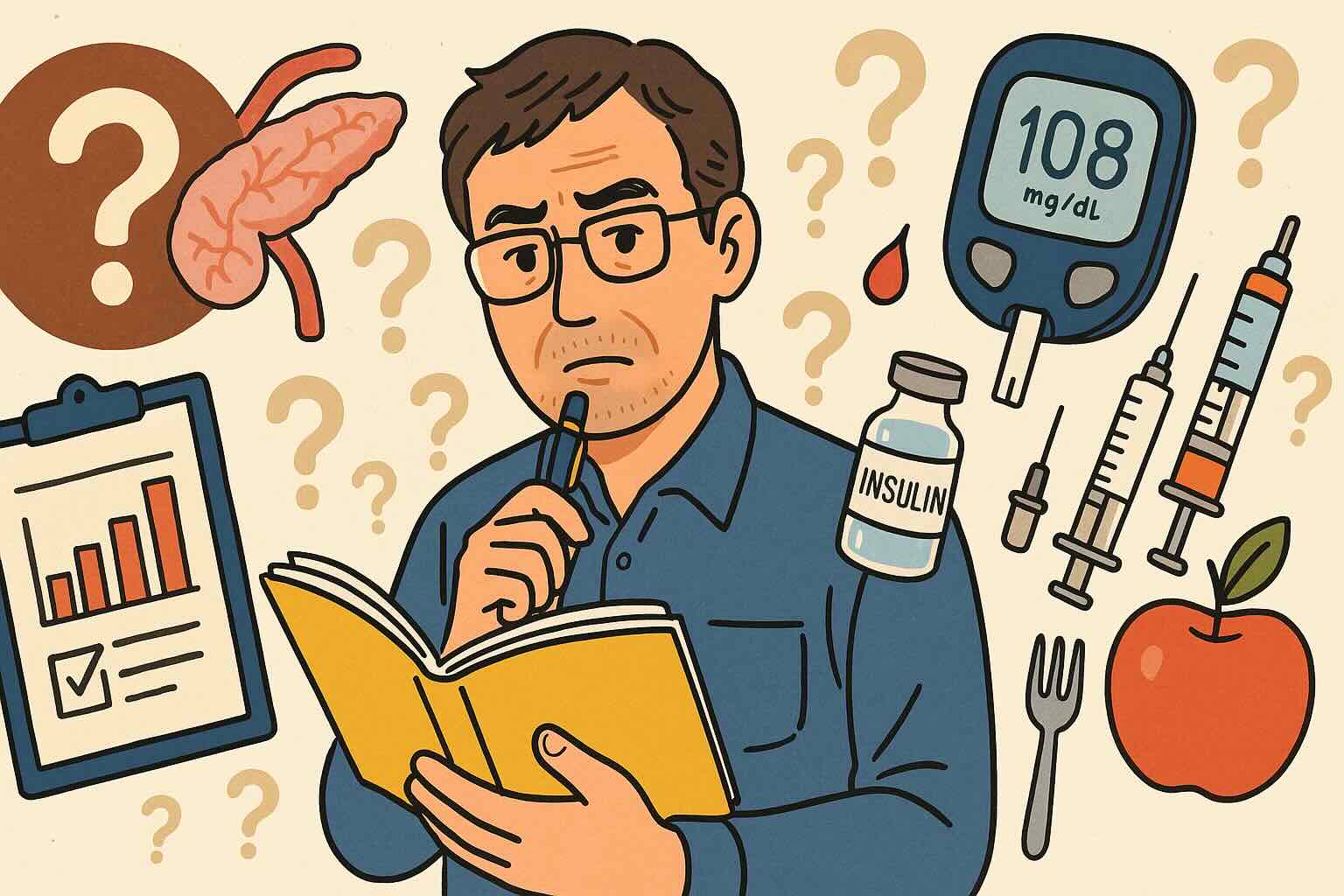
コメント