筆者 taoは、社会人になって以降、40年以上、自民党を支持してきました。お金を払って自民党党員になっていた時期もあります。それも、岸田政権時のあのLGBT法案可決で党員を辞めました。以降、国政選挙においては自民党以外で投票してきました。
そんなこんなで、昨年10月の総裁選での逆転劇を生放送で見て、生きている限り、金輪際、自民党は推さないと決めたのですが…。
今月4日の総裁選で高市氏が見事総裁になって、気になっていたのは自公連立です。同党は、中国べったりだし、護憲だし、この20数年間、政権安定弁にはなっていても、正しい政治を行うには、大きなブレーキになっていたのが公明党だと認識しています。
今日の公明党からの一方的な自公連立離脱宣言、これは自民党が変わるチャンスです。
もしかしたら、4日の総裁選で高市氏に入れた議員たちのなかにも「公明党のサポートがなくて次の選挙困った」という者が多いのかもしれません。そんなこんなで、これからの高市氏はさらなる茨の道です。
ところで、ついさっきまで「自公連立の見込みは」というような記事を書いていました。ほぼほぼ書き終わり、あとは「公開ボタン」ポチっとするだけでしたが、「公明党、自公連立離脱」の速報が入り、こうして、祝辞記事を書いている次第です。
北村晴男代議士などの緊急動画、5つ紹介
今回の「公明党からの連立離脱宣言」に対して、全うなる意見の動画を公開してくれた北村晴男議員。まずは、北村議員のその動画を紹介させてください。
とくにコメントはつけません。ぜひ、通してこの動画をご覧ください。
そして、2つ目、高橋洋一氏の動画を紹介させてください。
3つ目は、竹田恒泰氏の動画紹介です。
4つ目は、渡邊哲也Show動画です。
ラストは、鮫島浩氏の動画です。
自公連立、自民党から見たデメリット
20年以上続いた自公連立。この連立継続のデメリットを、自民党視点(主に党運営と政策実現の側面)でまとめました。
選挙協力への過度な依存と議員の不安定化
自民党にとって公明党の連立維持の最大の理由は、公明党が選挙において提供する票への高い依存度にあります。この依存構造は、自民党にとって以下のようなデメリットを生じさせてきました。
- 選挙における落選リスク
- (1) 公明党(創価学会票)の支援を失った場合、特に僅差で当選した自民党議員(小選挙区で敗北し比例復活した53名や、得票差が5,000票以下の推定25〜30名)は、合計で推定50〜80名が次期衆院選で落選する深刻なリスクに直面します。
- (2) ただし、これは「選挙において公明党を長く頼りにしてしまった結果、自民党の選挙を戦い抜く力が劣化し、それを修正し、向上させるチャンスを失っていた」ということです。
- つまり、(1)がこれから直面するデメリットですが、実は、その背景には(2)というデメリットがあったのです。
- 地方組織の資金源への脅威
- 公明党が要求する企業・団体献金の規制強化(献金の受け皿を政党本部と都道府県組織に限定する案)は、自民党の地方組織の資金源に直結する問題であり、これを「丸飲み」することは地方組織の猛反発を招くため極めて困難です。
- 党内指導層からの不満
- 連立継続の制約が自民党の行動を縛ることから、自民党関係者からは公明党を「何かと足枷となってきた」や「ガン」と見なす声が漏れています。
政策決定における主導権の制約(ブレーキ役の存在)
公明党は自らを「右傾化や権力の暴走を阻止するための「ブレーキ役」」と認識しており、自民党の政策に強い制約を課してきました。それはブレーキ役ではなく、自民党政策を実現するためのブレーキだったのです。
- 右傾化・保守政策の抑制
- 自民党が重視する外交・安全保障分野や憲法改正などにおいて、公明党が理念や政策面で強い影響力(議席数以上の影響力)を行使するため、自民党は政策面で大きく譲歩せざるを得ませんでした。
- 安保・改憲の停滞
- 自民党が目指す集団的自衛権の「フルスペック」容認が、公明党との協議の結果「新3要件」に限定された例など、最重要事項で譲歩が強いられます。憲法改正においても、公明党の「加憲」案が議論の対象となるなど、自民党の積極的な改憲論議が抑制されてきました。
- 幹部の保守的言動の制限
- 特に高市総裁のような保守色の強い指導者の場合、靖国神社参拝や歴史認識、外国人との共生に関する保守的な政策などが公明党の懸念事項となり、外交問題に発展する可能性を避けるため、行動が制限されてきました。
慣例ポストの固定化と行政への影響
連立の慣例化により、特定の重要ポストが公明党に固定化されることによるデメリットが指摘されてきました。
- 国土交通大臣ポストの固定化
- 2004年以降、国土交通大臣のポストは公明党の慣例的な指定席となっており、自民党内からは「ポストを政党で固定化するのはよくない」という不満の声が上がっています。
- 行政に精通した自民党議員の減少
- 国交相ポストが公明党に固定化された結果、運輸相・建設相時代を含めて国交行政に精通する自民党議員が減少し、インフラ整備などの推進に悪影響を与える懸念も指摘されています。
自公連立、日本国という視点から見たデメリット
次に、長く続きすぎた連立のデメリットを、日本国という視点(主に政治と経済の側面)でまとめました。
政治の不安定化と政策遂行能力の低下
公明党の存在がなければ政権が成り立たないという状況そのものがデメリットになっていました。連立が崩壊した場合、国政運営に深刻な影響を与えるからです。今回の公明党連立離脱は、これを再構築するチャンスです。
- 少数与党による機能不全のリスク
- 自公連立が解消された場合、高市政権(または石破政権)は衆参両院で過半数割れの少数与党単独政権となり、政権運営は極めて不安定になります。
- 法案成立の難化
- 与党は野党の協力なしに法案を可決できず、政策ごとに野党との「部分連合」を組まざるを得なくなります。この交渉の複雑化は、政権運営の行き詰まりや国会審議の停滞を招きます。
- 政治不安指数の高騰
- 衆参両院で多数派を失った結果、日本の政治の不安定さの度合いを示す政治不安指数(PUI)が、2012年以降で最も高い水準(PUI 136.6)を記録しており、この不透明感の高まりは経済活動に負のインパクトをもたらし、景気の先行きを下振れさせる要因となります。
経済政策の停滞と国民生活への影響
長期にわたる自公連立政権の継続は、経済の停滞と国民の負担増と重なる側面があります。
- 「失われた30年」との時期的な重なり
- 1999年から続く自公連立政権の歴史は、日本経済の「失われた30年」の歩みとも重なっており、長期政権が国民生活を上向かせられなかったという事実が批判されています。
- 国民負担率の上昇
- 経済成長の恩恵を得られない状況下で、国民負担率(租税負担と社会保障負担)は2014年頃から40%を超えて上昇し続けており、物価高と相まって国民生活の困窮を招く要因となっています。
- 政策実現の遅れによる不満
- 連立維持のための交渉が難航することで、物価高対策への対応が遅れるなど、国民生活に直結する政策の遅延が公明党へも批判の矛先を向けさせる可能性があります。
理念的な対立による政治的エネルギーの浪費
連立を維持するための内部調整や駆け引きに、政治的エネルギーが浪費されます。
- 政治的エネルギーの消耗
- 異なる理念(保守と中道)を持つ政党が連立を維持するためには、政策や人事を巡る交渉(チキンゲーム)が必要となり、そのエネルギーが本来取り組むべき国家的な重要課題から逸れる可能性があります。
- 「出来レース」による幻滅
- 専門家からは、連立維持や連立拡大を巡る一連の動きは、各プレイヤーが合理的に行動した結果、体制を安定させるための「壮大な『鎮静剤』」として機能する「出来レース」の構造があるとの分析があり、国民の政治に対する期待や熱狂が幻滅に変わるという残酷な結果を伴う可能性が指摘されています。
まとめ
★衆院選は年内にあるかもね♪
自公連立解消という激動の局面は、日本の政治が「自民党支配」のあり方の一大転機を迎えたことを示しています。長年にわたり政権運営の「ブレーキ役」として自民党の政策に制約を加えてきた公明党との枠組みが白紙に戻った今、高市総理にはこの危機を「改革の破壊者」として前向きに捉えることが求められています。
高市総裁は、自民党の党員票で圧倒的な支持を得て選出された存在であり、その誕生は保守層から「託された最後の希望」と見なされています。この連立解消は、公明党や穏健派という「足枷となってきた」勢力からの制約から解放され、高市総理が掲げる「責任ある積極財政」や「サナエノミクス」といった明確な経済政策を実行するための大きな好機となるでしょう。
現実に、高市総裁誕生後、市場は減税や積極財政への期待から株高・円安の「高市トレード」を引き起こしました。この期待を現実の成果につなげるためには、従来のしがらみにとらわれず、政策的な親和性の高い国民民主党など新たなパートナーとの連携を積極的に模索し、政策を順次実行していくことが不可欠です。
公明党との連立解消は、高市総理が「しがらみと戦う孤高のリーダー」という物語を演じきり、政権運営の困難さを示す政治不安指数(PUI)が過去最高水準にあるこの不安定な政局を巧みに乗りこなすための政治的資産を確立する機会でもあります。
今、国民が求めているのは、長引く「失われた30年」を終わらせ、物価高対策をはじめとする生活に直結した課題に対する迅速果断な政策遂行です。
高市総理には、少数与党という困難な状況下でこそ、党員・国民が期待した改革の旗手として、臆することなく「新しい政治秩序」を築くべく、その強固な意思と卓越した舵取りを発揮されることを、強く期待いたします。
_/_/_/
筆者 taoは40年にわたり自民党を支持してきたことは冒頭に書きました。その自民党が、今、変化のチャンスを得ていることには大きな期待をしています。公明党から連立離脱宣言があったことは、その大きな一歩です。チャンスです。
ただし、このブログでは何回も書いていますが、今筆者は、日本保守党を支持していますので、「公明党からの連立離脱宣言」の結果がどうなろうが、「日本を豊かに、強く。」の方向に動く契機となればいいと考えています。
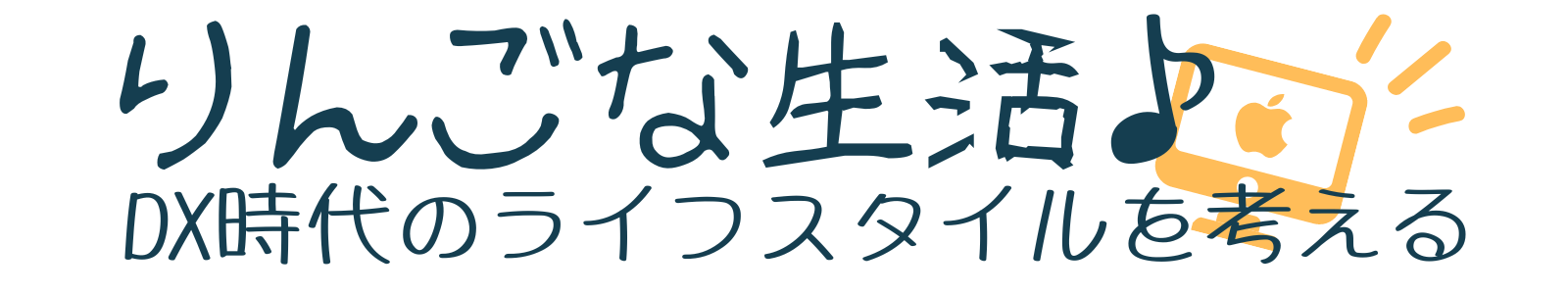
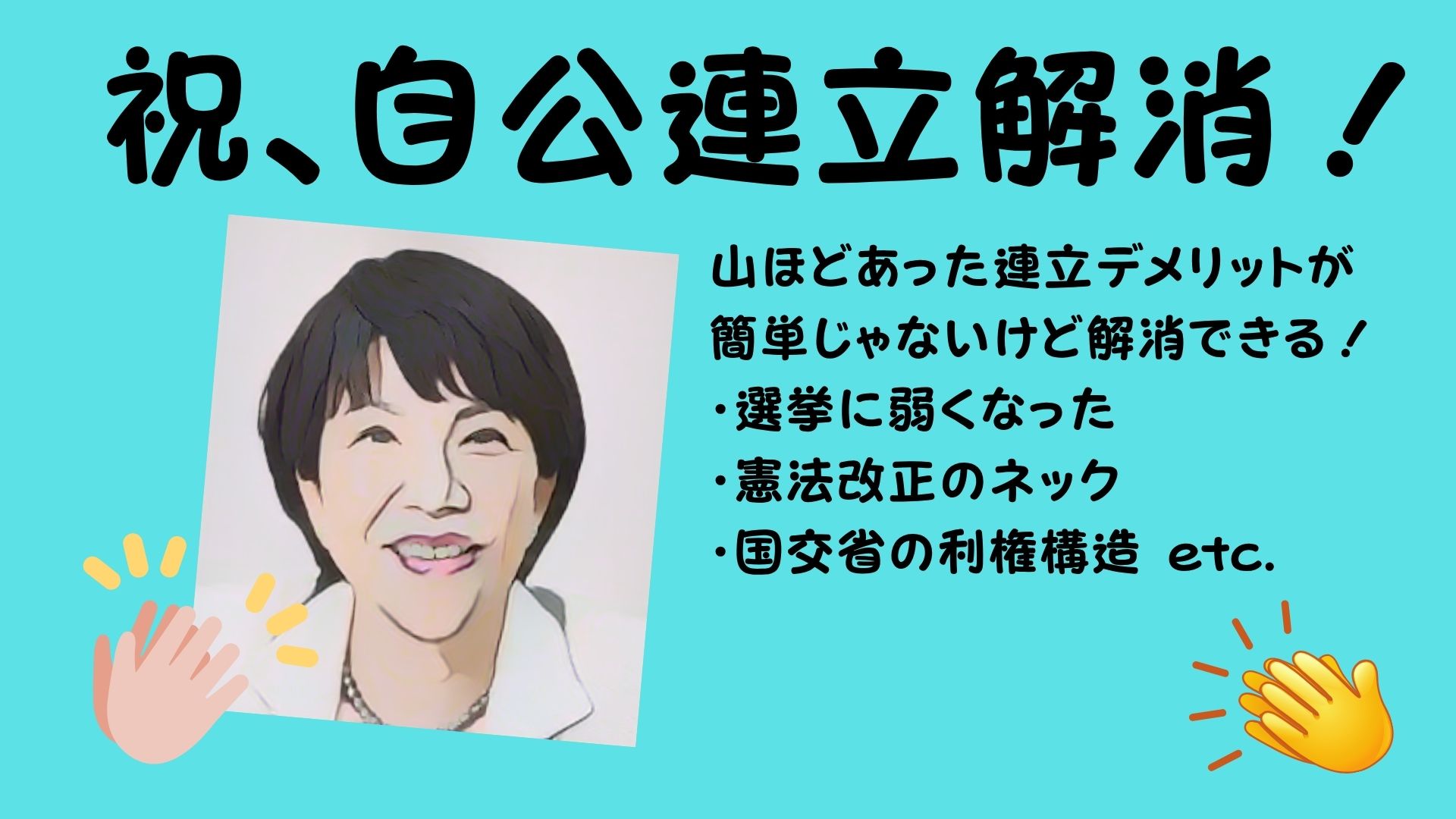
コメント