2023年度(令和5年度)以降、日本全国でクマ類(ツキノワグマ、ヒグマ)の出没件数と人身被害が過去最多のペースで急増し、危機的な状況が続いています。
特に、東北地方ではブナ科堅果類の大凶作の影響により、「超大量出没」と同じような状況が発生しました。この大量出没の背景には、奥山からの生息域の拡大や里山の藪化という長期的な社会構造の変化が根底にあり、食物資源の不足が引き金となっています。
人の生活圏に近づいたクマに対し、行政は捕獲による対応を迫られていますが、市街地での銃猟の法的制約、駆除を担う人材の高齢化、そして「クマを殺すな」という感情的な社会的圧力という、複雑で根深い課題に直面しています。
本記事では、この人身被害の危機的な実態と、駆除を阻む制度的・社会的な「壁」を深掘りし、人が安心して暮らすための対策と、クマとの持続可能な「すみ分け」のあり方を考察します。
- 熊被害が過去最悪となった原因と、生息域拡大や餌不足などその背景がわかります。
- クマ駆除の判断を阻む法的な制約や、現場で直面する人材不足・社会的な課題がわかります。
- 人とクマの軋轢を減らすための「ゾーニング管理」や「誘引物除去」など具体的な対策と制度改善の方向性がわかります。
本記事の音声解説♪
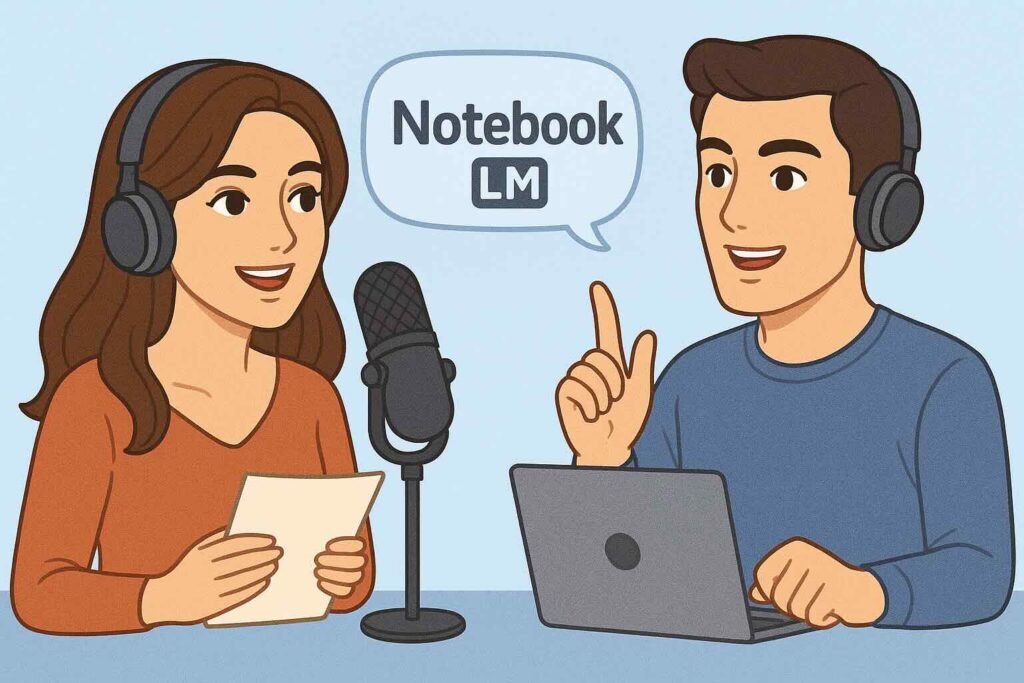
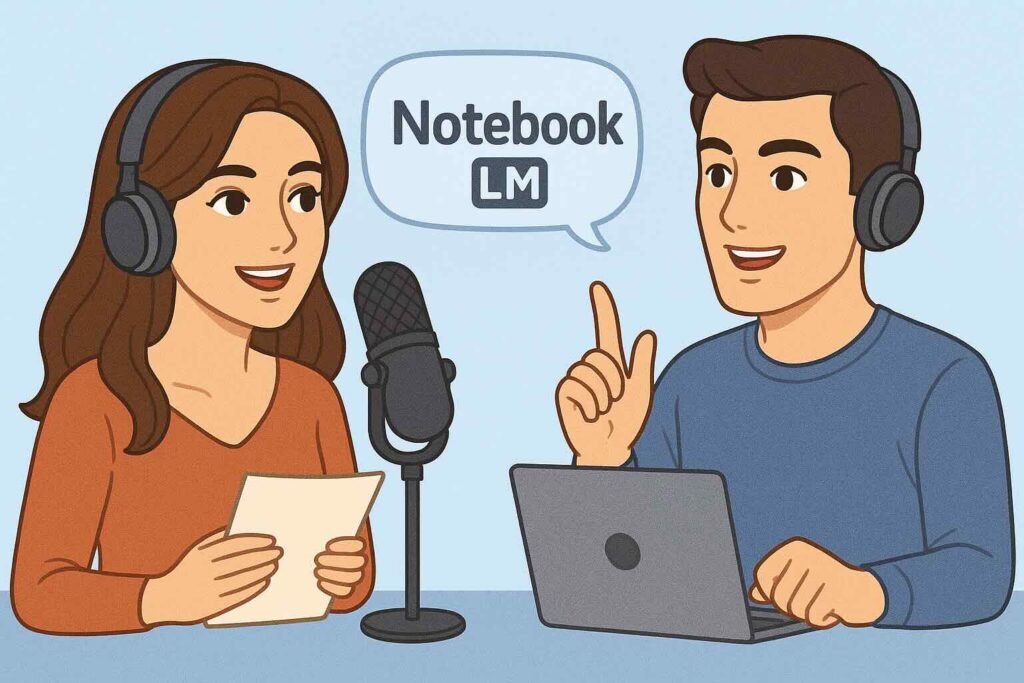
本記事をベースとした音声解説をつくりました。AIとやりとりしながらつくっています。
誤読についてはご容赦ください。
なお、再生速度については、下記バーの右端にある「縦に並んだ3つの点」をクリックして、「再生速度」を選択して、求める再生速度を設定してください。
- 熊被害・熊駆除に関するの音声解説
なぜ今、熊被害が深刻化しているのか?
熊による死亡・重傷事故:直近数年の傾向と実例
環境省のデータによると、令和5年度(2023年度)のクマ類による人身被害の発生件数(人数)は、平成18年度以降で過去最多のペースで記録されており、2023年12月末時点で197件(218人)、うち死亡者は6人に上りました。
人身被害の発生場所は、山林内だけでなく、人家周辺(約42%)や農地(約18%)、市街地(約3%)など、人の生活圏での活動中に発生する割合が高まっています。大量出没年においては、農地や住宅地、屋内での人身被害の発生割合が高くなる傾向が示されています。
死亡事故の実例として、北海道では2025年8月に羅臼岳で登山客がヒグマに襲われ死亡し、加害個体と確認された親子グマ3頭が捕殺されました。また、同年7月には北海道福島町で新聞配達員がヒグマに襲われ死亡しましたが、この個体はDNA鑑定により4年前に同町の山林で別の女性を死亡させた個体であることが判明しています。
また、直近では2025年10月8日午前、岩手県北上市山林で損傷の激しい男性の遺体が発見されました。遺体には複数の爪痕があり、きのこ採りに出かけたまま行方不明となっていた73歳の男性がクマに襲われたとみて、警察が捜査をしています。
熊出没が急増する背景:山と人里の変化
クマの出没件数は、2023年度同時期(8536件)と比較して、2023年12月末時点でのツキノワグマの出没件数は全国で1万2067件と約1.4倍に増加しています。
- 長期的な要因:生息域の拡大と里山の藪化
- ツキノワグマの分布域は、過去40年間で約1.5倍に拡大しており、四国を除いた多くの地域で低標高域を含む平野部への分布拡大が確認されています。
- この原因は、少子高齢化や都市への人口集中に伴い、奥山や中山間地域から人が撤退し、耕作放棄地が増加して森に戻りつつあるという社会の変化です。
- 放棄された田畑はすぐに藪化し、クマが利用したり身を隠したりできる藪地が集落内にパッチ状に発生しています。クマは、河川や河畔林、段丘林といった移動ルート(コリドー)を利用して、集落内部の藪地へ簡単にアプローチできるようになっています。
- 短期的な要因:食物資源の不足
- 2023年度は、東北地方(青森、岩手、宮城、秋田、山形)でブナ科堅果類(ドングリなど)の開花・結実ともに大凶作でした。知床半島においても、主要食物であるハイマツ球果、サケ科魚類、ミズナラ堅果のうち、複数の資源が不足する状況が、ヒグマの行動圏拡大(国立公園外への移動)や人里への接近を引き起こしました。
- 山の餌が不足した結果、クマは餌を求めて人里に降りてきて、柿や栗といった人里の誘引物に執着する個体が増加しました。例えば石川県の事故現場周辺では、冬眠前の時期にカキノキの果実や水田の二番穂が実をつけており、これらがクマを住宅地へと導いたと考えられています。
熊が人を襲う理由:本能か、人間側の要因か?
クマによる事故の大半は、クマと人が不意に遭遇する「鉢合わせ」によるものですが、近年は人の生活圏で効率良く食物を確保できることを学習した個体(人慣れ個体)の増加が問題視されています。
- 誘引物への執着と行動のエスカレート:
- クマが空き家や小屋に侵入し、食料やゴミの味を覚えると、行動が大胆になります。これが放置されると、最終的に人がいる家屋への侵入にエスカレートするおそれがあります。
- 親子の防御行動:
- 親子連れのクマと遭遇した場合、母グマは子グマを守ろうと攻撃的行動をとるため、極めて危険です。子グマを見ても近づかず、速やかにその場を離れることが必要です。
- 防御姿勢の重要性:
- 万が一クマに襲われた場合、ツキノワグマは顔面・頭部を攻撃することが多いため、両腕で顔面や頭部を覆い、直ちにうつ伏せになるなど防御姿勢をとり、致命的ダメージを最小限に留めることが推奨されています。富山県では、県民全員が防御姿勢を実践できるよう普及したいという考えが示されています。
駆除できないのはなぜ?制度的な壁とその仕組み
鳥獣保護管理法と「特定鳥獣保護管理計画」とは?
クマ類(ヒグマ、ツキノワグマ)の保護管理は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)に基づき行われます。野生鳥獣の捕獲は原則禁止されていますが、有害捕獲(有害駆除)や特定計画に基づく管理捕獲などの許可捕獲が認められています。
- ゾーニング管理:
- 都道府県知事は、管理を行う際、第二種特定鳥獣管理計画(特定計画)を策定でき、人の生活圏とクマ類の生息域を区分するゾーニング管理が推奨されます。
- 「コア生息地」(奥山)は保護を優先します。
- 「排除地域・防除地域」(人の生活圏)は人の生活を優先し、出没時には捕獲が基本的な対応となります。
- 「緩衝地帯」(里山周辺)は、クマの定着をさせない環境管理と捕獲が重要とされます。
- 都道府県知事は、管理を行う際、第二種特定鳥獣管理計画(特定計画)を策定でき、人の生活圏とクマ類の生息域を区分するゾーニング管理が推奨されます。
- 指定管理鳥獣への指定:
- 2024年4月16日、本州以南のツキノワグマとヒグマ(四国の個体群を除く)は指定管理鳥獣に指定されました。これにより、国の交付金を活用した捕獲と未然防除への財政的・技術的支援が強化されました。
駆除判断のフロー:申請、許可、実行までのプロセス
クマが出没した際の対応は、事前に作成された対応フロー図に基づき、緊急性や出没地点のゾーニング区分を考慮して、追い払い、捕獲(檻、猟銃、麻酔銃)、監視などの方法が決定されます。
- 現場での役割:
- 緊急対応時、現場では混乱を防ぐため、指揮命令者(情報を集約し指示を出す)、対応者(銃等で直接対応する)、監視役、調整役(住民、警察、報道との調整)などの役割分担が明確にされます。
- 猟銃による捕獲:
- 殺傷力が強いため、周囲の安全に十分注意が必要です。秋田県で住宅地近くの廃屋に隠れたクマを猟銃で捕獲した事例では、住宅2階から地面に向けた撃ち下ろしなど、入念な安全確認と打合せが実施されました。
- 麻酔銃による捕獲:
- 猟銃に比べ周囲への危険は少ないですが、命中してから不動化までに約5~10分かかります。麻酔銃による捕獲は、住居集合地域等で使用する場合、警職法の適用または鳥獣保護管理法による麻酔銃猟の許可が必要です。
行政・現場が動けない“法的リスクと社会的圧力”
人身被害を未然に防ぐための迅速な駆除対応を難しくしているのが、法制度上の制約と社会的な反発です。
- 法的制約(住居集合地域等での銃猟禁止):
- 鳥獣保護管理法第38条により、住居集合地域等(多数の者が集合する場所)での銃猟が原則禁止されています。ただし、緊急時には警察官や猟友会が特別な許可を得て対応する場合があります。
- クマが市街地や建物内に立てこもるなど緊急性が非常に高い状況でも、猟銃の使用が厳しく制限されており、迅速な捕獲が困難となり、監視だけの対応にならざるを得ないケースが多く、問題が長期化しやすいという課題があります。この問題に対処するため、国は法改正も含めた対応方針の検討・整理を早急に行うとしています。
- 社会的圧力(駆除に対する反発):
- 秋田市のスーパーに侵入したクマの駆除に対し、市などに「人間の都合で殺すな」「山に返すべき」「かわいそうだ」といった数百件もの感情的な抗議や苦情が寄せられました。
- こうした非人道的な電話や嫌がらせは、駆除活動を担う猟友会や行政担当者の公務遂行の妨げとなり、現場が萎縮する要因となっています。
- 駆除に反対する意見の背景には、クマを人間と生命的に平等な存在と捉える日本独自の動物観が影響している可能性が指摘されています。
現場で直面する“本当の課題”とは?
駆除を担う猟師の高齢化と人手不足
鳥獣捕獲を担う狩猟者の減少と高齢化は深刻です。
- 担い手の減少:
- 大量出没が起きても、対応できる人員や資金などの資源が不足しており、捕獲技術者の育成と確保は喫緊の課題とされています。
- 銃規制の影響:
- 命中精度の高いハーフライフル銃の所持が規制されると、経験の浅い捕獲者の学習機会や狩猟意欲が奪われ、クマ管理の担い手育成に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。
- ベアドッグの活用:
- 長野県軽井沢町や北海道知床地域では、ベアドッグ(クマ対策犬)がクマの追跡・威嚇・追い払いに成果を上げていますが、ベアドッグ単独ではクマを捕獲できず、最終的な捕獲や処置は人間の役割となります。
自治体の予算・リソースの限界と対応力の差
クマの生息状況のモニタリングや対策のための予算が、これまで都道府県単独では十分に計上されてこなかった経緯があります。
- 専門人材の不足:
- 行政は人事異動が宿命であるため、対策経験がリセットされるという課題があります。このため、鳥獣対策を専門とする人材を外部委託や嘱託職員として配置する事例が増えています。
- 鳥獣プロデータバンク:
- 国は、鳥獣保護管理に関する専門家を登録し、地方公共団体に紹介・派遣を支援する「鳥獣プロデータバンク」の活用を推進しています。専門家は計画策定の助言や被害防止対策の指導などを担います。
駆除に対する地域住民や団体からの反発と分断
駆除を巡っては、猟友会や行政担当者が匿名での誹謗中傷や非人道的な電話などの言われのない非難にさらされています。
また、クマの保護を訴える団体(日本熊森協会など)と、駆除を担う猟友会や行政の間で意見の衝突が見られます。
- 保護団体の主張:
- 日本熊森協会は、生け捕りにしたツキノワグマについて、終生大事に「保護する」活動を行っていると述べています。また、駆除を巡っては、保護団体側が保護するための準備を整えて待機していたのに、行政側が勝手に駆除に踏み切ったと主張する事例もあります。
- 駆除推進側の主張:
- 北海道猟友会支部は、一度町に出たクマは必ずまた出てくるため殺傷は不可避であり、殺傷せずにいたら人間に被害が出た場合、保護団体は被害者への保証をしてくれるのかと指摘しています。
この対立により、現場では関係者間の協力体制の構築が難しくなっています。
どう向き合うべきか?制度・意識・体制の再設計
駆除と保護のバランスをどう取るか:倫理と実利の視点
クマ類の管理の基本的な考え方は、地域個体群を維持しつつ、人の生活圏への出没を防ぎ、すみ分けを図ることです。
- 捕獲圧の焦点:
- 個体数調整を行う際でも、奥山でまんべんなく数を減らすのではなく、人里に侵入しやすい集落周辺の個体(緩衝帯にいる個体)に捕獲圧を上げることが重要であると考えられています。これは、奥山での個体群を保全しつつ、人里への侵入個体を減らすという実利的な目的を持ちます。
- 順応的な管理:
- 捕獲を含む対策を実施した結果をしっかりとモニタリングし、データに基づいて管理手法を柔軟に見直していく「順応的な管理」が求められています。
- 問題個体の管理:
- 全体的な個体数管理だけでなく、農作物を食害する個体や人家付近への出没を繰り返す「問題行動を起こすクマ」を対象とした個体レベルの管理が重要です。
地域主導の危機管理体制モデル:早期発見・初動対応の強化
クマの被害を減らすためには、「出没しにくい環境作り」が大切であり、対策は侵入防止対策、生息環境管理、個体群管理の3本柱で推進されます。
- 誘引物の徹底除去と管理:
- カキやクリなどの放任果樹の伐採、生ゴミ、ペットフード、さらにはにおいの強い塗料やガソリン・混合油などの燃料といった誘引物を徹底的に除去または管理することが、出没抑制の最も重要な対策です。特に秋田県では、放任果樹の面的な伐採事業をスタートさせています。
- 緩衝帯の整備:
- 耕作放棄地や河畔林、段丘林など、クマの移動ルートや隠れ場所となりやすい藪を刈り払い、見通しを確保し、クマが利用しづらい緩衝帯を整備します。岩手大学の研究会のように、住民や行政と協働して刈り払いを進める活動事例もあります。
- 早期発見・情報共有体制の強化:
- クマの目撃情報をマップ化・公開するシステム(富山県の「クマっぷ」など)を活用し、地域内で情報を共有します。また、自動撮影カメラなどを利用してクマの姿を「見せる」ことで、住民の危機意識を高めることも有効です。
- 専門人材の活用と訓練:
- 出没時の対応に備え、警察や猟友会などの関係機関が合同で、役割分担や動きを確認する机上訓練や現地訓練を日常的に実施することが重要です。
制度改善・例外措置・現場裁量のあり方を考える
- 法制度の改善:
- 住居集合地域等における銃猟禁止(鳥獣保護管理法第38条)の課題については、人の生命保護の観点から、国が法改正を含めた対応方針を早急に整理することが求められています。
- 人材育成の支援:
- 認定鳥獣捕獲等事業者制度の導入や、国の交付金による研修会開催など、捕獲技術者(猟師)の育成・確保の支援策が推進されています。
- 科学的な情報発信:
- 駆除に対する過度な苦情に対応するため、行政は科学的な情報発信を強化し、クマ管理の目的や必要性について社会の理解を深める努力が求められます。クマの保護管理は、行政、地域、市民、研究者がそれぞれの立場で何ができるかを考える必要がある課題です。
熊被害に関するFAQ
ここまでの本文と重複しない内容で、熊被害についての、よくあるQ&Aをリストしました。
- Q1. 日本にはどのようなクマが生息していますか?
- A1. 日本には北海道にヒグマ、本州・四国にツキノワグマが生息しています。四国のツキノワグマは絶滅寸前で、残り数十頭程度しかいません。
- Q2. クマ類はいつ頃冬眠しますか?
- A2. クマ類は11月下旬〜12月頃から冬眠期に入り、3月〜5月頃まで冬眠します。出産したメスは冬眠明けが遅い傾向があります。
- Q3. クマに遭遇してしまった場合の対処法を教えてください。
- A3. 落ち着いて、クマに背を向けずに、ゆっくりとその場から離れましょう。大声を出したり、走って逃げたりするのは、クマを驚かすためやめましょう。
- Q4. 誘引物となる「においの強いもの」には何がありますか?
- A4. 熟した果実や生ゴミの他、ハチの巣、家畜飼料、さらには草刈機などに使われるガソリンや混合油などの燃料もクマ類を誘引します。
- Q5. クマとの事故を防ぐために、入山者が持っていくべき装備は何ですか?
- A5. 鈴やラジオなど音の出るものを携帯し、人の存在を知らせましょう。万が一の遭遇に備えて、唐辛子成分であるカプサイシンを発射するクマ撃退スプレーの携帯も推奨されます。
- Q6. 有害駆除(許可捕獲)は増加していますが、狩猟による捕獲はどうなっていますか?
- A6. ツキノワグマ、ヒグマともに有害捕獲頭数は増加傾向にありますが、狩猟による捕獲頭数はほぼ横ばいです。
- Q7. 錯誤捕獲とは何ですか?
- A7. シカやイノシシなどの捕獲を目的としたわな(箱わな、くくりわな)に、クマ類など本来の捕獲対象以外の鳥獣が誤って捕獲されてしまうことです。錯誤捕獲された個体は、原則として放獣しなければなりません。
- Q8. 錯誤捕獲が増加すると、どのような問題が生じますか?
- A8. 錯誤捕獲が増加すると、本来の捕獲対象ではないクマの個体群への負の影響、負傷などアニマルウェルフェア上の課題、シカ・イノシシの捕獲効率の低下、行政コストの増加、そして捕獲従事者や通行人等の安全上のリスクが生じます。
- Q9. 学習放獣とは何ですか?
- A9. 生け捕りしたクマに対し、人間は怖い存在だと学習させるため、クマ撃退スプレーを噴射したり、爆竹を鳴らしたりする「忌避条件付け」をしてから山に放獣する方法です。
- Q10. 人身被害を防ぐための防御姿勢とは具体的にどうしますか?
- A10. クマは顔面・頭部を攻撃することが多いため、襲われたら両腕で顔面や頭部を覆い、直ちにうつ伏せになるなどの防御姿勢をとり、致命的ダメージを最小限に留めることが重要です。
- Q11. ゾーニング管理における「緩衝帯」の役割は何ですか?
- A11. 緩衝帯(バッファーゾーン)は、人の生活圏(排除地域)とクマの生息域(コア生息地)の間にある地帯で、クマの定着をさせない環境管理(刈り払い、捕獲など)が求められます。
まとめ
2023年に顕在化したクマの「超大量出没」は、奥山からの生息域拡大と里山の藪化という長期的な社会構造の変化に加え、山の堅果類の凶作による食料不足が引き金となり、人の生活圏に慣れた個体が増加した結果です。
この人身被害の危機に対し、行政はゾーニング管理に基づき対応を強化しようとしていますが、市街地での銃猟の法的制約、駆除を担う猟師の高齢化・人材不足、そして「クマを殺すな」という社会的反発という、三つの大きな壁に直面し、駆除対応が困難になる現実があります。
この「異常」な状態を「通常」にしてはならないという認識のもと、今後の対策においては、奥山の個体群を保全しつつ人里への侵入個体に捕獲圧を集中させるゾーニング管理を軸に、地域住民による誘引物の徹底除去(柿やゴミなど)と緩衝帯の整備を継続することが不可欠です。
また、行政は、住居集合地域での銃猟規制に関する法改正を含めた検討を急ぎ、専門人材や捕獲技術者の育成・確保に恒常的に資源を投入するとともに、警察や猟友会と連携した緊急時対応体制の整備を強化する必要があります。
クマと人の「すみ分け」を将来にわたって実現するためには、関係者全員が当事者意識を持ち、この問題を「風化させない」継続的な取り組みが求められます。


コメント