「12月2日で現行の保険証が発行停止」 「7700万人分の保険証が期限迫る」
Yahoo!ニュースなどでこんな見出しを見て、「えっ、私の保険証も使えなくなるの?」「病院に行けなくなる?」と不安を感じた方も多いのではないでしょうか。
現状の保険証の期限は、2025年12月1日です。以降は、この保険証は医療窓口などでは使えないのです。ただし、厚生労働省は患者や医療現場の混乱を避けるため、期限切れ保険証での受診も来年3月末まで特例的に認める方針となっています。
ところで現行の保険証の期限が切れた人には、『資格確認書』、お住まいの市区町村から送付されます。保険証の期限が切れても、この『資格確認書』を提示すれば、これまで通りの負担割合での受診などができるというもの。
そして、報道では「マイナ保険証を持っていない人には、自動的に『資格確認書』が送られるから大丈夫」などと言われています。
しかし、詳しく調べてみると、この「自動送付」の仕組みは保険者(健保組合や自治体)によってバラバラで、非常に複雑であることがわかりました。
「待っていれば資格確認書が届くはず」と信じていたのに、いざ病院に行こうと思ったら『資格確認書』が無い……そんな事態は絶対に避けなければなりません。
この記事では、ニュースの数字のカラクリと、あなたが『資格確認書』を確実に受け取るために今すぐ確認すべき具体的な手順を解説します。
この記事で分かること
- ニュースで騒がれている「7700万人」の正体と、本当のリスク
- 「『資格確認書』は自動送付」を過信してはいけない理由と、保険者ごとの複雑な実情
- あなたが対象者か今すぐ判定できる「3ステップ確認フロー」
ニュースの「7700万人」という数字の正体
一つの事例として、Yahoo!ニュースにあった記事を紹介します。
まず、メディアが報じている「7700万人」という数字について冷静に見ていきましょう。 これを見ると、「日本人の大半がマイナンバーカードを持っていないの?」と錯覚してしまいますが、事実は違います。
実際のマイナンバーカードの保有枚数は約1億枚近くに達しており、人口の約8割がすでにカード自体は持っています。 では、この7700万人とは誰のことでしょうか?
- マイナンバーカードを持っていない人
- マイナンバーカードは持っているが、健康保険証としての利用登録をしていない人
実は、この「2」の人たちがかなりの割合を占めているのです。「カードはあるが、紐付け作業をまだ行っていない」という層です。
この方々は、12月2日以降、現行の保険証の有効期限が切れた段階で、マイナ保険証の代わりとなる『資格確認書』が必要になります。
「自動で届くから安心」は罠? 複雑すぎる送付の仕組み
国は「『資格確認書』はプッシュ型(申請なし)で送る」としていますが、保険者ごとに対応が異なるため、これを鵜呑みにするのは注意が必要です。
なぜなら、あなたが加入している保険(協会けんぽ、組合健保、国民健康保険など)によって、「誰に」「いつ」送るかの判定基準やタイミングにズレがあるからです。
実際に起きうる「タイムラグ」のリスク
例えば、協会けんぽの場合、『2025年4月30日時点』などの基準日でマイナ保険証を持っていない人を抽出するケースがあるとされています。
また、マイナ保険証の登録を解除した直後の人や、転職・引越しをしたばかりの人は、情報の反映が間に合わず「自動送付リスト」から漏れてしまう可能性もゼロではありません。
『役所のシステムだから完璧だろう』と思っていると、タイミングによっては手元に書類が届かない可能性があります。
あなたが「自動送付の対象者」か今すぐチェック! 3ステップ確認法
自分が『資格確認書』の自動送付対象になっているのか、それとも何らかの手続きが必要なのか。 不安な方は、以下の3つのステップで確認することをおすすめします。
ステップ1:マイナポータルで「登録状況」を見る
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマホで「マイナポータル」にログインしてください。 トップ画面の「健康保険証」メニューを確認し、「未登録」と表示されていれば、あなたは原則として「自動送付」の対象です。 逆に、ここで「登録済み」になっているのにカードを紛失している場合などは、自動では届かないため、再発行申請が必要です。
ステップ2:会社員なら「総務」に聞く(協会けんぽ等の場合)
多くの企業(事業所)には、保険者から「資格確認書が必要な人のリスト(対象者一覧)」が事前に送付されているケースがあります。 会社の総務や人事担当者に、「私、資格確認書の送付対象リストに入っていますか?」と聞いてみるのが、最も確実で早い方法です。
ステップ3:保険者の公式サイトを確認・問い合わせる
お手元の健康保険証を見て、「〇〇健康保険組合」「〇〇市 国民健康保険課」などの名称を確認してください。 多くの自治体や組合の公式サイトには、「資格確認書の自動送付対象者」についての詳細ページがあります。
- 「〇月〇日までにマイナ保険証未登録の方が対象」
- 「〇月下旬から順次発送」
といった記載を確認しましょう。もし発送予定日を過ぎても届かない場合は、記載されている窓口へ直接電話で問い合わせるのが確実です。
正直、確認が面倒なら「スマホ利用」が一番ラク!
ここまで読んで、「確認するの面倒くさいな…」と思った方。 もし手元にマイナンバーカードがあるなら、いっそのこと「スマホを保険証にしてしまう」のが、一番手っ取り早い解決策かもしれません。
『資格確認書』がいつ届くかヤキモキするより、スマホでサクッと登録してしまえば、カードを持ち歩く必要すらなくなります。 登録作業は、カードをスマホにかざすだけで一瞬で終わります。
▼スマホでサクッと登録したい方はこちら
すでに多くの方が実践している「スマホでの登録手順」を、画像付きで徹底解説しています。
不安な方はぜひ参考にしてください。


健康保険証に関するFAQ(よくある質問11選)
制度が変わるタイミングで、よくある疑問をまとめました。なお、随時、対応などが変更する場合もありますので、詳細な確定情報については、お住まいの市区町村の窓口などでご確認願います。
- Q1. マイナンバーカードを紛失しました。病院にかかれますか?
- A1. 再発行中などの場合、申請すれば『資格確認書』が交付されるため、それを使って受診可能です。
- Q2. 暗証番号を忘れてしまいました。ロック解除はどこでできますか?
- A2. ロック解除は自分では出来ない仕様になっています。お住まいの市区町村の窓口で再設定(ロック解除)の手続きが必要です。面倒な手続きはありませんので、出向いて再設定しましょう。
- Q3. 高齢の親がカードを作りたがりません。どうすればいいですか?
- A3. 無理に作る必要はありません。期限が来れば『資格確認書』が送られてくるので、それを保険証として使えばOKです。
- Q4. 生まれたばかりの赤ちゃんの保険証はどうなりますか?
- A4. 出生届提出後、マイナンバーカードを作るまでは『資格確認書』が発行され、医療を受けられます。
- Q5. 転職しました。マイナ保険証の手続きは必要ですか?
- A5. マイナ保険証自体の再発行は不要ですが、新しい会社での「健康保険の加入手続き」は必要です。情報が反映されるまで数日かかる場合があります。
- Q6. 引っ越して住所が変わりました。カードはどうすれば?
- A6. 市区町村の窓口で、マイナンバーカードの券面事項更新(住所変更)の手続きが必要です。窓口での面倒な手続きはありませんので、引っ越し後、早めに手続きしましょう。
- Q7. お薬手帳は今後も持ち歩く必要がありますか?
- A7. マイナ保険証対応の病院・薬局で情報提供に同意すれば基本的には不要です。
- Q8. 「限度額適用認定証」の申請は必要ですか?
- A8. マイナ保険証を利用し、情報提供に同意すれば、事前の申請なしで高額療養費制度の自己負担限度額が適用されます(一部例外あり)。
- Q9. 家族の分も私のスマホで管理できますか?
- A9. マイナポータルアプリを使えば、代理人設定をすることで、親や子供の情報を自分のスマホで確認することが可能です。
- Q10. 今持っている健康保険証はいつまで使えますか?
- A10. 記載されている有効期限までは使えます(最長で2025年12月1日までという経過措置があります)。
- Q11. 有効期限が切れた古い保険証は返却が必要ですか?
- A11. 基本的には加入していた健保組合や自治体へ返却するか、自身で裁断して破棄する指示がある場合が多いです。指示に従ってください。
まとめ – ニュースに踊らされず、自分の状況を確認しよう!
「7700万人」という数字に驚かされますが、重要なのは「自分がどの状態にあるか」を把握することです。
- マイナンバーカードなし・未登録の人
- → 原則『資格確認書』が届くが、保険者によって時期が違うので要確認。
- マイナンバーカードがある人
- → この機会にスマホ登録を済ませてしまうのが、一番ストレスフリー。
「自動だから大丈夫」と過信せず、一度ご自身の登録状況や、加入している保険組合の案内をチェックしてみてください。それが、いざという時に困らないための唯一の方法です。

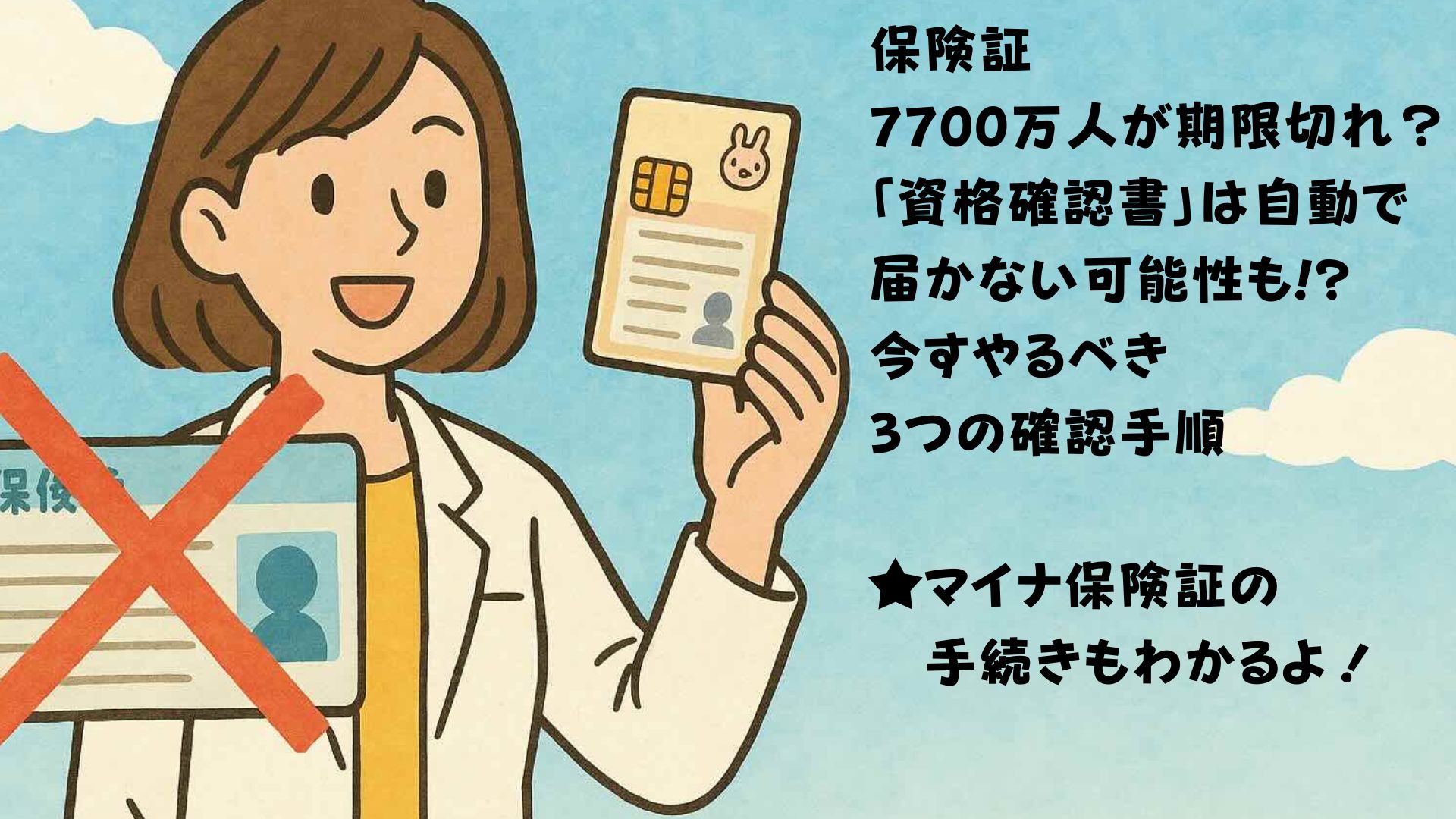

コメント