大相撲ファンのTOPIOです。
九州場所に期待することは、割と公平に次の記事を書いていますので、ご覧いただけると嬉しいです。

さて、この2つの記事とは全く違う切り口で、書きたいことを書かせていただきます。
それは…
タイトル通りに「大の里の全勝優勝と、安青錦が14勝をあげて、場所後に大関昇進を果たすこと」です!
この観点で言えば、初日は思い通りでホッとしました。
大の里の全勝優勝
2025年、大の里はすでに3回の幕内優勝を果たしています。年間最多勝も先場所が終わった段階で確定しています。
- 3月場所、東大関、12勝3敗(通算3度目の優勝)
- 高安との優勝決定戦で、初めて高安に勝ち優勝。
- 5月場所、東大関、14勝1敗で連続優勝(通算4度目)
- 2場所連続優勝で、場所後、横綱昇進を果たす。
- 初土俵から所要13場所での横綱昇進は史上最速。
- 9月場所、東横綱、13勝2敗(通算5度目)
- 豊昇龍との優勝決定戦で、横綱として初めての優勝。
- 2025年の年間最多勝も確定。
ちなみに、過去2回の優勝はこれ。
- 2024年5月場所、西小結、12勝3敗で初優勝
- 初土俵から7場所目での優勝は、史上最速。
- 2024年9月場所、西関脇、13勝2敗(通算2度目)
- 初土俵から所要9場所での大関昇進は昭和以降最速。
大の里は、なんと直近の9場所で5度も優勝しています。
優勝の率は、5割5分5厘、とんでもない大物です。
しかし…
これまで大横綱と言われる人たちが成し遂げたことを、大の里はまだやっていません。
それが「全勝優勝」です。
優勝回数が多い横綱の「全勝優勝回数」を載せますね。
優勝回数 | 全勝回数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 白 鵬 | ||||
| 大 鵬 | ||||
| 千代の富士 | ||||
| 朝青龍 | ||||
| 北の湖 | ||||
| 貴乃花 | ||||
| 輪 島 | ||||
| 武蔵丸 | ||||
| 曙 | ||||
| 若乃花(初代) | ||||
| 北の富士 | ||||
| 照ノ富士 | ||||
| ★「順位」は「通算優勝回数」の順位。 ★優勝がすべて1年6場所制以降である力士を対象とします。 |
||||
表からも明らかですが、優勝回数ベスト10(のべ12人)は全員横綱で、うち、曙を除く11人は、全勝優勝を果たしています。
白鵬の16回は別格ですが、まずは、1回を達成してほしい。
そのあとは、輪島の3回、貴乃花の4回に追いつき、追い越してもらいたい。
ところで…
筆者 TOPIOの常々の思いは「強い横綱・大関の実現」です。
この「トップ1・2の地位にある横綱・大関が弱くて、下剋上になる」・・・のも面白いかもしれませんが、やはり、強い横綱・大関の時代を見たいのです。
今年、5月場所を終えて、ようやく「2横綱体制」となりましたが、「大豊時代」になるとは・・・思えません。
で、続く新横綱を待つばかりなのですが、その前に「強い横綱の代名詞でもある全勝優勝」を成し遂げてほしい。
大の里はすでに横綱昇進を決めた5月場所で14勝を成し遂げていますので、あと一つ(この一つがとてつもなく大変なことはわかっていますが…)。
大関・横綱6場所、大の里の敗因分析
直近6場所の大の里の黒星について。
| 令和6年11月 | 西大関2 | 4日目 | 東前頭3 | 阿 炎 | 掬い投げ |
| 6日目 | 東前頭2 | 若隆景 | 押し出し | ||
| 10日目 | 西関脇 | 大栄翔 | 寄り切り | ||
| 11日目 | 東前頭6 | 隆の勝 | 押し出し | ||
| 13日目 | 西大関1 | 豊昇龍 | とったり | ||
| 14日目 | 東大関1 | 琴 櫻 | 上手投げ | ||
| 令和7年1月 | 西大関2 | 1日目 | 東前頭2 | 翔 猿 | 引き落とし |
| 4日目 | 東小結 | 阿 炎 | 引き落とし | ||
| 5日目 | 西前頭3 | 王 鵬 | 送り出し | ||
| 11日目 | 西前頭14 | 金峰山 | 突き倒し | ||
| 13日目 | 西大関1 | 豊昇龍 | 首投げ | ||
| 令和7年3月 | 東大関 | 4日目 | 西前頭1 | 若元春 | 押し出し |
| 10日目 | 東前頭4 | 高 安 | 寄り切り | ||
| 13日目 | 西関脇 | 王 鵬 | 押し出し | ||
| 令和7年5月 | 東大関 | 15日目 | 東横綱 | 豊昇龍 | 上手捻り |
| 令和7年7月 | 西横綱 | 4日目 | 東前頭2 | 王 鵬 | 押し出し |
| 8日目 | 東前頭4 | 伯桜鵬 | 押し出し | ||
| 10日目 | 西前頭4 | 玉 鷲 | 突き落とし | ||
| 13日目 | 東前頭15 | 琴勝峰 | 上手投げ | ||
| 令和7年9月 | 東横綱 | 4日目 | 東前頭2 | 伯桜鵬 | 突き落とし |
| 15日目 | 西横綱 | 豊昇龍 | 押し出し |
直近6場所(大関・横綱の場所)には、上述の表のように21個の黒星があります。
このなかで2回以上負けた相手は次の通り。
- 4回 豊昇龍
- 3回 王 鵬
- 2回 阿 炎
- 2回 伯桜鵬
要するに、今場所、大の里が全勝優勝するためには、この4人が最重要マークの対戦相手ということになります。
九州場所2日目の対戦相手は、初日で豊昇龍を破った伯桜鵬。まさに、大の里にとって、2日目は全勝優勝が果たせるかどうかを大きく左右する取組となります。
ところで…
大の里の体軀は身長 192cm、187kgと、幕内では一番大きい関取といってもいいかもしれません。だからこそ、大の里の立ち合いからのパワーは図抜けたものがあるのです。
しかし、前述の負けの表をもう一度ご覧ください。
負けの決まり手が意外なんです。
- 7回 押し出し
- 2回 寄り切り
押し出しで負ける、寄り切りで負ける・・・つまり、負けパターン21回のうち、9回は「大の里がパワーで負けている」のです。その率は .429。アバウト、半分は力負けしている?
過去、大の里の敗因分析を取組動画を何回も見て分析したことがあります。これ、不用意な引き技の結果、押し出し・寄り切りで負けるという大の里の典型的な負けパターンなんです。
なぜ、こうなるか。右四つ得意の大の里が、右下手を取れないときなど、バタバタして思わず引いてしまうという、あの悪い癖です。NHK大相撲解説者・琴風氏がいう「毒まんじゅう」。
この対策は1つ。立ち合い後、自分得意の形が取れない場合のBプランをどうするか・・・です。筆者 TOPIOには、Bプランの詳細は分かりません。
それともう一つ。
さきほど、豊昇龍には4回も負けていることを書きました。その4回の決まり手がこれです。
- とったり、首投げ、上手捻り、押し出し
要するに、豊昇龍は型らしい型を持っていない関取なんです。そして、トリッキー。
これからより強い横綱になる大の里にとっては、当面は最大のライバルであることは間違いありません。
なので、型を持たないトリッキー満載の横綱・豊昇龍、千秋楽で絶対に対戦する豊昇龍に対策は、「全勝優勝」という切り口では、さきほどのBプラン同様に大切なんです。
これも、筆者 TOPIOには、思いつくことができませんが・・・。
_/_/_/
それ以外の負けを分析すると・・・
- 2回 引き落とし
- 2回 突き落とし
- 1回 送り出し
- 1回 突き倒し
- 2回 上手投げ
- 1回 掬い投げ
今回、この切り口で過去の対戦動画を分析することはしていませんが、これまで大の里動画を分析した内容で判断すると、これらの負けパターンは、勢いよく相手を土俵際まで追い詰めたものの、攻め急いで、土俵際で逆転を食うという展開です。
これは「毒まんじゅう」(引き技)の次の、大の里の「負け癖」です。
_/_/_/
大の里の負け分析をまとめると、大の里が「全勝優勝」をするためには次の3つが重要だということになります。
- 引き技完全封印
- 土俵際で攻め急がない
- 万全の豊昇龍対策
安青錦の14勝
安青錦は、幕下付け出しを除くと、史上最速で関脇まであがってきた、たぐいまれな強い関取です。
関取になってからの成績は次の通り。
- 令和6年11月場所
- 東十両11、10勝5敗
- 令和7年1月場所
- 西十両5、12勝3敗
- 令和7年3月場所
- 東前頭15、11勝4敗
- 令和7年5月場所
- 東前頭9、11勝4敗
- 令和7年7月場所
- 東前頭1、11勝4敗
- 令和7年9月場所
- 西小結、11勝4敗
十両昇進以降、6場所連続の二桁白星、入幕してからの4場所では連続の11勝。
ものすごい安定度です。付け出しを除くと、史上最速の昇進を実現し続けている安青錦。
そのパワーの源泉は、あの「相手の胸に低く頭をつける」独特の型です。
あえて苦しい体勢での型の威力は凄く、すべて勝てるとはいいませんが、その型を実現したあとの勝率は高いのです。結果、入幕後の連続11勝となったわけです。
しかし、これは逆にいうと、毎場所4つは負けているということ。
そして、11勝の壁を抜けられていないということ。
それでは、大の里のときのように、安青錦が関取になってからの負け分析をしてみましょう。
| 令和6年11月 | 東十両11 | 5日目 | 西十両14 | 欧勝海 | 突き落とし |
| 7日目 | 西十両12 | 栃大海 | 突き落とし | ||
| 9日目 | 西十両7 | 剣 翔 | 上手投げ | ||
| 10日目 | 東十両4 | 玉正鳳 | 叩き込み | ||
| 15日目 | 西十両1 | 金峰山 | 突き出し | ||
| 令和7年1月 | 西十両5 | 2日目 | 西十両6 | 友 風 | 叩き込み |
| 12日目 | 西十両4 | 獅 司 | 突き落とし | ||
| 13日目 | 東十両3 | 竜 電 | 小手投げ | ||
| 令和7年3月 | 東前頭15 | 1日目 | 西前頭14 | 美ノ海 | 押し出し |
| 2日目 | 東前頭16 | 朝紅龍 | 送り出し | ||
| 13日目 | 東関脇 | 大栄翔 | 叩き込み | ||
| 令和7年5月 | 東前頭9 | 1日目 | 西前頭8 | 金峰山 | 押し出し |
| 10日目 | 西小結 | 若隆景 | 肩透かし | ||
| 11日目 | 西大関 | 琴 櫻 | 小手投げ | ||
| 12日目 | 東関脇 | 大栄翔 | 突き出し | ||
| 令和7年7月 | 東前頭1 | 2日目 | 西横綱 | 大の里 | 押し出し |
| 6日目 | 西小結 | 高 安 | 上手投げ | ||
| 14日目 | 東前頭14 | 草 野 | 寄り切り | ||
| 15日目 | 東前頭15 | 琴勝峰 | 突き落とし | ||
| 令和7年9月 | 西小結 | 1日目 | 東横綱 | 大の里 | 寄り倒し |
| 4日目 | 西前頭2 | 王 鵬 | 小手投げ | ||
| 11日目 | 東前頭11 | 正 代 | 寄り倒し | ||
| 15日目 | 西前頭4 | 若元春 | 寄り切り |
この期間、安青錦は通算で52勝23敗で、勝率は .693です。
素晴らしい安定度。
安青錦が2回負けたのは、次の3人です。
- 大の里、大栄翔、金峰山
おそらく、大栄翔も金峰山も九州場所は上位戦がないでしょうから、気にするのは大の里だけ。この対策は、安青錦に頑張ってもらいましょう。
次に負けの決まり手は次の通り。
- 4回 突き落とし
- 3回 叩き込み
- 3回 押し出し
- 3回 小手投げ
- 2回 上手投げ
- 2回 寄り切り
- 2回 寄り倒し
- 2回 突き出し
- 1回 送り出し
- 1回 肩透かし
これ分類すると次のようになります。
- ★差し手争いでパタリ
- 得意の型になる前に
- 4回 突き落とし
- 欧勝海、栃大海、獅司、琴勝峰
- 3回 叩き込み
- 玉正鳳、友風、大栄翔
- ★パワーで負ける
- 立ち合いで相手の力を逸らせないと…
- 3回 押し出し
- 美ノ海、金峰山、大の里
- 2回 寄り切り
- 草野、若元春
- 2回 寄り倒し
- 大の里、正代
- 2回 突き出し
- 金峰山、大栄翔
- 投げの打ち合いで負ける
- 得意の型になっても…
- 3回 小手投げ
- 竜電、琴櫻、王鵬
- 2回 上手投げ
- 剣翔、高安
- ★スキを突かれる
- 大きくない相手にこそ注意…
- 1回 送り出し
- 朝紅龍
- 1回 肩透かし
- 若隆景
安青錦の昇進速度が速いということも原因だと思いますが、意外と番付がかなり下の者に負けるんです。
そして、上記の①〜④を見ると、分かったことがあります。
安青錦は、抜群の能力はあるのですが、①〜④といった違った切り口で負けるということはこういう原因だと思います。
- 圧倒的な場数の少なさ
要するに、圧倒的に能力はあるものの、同時に圧倒的に体験が少なすぎるということです。
これは稽古しかありません。
なので、安青錦が猛稽古をしながらも、これから大関になり、横綱になり、強い相撲取りとして活躍し続けるためには、取りこぼしを一つ一つ対策して直すことでしょう。
まずは①。これで11勝の壁は抜けるのでは。これは得意の型を磨くということだと思います。
そして②。これが実現できれば14勝も夢ではありませんし、大関は近づくのではないでしょうか。難しいことは分からないのですが、相手の力を逸らすやり方があると思うのです。大相撲以外の世界にそのヒントがあるような気がするのですが。
③は稽古。
④は場数でしょうか。
_/_/_/
昨日のNHK大相撲解説者・琴風氏も言っていましたが、今場所11勝だと難しいが、12勝以上なら、場所後の大関昇進もあるのではと期待しています。
だからこそ、11勝の壁を越えることが、来年以降の安青錦の活躍にとって、目下、一番大切なことだと思うのです。
まずは今日の若元春戦、明日の伯桜鵬戦を、得意の型で撃破することです。応援しています。
まとめ
書きたいことを勝手に書き綴りました。
とくに推敲することなく、そのまま公開してしまいます。
あと1時間もしないで、幕内取組がはじまりますから。
今日も、大相撲楽しませていただきます。
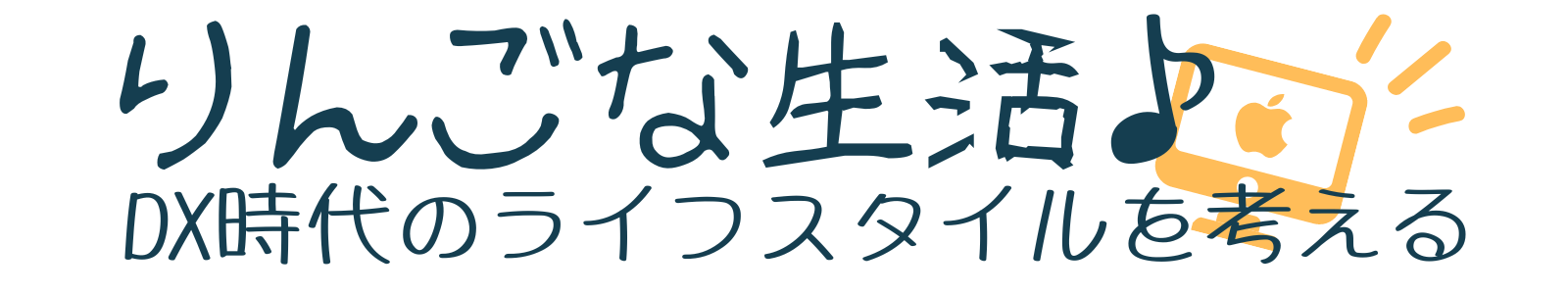

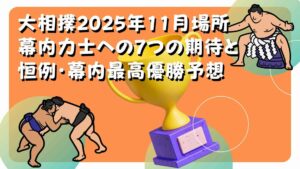
コメント