岸田首相(当時)肝いりで2023年4月に発足した「こども家庭庁」。少子化の加速 や児童虐待の増加 といった危機的状況を打開するため、子ども政策の「司令塔」として大きな期待を背負ってスタートしました。
しかし、その年間予算は7兆円超と巨額である一方で、「少子化は止まらない」「税金の無駄遣いではないか」といった厳しい批判がSNSなどで渦巻いているのも事実です。
特に子育て世帯や、将来の社会保障を担う若い世代にとって、この新しい省庁が「本当に役に立っているのか」は重大な関心事でしょう。
本記事では、こども家庭庁の設立背景から、実際にどのような施策を実施し、7兆円規模の予算がどこに使われているのかを徹底的に検証します。
批判の根拠と、今後期待される真の改革についても深掘りし、その有用性を読者自身が判断できるようにわかりやすく解説します。
- 「子ども家庭庁」が何をする機関なのか、その基本的な役割を理解できます。
- 「子ども家庭庁」がこれまでに実施した「こども誰でも通園制度」などの主な施策を把握できます。
- 年間7兆円規模とされる「子ども家庭庁」の予算内訳と、「意味ない/無駄」という批判の根拠を検証できます。
本記事の音声解説♪


本記事をベースとした動画解説&音声解説をつくりました。AIとやりとりしながらつくっています。
誤読についてはご容赦ください。
「子ども家庭庁」設立の裏事情?
本文に入る前に、もう一つ。高橋洋一氏の分析から。
ぜひ、一度、この動画をご覧いただきたいですが、お忙しい向きのために、高橋氏がいう「裏事情」について、ざくっとまとめます。
- 厚生労働省は大きな省になりすぎた、子ども家庭庁のように一部でも分割することで、大臣級が1人増える。
- 財源が必要になるから、いずれ消費税増税論につながる。
「子ども家庭庁」とは?こちらは表向き!
それでは本文。まずは、設立背景と目的から。
なぜ設立された?日本の子ども政策の課題
こども家庭庁設立の最大の背景にあるのは、待ったなしの深刻な社会課題と、従来の「縦割り行政の限界」です。
従来、子どもに関する政策や支援は、厚生労働省(保育、福祉、虐待)、文部科学省(教育、いじめ)、内閣府(少子化対策)など複数の省庁に分散していました。例えば、就学前の子どもの受け入れ先一つをとっても、保育所は厚労省、幼稚園は文科省、認定こども園は内閣府が所管するという状況でした。
この縦割りの結果、政策の隙間に支援が必要な子どもが取りこぼされたり、少子化の加速、児童虐待相談件数の増加、子どもの貧困 といった問題に対して総合的かつ迅速な対応が困難になっていました。
こうした状況を打開するため、「常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもまんなか社会(★コラム参照)の実現に向けて専一に取り組む独立した行政組織」として、こども家庭庁が創設されました。
コラム1:こどもまんなか社会とは?
「こどもまんなか社会」とは、全ての子どもや若者、そしてその保護者の視点を最も大切にし、子どもに関する取り組みや政策を社会の真ん中に据えて強力に推進していく、というこども家庭庁が掲げるスローガンであり、「こども基本法」の理念です。
この社会の目的は、日本国憲法と児童の権利に関する条約の精神に基づき、心身の状況や置かれている環境にかかわらず、全ての子どもが自立した個人として尊重され、将来にわたって幸福な生活(ウェルビーイング)を送れるようにすることです。
その実現のため、以下の基本理念が柱となります。
- 最善の利益の優先:
- 子どもの今とこれからにとって最もよいことを優先して考えること。
- 権利の主体:
- 子どもを「保護の客体」ではなく「権利の主体」と認め、意見を表明する機会と、その意見を政策に反映させる仕組みを確保すること。
- 切れ目のない支援:
- 妊娠期から社会に出るまで、縦割り行政の壁を越えて一貫した支援を提供すること。
これは、大人が中心になって作ってきた社会を、子どもの声をまんなかに置いて作り変えていくという、行政の新しい基本姿勢です。
いつから?どんな組織?発足までの流れ
こども家庭庁は、2023年4月1日に内閣府の外局として正式に発足しました。この組織には、内閣府の子ども・子育て本部や厚生労働省の子ども家庭局などが移管されています。
設立の理念的な根拠となっているのが、令和5年4月1日に施行された「こども基本法」です。この法律は、日本国憲法と児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全ての子どもが個人として尊重され、健やかに成長できる社会の実現を目指すものです。
「子ども家庭庁」が担う主な役割と業務
こども家庭庁のミッションは、大人が中心になって作ってきた社会を「こどもまんなか社会」へと作り変えていくための「司令塔」機能を発揮することです。
支援対象は誰?家庭・子ども・妊産婦までカバー
こども家庭庁は、「こども」だけでなく、「こどものある家庭」及び「妊産婦」など、母性の福祉増進も支援の対象としています。
支援は、妊娠前・乳幼児期・学齢期以降といったライフステージを通じて切れ目なく行われます。その具体的な業務範囲は非常に広く、児童虐待防止対策、母子保健、社会的養護、障害児支援、いじめ防止対策、不登校対策 など多岐にわたります。
他省庁との違いは?「一本化」の意味
こども家庭庁の組織的な特徴は、従来の省庁の縦割りを打破し、子ども政策を強力に推進するための「司令塔」機能を持つ点です。
庁内は以下の1官房2局体制で構成されています。
- 長官官房(企画立案・総合調整部門):
- 子ども政策全般の企画立案と、関係省庁との総合調整を担います。少子化対策や、こども大綱の策定、こどもの意見聴取と政策への反映などが主な役割です。
- 成育局:
- 子どもの健やかな成長や安全、就学前の教育・保育(保育対策、母子保健、こどもの安全など)を担当します。
- 支援局:
- 児童虐待防止、社会的養護、貧困対策、ひとり親家庭支援、障害児支援など、困難を抱える子どもや家庭への切れ目ない支援を担当します。
さらに、こども家庭庁は他の省庁に対し、子どもに関する政策の改善を求める「勧告権」(★コラム参照)を持っています。これは、政策の進展を促す上で重要な権限です。
コラム2:勧告権とは?
子ども家庭庁の「勧告権」とは、同庁が子ども政策の「司令塔」として機能するための強力な権限の一つです。
これは、子ども政策を担当する内閣府特命担当大臣が有する権限で、他の省庁や関係行政機関に対し、子どもに関する政策の改善を強く求めることができるものです。
勧告権の目的は、従来の縦割り行政の弊害を打破し、関係省庁間の連携を促すことで、進展しない事案を是正し、政策の実施を加速させる点にあります。ただし、この権限を真の司令塔機能として発揮するためには、さらなる権限の強化が必要であるとの指摘もあります。
実際にやったこと:2023〜2025年の主な施策
発足後、こども家庭庁は「こども未来戦略」 や「こどもまんなか実行計画2025」 に基づき、多岐にわたる施策を展開しています。
こども誰でも通園制度、ヤングケアラー支援など
具体的な政策には、次のようなものが挙げられます。
- 児童手当の拡充:
- 児童手当の制度が拡充されました。
- こども誰でも通園制度(仮称):
- 就労要件を問わず、時間単位で柔軟に保育施設を利用できる新たな通園給付制度として、2025年度に制度化し、2026年度からの全国実施を目指しています。
- 社会的養護の見直し:
- 里親養育包括支援(フォスタリング)事業など、社会的養護の充実も図られています。
- 子育て支援の強化:
- 妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金) や、ヤングケアラーの支援体制強化 が進められています。
- こどもの居場所づくり:
- 「全ての子どもが安全で安心して過ごせる居場所」を提供するため、指針の策定やモデル事業を通じた推進が行われています。
これらの施策の結果、待機児童数は減少傾向にあるといった成果も出ています。
法改正やガイドライン整備の動き
組織の基盤となる法的・制度的整備も進められています。
- こども基本法の施行:
- 令和5年4月1日に施行され、「こども大綱」の策定と推進が進められています。こども大綱では、従来の少子化対策大綱、子ども・若者育成支援推進大綱、子どもの貧困対策に関する大綱が一元化されました。
- こども性暴力防止法(日本版DBS):
- こども関連業務従事者の性犯罪歴等を確認する仕組み(日本版DBS)の創設に向けた検討が行われており、2030年までに事業者の制度認知率75%以上を目指しています。
- 相談支援体制の強化:
- 母子保健機能と児童福祉機能の一体的な運営を行う「こども家庭センター」の設置が促進されています。
- 意見反映の仕組み:
- 小学生から20代の子ども・若者の意見を直接聴き、政策に反映させるための仕組み「こども若者★いけんぷらす」が構築されました。
「子ども家庭庁の予算」どう使われている?
こども家庭庁の予算は、その巨額さゆえに発足当初から最も厳しい批判にさらされている論点の一つです。
ここでは、年間7兆円超とされるこの巨額な資金が、具体的にどのように構成され、何に使われているのかを、一般会計と特別会計に分けて詳しく解説します。
年間予算の内訳と主な使途
こども家庭庁の予算は、単なる行政運営費だけではありません。国全体の主要な子ども・子育て支援施策の費用が計上されており、その総額は一般会計と特別会計を合わせると7兆円超に及びます。
例えば、令和8年度の概算要求総額は7兆4,229億円とされています(デジタル庁一括計上予算は除く)。このうち、約6割が一般会計、約4割が特別会計で構成されています。
一般会計について
一般会計は、国庫負担金や補助金といった形で、子ども政策の基盤となる費用や、特別会計の財源として充てられる部分を担っています。
- 令和8年度概算要求額:4兆3,082億円
一般会計の主な使途は、以下の通りです。
- 子ども・子育て支援特別会計への繰入:
- この繰入金は、特別会計で執行される児童手当や子どものための教育・保育給付といった基幹事業の財源となります。
- 保育・児童福祉関連:
- 保育対策費(保育所の運営費補助の一部など)。
- 児童虐待防止等対策費(児童相談所運営、社会的養護の充実など)。
- 母子保健衛生対策費(未熟児養育医療、不妊治療支援など)。
- 国立児童自立支援施設の運営経費や整備費。
- 経済的支援・教育支援関連:
- 母子家庭等対策費(児童扶養手当の給付費負担金、母子父子寡婦福祉資金の貸付金など)。
- 大学等修学支援費(授業料の減免や学資支給金補助など)。
特別会計について
特別会計は、特定の事業の経理を一般会計と区別して行うために設けられています。こども家庭庁関連の事業は、主に「子ども・子育て支援特別会計」を通じて執行されます。この特別会計は、従来の年金特別会計の子ども・子育て支援勘定と、労働保険特別会計の育児休業給付関係を統合し、令和7年度に創設されました。
- 令和8年度概算要求総額:3兆1,147億円
この特別会計は、さらに「子ども・子育て支援勘定」と「育児休業等給付勘定」の2つに分かれています。
【子ども・子育て支援勘定】
- 令和8年度概算要求額:2兆416億円
- 主な使途:
- 子どものための教育・保育給付等(幼児教育・保育の無償化など)。
- 児童手当交付金。
- 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金の制度化など)。
- 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度など、2026年度からの全国実施を目指す)。
- 地域子ども・子育て支援(放課後児童クラブ、病児保育事業など)。
- 主な財源:一般会計からの繰入、事業主拠出金、そして令和8年度から導入される子ども・子育て支援納付金。
【育児休業等給付勘定】
- 令和8年度概算要求額:1兆731億円
- 主な使途:
- 育児休業給付に必要な経費。
- 出生後休業支援等給付費(出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金など)。
- 主な財源:雇用保険料(労働保険特別会計から繰入)、子ども・子育て支援勘定からの繰入(支援納付金が充当される部分)など。
無駄遣い?成果?費用対効果の検証
これほどの巨額な予算が動く中で、国民からは「本当に効果があるのか」という費用対効果や使途の透明性に関する厳しい目が向けられています。
【批判の根拠】
- 予算規模の異常な膨張:
- 旧厚生労働省が3.2兆円で行っていた業務を引き継いだにもかかわらず、予算が7兆円超に膨れ上がっているという指摘があります。
- 成果の欠如と「独身税」批判:
- 発足後も出生数が過去最低を更新し続けているため, 「7兆円以上使っても少子化は止まらない」という不信感が根強くあります。特に、2026年度から導入される子ども・子育て支援金制度が、公的医療保険料に上乗せして徴収される仕組みであることから、恩恵が少ない独身者を中心に「独身税」だと揶揄され、大きな反感を買っています。
- 「中抜き」や失敗したDX投資:
- 設立時の重要ポストの大量新設 や、広報・調査研究といった分野で広告代理店などに巨額の予算が流れているという批判があります。ある情報では、若者向けの調査で電通に数十億円が投じられたとも指摘されています。
- 児童虐待の疑いをAIで判定するツールに10億円が投じられましたが、試験導入で誤判定が多く、全国導入が見送られたことも、予算の無駄遣いの象徴として批判されています。
【成果と反論】
一方で、予算の大部分は、児童手当や保育所・放課後児童クラブの運営費といった、子育て世帯にとって欠かせない既存の基幹施策の継続に充てられています。そのため、「解体すれば新生児1人あたり1000万円を配れる」という批判に対し、「すでに国民に届いているお金が多くを占めるため、解体しても財源は確保できない」という反論もあります。
また、子育て支援は少子化対策のためだけでなく、少子化であろうがなかろうが本来行うべき政策である という指摘もあります。発足後、待機児童の減少 や、妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)といった成果も出ています。
【真の課題:予算よりも「権利」の壁】
批判に真摯に向き合い、EBPM(エビデンスに基づく政策立案)(★コラム参照)を徹底し、予算の使途の透明性を向上させることが今後の重要な課題です。
しかし、巨額な予算配分の是非以上に、この組織の根源的な課題として指摘されているのが、子どもの「権利擁護」の法的整備の遅れです。
例えば、児童相談所による「一時保護」は事実上の身体拘束ですが、子ども本人がその決定に対して異議を申し立てる権利や、外部の弁護士にアクセスできる権利は法律に規定されていません。これらの子どもの人権を保障する法改正は、数兆円単位の予算を必要としませんが、「業者の陳情が来ない」ために政治的に優先されないという、行政構造の根本的な歪みが指摘されています。
真に「こどもまんなか社会」を実現するには、予算配分の最適化と同時に、子どもの権利を法的に守る「法改正の本気度」が問われていると言えるでしょう。
コラム3:EBPMとは?
「EBPM(エビデンスに基づく政策立案)」とは、客観的で定量的なデータや科学的な根拠に基づき、政策の立案、評価、改善を行う手法です。
こども家庭庁は、その司令塔機能を発揮するため、EBPMの徹底を重要な課題として掲げています。特に「こども大綱」に基づき、課題抽出の事前段階から施策の効果の事後評価・公表に至るまで、多面的に施策を見直すPDCAサイクルの構築を目指しています。
この推進のため、庁内にはEBPM推進体制が整備されており、EBPMアドバイザーなどの外部専門家と連携し、施策担当者への伴走支援を実施しています。EBPMは、限られた財源を最大限有効活用し、政策の透明性を高め、国民の理解を得る上で不可欠な取り組みと位置づけられています。
意味ある?ない?世間の評価と今後の課題
この動画は、三浦大臣の定例記者会見です。素晴らしすぎる内容です(^_^;)
それでは世間の評価など…。
「意味ない」と言われる理由と反論
世間では「子ども家庭庁は意味がない」という批判が根強いです。
「意味ない」と言われる主な理由:
- 少子化の未改善:
- 発足後も出生数が過去最低を更新し続けており、「7兆円以上使っても成果が出ていない」との不信感があります。
- 独身税批判:
- 2026年度から始まる子ども・子育て支援金制度 が、公的医療保険料に上乗せして徴収される仕組みであるため、直接恩恵のない独身者を中心に「独身税」だと揶揄され、反感を買っています。三原じゅん子こども政策相(当時)は「独身税ではない。将来の社会保障の担い手となる子どもを育てることは、独身の方を含め全員にメリットがある」と説明しましたが、炎上は収まりませんでした。
- 主要指標の未改善:
- 出生率だけでなく、子どもの自殺率の減少が見られず、不登校児童数や児童虐待件数も減少していないという批判があります。
反論・本来の目的:
こども家庭庁の目的は、少子化対策だけでなく、「こども基本法の理念を実行し、子どもの人権が保障される状況にすること」です。また、支援が必要な人に制度を届けるプッシュ型支援を推進するなど、行政の姿勢そのものを変えることを目指しています。
今後どうなる?期待される変化と課題
こども家庭庁の今後の方向性として、批判に真摯に向き合い、「透明性の向上」と「EBPM(エビデンスに基づく政策立案)の徹底」が求められています。特に予算の使途について、どの施策にいくら使われ、どのような効果があったのかを明確にすることが、国民の理解を得る上で不可欠です。
しかし、根源的な課題は、「子どもの権利擁護」の法制化の遅れです。
例えば、児童相談所による「一時保護」は、実際には外部との通信や面会が制限される事実上の身体拘束であるにもかかわらず、子ども本人が不当な拘束に異議を申し立てる権利は法律に規定されていません。また、子どもが弁護士にアクセスできる権利も、法的根拠がないまま一部自治体で試行的に導入されている状態です。
真の「こどもまんなか社会」を実現するには、巨額の予算配分よりも、児童福祉法に「子どもの異議申立て権」を明記する、弁護士アクセス権を法制化する など、法的権利の明文化が最優先の課題として強く指摘されています。
おまけ、「子ども家庭庁」に関するエックスポスト
エックスで「子ども家庭庁」と検索して出てくるポストを上から3つ載せます。忖度無しに上から3つです。ただし、広告他、子ども家庭庁とは無関係なポスト、及び、なぜか埋め込みできないものは除く。
このあとも、否定的なポストが続きます。
子ども家庭庁に関するFAQ
ここまでの本文内容と重複しない形で、子ども家庭庁に関するFAQをまとめました。
- Q1: こども家庭庁が掲げるスローガンは何ですか?
- A1: 「こどもまんなか社会」の実現です。
- Q2: こども家庭庁が他の省庁に持つ「勧告権」とは何ですか?
- A2: 他の省庁に対して子どもに関する政策の改善を強く求めることができる権限です。
- Q3: 「こども基本法」は何年に施行されましたか?
- A3: 令和5年(2023年)4月1日に施行されました。
- Q4: 従来の「少子化社会対策大綱」などは現在どうなっていますか?
- A4: 「こども基本法」に基づき、これまでの3つの大綱(少子化社会対策、子ども・若者育成支援、子どもの貧困対策)を束ねた「こども大綱」に一元化されました。
- Q5: 虐待防止対策の地域拠点として設置が進められている組織は何ですか?
- A5: 母子保健機能と児童福祉機能の双方を一体的に運営する「こども家庭センター」です。
- Q6: 子ども・若者の意見を政策に反映させるための仕組みは何ですか?
- A6: 小学生から20代を対象とした意見聴取の仕組み「こども若者★いけんぷらす」です。
- Q7: 2026年度から全国で実施される予定の新たな通園給付制度は何ですか?
- A7: 「こども誰でも通園制度」です。就労要件を問わず、月一定時間まで時間単位で利用できます。
- Q8: 子ども政策推進会議の会長は誰が務めていますか?
- A8: 内閣総理大臣です。
- Q9: 子ども家庭庁の組織は大きく分けて3つの部門がありますが、それぞれ何ですか?
- A9: 長官官房(企画立案・総合調整部門)、成育局、支援局の3部門です。
- Q10: 子ども関連業務従事者の性犯罪歴等を確認する仕組みを指す略称は何ですか?
- A10: 「日本版DBS」です(こども性暴力防止法に基づく)。
- Q11: 児童相談所による「一時保護」に関して、子ども本人に保障されていない権利の一つは何ですか?
- A11: 異議申立て権(法律に規定なし)や、外部の弁護士へのアクセス権などです。
まとめ
- こども家庭庁は、縦割り行政の打破を目指す内閣府の外局の「司令塔」です。
- 主な役割は、妊娠期から社会に出るまでの切れ目ない支援と、児童虐待防止対策です。
- 年間予算は7兆円超で、大部分は児童手当や保育所運営費といった既存施策に使われています。
- 少子化の未改善や支援金制度への批判から、「予算の無駄遣い」という厳しい世論に直面しています。
- 真の課題は、子どもの「異議申立て権」など、人権擁護のための法的整備が遅れていることです。
こども家庭庁は、深刻化する少子化や児童虐待、子どもの貧困といった課題に対し、従来の省庁の縦割りを解消し、子ども政策を強力に推進する「司令塔」として2023年4月に発足しました。そのミッションは、常に「こどもの最善の利益」を考えた「こどもまんなか社会」を実現することです。
発足後の主な実績としては、児童手当の拡充、「こども誰でも通園制度」の創設準備、そして子ども・若者の意見を直接聴く「こども若者★いけんぷらす」の導入 など、多岐にわたる施策を展開しています。組織の権限強化として、他省庁への勧告権を持つ点も特徴的です。
一方で、年間7兆円規模の予算 に見合うだけの少子化対策の成果が見えないこと や、「子ども・子育て支援金制度」が「独身税」と揶揄されるなど、世論の厳しい批判に直面しています。特に、10億円をかけた虐待判定AIの失敗 や、広報・調査研究費の使途に対する「中抜き」の疑念は、予算の透明性に対する不信感を高めています。
最も根源的な課題は、子どもの「権利の主体」としての法的権利擁護が未整備な点です。児童相談所での子どもの異議申立て権や弁護士へのアクセス権の法制化は、巨額の予算を必要としないにもかかわらず、政治的に優先順位が低いという構造の歪みが指摘されています。今後、こども家庭庁が真に機能するためには、予算の使途を明確化するEBPMの徹底とともに、子どもの権利擁護を最優先する法改正を断行する「本気度」が問われるでしょう。
_/_/_/
ここまで「子ども家庭庁」について、できる限り中立的な(肯定的・否定的両論併記)組み立てで書いてきました。
ラスト、筆者 taoの意見を。
子ども家庭庁は不要だ!・・・というような「0か1か」という主張は問題があると考えます。現在の子ども家庭庁の業務(役割)の半分くらいは、厚生労働省にすでにあったものを引き継いでいます。それらは、それなりの必要に応じて作られた制度・仕組みです。ただし、これらの既存の仕組みの見直しを継続することは必要です。
一方、厚生労働省のときと比較すると、子ども家庭庁の予算規模はざっくり言って倍くらいになっています。この増えた分の検証・検討は必要です。そして、こども家庭庁の予算規模増大が、将来的な消費税増税の理由の1つとなることについては、十分な議論が必要です。

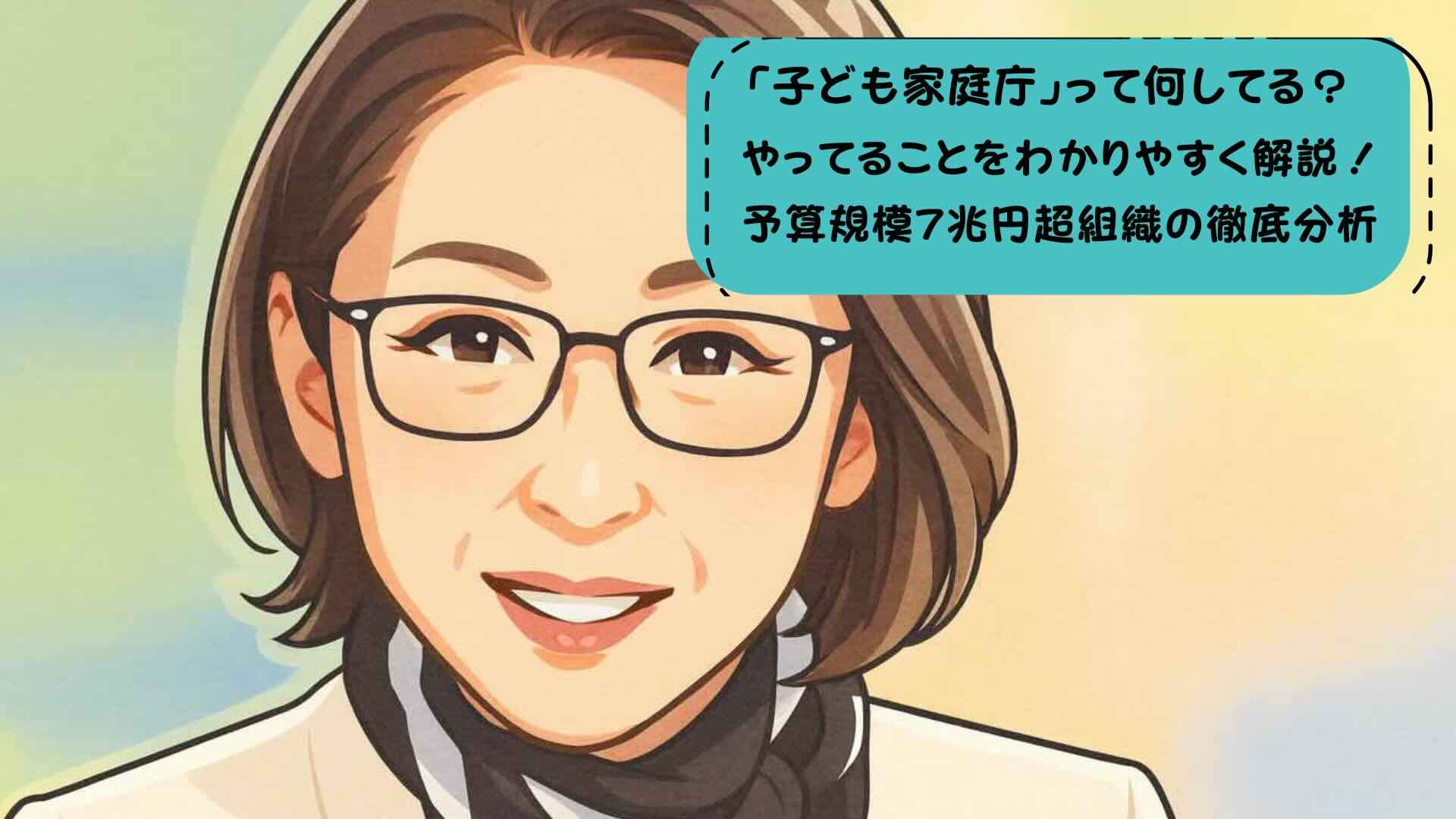
コメント