EU(欧州連合)の競争法当局は、再販価格維持(RPM: Resale Price Maintenance)をめぐる独占禁止法違反に対し、厳しい監視の目を光らせています。
特に近年、高級ブランド業界において、巨額の制裁金が科される事態が続いています。欧州委員会は、グッチ(GUCCI)、クロエ(Chloé)、ロエベ(LOEWE)の3ブランドに対し、合計1億5,700万ユーロ(約270億円 ★1)もの制裁金を科したと発表しました。
RPMとは、メーカーが販売代理店に対し「定価から値引きしないように」と求める行為のことで、ブランドの価値や利益を守るために行われがちですが、その実態は公正な競争を妨げ、消費者利益を損なう重大な競争法違反とみなされます。
この制裁事例は、国際的なビジネスを展開する企業、特に日本企業にとっても、EU市場における法務リスクの認識を新たにするきっかけとなります。
この記事では、再販価格維持の基本から、なぜ高級ブランドが制裁の対象となったのか、そしてEU競争法の厳格な姿勢が今後のビジネスにどのような影響をもたらすのかを解説します。
- ★1. 1ユーロ、176円換算(本記事公開日現在レート)
- 再販価格維持(RPM)の基本的な意味と規制の枠組みを理解できる。
- 高級ブランド3社(グッチ、クロエ、ロエベ)が制裁を受けた具体的な事案の内容を把握できる。
- 再販価格維持に関するEU競争法の規制の厳しさや、日本企業への影響の可能性を理解できる。
動画解説
本記事は、ちょっと難解な部分があるかも…。ということで、動画解説をつくりました。これは、Notebook LMというAIで作りました。誤読その他、多少気になるところがあるかもしれませんが、ご了承ください。
8分ほどの短い動画です。これを見ていただいてから本記事を読むと、より理解度が高まると思います!
再販価格維持とは?
まずは、制度の概要と違法になるケースを理解しましょう。
RPM(再販売価格維持)とは何か?基本の意味と仕組み
再販売価格維持(RPM)とは、商品のメーカーなどのサプライヤーが、小売店などの再販業者に対し、製品の最低販売価格などを指定し、再販業者が自由に販売価格を設定することを制限する行為を指します。
これは、生産あるいは流通の流れの異なる段階(メーカーと流通業者など)で事業を行う2つ以上の事業者間で締結される「垂直的協定」(垂直的制限行為)の一つです。
「再販売」と呼ばれるのは、流通業者が商品を購買した後、それを加工せずにそのまま第三者に販売するためです。
メーカー側は、RPMを通じて小売段階での価格競争が回避されることで、卸価格の安定や利益の変動抑制を図る傾向があります。
また、小規模の小売業者にとっては、最低利潤が保証されることで薄利多売を回避できる利点があるとされています。
日本とEUでの再販価格維持の規制の違い
再販売価格維持に対する規制の枠組みは、国や地域によって異なりますが、先進諸国では厳しく規制されています。
| 比較の視点 | 日本 | EU |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 独占禁止法(独禁法) | EU機能条約 第101条第1項(競争法) |
| 原則 | 原則禁止(不公正な取引方法に該当) | 原則違法(ハードコア制限行為) |
| 例外 | 「正当な理由」がある場合(公正な競争秩序を阻害するおそれがない場合)。著作物(書籍、雑誌など)は法定例外。 | 個別に効率性の主張が認められる可能性はあるが、欧州委員会が適用免除を認めた事例は存在しない。 |
| 推奨価格 | 認められるが、実質的な価格拘束となれば違法。 | 認められるが、実質的な価格固定に至らないことが条件。 |
日本では、独占禁止法上、RPMは『正当な理由がないのに』行われる場合に禁止されており、この『正当な理由』の判断は、消費者利益や市場競争への影響を総合的に考慮して行われます。
一方、EUにおいては、RPMは「ハードコア制限行為」とされ、競争を制限することが強く推定されます。
たとえ効率性の改善(例:ただ乗り防止)が主張されたとしても、EU競争法第101条第3項が求める「消費者への利益の公平な分配」などの要件をすべて満たす可能性は低いと推定されています。
「価格拘束」が違法になる理由と背景
再販売価格維持行為が競争法で厳しく規制される主な理由は、価格競争の減少または削減という、公正な競争秩序に対する負の影響が非常に大きいと見なされるためです。
RPMがもたらす主な負の効果としては、以下の点が挙げられます。
- ブランド内競争の消滅:
- 同一ブランド製品を扱う小売業者間での価格競争がなくなるため、小売価格が上昇し、消費者は安価な購入手段を得られず、消費者余剰が減少します。
- 流通の非効率化:
- 価格競争が不要になることで非効率的な取引慣行が温存されやすく、流通の合理化が進まない原因となります。
- イノベーションの低下:
- 再販価格維持は、価格競争を妨げることで、より効率性の高い小売業者の市場参入や低価格に基づく販売形態(ディスカウント業者など)の拡大を阻止または妨害し、販売段階のダイナミズムやイノベーションを低下させます。
ただし、価格を直接的に固定するだけでなく、推奨価格を順守しない小売店への製品供給の遅延・停止や、リベート・払い戻しの拒否/削減、警告、罰則など、実質的に再販価格を固定するインセンティブや制裁も、間接的な価格固定手段として違法と見なされます。
コラム:EU競争法における規制概念の概要
EU競争法における規制概念の全体像
EU競争政策は、域内単一市場における公正かつ自由な競争を促し、消費者利益と経済の健全な発展を図ることを目的としています。法的根拠は「EUの機能に関する条約」(TFEU)にあり、主に以下の3本柱で構成されています。
- 反トラスト(独占禁止)規則:
- 水平的(カルテルなど)または垂直的(再販価格維持など)な合意による競争阻害や、市場支配的地位の濫用を禁止します。
- 企業結合規制:
- 合併・買収(M&A)が市場支配的な地位の構築や強化を通じて競争を阻害しないよう事前に審査します。
- 国家補助の規制:
- 加盟国による特定の企業への補助が競争を歪曲しないよう規制します。
これらの規則は、企業がEU域内で活動する限り、その本拠地がEU域外であっても適用されます。
EU機能条約第101条第1項により禁止される競争制限的な合意であっても、一定の条件(効率性の向上や消費者への利益の公平な分配など)を満たせば適用免除(第101条第3項)が宣言される可能性があります。
垂直的制限(Vertical Restraints/Vertical Agreements)とは?
垂直的制限とは、生産または流通の流れの異なる段階で事業活動を行う2つ以上の事業者間で締結される合意または協調的行為で、商品やサービスの購入、販売、または再販売の条件に関するものを指します。
典型的にはメーカー(供給者)と販売店(購入者)の間で生じます。
EU機能条約第101条第1項は、域内市場の競争を制限・阻害・歪曲する目的または効果を有する垂直的制限を原則禁止しています。
垂直的制限の主な類型には、再販売価格維持(RPM)、排他的流通契約、選択的流通制度、競業避止義務などがあります。
垂直的制限は水平的制限に比べて悪影響が少ないものの、市場支配力が存在する場合に競争上の懸念が生じます。
ハードコア制限(Hardcore Restrictions)とは?
ハードコア制限とは、EU競争法上の一括適用免除規則(VBER)垂直的協定全体から除外する競争制限行為のことです。
これらの行為は競争を制限することが強く推定され、EU機能条約第101条第1項に該当すると推定されます。
ハードコア制限には、主に再販売価格維持(RPM)(最低販売価格等の維持)や、販売対象地域または販売対象顧客の厳格な制限などが該当します。
RPMはハードコア制限の典型であり、たとえ効率性改善の主張があったとしても、欧州委員会が個別に適用免除を認めた事例は過去に一つもありません。
なぜ問題に?高級ブランド3社に下ったEUの制裁とは
グッチ・クロエ・ロエベに何があったのか
欧州委員会が2025年10月14日に発表した制裁の対象となったのは、高級ブランドのグッチ、クロエ、ロエベの3社です。
これらの高級ブランドは、自社のブランドイメージや利益構造を維持するため、販売店に対して価格統制を行っていたと見られています。
報道によると、3社は、オンラインと店舗の両方で小売業者に対し、小売価格、割引率、セール期間などを制限し、時には割引を禁じる行為を行っていました。
RPMは、メーカー側が価格統制を通じて利益を維持しようとする行為ですが、競争法上は消費者への価格上昇や選択肢の制限につながる重大なリスクを伴います。
EUが約270億円の制裁金を科した理由
欧州委員会がこれらの3ブランドに科した制裁金は、合計で1億5,700万ユーロ(約270億円)という巨額に上ります。
EU競争法(EU機能条約第101条)は、欧州市場における競争を確保することを目的とした「条約」の中で規定されており、その法規範の格は非常に高いとされています。
この競争法に違反した場合の制裁は厳しく、グループ全体の全世界売上高の10%を上限とする制裁金が科される可能性があります。
これは、話題となった個人情報保護法GDPR(上限4%)よりも高い上限であり、EUが競争法をいかに重要視しているかを示しています。
再販価格維持行為は、競争に与える影響が大きい「ハードコア制限行為」の一つとされており、競争制限の目的がある行為は、その競争制限効果の程度を検討するまでもなく原則違法(競争法第101条第3項の適用免除を受けない限り)とされます。
調査対象となった「価格制御」の具体手法
現代の流通においては、インターネット販売の拡大に伴い、価格制御の手法も巧妙化しています。
調査対象となった価格制御の具体的手法には、直接的な価格指定に加え、以下のような間接的な手段が使われます。
- 価格監視ソフトウエアの利用:
- サプライヤーが自社製品や競合製品のネット上での販売価格を監視ソフトで調べ、割引価格で販売していた小売店を特定するために利用します。英国の競争・市場庁(CMA)の摘発事例でも、この手法が確認されています。
- ペナルティの賦課:
- 推奨価格(レコメンド)を順守しない小売店に対し、製品の供給遅延や供給停止、または契約解除といった制裁行為を行うことで、実質的に再販価格を固定します。
- リベート/払い戻しの制限:
- 価格水準に従うことを条件とした販売促進費用のリベートや払い戻しを設定し、価格固定を間接的に達成します。
これらの行為は、価格の固定化を達成するための補助的手段と見なされ、再販売価格維持につながると判断されます。
再販価格維持をめぐるEU規制の視点と今後の展開
EU競争法が問題視する3つのポイント
EU競争法が垂直的制限(RPMを含む)に対して問題視する主な負の効果(反競争的効果)は、以下の3点です。
- ブランド内競争の減少:
- 同一ブランド製品を扱う販売業者間(小売業者間など)の価格競争が抑制されること。
- 市場閉鎖:
- 競合する供給者や購入者が、反競争的な方法で市場から排除されること。
- 共謀(カルテル)の促進:
- 供給者間、または購入者間での競争が緩和され、明示的または黙示的な共謀(意識的並行行為)が助長されること。特に再販価格維持は、市場の価格透明性を高め、供給者間の共謀を助長する効果を持ちます。
これらの負の効果は、特に川上または川下において市場支配力が存在する場合に、価格、生産、イノベーション、または製品の品質・バラエティーに悪影響を及ぼす可能性が高まります。
ブランド側の主張と、規制当局の対応の違い
ブランド側が再販価格維持を正当化するために主張する主な理由は、「効率性の向上」や「消費者利益」に関するものです。
| 主張のポイント(効率性の主張) | 内容 |
|---|---|
| ただ乗り(フリーライダー)問題の防止 | 高水準の販売前サービス(詳細な説明、展示など)を提供する小売業者が、そのサービスを利用しない低価格の小売業者に顧客を奪われるのを防ぎ、サービス提供のインセンティブを維持する。 |
| 新製品の導入促進 | 新製品の導入時に、販売業者の販売努力を促す手段を提供し、製品の投入を成功させる。 |
| 二重限界性の防止 | 川上(メーカー)と川下(小売店)の双方が独占力を持つ場合に、それぞれが利潤最大化を図ることで価格が高くなりすぎることを防ぐ。 |
規制当局の対応
EU競争当局は、RPMが競争を制限すると強く推定しており、これらの効率性の主張が認められるためのハードルは極めて高いです。
EU機能条約第101条第3項に基づき、適用免除が認められるには、次の4つの要件をすべて満たし、事業者がそれを立証する必要があります。
- 商品の生産・販売の改善または技術的・経済的進歩の促進に役立つこと。
- 当該行為によって生ずる利益が消費者に等しく行き渡ること(負の効果を上回る効率性が消費者にもたらされること)。
- 上記目的達成のために必要以上の制限を課すものでないこと。
- 対象商品の実質的な部分について、参加事業者間の競争を排除するおそれがないこと。
欧州委員会は、ガイドラインで効率性の主張が成立する可能性のある例(新製品投入時、フランチャイズでの短期キャンペーン、ただ乗り防止など)を紹介しているものの、これまで事業者の主張を認めて個別に適用免除を決定した事例は一つもありません。
今後、日本企業にも影響する可能性とは?
欧州市場において事業を展開する日本企業にとって、EU競争法への対応は喫緊の課題です。
- 日本企業は摘発の筆頭である事実:
- 英調査会社PaRRによると、2003年から2016年までの13年間で、EU当局からEU競争法違反(主にカルテル)で科された制裁金総額のうち、9.9%が日本企業に対するものであり、米国、韓国、台湾を上回る割合となっています。近年は、ヤマハやローランドなどの日本の大手楽器メーカーも垂直的制限行為で摘発対象に含まれるなど、カルテルに限らず、垂直的制限に関する摘発事例も目立っています。
- オンライン販売に伴う監視強化:
- ネット販売が活発化する現代において、再販価格維持や販売地域制限などの垂直的制限行為に対するEU当局の監視は特に厳しくなっています。サプライヤーが価格監視ソフトウエアを用いて、小売店の割引販売を特定・阻止する行為は、競争法違反の手段と見なされています。
- 規制への対応の必要性:
- EU競争法は、日本独禁法と比較して適用免除のハードルが非常に高く、違反した場合の制裁リスクは巨額です。欧州市場で商品を販売する企業は、EU委員会による垂直的制限に関する一括適用免除規則(VBER)およびガイドラインの改定(2022年6月1日施行予定)に合わせて、現地販売店との契約関係や流通体制を適時に見直す必要があります。
再販価格維持についてのFAQ
ここまでの本文と重複しない内容で、再販価格維持についてのFAQをまとめました。
- Q1. 再販売価格を推奨すること(希望小売価格)は違法ですか?
- A1. サプライヤーが小売店に対し再販売価格を推奨すること自体は認められています。ただし、推奨価格を順守しない小売店に供給停止や遅延などの制裁行為があれば、実質的な価格固定とみなされ違法となる可能性が高いため注意が必要です。
- Q2. 日本の独占禁止法で再販が例外的に認められている「著作物」には具体的に何が含まれますか?
- A2. 公正取引委員会の解釈では、書籍、雑誌、新聞、レコード盤、音楽用テープ、音楽用CDの計6品目のみが再販行為可能な著作物とされています。映像ソフト(DVD、ブルーレイ)、コンピュータソフト、電子データ・電子書籍などは含まれません。
- Q3. 日本でかつて「指定再販商品」とされていたものは何ですか?
- A3. 1953年から1959年にかけて、化粧品、毛染め、歯磨き、家庭用石けん・合成洗剤、雑酒、キャラメル、医薬品、写真機、ワイシャツの9商品が指定されました。しかし、1997年3月31日までにすべて指定が廃止され、現在指定再販商品はありません。
- Q4. なぜ再販価格維持行為は競争に悪影響を及ぼすとされるのですか?
- A4. 主に、ブランド内競争(同一ブランド製品を販売する業者間の競争)の消滅による小売価格の上昇、流通の合理化の停滞、および消費者余剰の減少をもたらすためです。
- Q5. 再販価格維持を回避するために、メーカーが採る「委託取引方式」とは何ですか?
- A5. 実質的にメーカーが販売していると認められる取引です。メーカーが在庫リスクおよび売れ残りのリスクを負担しているなど一定の要件を満たしていれば、再販行為を行っても通常は違法とされません。
- Q6. EU競争法における「垂直的協定」とはどのようなものですか?
- A6. 生産あるいは流通の流れの異なる段階で事業を行う2つ以上の事業者間で締結される協定または協調的行為で、商品またはサービスの購入、販売、または再販売の条件に関係するものを指します。
- Q7. EUの競争当局は、再販価格維持の効率性向上(ただ乗り防止など)の主張をどのように評価しますか?
- A7. 効率性の主張を検討する際も、その行為がEU機能条約第101条第3項のすべての要件(消費者への利益の公平な分配、必要以上の制限でないことなど)を満たすことを説得力をもって証明する必要があります。
- Q8. 日本の新聞業に適用される「新聞特殊指定」とは何ですか?
- A8. 新聞業において新聞の値引きの禁止などを定めた特殊指定です。再販制度と異なり、法によって原則として定価販売が強制される点が特徴です。
- Q9. 再販価格維持の違法性を判断する際に、EUと米国の主なアプローチは何ですか?
- A9. EUは再販売価格維持を「ハードコア制限」として原則違法と推定し、米国は「合理の原則」を適用し、競争促進効果と競争制限効果を比較衡量します。
- Q10. 最近、日本の家電業界で導入が進んでいる「指定価格制度」とは、RPMとどう違いますか?
- A10. 指定価格制度は、販売店に対して返品を条件とするなど、メーカーが製品の価格を指定できる制度です。これは、メーカーが在庫リスクを負担する委託取引に近い形態で、独占禁止法に抵触しないよう設計されています。
- Q11. EU競争法で、最大再販売価格または推奨再販売価格を設定することは許容されますか?
- A11. 当事者の市場シェアが30%を超えない場合、最大再販売価格の設定は一括適用免除の対象となる可能性があります。ただし、それが圧力やインセンティブの結果、最低または固定販売価格に至らないことが条件です。
まとめ
- 再販価格維持(RPM)は、競争に重大な悪影響を及ぼすとされる『ハードコア制限行為』の一つとして扱われ、原則的に禁止されます。
- 高級ブランド3社への制裁は、オンライン・店舗での価格・割引率の制限が独禁法違反と認定された事例である。
- EU当局は、RPMの効率性主張をほとんど認めず、違反時の制裁金は全世界売上高の10%が上限となるなど非常に厳しい。
- 日本企業は垂直的制限行為での摘発事例も増えており、現地での流通慣行の見直しが不可欠である。
欧州委員会が高級ブランド3社(グッチ、クロエ、ロエベ)に対し、再販価格維持(RPM)を理由に約1億5,700万ユーロ(約270億円)の巨額な制裁金を科した事案は、EU競争法の厳格な姿勢を明確に示すものです。
再販価格維持(RPM)は、メーカーが小売店に対し最低販売価格などを指定し、価格の自由な決定を拘束する行為であり、EU競争法では競争に最も悪影響を及ぼす「ハードコア制限行為」として扱われ、原則的に禁止されます。その主な理由は、同一ブランド製品間での価格競争を消滅させ、流通のダイナミズムを低下させ、消費者利益を損なうためです。
たとえブランド側が「ただ乗り防止」や「新製品の市場導入」といった効率性向上の主張を行ったとしても、EU競争法第101条第3項の適用免除を受けるハードルは極めて高く、欧州委員会が個別の事案で適用免除を認めた事例は過去にありません。これは、日本の独占禁止法における「原則禁止・例外あり」というアプローチよりも厳格な姿勢です。
日本企業は、過去にEU競争法違反で多額の制裁金を科された経緯があり、特にインターネットを通じた取引が増加する中で、価格監視ソフトの利用や、推奨価格を逸脱した販売店への供給停止といった間接的な価格拘束手段が、当局による摘発の対象となり得ます。
欧州市場において事業を継続する企業は、高額な制裁金リスクを避けるため、現地販売店との契約や流通慣行について、実質的な価格拘束につながる一切の行為を排除するよう、早急に法務リスクの見直しを図る必要があります。

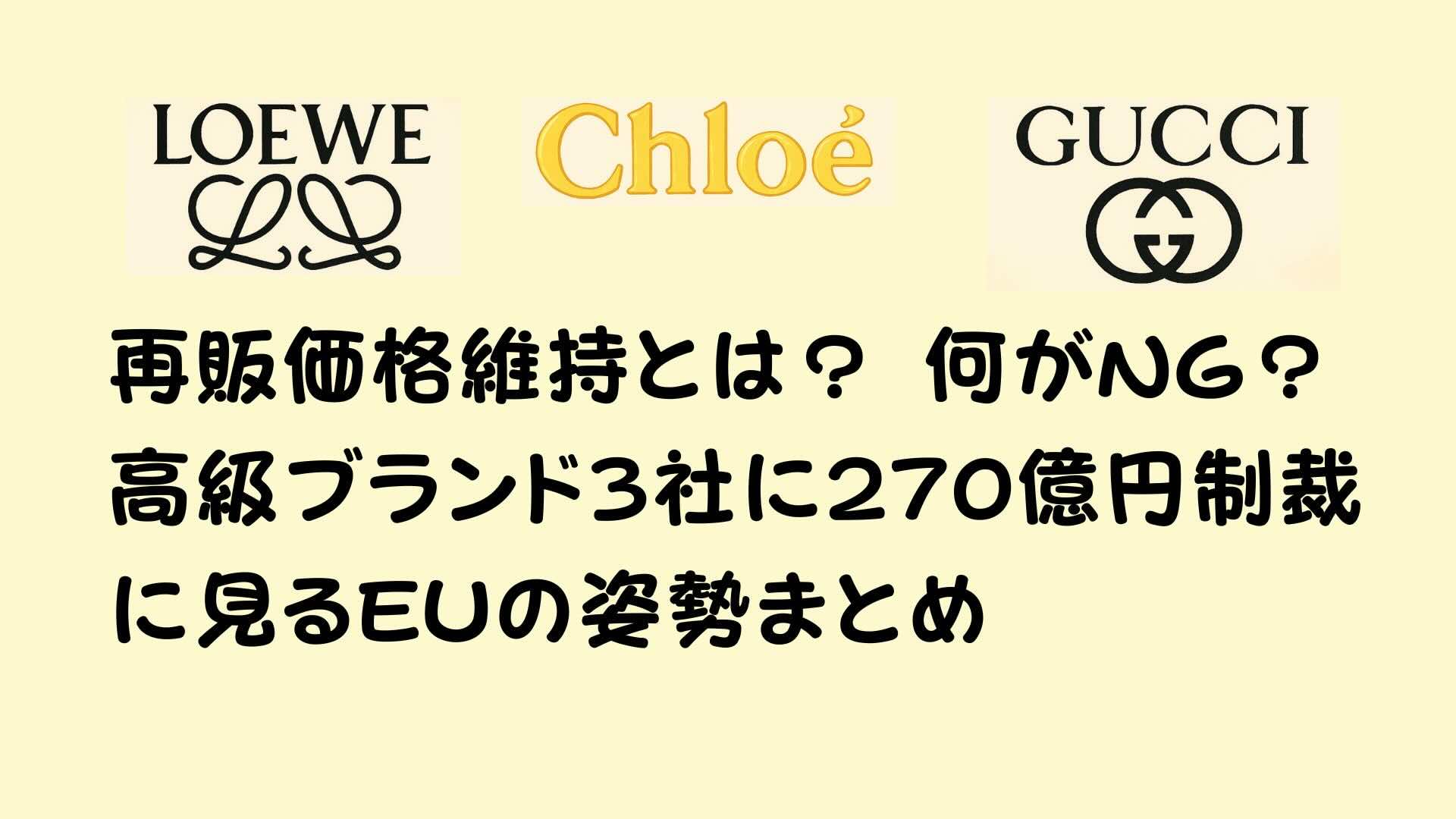
コメント