2025年10月6日、医学の世界に歴史的なニュースが飛び込みました。大阪大学の坂口志文(さかぐち しもん)特任教授(74歳)が、Mary E. Brunkow氏、Fred Ramsdell氏と共にノーベル生理学・医学賞の受賞が発表されました。
受賞理由は、免疫反応を抑える「制御性T細胞(Treg)」の発見、すなわち「末梢免疫寛容に関する発見」という、人類の健康を根底から変える可能性を秘めた偉業です。
Tregは、免疫の過剰な暴走を防ぐ「ブレーキ役」として機能し、特に自己免疫疾患の治療に革命をもたらすことが期待されています。
本記事では、この画期的な発見の科学的な意義、自己免疫疾患治療への具体的な応用可能性をまとめました。
そして長年の研究を支えた夫婦の人間ドラマも深掘りしました。
なお、ノーベル賞受賞に関しては、こちらのノーベル化学賞受賞・北川進氏の記事もどうぞ。


本記事の音声解説♪
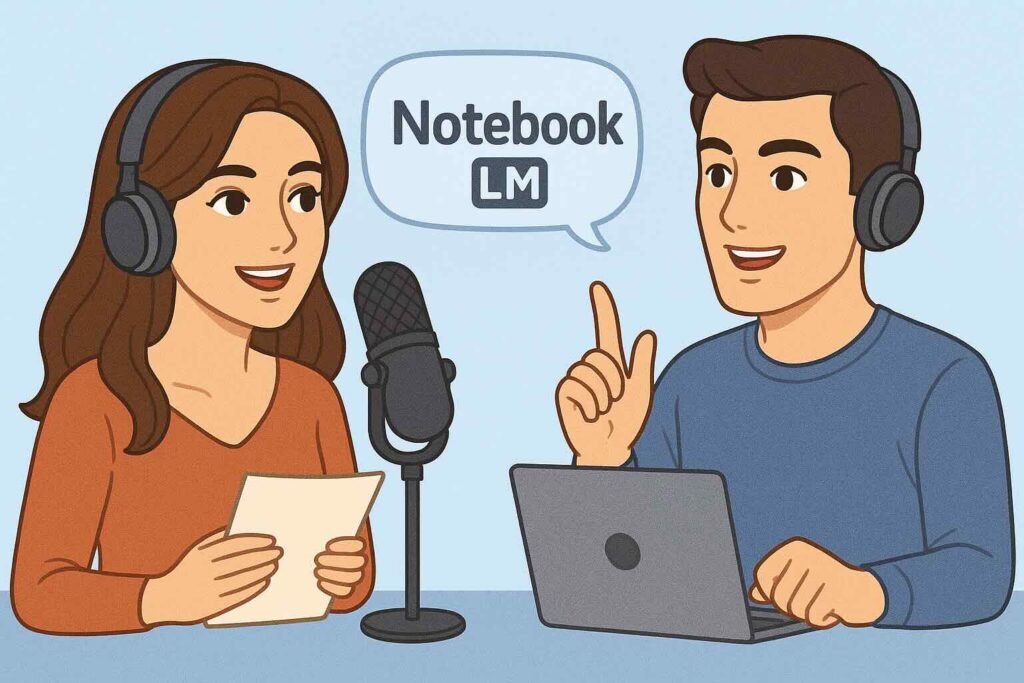
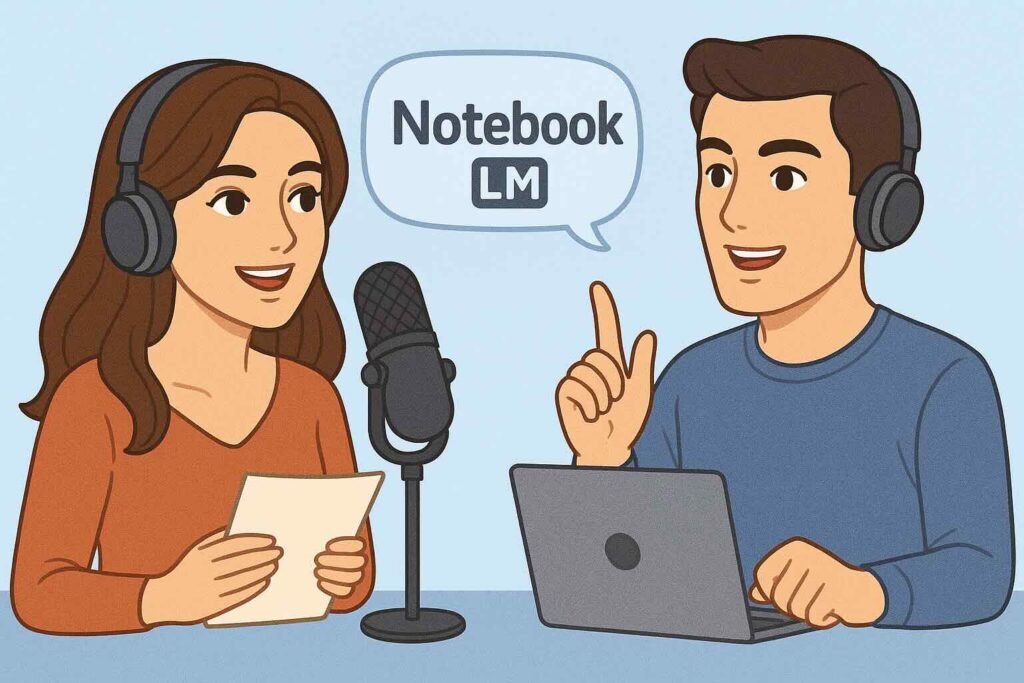
本記事をベースとした音声解説をつくりました。AIとやりとりしながらつくっています。
二人三脚を「ふたりさんきゃく」なんて読んでしまっています。誤読についてはご容赦ください。
なお、再生速度については、下記バーの右端にある「縦に並んだ3つの点」をクリックして、「再生速度」を選択して、求める再生速度を設定してください。
- ノーベル賞受賞が決まった坂口志文氏の業績についての音声解説
坂口志文教授のノーベル賞受賞とは?
ノーベル生理学・医学賞2025の受賞内容
2025年のノーベル生理学・医学賞は、坂口志文氏(大阪大学特任教授)のほか、Mary E. Brunkow氏、Fred Ramsdell氏の3名に授与されることが、スウェーデンのカロリンスカ研究所によって発表されました。
授賞の理由は、ヒト免疫システムの「制御性T細胞」を特定し、新たな研究分野の基盤を築いた「末梢免疫寛容に関する発見」です。
個人での日本人のノーベル賞受賞者として、2021年の物理学賞を受賞した真鍋淑郎氏以来、4年ぶりとなります。また、生理学・医学賞に限定すれば、2018年の本庶佑氏以来7年ぶり、日本人の生理学・医学賞受賞は6人目となります(外国籍含まず)。
なお、坂口氏は、ノーベル賞の登竜門の一つとされる『ガードナー国際賞(Gairdner International Award)』を2015年に受賞しています。
大阪大学で初のノーベル賞受賞者
今回の受賞は、『大阪大学で現職として在籍中の研究者』としては初のノーベル賞受賞決定という快挙でもあります。
坂口氏は現在、大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授を務めています。
免疫学の常識を覆した「制御性T細胞」の発見
制御性T細胞(Treg)は、ウイルスなどの外敵を攻撃する免疫機能が、誤って宿主である自分の細胞を攻撃しないように制御する「ブレーキ役」を担う細胞集団です。
坂口氏がこの制御性T細胞の概念を提唱し、その存在を実験的に示し始めた1990年代当時、多くの研究者は、免疫が自己を攻撃しない仕組み(免疫寛容)は、胸腺で有害な免疫細胞が排除される「中枢性免疫寛容」によってのみ確立されると考えていました。
そのため、免疫を抑制する細胞が存在するという坂口氏の仮説は、「免疫を抑える細胞など存在しない」という当時の学界の潮流に逆らうものであり、「眉唾」と見なされ、長らく注目を集めませんでした。
免疫の「アクセル」と「ブレーキ」の比喩で説明
免疫のシステムを車に例えるなら、外敵を攻撃する免疫細胞は「アクセル」であり、病原体を排除するための駆動力です。
しかし、アクセルだけの車は暴走してしまいます。ここで、制御性T細胞(Treg)は、過剰な免疫反応を抑制し、免疫システム全体が暴走しないように調整する「ブレーキ役」として機能します。
Tregは免疫システムにおいて、攻撃が過剰にならないよう抑える「警察官」にも似た存在です。
制御性T細胞が解明した免疫の仕組み
免疫が自分自身を攻撃してしまうメカニズム
私たちの免疫システムは、侵入する何千種類もの微生物から身体を常に守っています。しかし、免疫反応が過剰に働くと、本来守るべき自分自身の組織や細胞を「非自己」と誤認し、攻撃してしまうことがあります。これが自己免疫疾患です。
坂口氏は、免疫が自分自身を誤って攻撃する現象(自己免疫疾患)を解明する中で、免疫システムの普遍的な原理が隠れていると確信しました。
彼は、どんな人でも正常な自己を攻撃する免疫細胞(自己反応性T細胞)を持っているが、それを抑制するTregが同時に存在することで何事も起こらない、という独自の哲学を貫きました。
制御性T細胞の「ブレーキ役」としての機能
Tregは、体内の免疫細胞のごくわずか(CD4陽性T細胞のうち約5%)しか占めていませんが、その小さな集団が、他の免疫細胞の活動を調整し、自己に対する免疫反応を抑制する極めて重要な役割を果たしています。Tregは免疫の恒常性維持、すなわち免疫システムの健全なバランスを保つ上で不可欠です。
Tregは、自己反応性T細胞に、抗原刺激に対して活性化せず反応できない「アネルギー状態」(免疫不応答状態)を誘導することで、長期的な免疫寛容を成立させ、自己免疫疾患を回避させていることが示されています。
自己免疫疾患はなぜ起こるのか
自己免疫疾患が起こる主な原因は、Tregの機能異常です。
Tregの機能が低下したり数が減ったりすると、免疫システムのバランスが崩れ、関節リウマチや1型糖尿病、多発性硬化症などの自己免疫疾患を引き起こします。このTregの働きをコントロールするカギとなるのが、Foxp3(フォックスピースリー)という転写因子です。
米国人研究者であるMary E. Brunkow氏とFred Ramsdell氏は2001年に、自己免疫疾患にかかりやすい特定のマウス系統にFoxp3遺伝子の変異があることを突き止め、さらにヒトにおける同等の遺伝子変異がIPEX症候群という重篤な自己免疫疾患を引き起こすことを示しました。
Foxp3は、制御性T細胞の分化と機能に不可欠なマスター転写因子であり、坂口氏はこのFoxp3遺伝子が自身が1995年に特定した制御性T細胞の発生を制御していることを証明し、遺伝子と病態を一本の糸で結びつけました。
この一連の発見により、免疫学の概念は一変しました。免疫は単に外敵を「攻撃」する力だけでなく、内部の「制御」と「調和」のバランスの上に成り立っているという新しい視点が浸透し始めました。
自己免疫疾患治療への応用と未来
制御性T細胞を使った治療法の現状
制御性T細胞(Treg)の研究は、病気の種類によって「増やす」か「抑える」かという正反対のアプローチが存在します。この「二つの方向性」が、免疫療法をより精密な個別化治療へと導いています。
- Tregを「増やす」治療:自己免疫疾患、アレルギー、移植医療。
- 過剰に働く免疫を抑え、炎症を鎮める目的で、Treg細胞の投与や強化療法が進められています。
- Tregを「減らす」治療:がん治療。
- がん細胞がTregを利用して免疫の攻撃を回避しているため、Tregを抑制または除去し、免疫反応を上げてがん細胞を攻撃する目的で行われます。
関節リウマチ、多発性硬化症など具体的な疾患への応用
Tregメカニズムが解明されたことで、関節リウマチや1型糖尿病などの自己免疫疾患の治療や発症防止に繋がる可能性があります。
特に期待されているのが細胞療法です。これは、患者さんからTreg細胞を取り出し、体外で増やしたり強化したりした後に体内に戻すことで、免疫機能のバランスを正常化させる手法です。
また、臓器移植における拒絶反応の抑制にも応用が期待されています。Tregの持つ抗原特異性という性質を利用することで、移植された臓器を攻撃する免疫反応だけをピンポイントで抑え、ウイルスや病原菌への防御機能は残すことが可能になるかもしれません。
今後期待される新しい治療アプローチ
現在、坂口研究室(大阪大学)では、約30名の研究者体制で、Tregを用いた細胞療法の実用化を目指した研究が進行しています。
画期的な進展としては、誘導型制御性T細胞(iTreg)の開発があります。中外製薬と大阪大学IFReCの共同研究では、Tregの機能維持に不可欠なマスター転写因子FoxP3の発現制御ネットワークを解明し、より機能的かつ安定的なiTreg誘導を可能にする知見が示されました。この成果は、新たな自己免疫疾患治療への応用が期待されています。
さらに、2012年にノーベル賞を受賞したiPS細胞(人工多能性幹細胞)技術とTreg研究の融合も進められています。iPS細胞から制御性T細胞を効率的に製造する技術開発が進められており、iPS細胞研究財団によると、2028年ごろまでにヒトでの臨床研究や治験開始が期待されています。これは、日本発の2つのノーベル賞級技術の組み合わせが、未来の個別化医療を加速させることを示しています。
実用化までの課題とスケジュール
Tregを操作する免疫制御技術は、その応用が期待される一方で、課題も残されています。
特に、免疫を意図的に操作するため、過剰反応や感染リスクなどの安全性の課題が伴います。坂口氏自身も、会見で「免疫を操る研究こそ、最も慎重であるべきだ」と語っています。
また、細胞医療は一般的にコストが莫大にかかるため、実用化と事業化に向けては、コストや品質規格の設定、多額の資金が必要であり、国内の製薬企業やベンチャー企業との早期アライアンスが求められています。研究者からは、実際の治療として患者に届くには「まだ何年も時間がかかる」という現実的な見通しも示されていますが、今回の受賞は実現に向けた大きな一歩と評価されています。
夫婦研究者の二人三脚〜発見の舞台裏〜
妻・教子さんとの30年にわたる共同研究
坂口氏の長年にわたる研究活動は、妻の教子(のりこ)さんという強力なパートナーによって支えられてきました。二人は愛知県がんセンター研究所での出会いを経て、1990年に研究のためにアメリカに渡りました。
留学当時、坂口氏が提唱した免疫抑制細胞の概念は学会で強い逆風にさらされており、「免疫を抑える細胞などあり得ない」という風潮が強い中、教子さんは助手として夫と共に実験に取り組みました。実験動物の世話から細胞解析に至るまで、研究活動のほぼ全てを夫婦二人で担っていたといいます。
帰国後の研究でも協働は続き、2015年に英科学誌『ネイチャー』に掲載された制御性T細胞に関する重要な論文では、教子さんが筆頭著者として名を連ねています。二人の協働の歩みこそが、世界的な成果へと結実したのです。
常識を疑い続けた研究姿勢
坂口氏の研究の原点は、1970年代後半に目にした「生後3日目のマウスから胸腺を摘出すると自己免疫性の炎症を起こす」という明瞭な実験現象です。胸腺を取り除けば免疫が弱くなるはずという当時の常識に反し、結果は正反対でした。彼は、この現象の裏に普遍的なメカニズムがあると確信し、流行の理論(抑制性T細胞)が目の前の現象を説明できないのであれば取り入れない、という信念を貫きました。
彼は、研究者としての姿勢について、「流行や周りの研究者に影響されることなく、自分が納得するまで続けることが重要」だと述べています。この常識を疑い続ける探求心と、目の前の確実な実験的事実を信じ抜く誠実さが、長年の「冬の時代」を乗り越える原動力となりました。
同じ研究室で今も活動する研究者夫婦の絆
世界的な発見を成し遂げた坂口夫妻は、現在も大阪大学の同じ研究室で活動を続けています。若手研究者からは、親愛を込めて「ラボママ」「ラボパパ」と慕われています。
研究の合間には、京都市内の自宅で穏やかに暮らし、鴨川沿いを散策するなど、静かな日常を大切にしています。坂口氏は、科学の進歩を支えたのは、信念を貫いた研究者の姿勢と、それを支える家族や仲間の絆だったと語っています。
発見当初の学界の反応(懐疑的だった時期)と突破
坂口氏の提唱した仮説は、1985年頃に論文として発表された際、先行する「抑制性T細胞」の失敗イメージが学界に広まっていた影響もあり、「免疫反応を抑える細胞」という考え方そのものを受け付けない空気の中で、誰にも注目されない「冬の時代」を経験しました。
しかし、坂口氏はアメリカで長期的な研究環境を保証する奨学金に恵まれ、また、免疫学界の重鎮であるイーサン・シェバック氏が、追試を経てその研究を強力に支持し始めたことで、学界の空気が変わり始めました。
そして1995年、ついにTregに特異的なマーカーであるCD25(IL-2受容体α鎖)を突き止め、この細胞の存在を誰もが客観的に確認できる方法を示しました。さらに2003年には、Tregの機能を決定づけるFoxp3遺伝子を発見し、制御性T細胞研究の分野は一気に開花し、免疫学の中心理論の一つへと成長したのです。
まとめ
坂口志文氏のノーベル賞受賞は、長年の基礎研究の積み重ねが、いかにして人類の医療に貢献するかを体現したものです。彼が発見した「制御性T細胞」は、免疫を単に敵を倒す「戦い」としてではなく、体内の「調和」を守るシステムとして捉える、「攻める医学」から「整える医学」への価値観の転換を象徴しています。
この発見は、免疫の暴走による自己免疫疾患やアレルギー、そして免疫の抑制を利用するがん治療、さらには臓器移植の拒絶反応抑制といった、多岐にわたる医療分野に新たな治療戦略という羅針盤を与えました。
特に、山中伸弥氏が発見したiPS細胞技術とTreg研究が融合し、個別化医療の実現に向けた開発が加速していることは、難病に苦しむ多くの患者にとって大きな希望となります。
逆風の中で信念を貫き続けた研究者の情熱と、妻・教子さんとの二人三脚で築かれた信頼の絆——。坂口氏の功績は、科学的な発見の重要性だけでなく、それを支える人間的な側面の重要性をも私たちに教えてくれます。免疫のバランスを見極める科学は、これからも静かに進化を続けていくでしょう。

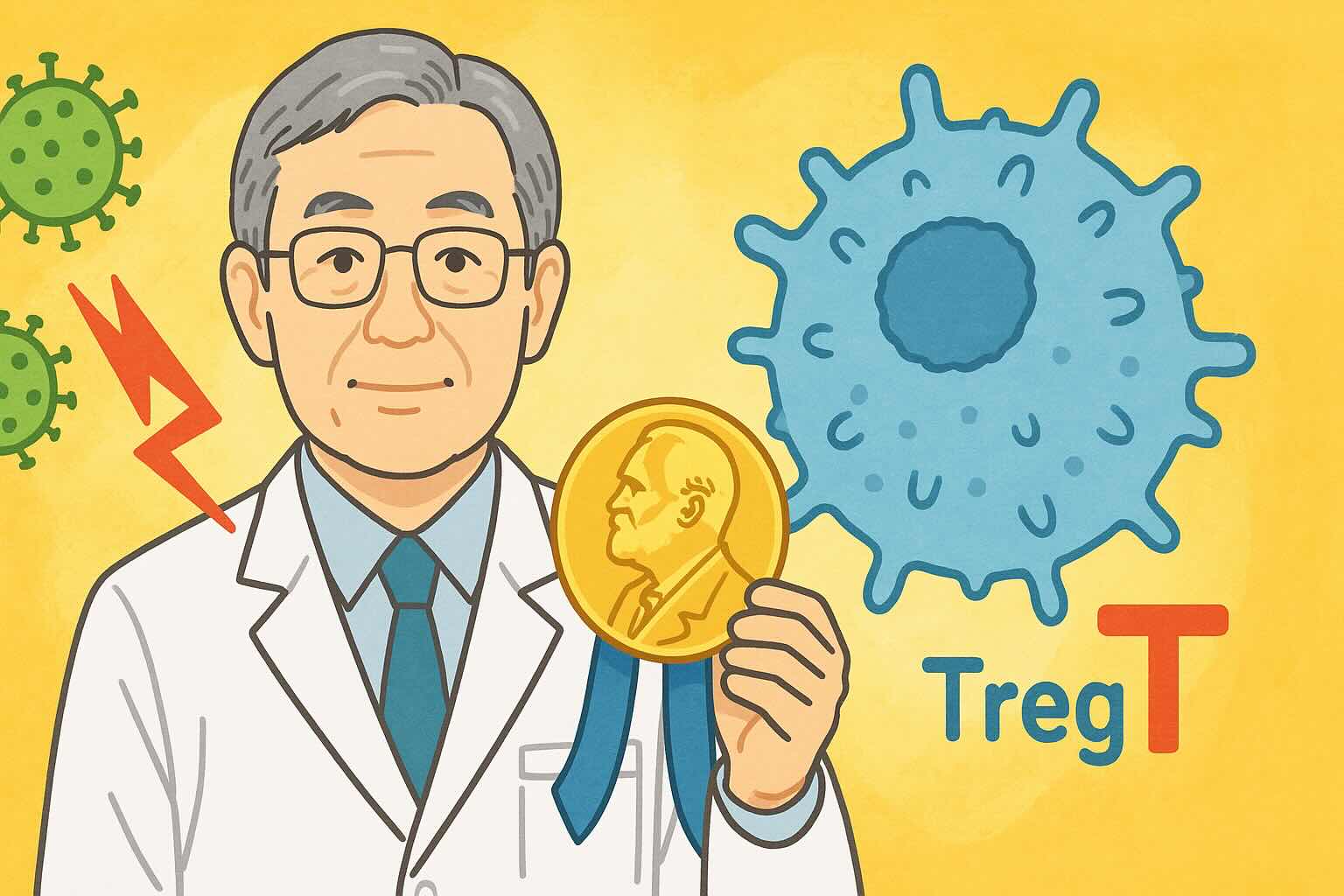
コメント