皆さん、普段自転車に乗りますか?
通勤・通学、買い物、レジャーなど、私たちの生活に欠かせない自転車ですが、2026年4月1日から大きな変化が訪れます。
これまで「注意」で済まされることが多かった自転車の交通違反に対し、自動車や原動機付自転車と同様に「青切符」による反則金制度が導入されることが閣議決定されました。
「知らなかった」では済まされない時代が目の前に来ています。
本記事では、この「自転車青切符」制度の全貌について、その目的から具体的な違反内容、車種別の注意点、そして対策まで、網羅的に分かりやすく解説します。
あなたの普段の運転をどう変えるべきか、注意すべきか。ぜひ最後までお読みください。
なお、私ごとですが、筆者 taoは20年来のロードバイク乗りです。今回の件はとても気になりますので、全力で、記事をまとめました!
音声解説♪
ところで、次の音声データは、この記事の音声解説です。AIで生成したので、少し誤読もありますがご了承ください。この音声解説を聞くことで、なにかをしながらでも「今回の自転車青切符制度」の概要が理解できます!
なお、この記事を公開した以降、2025年9月に警察庁交通局から「自転車ルールブック」が発表されました。その資料をよりわかりやすくまとめることで、「青切符制度」の説明として、あらためてブログ記事を書いたのが次のものです。
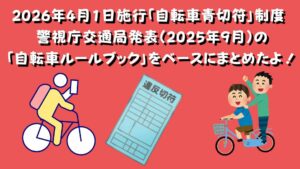
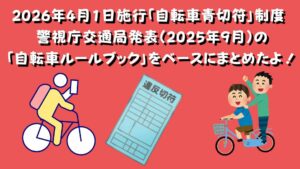
「自転車青切符」制度の全貌:その目的と仕組み


まずは、2026年4月1日から施行される「自転車青切符」制度がどのようなものなのか、その基本的な情報から見ていきましょう。
青切符(交通反則通告制度)とは?
「青切符」とは、正式には「交通反則告知書」と呼ばれるもので、交通反則通告制度に基づき、比較的軽微な交通違反(反則行為)をした場合に警察から交付される「青色の用紙」のことです。
この制度の最大の特徴は、本来であれば懲役刑や罰金刑(刑事処分)が科される違反行為について、反則金を納付することで刑事処分を免れることができるという点にあります。つまり、反則金を支払えば、前科が付く心配がありません。
ただし、注意が必要です。反則金の納付はあくまで「任意」です。「任意」なのですが…
もし、青切符を受け取ってから指定された期間内(原則8日以内)に反則金を納付しない場合、その事案は道路交通法違反事件として刑事手続きに移行し、検察官の判断によっては起訴され、刑事裁判を受ける可能性があります。有罪となれば罰金刑や懲役刑が科され、前科が付くことになります。
これまでの青切符制度の対象は自動車と原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む)でしたが、2026年4月1日以降は自転車もこの制度の対象となります。
なぜ今、自転車に「青切符」が導入されるのか?
「なぜ今、自転車に厳罰化が必要なのか?」と疑問に感じる方もいるかもしれません。この制度導入の背景には、看過できない交通事情の変化と課題が存在します。
自転車関連事故の増加と法令違反割合の高さ
交通事故全体の発生件数は減少傾向にあるものの、自転車が関連する事故の割合は増加傾向にあります。特に、自転車が当事者となった死傷事故のうち、約70%で自転車側に何らかの法令違反が認められているというデータもあり、その割合は増加傾向にあります。安全不確認や一時不停止といった交通違反が多く報告されています。
従来の指導・警告による抑止力の限界
これまで、自転車の交通違反に対しては、注意を促すための「黄色切符(指導警告票)」が交付されるケースがほとんどでした。反則金がなく、その場で注意するだけで処理されていたため、悪質・危険な運転行為の抑止には限界がありました。制度導入は、反則金という金銭的ペナルティを課すことで、違反抑止力を高め、利用者のルール遵守を促すことを最大の目的としています。
次世代モビリティやシェアサイクルの普及
電動キックボードなどの次世代モビリティやシェアサイクルの普及により、自転車が通勤・通学、観光など日常的な移動手段として急増しています。手軽に利用できる反面、交通ルールを十分に理解しないまま走行するケースが増え、違反や事故のリスクが高まっているのが現状です。
_/_/_/
こうした背景を踏まえ、政府は自転車への青切符制度の導入に至ったとされています。これにより、「自転車も車両である」という原則を社会全体に改めて強く認識させる狙いがあります。
制度の対象者と対象となる違反行為
自転車の青切符制度は、2026年4月1日以降、16歳以上の自転車運転者が対象となります。
16歳以上が対象となる理由
この年齢設定は、義務教育を修了し、基本的な自転車の交通ルールに関する最低限の知識を有していること、また、特定小型原動機付自転車の運転や原付免許・自動二輪免許の取得が可能になる年齢であることが根拠とされています。
16歳未満への対応
16歳未満の運転者については、理解度に個人差があると考えられているため、違反行為は引き続き指導・警告が中心となります。ただし、危険な違反が確認された場合には、警察から家庭や学校へ情報が共有され、注意喚起が強化される方針です。
また、14歳未満の者は刑事未成年であり刑罰は科せられませんが、接触事故などで相手に怪我をさせるなど重大な事故を起こした場合は、民事上の責任(損害賠償)を保護者が問われる可能性があるため、年齢に関わらず交通ルールを守る意識が重要です。
対象となる違反行為の種類
青切符の対象となる違反行為は、信号無視や一時不停止など、自動車等でも反則行為とされている約110種類に加え、普通自転車の歩道徐行義務違反など自転車に固有の違反行為5種類を含む、合計約113種類に及びます。警察官がその場で確認可能で、事実が明白かつ定型的な違反が対象となります。
「非反則行為」(赤切符対象)の例
青切符の対象外となる「非反則行為」としては、自動車等でも反則行為とはされていない約20種類の違反行為や、自転車固有の4種類の違反行為があります。
特に、酒酔い運転や妨害運転(あおり運転)といった、反社会性・危険性が高く、簡易迅速な処理になじまない違反行為は、引き続き「赤切符」の対象となり、直接刑事手続きに移行します。
知っておくべき主な違反事例と反則金・罰則


新制度の導入に伴い、日常の運転で特に注意すべき主な違反行為と、それぞれに科される反則金額を具体的に見ていきましょう。
ながら運転(携帯電話使用等)反則金額:12,000円
自転車を運転中に、携帯電話などを手で持って通話したり、画面を注視したりする行為は「ながら運転」として取り締まりの対象です。
これは、青切符制度の対象となる違反の中で最も高額な反則金が設定されており、社会がその危険性を極めて深刻に捉えていることを示しています。
固定されているスマートフォンをナビとして見る分には問題ありませんが、画面を触った瞬間に違反となります。ハンドルにスマホを固定していても、注視し続ける行為も違反の対象です。
例えば、携帯電話を見ながら赤信号を無視した場合や、警察官の警告に従わずに携帯電話を使用し続けた場合も取り締まりの対象となります。
2017年には、電動アシスト自転車に乗りながらスマートフォンを操作していた女子大学生が歩行者と衝突し、死亡事故に至った痛ましい事例も報告されています。
視線が画面に集中することで前方不注意となり、事故に直結する非常に危険な行為です。
信号無視 反則金額:6,000円
信号機の表示に従わずに交差点などに進入・進行する行為が信号無視です。
自転車は「車両」として扱われるため、信号のルールも自動車と同様に守ることが大切です。特に注意が必要なのは、歩行者・自転車専用信号やスクランブル交差点です。
歩行者用信号が青でも、自転車は車両用信号機に従うのが原則です。歩行者用信号がチカチカ点滅していても、車両用信号が赤であれば進行できません。
もし歩行者用信号に従って自転車で渡ってしまうと、信号無視となり反則金の対象です。
2024年には、大阪市で信号無視をした10歳児が自転車で乗用車と衝突し、自転車側の過失が100%と認定された事例もあります。
信号遵守は、交通社会に参加する上での最も基本的なルールであり、違反は重大事故に直結します。
通行区分違反(歩道通行・逆走)反則金額:6,000円
自転車は道路交通法上「軽車両」に位置づけられ、歩道と車道の区別がある場所では、車道を通行することが原則です。
歩道走行の原則と例外
原則は車道ですが、以下のような場合は歩道通行が認められています。
- 「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転している場合
- 道路工事や連続した駐車車両などで、車道の左側部分を通行するのが著しく困難な場合
- 自動車の交通量が著しく多く、車道の幅が狭いなどのため、追越し車両との接触事故の危険性があると認められる場合
上記例外に該当し歩道を通行する場合でも、無条件に走行できるわけではありません。
歩道の中央から車道寄りの部分を、直ちに停止できる速度で徐行(時速8km〜10km程度が目安)し、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は一時停止しなければなりません。歩行者は絶対的に優先されます。
警察庁も「単に歩道を通行しているといった違反にについては、これまでと同様に通常指導警告が行われ、青切符の導入後も基本的には取り締まりの対象となることはない」としていますが、スピードを出して歩行者を驚かせたり、立ち止まらせたりした場合は取り締まりの対象となります。
警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合も同様です。
逆走の危険性
一方通行に指定された道路を、指定された方向とは逆に進行する「逆走」も違反です。補助標識で**「自転車を除く」と表示されている場合は逆走が許可**されますが、その場合でも道路の左側部分を通行する義務は免除されません。逆走してくる自転車は予期せぬ動きであり、正面衝突のリスクが極めて高い危険行為です。
一時不停止 反則金額:5,000円
「止まれ」の道路標識や路面表示がある場所では、停止線の直前(停止線がない場合は交差点の直前)で、タイヤの回転が完全に止まるまで、車両が完全に停止し、左右の安全確認を行う義務があります。
速度を落とす「徐行」では違反となります。
一時停止は出会い頭事故を防止するための最も基本的なルールであり、新制度では重点的に取り締まられる違反行為とされています。
見通しの悪い場所では標識がなくても徐行し、安全確認を怠らないようにしましょう。
傘差し運転 反則金額:5,000円
傘を差しながらの運転は、片手運転による操作性の低下、傘による視界の妨げ、強風時にあおられてバランスを失う危険性などから、多くの都道府県で禁止されています。
自転車のハンドルに傘を固定する「傘スタンド」の使用も、多くの自治体で違反とみなされる場合があります。固定されていても、傘が視界を妨げたり、風の影響で安定性を失うおそれがあるためです。
また、積載物のサイズ制限(幅0.3m、高さ2mなど)を超える可能性もあります。雨天時に自転車を利用する場合、レインウェアを着用することが最も安全で合法的な対策です。
イヤホン・ヘッドホン使用 反則金額:5,000円
イヤホンやヘッドホンの使用そのものが直ちに違反となるわけではありません。
法律が禁じているのは、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえない状態」で運転することです。
具体的には、緊急車両のサイレン、警察官の指示、他の車両の警音器などが聞こえない状態を指します。
片耳のみの使用や、骨伝導タイプ、オープンイヤー型イヤホンであっても、音量が大きければ違反と判断される可能性があります。
警察官からの声掛けに気づくかどうかが、取り締まりの現場における一つの判断基準となり得ます。
最も確実な安全策は、運転中はイヤホン類の使用を完全に控えることです。
多くの都道府県では、独自の条例や規則でイヤホンの使用を禁止している場合もあるため、お住まいの地域の条例も確認しましょう.
夜間の無灯火 反則金額:5,000円
夜間(日没から日の出まで)に、前照灯(フロントライト)を点灯せず、かつ尾灯(テールライト)または後部反射器材(リフレクター)を備え付けずに走行する行為が対象です。
前照灯は、白色または淡黄色で、夜間に前方10メートルの距離にある障害物を確認できる光度が必要です。このため、点滅モードは前照灯として認められておらず、点灯モードでの使用が必須です。
後部には、橙色または赤色の尾灯を点灯するか、夜間に後方100メートルからの自動車前照灯で容易に確認できる反射器材を装着する義務があります。尾灯を点滅モードで使用する場合は、反射器材との併用が必須となります。
夜間の無灯火は、自分自身の視界が遮られるだけでなく、相手からの視認性が大きく下がり、交差点や暗がりでの衝突事故を起こす危険性が非常に高まります。
制動装置不良 反則金額:5,000円
ブレーキが効かない自転車で運転する行為が対象です。
自転車には、前後輪それぞれに独立したブレーキが装備されている必要があります。
ブレーキの不備は、とっさの時に停止できず、事故に直結する極めて危険な状態です。定期的な点検や整備を怠らないようにしましょう。
二人乗り(軽車両乗車積載制限違反)反則金額:3,000円
自転車は、原則として運転者以外の同乗を禁止されています。
友人や恋人を荷台やハンドルに乗せる行為は明確な違反です。
主な例外としては、16歳以上の運転者が、幼児用座席を設けた自転車に小学校就学前の幼児を乗せる場合です。「幼児2人同乗基準適合車」と認定された自転車では、幼児2人まで同乗が可能です。
2人乗り運転は自転車の重心を不安定にし、制動距離の延長や転倒に直結する極めて危険な行為です。
2024年には、2人乗りで歩道を走行中にガードレールに衝突し、1人が亡くなる事故も発生しています。
並進禁止 反則金額:3,000円
道路交通法第19条により、軽車両が横に並んで走行すること(並進)は明確に禁止されています。
特に車道での並走は、後続車両の通行を妨げたり、追い越し時の危険性を高めたりするため、非常に危険です。
集団走行(グループライド)の場合も、一列の隊列(トレイン)を組むことが法的な原則となります。
歩道で並進した場合、並進禁止違反と歩道通行違反の両方の違反が成立する可能性もあります。
ヘルメットの着用 罰則:なし(努力義務)
2023年4月1日から、年齢を問わず、すべての自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用が「努力義務」頭部損傷が致命傷となっており、ヘルメット着用者の致死率は非着用者に比べて約2.1倍低いという統計もあります。
万が一事故に遭った場合、ヘルメットを着用していなかったことが過失割合の算定で不利に考慮され、受け取れる損害賠償額が減額される可能性も指摘されています。
命を守るための最も効果的な自己防衛策として、積極的に着用しましょう。
ロードバイク・マウンテンバイク利用者が注意すべき点


ロードバイクやマウンテンバイク(MTB)は、一般的な「ママチャリ」とは異なる特性を持つため、特に注意すべき点があります。
ロードバイク
ロードバイクは高速性能が特徴ですが、公道では「競技」ではなく「車両の運転」としての責任が伴います。
高速走行に伴う法的責任の加重
道路交通法には自転車に対する法定速度の定めはありませんが(道路標識による指定がある場合を除く)、すべての運転者には「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」という「安全運転の義務」が課せられています。
速度が上がれば上がるほど、危険を回避するまでの時間と距離は短くなり、事故時の被害も甚大になります。高速で走行するロードバイクの運転者には、より高度な注意義務が課せられていると解釈され、事故時には走行速度が高かった事実が過失割合を判断する上で不利な要素となります。
集団走行(グループライド)の法とマナー
仲間との集団走行はロードバイクの醍醐味ですが、公道では「並進の禁止」が適用されます。一列の隊列(トレイン)で走行するのが原則です。
空気抵抗を減らす「ドラフティング」自体は違法ではありませんが、公道では急ブレーキや障害物回避に対応できる安全な車間距離(最低でも自転車1台から1.5台分)を確保することが絶対条件です。
先頭交代時も、周囲の交通状況を完全に確認し、ハンドサインや声掛けで意図を明確に伝えましょう。
ハンドサインの重要性と実践
集団走行における安全確保には、後続への的確な情報伝達が不可欠です。右左折や停止時の「手信号」は法で規定されていますが、実際のグループライドでは、路面の穴や障害物を指さしたり、減速時に手のひらを後方に見せたりといった、より直感的で分かりやすい慣習的なサインが多用されます。
最も重要なのは、形式よりも「意図が確実に伝わること」です。
公道走行に必要な装備
ロードバイクは競技での使用を前提に販売されることが多く、公道走行に必要な装備が付属していない場合があります。
しかし、公道を走行する以上、前後輪に独立したブレーキ、警音器(ベル)、後部反射器材(または尾灯)は法律で義務付けられています。例えば、ブレーキの無い競技用ピストバイクで公道を走るのはだめです。
これらの装備がない状態で公道を走行すると、整備不良車両として取り締まりの対象となり、特にブレーキの不備は「制動装置不良」として5,000円の反則金が科される可能性があります。
マウンテンバイク(MTB)
MTBは頑丈な構造とオフロード性能が特徴ですが、公道走行では「普通自転車」の定義に注意が必要です。
「普通自転車」の法的定義とハンドル幅の罠
歩道通行などの特例が認められる「普通自転車」は、車体の幅が60cm以内と厳格に定められています。
しかし、近年のMTBは高い操作性を追求するため、ハンドル幅が70cm、あるいは80cmに達するものも少なくありません。
ハンドル幅が60cmを超えたMTBは、法的には「普通自転車」のカテゴリから外れます。
これにより、たとえ「自転車通行可」の道路標識がある歩道であっても、そのMTBで走行することは法律上許可されず、走行が許されるのは車道と路側帯のみとなります。
この場合、歩道通行は通行区分違反(反則金6,000円)となります。
オフロード用装備と公道走行のリスク
MTB特有の装備は、舗装路(オンロード)では性能の足かせとなる場合があります。
オフロードの不整地でグリップ力を発揮するブロックタイヤは、舗装路では路面との摩擦抵抗が大きく、ペダリングが重くなるだけでなく、雨天時のマンホールや白線の上などでは滑りやすい傾向があります。街乗りが主体であれば、「セミスリックタイヤ」などに交換することが推奨されます。
また、路面からの衝撃を吸収するサスペンションは、舗装路でのペダリングの推進効率を低下させます。多くのサスペンションには動きを一時的に固定する「ロックアウト機能」が搭載されているため、公道を走行する際はこれを活用すると良いでしょう。
走行場所の法的区分
MTBの性能を活かせる山道や林道での走行には、法的な理解とマナーが不可欠です。
自動車が通行する林道は公道に準じて走行できる場合もありますが、ゲートで封鎖されている私有林道や、車両の進入が禁止されている場所も多数あります。
登山道や自然公園内の歩道は、原則として歩行者のためのものであり、自転車の乗り入れが禁止されていることがほとんどです。
走行前には必ずその土地の管理者が定める規則を確認しなければなりません。
自動車運転者も注意!自転車追い越し時の新ルール
今回の制度改正では、自転車利用者に加え、自動車運転者にも新たな義務が課されます。
2026年4月1日から施行される「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」には、自動車が自転車の右側を通過する際の義務に関する規定が盛り込まれています。
自動車側の義務
自動車等が自転車等の右側を通過する場合(側方通過時)において、十分な間隔を確保し、安全な速度で進行することが義務付けられます。
概ね1mから1.5mほどの側方間隔が基本とされています。この義務に違反した場合、自動車の運転手には反則金7,000円、点数2点が科されます(普通車の場合)。
自転車側の義務
同時に、自転車側にも、自動車に追い抜かれる際はできる限り道路の左側端に寄って通行することが義務付けられます。この義務に違反した場合、自転車には反則金5,000円が科される可能性があります。
この新ルールは、自動車と自転車が安全に共存するための重要な措置です。お互いがルールを守り、安全意識を持って通行することが求められます。
まとめ:安全な自転車社会の実現に向けて
2026年4月1日から導入される自転車への「青切符」制度は、単なる罰則強化にとどまりません。
これは、すべての自転車利用者に対し、自らが「歩行者の延長」ではなく、交通社会の一員としての責任を負う「車両の運転者」であるという自覚を求める、国からの明確なメッセージです。反則金を回避するという消極的な理由からではなく、自らの安全、そして他者の安全を守るという積極的な意志を持って、交通ルールを再学習し、日々の運転で遵守する意識改革が、今、一人ひとりに求められています。
一方で、「車道は怖いから歩道を走らざるを得ない」という多くの利用者の声も無視できない現実です。
罰則という「ムチ」を強化するのであれば、同時に、自転車が安全に車道を走行できる環境、すなわち自転車専用レーンの整備、路上駐車の厳格な取り締まり、交差点の改良といった物理的インフラ(ハード面)の整備も不可欠です。警察庁も、交通安全教育の充実や自転車通行空間の整備に取り組む方針を示しています。
今回の法改正が、単なる取り締まり強化に終わるのか、それとも安全なインフラ整備への社会的・政治的な機運を高めるきっかけとなるのか。制度の実効性を確保し、社会全体の理解と協力を得ながら、法制度と物理的環境の両輪で安全対策を進めていくことが、今後の大きな課題となるでしょう。
私たちは自転車を利用する上で、「自転車安全利用五則」を常に意識し、安全運転を心がけましょう。
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行:歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
あなたの安全運転が、より良い交通社会を築く第一歩となります。
更新メモ:2025年9月8日 1658 917
更新メモ:2025年9月9日 1693 932


コメント