音楽評論家・渋谷陽一が日本のロックシーンに遺したもの…。
日本の音楽シーンにおいて、その批評、雑誌づくり、そしてロックフェスティバルのプロデュースを通じて、計り知れない影響を与え続けてきた人物、それが音楽評論家の渋谷陽一さんです。
2025年7月14日、74歳で永眠された彼の生涯は、まさに日本のロック史そのものと言えるでしょう。
この記事では、渋谷陽一さんが日本の音楽文化に刻んだ軌跡と、その多岐にわたる功績を深掘りし、彼の哲学と思想に迫ります。
第1章: 『rockin’on』創刊と批評の思想
渋谷陽一さんは、1951年6月9日に東京都新宿区に生まれました。
1971年、19歳の時に『ミュージックライフ』誌で音楽評論家としてデビューを果たします。しかし、彼の最も革新的な功績は、その翌年、1972年に21歳で個人事業として洋楽ロック批評・投稿誌『rockin’on』を創刊したことでしょう。
この雑誌は、単なる音楽情報誌ではなく、「ロックは聴く者の中にある」という明確で強い思想に基づいたものでした。ロックスターや音楽業界の中にあるのではなく、リスナー一人ひとりの心の中にロックがあるという哲学から、読者投稿型の雑誌という形式が採用されました。
評論家としての渋谷さんは、時代における先進性を持ったバンドを高く評価する一方で、その音楽性が「様式化」したバンドには批判的でした。
例えば、彼はブラック・サバスを評価する一方で、ジューダス・プリーストを批判していました。その一方で、レッド・ツェッペリン、ビートルズ、プリンスといったアーティストに対しては、その革新性と大衆性を兼ね備えた理想的な存在として一貫して高く評価し、自身の批評哲学の根幹に据えて論じ続けました。
クイーンについては、ブライアン・メイのギターを中心とした空間を埋め尽くすような建築工学的な厚みのあるサウンド、日本人の感性に訴えかけるメロディーの明快さ、そしてハリウッド大作映画に通じる質の高いエンターテイメント性を魅力として挙げ、高く評価しています。
インターネットがなかった時代において、渋谷陽一さんは、どの音楽を聴けばいいのか教えてくれる「音楽選びの先生」的な存在であり、その「評論家」としての権威は絶大でした。
彼は、メディアを自ら組織していくという行為そのものが批評行為の一部であると捉えていました。
第2章: 多彩なメディア事業と雑誌の展開
『rockin’on』の成功にとどまらず、渋谷さんはその後も多岐にわたる雑誌を創刊し、日本のメディア業界に大きな足跡を残しました。
1986年には邦楽ロック批評誌『ROCKIN’ON JAPAN』を創刊。その後もカルチャー誌『CUT』(1989年創刊)、邦楽専門誌『bridge』(1994年創刊)、サブカルチャー誌『H』(1994年創刊)、総合誌『SIGHT』(1999年創刊)、美術誌『SIGHT ART』(2014年創刊)などを次々と世に送り出しました。
彼は新雑誌の立ち上げに際しては編集長として積極的に関わり、その手腕は高く評価されています。
特に「映画」ジャンルには意欲的に関わり、黒澤明、北野武、宮崎駿、押井守といった巨匠たちに直接インタビューを行うなど、ジャンルを超えた活動を展開しました。
晩年には、原稿を書くことよりも出版社の経営者としての立場を重視し、「広告営業をしている方が楽しいし、資質的にも合っている」と公言するなど、根っからの編集者であり経営者としての側面を強めていました。
第3章: フェスプロデューサーとしての革新
2000年代に入ると、渋谷陽一さんは新たな領域へと挑戦します。それが、大規模なロックフェスティバルのプロデュースでした。
彼はロックフェスティバルを「ひとつのメディアであり、雑誌作りによく似たトータルな表現である」と捉え、ここでも「観客が主役だ」という彼の思想を貫きました。
彼がプロデューサーとして初開催した主要なフェスティバルには、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」 (2000年)、全国初となる冬の年越し屋内フェスティバル「COUNTDOWN JAPAN」 (2003年)、そして「JAPAN JAM」 (2010年)などがあります。
さらに、坂本龍一さんをオーガナイザーとして迎えた脱原発フェス「NO NUKES」(2012年) も開催しています。
ロッキング・オン創刊以前から小さなコンサートを主宰し、資金集めのためにフィルムコンサートを催していた彼の初期の活動は、後に15万人規模の夏フェスを成功させる原点になったと評されています。
第4章: 晩年と遺産
渋谷陽一さんは、2023年11月に脳出血を発症し、緊急入院しました。手術後は療養とリハビリを続けていましたが、2025年に入り誤嚥性肺炎を併発し、74年の生涯を終えました。
病気療養中の2024年3月、ロッキング・オン・グループは経営体制の変更を発表。渋谷氏は3月31日付で長年務めた代表取締役社長を退任し、翌4月1日付で代表取締役会長に就任しました。
また、1997年から27年間にわたりDJを務めてきたNHK-FMの長寿番組「ワールドロックナウ」も、彼の体調不良を受けて2024年3月30日に終了しました。
渋谷陽一さんが逝去された際、ロッキング・オン・ホールディングス/ロッキング・オン・ジャパン代表取締役社長の海津亮氏と、株式会社ロッキング・オン代表取締役社長の山崎洋一郎氏は、それぞれ追悼の辞を寄せています。
海津氏は、渋谷さんという存在そのものがメディアであり、ロッキング・オン社という組織体が続く限り、その影響は永遠に生き続けるだろうと述べています。
山崎氏は、渋谷さんから直接仕事を教わったことは一度もなかったものの、「ロックは聴く者の中にある」という彼の思想が、ロッキング・オンの雑誌やフェスにおいて一貫して受け継がれていることを強調しています。
渋谷陽一さんは、批評家として、編集者として、そしてプロデューサーとして、日本の音楽シーンに多大な功績を残し、その哲学はこれからも受け継がれていくことでしょう。
第5章: 渋谷陽一さんに関する、よくあるQ&A
- Q1: 渋谷陽一さんの主な肩書は何ですか?
- A1: 渋谷陽一さんは、音楽評論家、編集者、DJ、そしてロッキング・オン・グループの代表取締役会長を務めました。
- Q2: 『ロッキング・オン』はいつ創刊されましたか?
- A2: 『rockin’on』は、渋谷陽一さんが20歳の時の1972年に創刊されました。
- Q3: 渋谷陽一さんがプロデュースした主な音楽フェスティバルは何ですか?
- A3: 彼は、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」(2000年)、全国初の冬の屋内フェス「COUNTDOWN JAPAN」(2003年)、そして「JAPAN JAM」(2010年)といった大規模なロックフェスティバルをプロデュースしました。
- Q4: 渋谷陽一さんはいつ亡くなりましたか?
- A4: 渋谷陽一さんは、2025年7月14日に74歳で永眠されました。
- Q5: 彼の死因は何でしたか?
- A5: 2023年11月に脳出血を発症し、その後療養を続けていましたが、2025年に入って誤嚥性肺炎を併発し、亡くなりました。
- Q6: 渋谷陽一さんの出身地はどこですか?
- A6: 彼は東京都新宿区の出身です。実家は目白のお屋敷街にあり、裕福な家庭で育ちました。
- Q7: 彼が長年DJを務めたラジオ番組は何ですか?
- A7: NHK-FMで1997年から2024年3月まで27年間にわたりDJを務めた「ワールドロックナウ」が有名です。
まとめ
渋谷陽一さんは、単なる音楽評論家にとどまらず、「ロックは聴く者の中にある」という哲学を貫き、メディアと音楽イベントを通じて日本の音楽シーンを形成し、牽引してきた稀有な存在です。
彼が創刊した数々の雑誌は、多くの音楽ファンに新たな視点と情報を提供し、プロデュースした大規模フェスティバルは、観客が主役となる「表現の場」として、日本のロック文化を根付かせました。
彼の活動は、まさに一つの巨大なメディアとして、現代の音楽文化に計り知れない影響を与え続けています。渋谷陽一さんの功績は、これからも日本の音楽史において、輝かしい指針として語り継がれていくことでしょう。
彼の生涯と功績は、まるで巨大なオーケストラを指揮するマエストロのようでした。
一人ひとりの楽器(リスナー)が奏でる音(ロック)が最も重要であると考え、それを最高の舞台(雑誌やフェス)で響かせ、全体として壮大なハーモニー(文化)を創り上げたのです。

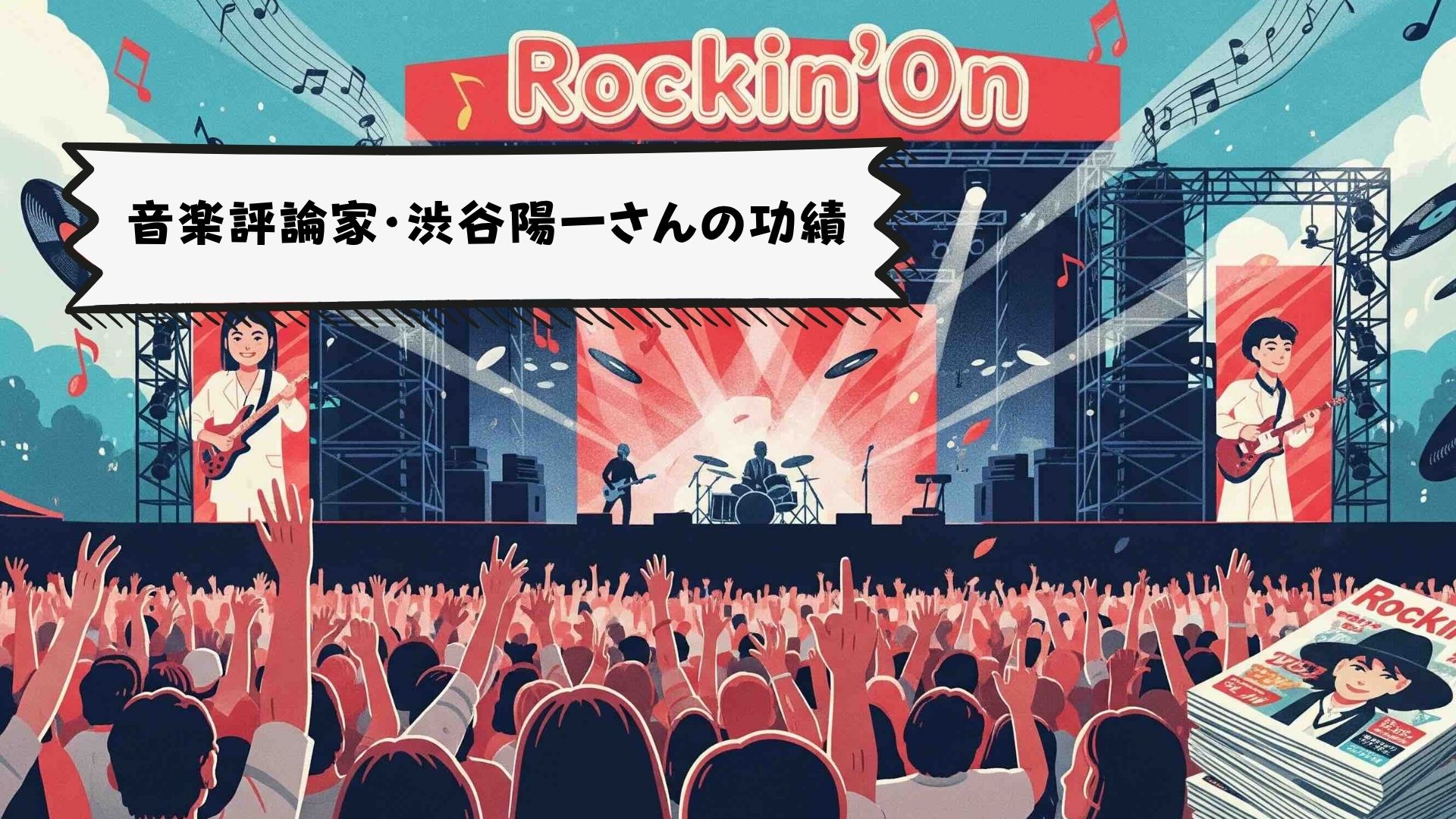
コメント